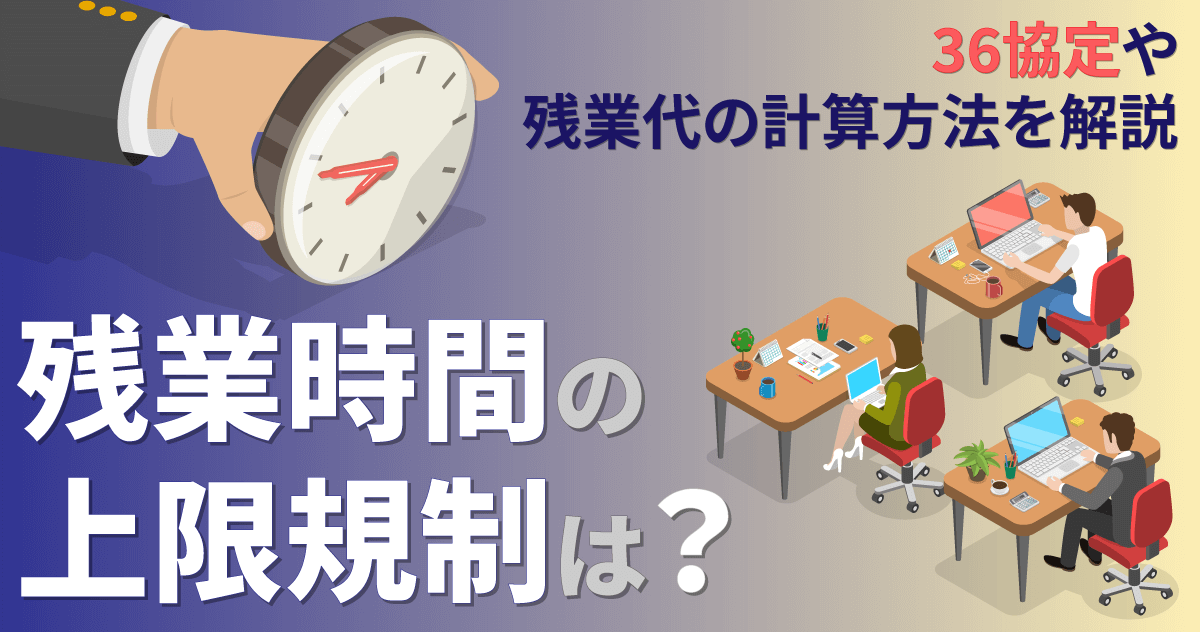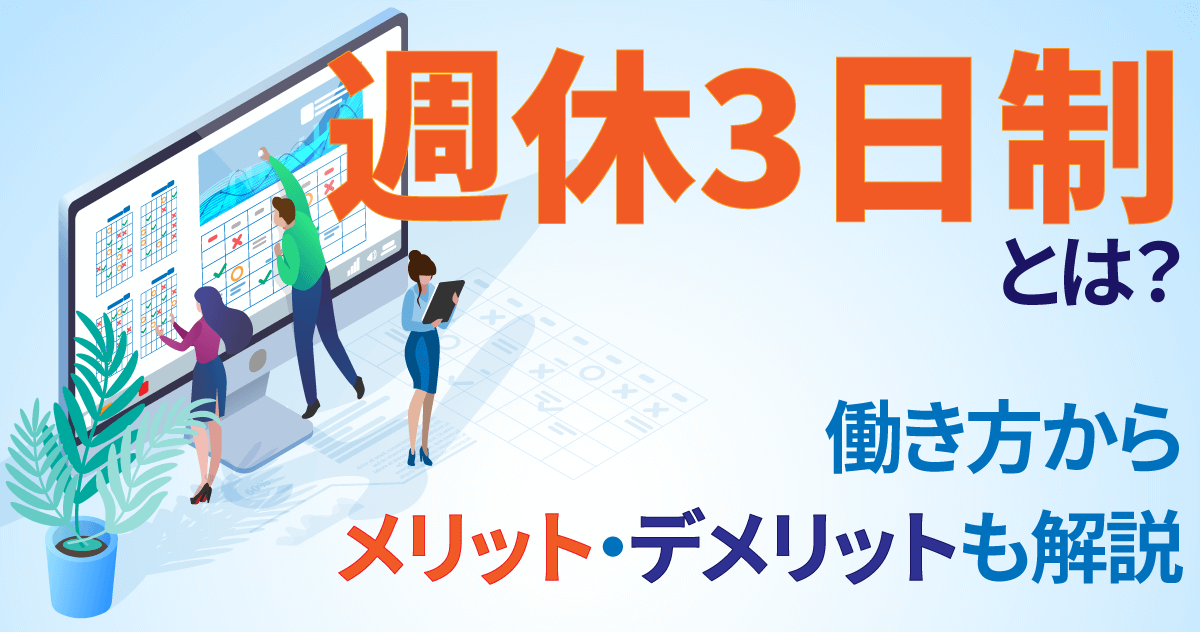年間休日数の最低基準とは?ブラック企業を見分けるポイントも解説!

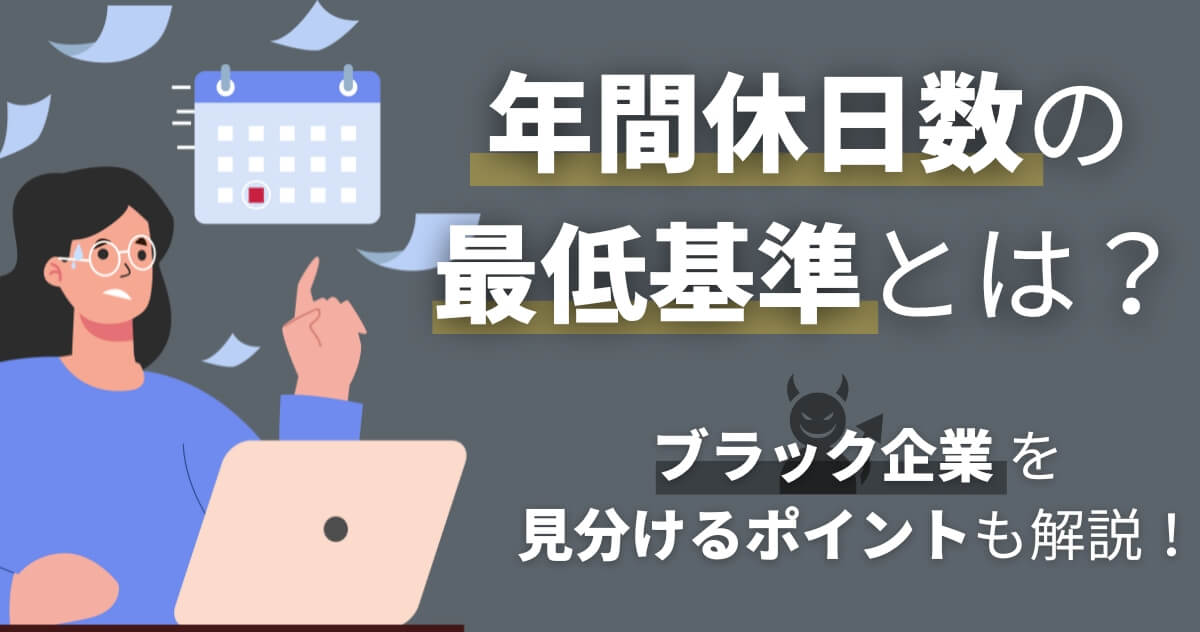
はじめに
- 年間休日数の最低基準は、フルタイム勤務の場合105日である
- 短時間勤務では105日より少ない休日数でも合法となる場合がある
- 36協定を結んでいる場合でも105日より休日が少ない場合がある
- 平均の年間休日数は112.1日だが、業種により平均休日数は変わる
- 「完全週休2日制」と「週休2日制」は意味が違うので注意しよう
労働基準法における「年間休日」とは
企業が定める1年間の休日総数を「年間休日数」といいます。年間休日には、労働基準法で定められた「法定休日」と、企業が就業規則で取り決める「法定外休日」があります。
「法定休日」とは
労働基準法では、最低限とるべき休日として「1週間に1日以上の休日」もしくは「4週間で4日以上の休日」を設定するよう定めています。これが「法定休日」です。一般的に、企業はこの法定休日を固定の曜日に決めて運用していることが多いようです。しかし、法定休日は特定の曜日に固定する必要はなく、企業によっては曜日を固定せずに運用することもあります。
「法定外休日」とは
多くの企業は、法定休日とは別の日に休日を定めており、これを「法定外休日」と呼びます。
たとえばある企業では、土曜日を法定外休日、日曜日を法定休日と定め、必ず週2日は休みを取れるようにしています。
年間休日数の最低基準とは?
前述の通り、労働基準法では、最低限とるべき休日として「法定休日」を週1日設定するように定めています。1年間は52週あるので、法定休日は年間52日です。
しかし、1日8時間労働のフルタイム勤務の場合、法定休日(年間52日)だけでは法定労働時間(後述)を超えてしまうため、企業は「法定外休日」を就業規則で設定し運用しています。
では、法定労働時間を考慮した最低限保証されるべき年間休日数は何日となるのでしょうか。次項より解説します。
労働基準法における最低基準
休日と労働時間について、労働基準法で次のように定められています。
- 労働基準法32条(要約)
労働時間の上限は、休憩時間を除いて1日8時間、週40時間まで(法定労働時間)
- 労働基準法第35条(要約)
毎週少なくとも1日、または4週間に4日の休日を与えなければならない
これらの規定から算出すると、1日8時間労働の場合、最低年間休日数は「105日」となります。
参考:厚生労働省 – 労働基準法(昭和22年04月07日法律第49号)
年間休日105日以下でも適法なケースがある
前項で述べた「年間休日数の最低日数は105日」は、週5日・8時間/日勤務の場合です。それ以外の働き方では、年間休日105日以下でも問題ない場合があります。
たとえば、6時間以下のパート勤務者は年間休日が105日以下になることが考えられます。「労働時間の上限を1日8時間、週40時間まで」を満たしていれば「毎週少なくとも1回、または4週間に4回の法定休日が必要」でも問題なく、したがってこの場合の年間休日数は最低52日です。
また、36協定(サブロク協定)を結んでいる場合も、最低休日数は変わるので注意が必要です。
36協定(サブロク協定)
労働時間の延長や休日労働を可能にするため、労働基準法第36条に基づいて労使間(労働者と使用者)の間で結ぶ協定のこと。36協定を労使間で結ぶことにより、法定労働時間を超えて働くことが認められる。ただし、時間外労働には上限があり、2024年4月からは原則として年720時間以内が労働時間の限度とされている(時間外労働の上限規制)。
36協定により、繁忙期に勤務時間・勤務日を増やすことが可能となり、法律に反しない範囲で休日数を減らせるため、年間休日105日以下となることがあり得ます。
年間休日に休暇・休業は含まれない
「休日」と混同してしまいがちなのが「休暇」「休業」です。
- 休暇
「休暇」とは、本来労働すべき日に労働義務が免除される日のこと。代表的なものに有給休暇がある。また、最近では企業が独自に休暇を設けることもあり、バースデー休暇、生理休暇などがある。これらの休暇は企業全体で定められた休日ではなく、個々の従業員によって取得するタイミングが異なるため、年間休日数には含まれない。
- 休業
企業に籍を置きながら、長期間労働から離れる場合を「休業」と呼称する。例としては病気による休業や産前・育児休業、介護休業などだ。個々の従業員によって取得するタイミングが異なるため、年間休日数には含まれない。
休暇・休業は「年間休日数」には含まれないということを覚えておきましょう。
業種ごとの平均的な休日数
前項で「労働基準法により、1日8時間勤務の場合、年間休日数は最低105日である」と説明しましたが、この105日はあくまで法定の最低年間休日数です。多くの企業では従業員がゆっくりと休暇を過ごせるように、年間休日数を105日以上に設定しています。
では平均の年間休日数は何日なのか、一般的に何日以上ならば休日が多い、また何日以下なら少ないといえるのか、気になる方も多いでしょう。次項より解説します。
平均年間休日数は112.1日
厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査」によると、1企業平均年間休日数は「112.1日」です。ただしこれはあくまで全体の平均で、実際は事業規模、業界・業種や、企業ごとに年間の平均休日数は変わってきます。
一般企業の年間休日数は110日~120日
前述の通り、平均年間休日数が112.1日であることから、110日未満の企業は休みが少なめと判断してよいでしょう。一般的な企業の年間休日数は110日~120日程度であることが多いようです。
- 120日
完全週休2日・祝日休みに加えてお盆休み、年末年始の休みがあると考えられる。
- 110日
週休2日および祝日が休日になる。
- 110日以下
週休1日となる週が出る・祝日出勤が出てくると考えてよい。
シフト制を採用する職場の年間休日数
人手不足が顕著な業界や、接客業・小売業などでは、シフト制を採用している職場が多く、土日祝が勤務日となることがよくあります。シフト制の場合、休日のとり方は通常「曜日は決まっていないが週2日の休みが割り当てられる」か「平日に固定休がある」のいずれかです。こうした職場は慢性的に人手不足であることが多く、年間休日が110日以下であることも珍しくありません。求人を探す際は、年間休日数が自分の希望と合致するかをよく確認するとよいでしょう。
- 人手がより多く必要な業界
飲食業界、宿泊業界をはじめとする接客業(休日や勤務時間がシフト制であることが多い)
- 24時間稼働が必要な職場
常時稼働の倉庫・工場、救急病院や老人ホームなどの医療・介護分野(日勤・夜勤交代制もしくは3交代制のシフト制が多い)
年間休日数が多い業種と少ない業種
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、年間休日数が多い業種と少ない業種は次の通りです。
- 年間休日数の多い業種
情報通信業121.6日、金融業・保険業121.5日、学術研究・専門/技術サービス業119.7日など
- 年間休日数の少ない業種
宿泊業・飲食サービス業97.5日、生活関連サービス業・娯楽業105.3日、運輸業・郵便業105.4日など
参考:厚生労働省 – 令和5年年間休日総数階級別企業数割合、1企業平均年間休日総数及び労働者1人平均年間休日総数(全国)
年間休日数からみるリスクの可能性
前項までで解説した通り、年間休日数は個々の働き方や生活に大きな影響を及ぼします。
次項からは、年間休日数にまつわるリスクについて解説します。
年間休日120日未満のリスク
休日が年間120日未満の場合、夏季休業・冬季休業がなかったり、月1回の土曜出勤が義務付けられていたりすることがあります。人によっては休日が不足していると感じることもあるでしょう。
求人票で休日数を事前に確認しなかったために、入社後に「夏季・冬季休業がなく、土曜日もほぼすべて出勤」という事実が発覚して、就職に失敗したと感じることもあります。年間休日数を重視する方は、求人票で休日の項目をよく確認するようにしましょう。
休日数が曖昧な求人票への注意点
求人票に休日数がはっきりと書かれていなかったり、休日の説明が複雑でわかりにくかったりといった場合があります。また中には、「土曜日や夏季・冬季休業に強制で有給休暇を充てる」といったような勤務形態を強いる企業も残念ながら存在します。
このような求人には十分注意し、疑問点や不明点を、ハローワークや求人媒体、あるいは募集企業に問い合わせるのもよい方法です。
シフト制や変形労働時間制の注意点
シフト制とは、前述の通り、職場スタッフが交代して休日をとる勤務形態です。シフト制では土日祝に出勤することが多く、休みが不定期になるため、生活リズムが崩れる懸念があります。カレンダー通りに休日を過ごす友人や家族と予定が合わず、思うように休日を楽しめないこともあるため、中にはデメリットと感じる人もいるでしょう。
また、変形労働時間制とは、繁忙期の勤務時間を長くする代わりに閑散期は多めに休みを取得できるといった勤務形態を指します。この勤務形態では、忙しい時期と暇な時期の差が激しく疲弊してしまう可能性が考えられます。
年間休日数からブラック企業を見分けるポイント
求人票の「年間休日数」の記述から、いわゆる「ブラック企業」を見抜くこともできます。本項では、年間休日数で確認すべき重要なポイントについて解説します。
「完全週休2日制」と「週休2日制」の違い
求人票の休日数を見ると、「完全週休2日制」や「週休2日制」と書かれていることがあります。これらは字面がよく似ているものの、それぞれの意味はまったく別物なので注意が必要です。
- 完全週休2日制
毎週必ず休暇が2日あるという意味。カレンダー通りの土日祝休みなどがこれにあたる。
- 週休2日制
「月1回以上、週2日となる週がある」という意味。つまり、すべての週が必ず2日休みになるとは限らない。
毎週2日の休みを重視する場合、求人票に「完全週休2日制」と記載があるかどうかをよく確認するとよいでしょう。
「年間休日〇〇日」の記載を確認するコツ
求人票に「休日:シフト制による」としか記載されていない場合もあります。このような年間休日数の不明点を解消したい場合、事前に企業側へ確認したり、面接時に質問したりするとよいでしょう。
年間休日数に限らず、求人票の不明点は入社前にきちんと確認することが希望に沿った職場へ近づくコツといえます。
シフト制や変形労働時間制の注意点
シフト制や変形労働時間制の場合、年間休日数だけでなく「どのように休日を取得するか」が重要です。中には、長時間勤務のあとに1日休みが取れたと思ったらすぐに、再び長時間労働が続くこともあります。勤務形態に不安がある方は、企業側に勤務状況や休日の取得状況、取得方法について詳しく説明してもらうことが肝心です。
まとめ
最低取得すべき年間休日数の基準は、労働基準法で決められています。フルタイム勤務の場合、最低105日です。ただし、短時間勤務や36協定を締結している場合、105日より少なくても適法となることがあります。
企業全体の平均年間休日数は112.1日ですが、休日数は業種によって大きく異なるようです。厚生労働省の調査では、休日数が多い業界と少ない業界の差は約20日にのぼります。
また、間違えやすい表現に「完全週休2日制」と「週休2日制」があります。週休2日制は、毎週必ず2日休めるわけではなく、週1日しか休めない週もあるので注意しましょう。
自分に合った休日数は、長く働き続けるために重要な要素です。就職・転職の際は自分の希望と求人票の「年間休日数」をよく照らし合わせて、納得のいく選択をしましょう。