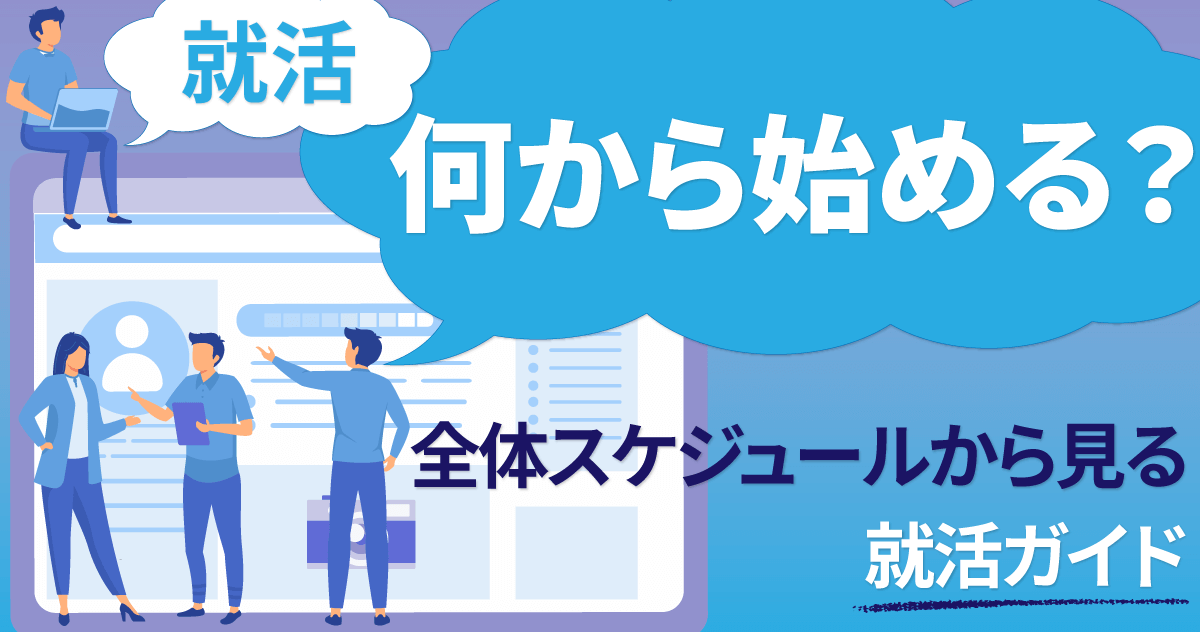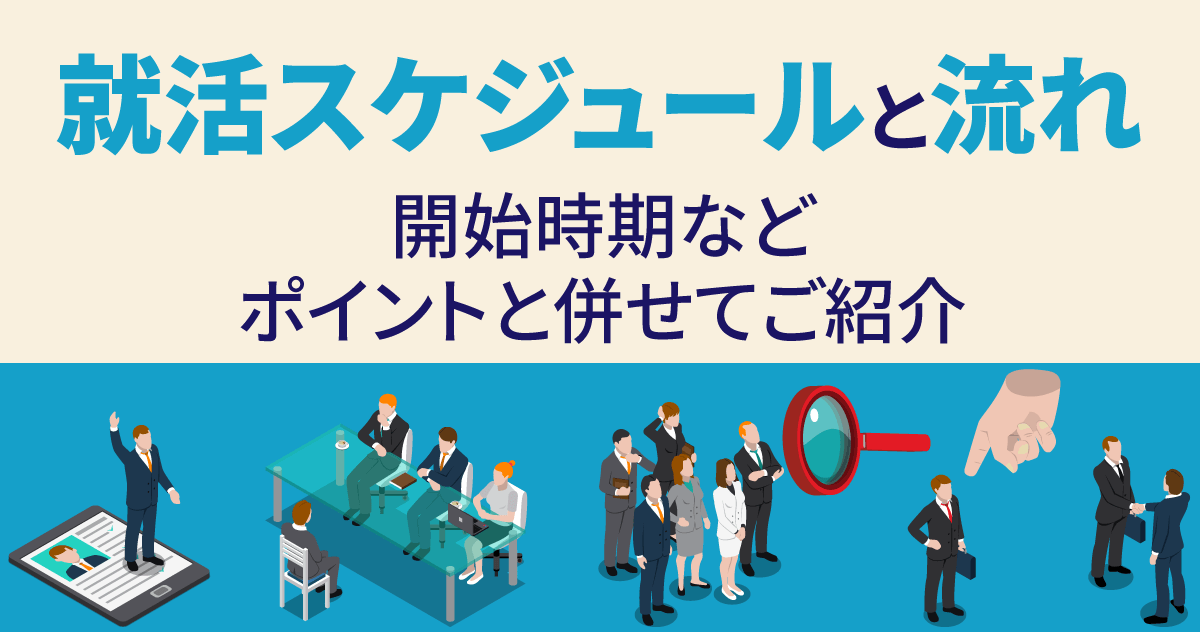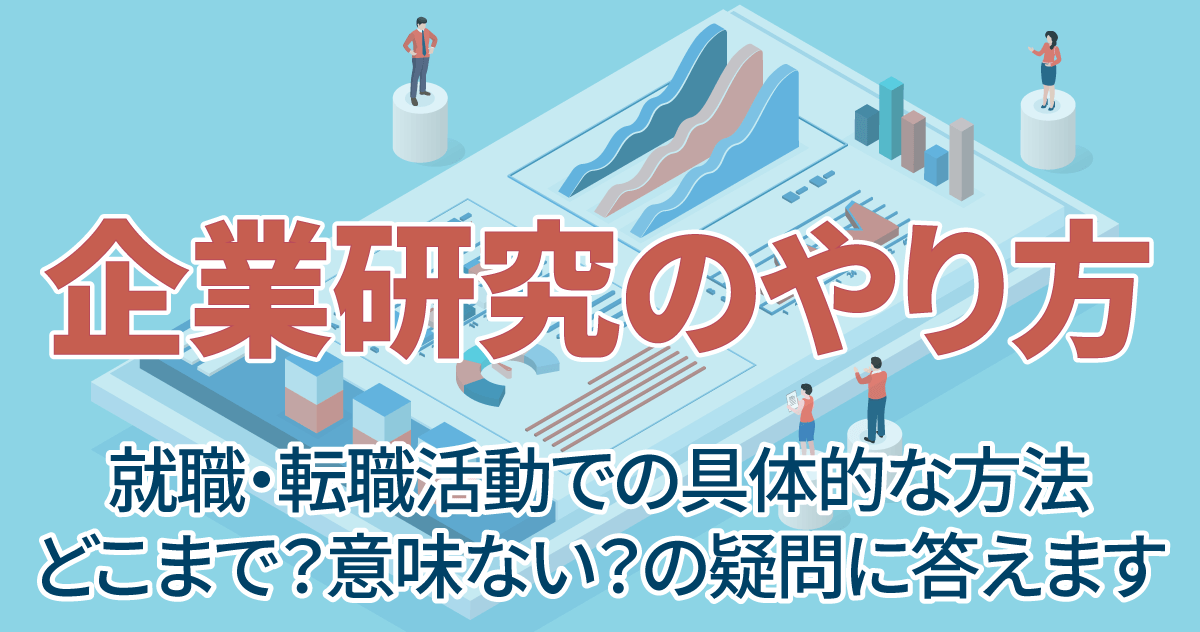就活ノートの作り方完全ガイド!内定につなげる活用法

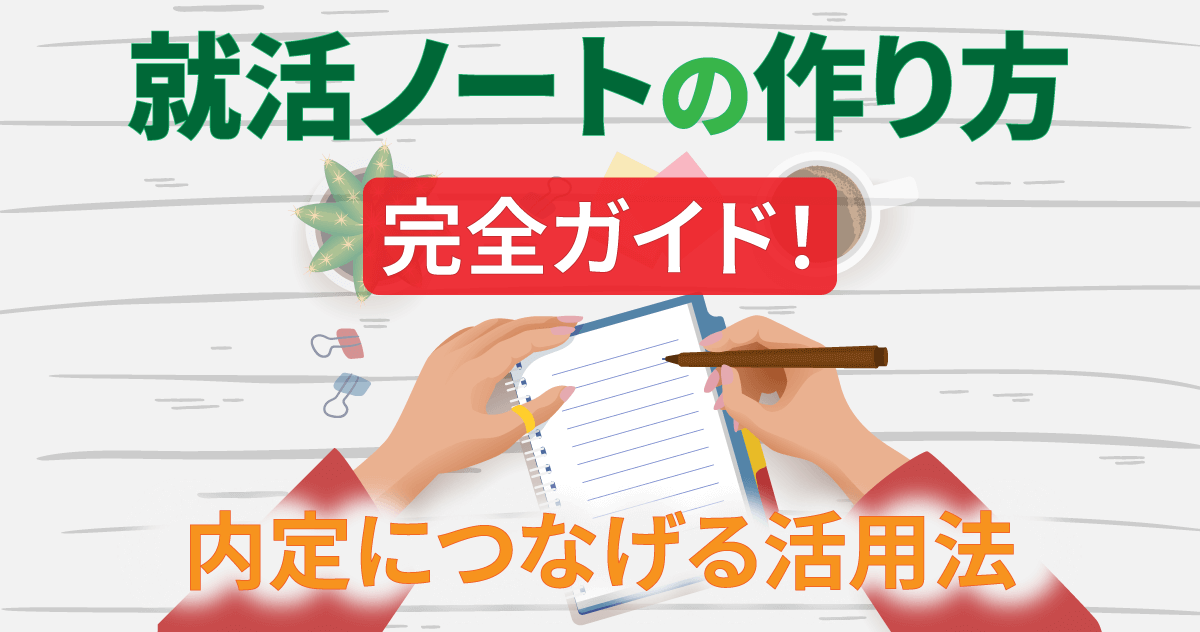
はじめに
- 「就活ノート」とは企業情報や就活スケジュールを記録・整理するためのノートである
- 企業ごとに情報を書くことで他企業との比較ができる
- 自己分析や他己分析を客観的な視点で実施できる
- 就活ノートは大学3年生の6~7月頃に作成を始めるのがおすすめである
- 「企業分析」「就活スケジュール」「就活記録」の項目に分けて書くと効果的である
大学生や転職を考える方が就活を始める際には、「就活ノート」の活用が内定を勝ち取るための鍵です。就活をスムーズに進めるには、就活ノートの重要性を理解し、記載内容を把握しておくことは重要なことでもあります。本記事を参考に、分かりやすく上手なまとめ方で就活ノートを作成してみましょう。
就活ノートとは
「就活ノート」とは、就活において志望企業の情報や就活スケジュールなどを記録・整理するためのノートを指します。企業説明会やセミナーなどで得た情報を一目で確認できるようにすることは、就活においては必要不可欠です。また、就活は時間に限りがあるため、スケジュール管理の工夫も重要でしょう。
就活ノートの重要性とメリット
就活における就活ノートの必要性と、具体的なメリットについて説明します。
就活ノートの重要性
就活では、面接から内定までに多大な労力や時間、精神的な負担がかかります。計画性がないと交通費などの金銭的コストも無駄にかさんでしまいます。やみくもに多くの企業にアプローチすることはかえって混乱を生む原因になりかねません。そのため、「就活ノート」は効率的に内定を獲得するための重要なツールといえます。
就活ノートのメリット
就活ノートを作成すると、以下のようなメリットがあります。
- ➀ 就活スケジュールを一覧で把握できる
- ② 企業ごとの情報の分析と比較が容易になる
- ③ 自己分析・他己分析を通じて客観的な視点が得られる
- ④ インターンや面接前にすぐ見返しができる
- ⑤ 就活のモチベーション維持・向上につながる
就活ノート作りはいつから始める?
就活ノートの作成開始時期は、インターンの申し込みが始まる大学3年生の6~7月頃が適切です。ただし、あまり早くから就活ノートの作成を始めてしまうと、企業情報や財務状況の変動に対応しきれない可能性があります。そのため、インターンシップや企業見学などで得た情報を記録していく観点から、大学3年生の夏の時期から始めるのが最適といえます。
就活ノートに記載する項目
就活ノートのポイントは、4つあります。「スケジュール」「企業」「選考」「自分自身」を意識して書くと、振り返る際にどの項目にあるかすぐ見つけられるでしょう。4つのポイントを踏まえて、就活ノートに記載すべき項目を説明します。
企業分析
企業や業界の状況は変化しやすいため、特徴と将来の動向をまとめておきましょう。最終的に志望先をしぼれるように、以下の内容で整理してみてください。
- 企業の基本情報(企業名・代表者・設立年度・資本金・経営理念)
- 企業の成長性や財務状況
- 企業の市場規模や従業員数
- 企業の労働条件(給与・昇給・勤務地・勤務時間・年間休暇)
- 競合他社との比較(強み・弱み)
就活スケジュール
就活では複数の選考が同時進行するため、書類の提出期限や面接の日時、場所を忘れてしまうこともあります。これを防ぐためにも、スケジュール管理は就活において重要です。以下の内容を集約して書くと良いでしょう。
- 企業説明会の日程
- 企業セミナーの日程
- エントリー申し込みの期限日
- エントリーシートの提出期限日
- Webテスト実施日
- 面接の日時や会場
就活記録
インターンシップやOB・OG訪問に参加した際は、職場の雰囲気や印象に残ったことを就活ノートに記録しておくと良いでしょう。実際の社員の働き方について、記憶が新しいうちに以下の項目を参考に記録しましょう。
- インターンシップの内容(担当者名・提出書類の記録)
- 企業説明会・セミナーの内容(質疑応答)
- エントリーシートの記載内容(結果・反省)
- 面接試験の内容(形式・レベル・質疑応答・結果・反省)
作り方のポイント
就活ノートは、必要な情報を整理して記載することが重要です。就活にかかる負担を減らすためにも、内定獲得に向けた効果的な作り方のポイントを説明します。
1冊に内容をまとめる
複数に分けたノートをすべて持ち歩くのは、情報を探す手間が増えてしまいます。就活ノートは1冊にまとめておくと、必要な情報にすぐアクセスでき、ノートの管理もしやすくなるでしょう。
テンプレートを活用する
前述の就活ノートに記載する項目で説明したように、決めておいた項目をテンプレート化して活用する方法があります。市販の就活ノートや関連書籍には、就活に特化したテンプレートが付録として含まれているものもあり、初心者でも活用しやすくなっています。また、厚生労働省のホームページでは無料の自己分析テンプレートを提供しているので、これを参考に自分に合った形式にカスタマイズするのもおすすめです。
参考:厚生労働省|自己分析ワークシート活用
情報は細かすぎず、簡潔に書く
情報を詰め込みすぎると、重要なポイントが埋もれてしまい、混乱の原因になります。作成時は適度な粒度で、シンプルかつ簡潔にまとめましょう。箇条書きを活用すると、後で見返す際に確認しやすくなります。
情報はインデックスで整理する
企業ごとにインデックスシートで区切り、必要な企業情報をすぐ探せるようにしましょう。また、手帳や就活ノートのように製本になっているものはインデックスシートを使えないため、インデックスシールを活用して企業名と情報に分けておくとすぐに見つけられます。
就活ノートのおすすめタイプ
就活ノート選びで何に注目したら良いか迷う人もいるでしょう。以下では、4つのおすすめタイプについて、それぞれの特徴とメリットを詳しく説明します。
手帳タイプ
A6やA8サイズのポケット手帳は、コンパクトで持ち運びに便利です。マンスリーとウィークリー両方の予定表がついているものや、メモ用のフリースペースが充実しているものがおすすめです。また、名刺を収納できるポケット付きの手帳は、特に企業訪問時に重宝します。
ルーズリーフタイプ
ルーズリーフは、製本された手帳や就活ノートと比べて、カスタマイズ性の高さが特徴です。必要に応じてページを追加できるため書き込みスペースの心配がなく、ページの入れ替えも自由自在です。さらに、サイズも自分の用途に合わせて選べるため、就活生にとって使い勝手の良いアイテムといえます。
市販の就活ノート
文房具店やオンラインショップでは、就活に特化したノートが販売されています。ページが上下に分かれたセパレート仕様など、使いやすさを追求した工夫が施されているものも見られます。企業研究とスケジュールを一元管理できるものもあるので、自分のニーズに合ったノートを選びましょう。
就活アプリ
手帳やノートと違って、スマートフォンやクラウド上で管理できる就活アプリは、Yahoo!やGoogleのスケジュール機能との連携ができるものもあります。また、検索機能を使えば、インデックスなしですぐに必要な情報にアクセスできます。ただし、企業の面接や施設見学時にスマートフォンを使用すると、マナーが悪いと判断されることがあるため、必要のない場面では使用を控えましょう。
まとめ
就活ノートの重要性と活用方法について理解できましたか? 志望先の内定を勝ち取るにはまず、企業の情報収集やスケジュール管理から始める必要があります。就活ノートを活用することで、企業分析の比較や振り返りが容易になるだけでなく、自己分析を客観的に行うことができ、就活へのモチベーションも高まるでしょう。
就活を成功に導くために、大学3年生の6~7月には就活ノートの活用を始めることをおすすめします。しっかり準備を進め、志望企業の内定獲得を目指しましょう。