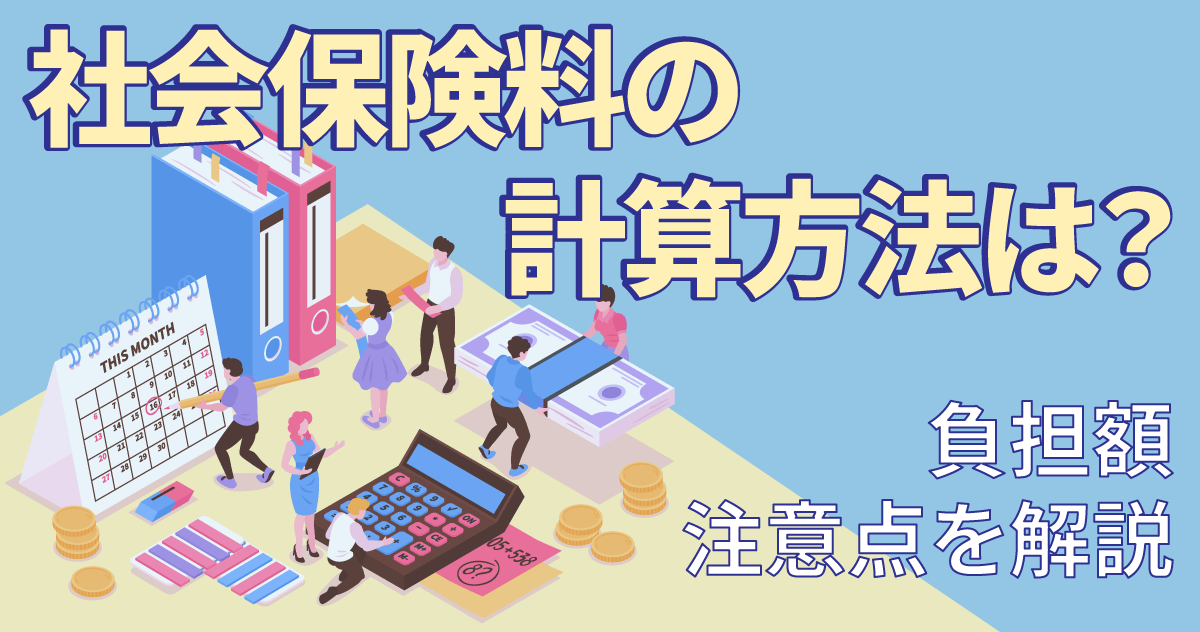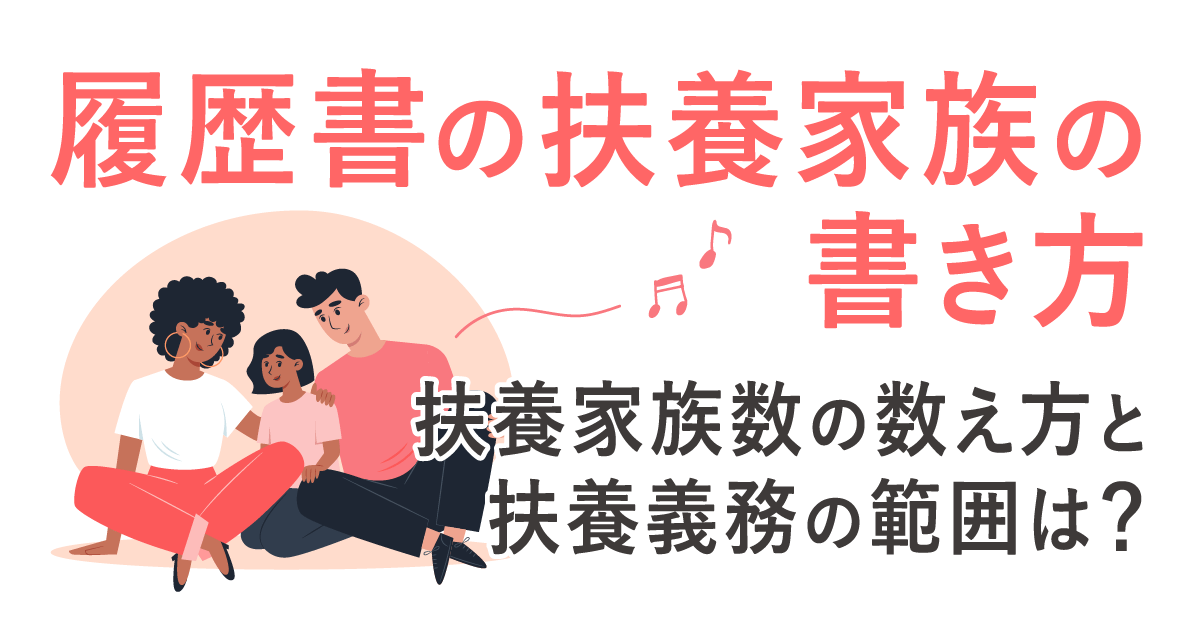社会保険と国民健康保険の違いとは?選び方をわかりやすく解説!

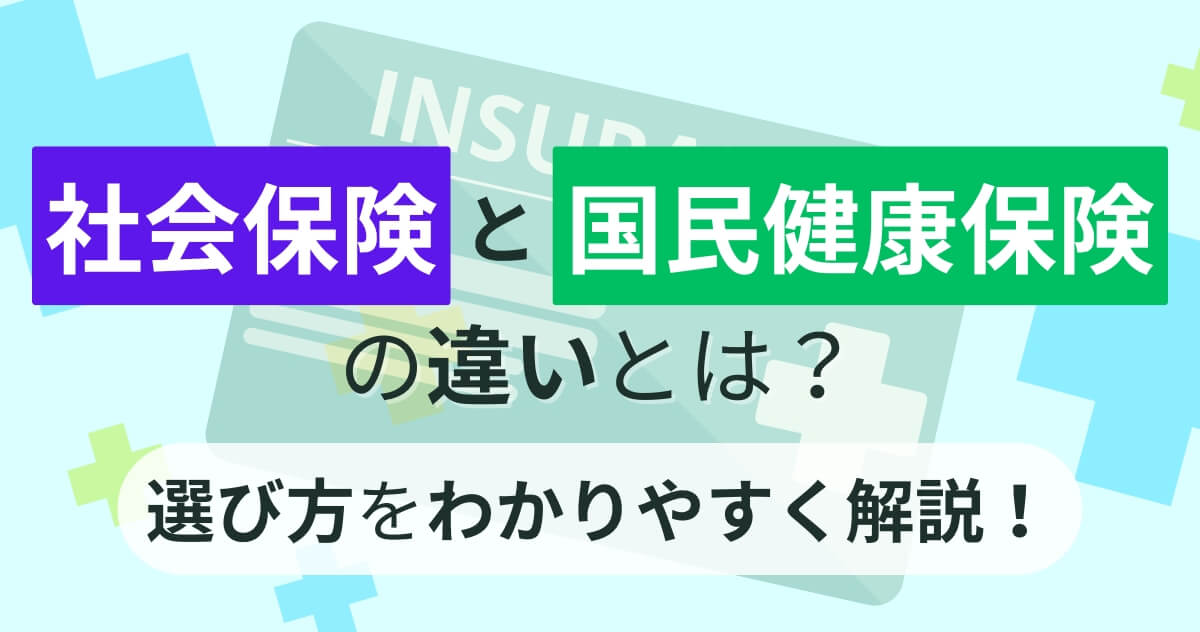
はじめに
- 社会保険の加入対象者は公務員や正社員、条件を満たした非正規社員
- 社会保険(健康保険)の運営は、全国健康保険協会や健康保険組合などが行う
- 短時間労働者は所定労働時間や日数など、社会保険(健康保険)の加入条件が異なる
- 国民健康保険は社会保険の未加入者が対象で、生活保護受給者は対象外
- どちらに加入するかを労働者側が選ぶことはできない
就職が決まった際に加入手続きを行う社会保険とは何か、国民健康保険と何が違うのか、疑問に感じた人も多いのではないでしょうか。この記事では、社会保険と国民健康保険それぞれの概要と、大きく違う点についてご紹介します。
社会保険とは
社会保険とは「健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険」の5つある保険種類の総称です。正社員や公務員、一定の条件を満たした非正規社員などを対象とした公的な強制保険制度です。社会保険に加入する条件を満たしている場合は、社会保険への強制加入となります。被保険者のケガや失業などといったさまざまなリスクに備えるために、厚生労働省・日本年金機構などによって運営されており、万一のことがあった際に給付が行われます。
社会保険の種類
社会保険は、前述したように5種類の保険制度から成り立っています。それぞれの保険制度の概要を表にまとめました。
| 健康保険 | 被保険者とその家族が病気・ケガをした場合に、治療などを受けられるように支援する制度のこと。「全国健康保険協会(協会けんぽ)」「健康保険組合」などに加入し、保険料を支払うことで制度が利用できる。 |
|---|---|
| 厚生年金保険 | 従業員が将来に備えるための公的な年金制度のこと。健康保険と同様に保険料を支払う必要があり、老後の年金額を増やしたり、障害年金などを受給したりできる。また、加入者が死亡した場合、遺族に支払われる遺族年金もある。 |
| 介護保険 | 介護が必要な人を社会全体で支えて、少ない負担額で介護サービスを受けられるようにする制度のこと。40歳以上の国民が支払う介護保険料と、国や自治体の予算を財源として成り立っている。 |
| 雇用保険 | 労働者に失業や育休などの事由が発生した際、条件を満たしていれば手当や給付が受けられる制度のこと。週の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある、非学生が加入対象にあたる。 |
| 労災保険 | 業務上または通勤時の事故や災害によるケガ、業務に起因する病気・障害などに対し、補償や社会復帰支援などを行う保険制度のこと。企業は、雇用が1人だけだとしても保険に加入しなくてはならない。 |
このうち「健康保険・厚生年金保険・介護保険」の3つを狭義の社会保険、残りの「雇用保険・労災保険」の2つを労働保険と呼ぶことがあります。
国民健康保険とは
国民健康保険も社会保険と同じく公的な強制保険制度であり、被保険者のケガや病気といったリスクに備えるため、加入者(被保険者)が保険料を出し合って医療費に充てる、相互扶助の制度です。
以下に該当する人を除いた、全日本在住民が加入対象です。
- 他の医療保険(健康保険)に加入している人、その被扶養者
- 生活保護受給者
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 短期滞在在留外国人など
国民健康保険の運営団体は、市区町村など地方自治体が主体となっています。自治体ごとに保険料や給付内容が異なるため、保険料の詳細やどのような給付があるか知りたい場合は、居住地域の役所に確認する必要があります。
土木・建築関係や開業医などの一部職種に該当する場合、職種ごとの国保組合が運営する国民健康保険への加入が可能です。
社会保険と国民健康保険は何が違う?
社会保険と国民健康保険は、加入条件や対象者、運営元など違う点が複数あります。
主に違う点は、以下の5点です。
- 加入条件
- 対象者
- 運営元
- 保険料の算出方法
- 扶養の有無
各項目を簡潔にまとめたものが以下の表です。
※タップで詳細が開きます
| 社会保険(健康保険) | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
ここからは、上記の表にまとめた各項目の内容について、一つずつ詳しくご紹介します。
加入条件
基本的に、すべての企業には社会保険制度への加入義務があります。社会保険に加入した企業は「適用事業所」と呼ばれ、該当する企業に雇用されている従業員は、試用期間中の従業員も含めて全員に社会保険への加入義務が発生します。ただし、時短勤務や契約社員、パート・アルバイトなど短時間労働者の場合は、週の所定労働時間および月の所定労働日数によっては、加入対象外となる場合があります。
ご自身が対象か確認したい場合は、以下の加入条件をご参照ください。
従業員が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する条件
- 75歳未満の正社員および企業の代表・役員など
- 週の所定労働時間および月の所定労働日数が、通常の正社員の4分の3未満であっても、以下の5つを満たす短時間労働者
- 勤務先の厚生年金保険の被保険者数が51人以上いる企業である
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 雇用期間が2ヵ月を超える見込みである
- 残業・賞与等を除いた月額給与が8.8万円以上である
- 学生ではない(夜間・通信制の学生は除く)
※厚生年金保険は70歳、健康保険は75歳で被保険者資格が喪失する
参考|適用事業所と被保険者:日本年金機構
個人事業主やフリーランス、無職などの理由で上記の加入条件を満たせなかった場合は、国民健康保険に加入することになります。土木・建築関係や開業医などの職種の場合は、職種ごとの国保組合が運営している国民健康保険があるため、そちらを選択することも可能です。
ただし、生活保護を受けている場合は別の医療費補助制度があるため、国民健康保険に加入できません。
対象者
社会保険と国民健康保険では、加入対象者も異なります。社会保険への加入対象者は、以下3点のうち、いずれかに該当する人が対象です。
- 75歳未満の正社員および企業の代表・役員など
- 週の所定労働時間および月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務に従事する正社員の4分の3以上
- 正社員の4分の3未満であった場合に、所定の条件を満たす短時間労働者
一方、国民健康保険は社会保険の対象外である74歳以下の人や、個人事業主やフリーランス、年金受給者など他の医療保険制度に加入していない人が対象です。ただし、該当していたとしても、社会保険に加入している家族に扶養されている場合は、加入の対象外です。
運営元
社会保険の健康保険は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」や「健康保険組合」が運営を行っています。
一般的な国民健康保険は市区町村などの地方自治体が運営を行っており、土木・建築関係や開業医など一部の職種は、前述したように職種ごとの国保組合に運営されています。該当職種であれば選択可能ですので、選択する前に運営元の情報を確認しておくといいでしょう。
保険料の算出方法
社会保険の保険料は、標準報酬月額や手当・賞与、被保険者の年齢から算出できます。
標準報酬月額の算出は、毎年4~6月の3か月間の給料の平均額を基にしており、残業代や通勤手当など、労働の対償として事業所から支給される各種手当も含まれています。ボーナスや決算手当は、年に4回以上支給される場合は算出に含まれますが、年3回以下であれば含まれないため、支給回数を確認しておくといいでしょう。
また、40歳以上になると介護保険への加入義務が発生し、社会保険料として毎月の給与と賞与から介護保険料が天引きされます。
国民健康保険の保険料は、総所得額から算出される「所得割額」と、世帯人数から算出される「均等割額」の合計額から決まります。「所得割額」は自治体ごとに掛ける保険料率が異なるため、居住地域によって差があります。「均等割額」は世帯人数が多いほど、保険料も上がると考えておくといいでしょう。
また、自治体によっては一定額を全世帯で等しく負担する「平等割」も算出に含まれることがあります。保険料がいくらになるか詳しく知りたい場合は、居住する地域の国民健康保険料を確認するといいでしょう。
扶養の有無
社会保険では、加入者の配偶者や子どもなど、家族を扶養に入れることが可能です。ただし、扶養に入っている人の年収が130万円を超えてしまうと、扶養から外れるため、その人自身で保険に加入しなければなりません。また、短時間労働者であっても社会保険の加入条件を満たした場合は、扶養に入れられないため、注意が必要です。
一方の国民健康保険には、扶養の概念がありません。世帯ごとではなく一人ひとりが被保険者として扱われるため、個々に保険料の支払いが必要です。そのため、世帯全体の保険料が高くなりやすい傾向にあります。ただし、土建国保や医師国保と呼ばれるような職種ごとの国民健康保険では、扶養に近い制度があり、世帯で加入が必要となる場合があります。
参考:被扶養者とは?|全国健康保険協会
参考:家族の加入について|東京都土木建築健康保険組合
社会保険と国民健康保険は選べる?
本人が社会保険か国民健康保険かを選ぶことは出来ません。
正社員もしくは必要条件を満たした短時間労働者は、社会保険への加入が義務付けられています。そのため、社会保険への加入を拒めません。加入義務のある従業員が加入しない場合、企業が罰則を受けたり、本人も未納期間が発生したりとデメリットが多くなりますので、条件を満たした場合は拒まずに加入しましょう。
また、国民健康保険は、通常「社会保険に加入していない人」に加入が義務付けられています。前述した、一部職種の人が加入できる国民健康保険組合も国民健康保険の一種です。
社会保険(健康保険)に切り替える際の手続き方法
多くの企業では社会保険への加入義務が発生するため、国民健康保険に加入している場合は社会保険への切り替え手続きが必要となります。企業側・従業員側の双方で必要な手続きがありますので、それぞれの手続きについてご紹介します。
従業員は、企業の手続きに必要なものの提出も求められるため、やるべきことが多くなりがちです。ミスのないよう一つひとつ確認して、手続きに臨みましょう。
企業側の手続き
新しく従業員を雇用する企業は、対象従業員の入社日から5日以内に従業員の「被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出し、社会保険加入手続きを行う必要があります。雇用する従業員に扶養家族がいる場合には、扶養家族分の「健康保険被扶養者(異動)届」の提出も必要です。
労働者側の手続き
労働者は、社会保険へ加入するにあたって、国民健康保険から脱退する手続きが必要になります。国民健康保険をやめる手続きは自動で行われないため、就職先の保険に加入した日から14日以内に、住んでいる自治体の役所で手続きを行いましょう。
必要となる書類は以下の6点です。
- 国民健康保険証または国民健康保険資格確認書
- 職場で新しく発行された健康保険証または健康保険資格確認書
(国民健康保険を脱退する全員分必要)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 世帯主のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
- 各役所にある国民健康保険異動届
マイナ保険証の場合は、マイナンバーカードと資格情報通知書(資格情報のお知らせ)があれば手続き可能です。マイナンバーカードとマイナポータルの健康保険資格情報画面を印刷したものでも、同様に手続きできます。ただし、自治体によっては手続きに時間がかかってしまう場合もありますので、上記の書類も用意しておくとスムーズに進められるでしょう。
まとめ
社会保険は「健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険」の5種類から成り立つ公的な強制保険制度です。正社員や一定の条件を満たした非正規社員が加入対象で、病気やケガなどのリスクに備えることが可能です。社会保険の健康保険は「全国健康保険協会」や「健康保険組合」によって運営されます。国民健康保険は、社会保険に加入していない人を対象にした公的な保険制度で、市区町村などが運営元です。
社会保険と国民健康保険は加入対象者や運営元以外にもさまざまな違いがあり、社会保険に加入する条件を満たしているかどうかで、どちらに加入するか決まります。選ぶことはできないため、必要な加入手続きはしっかりと行いましょう。