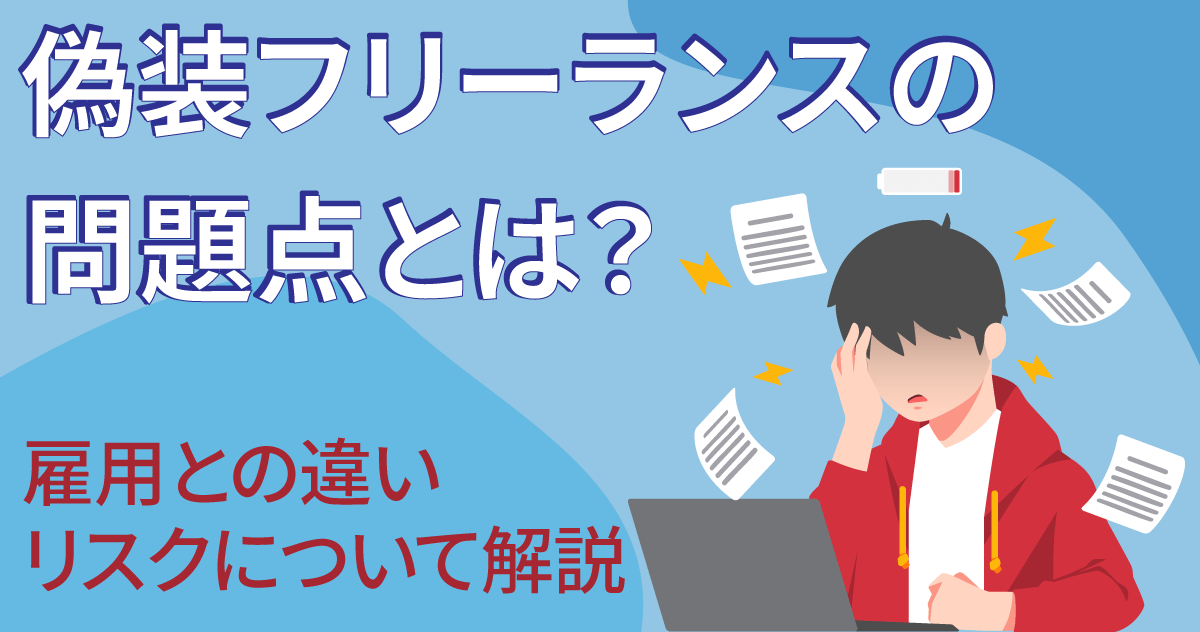業務委託と個人事業主の違いとは?メリット・デメリットを徹底解説

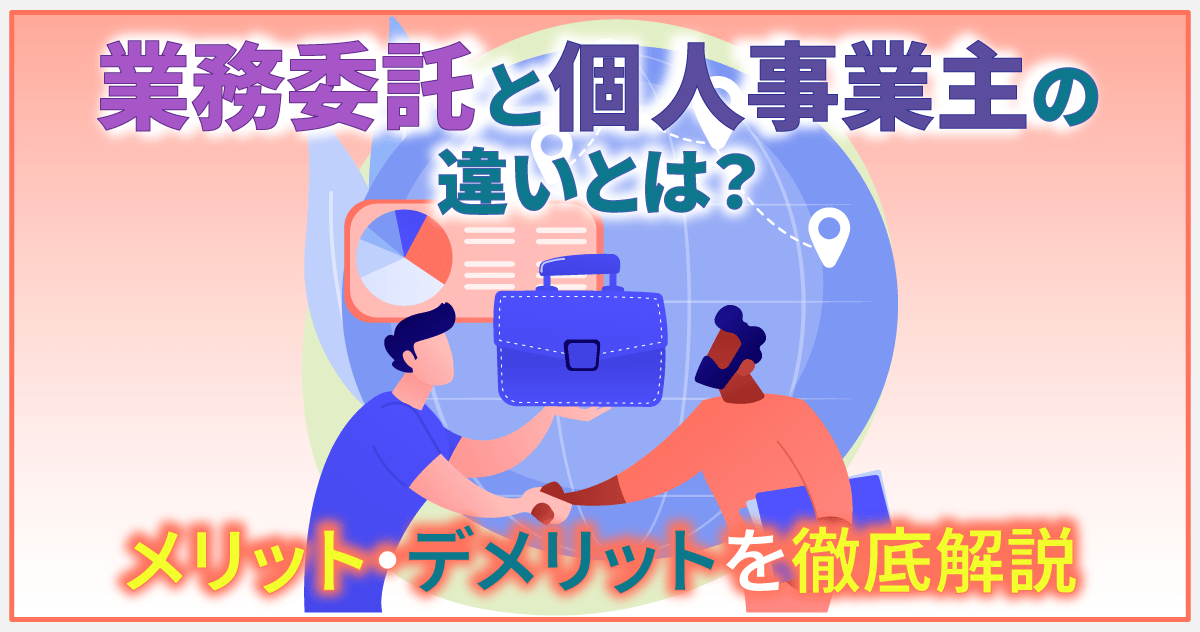
はじめに
- 個人事業主とは法人をつくらず個人で事業を営む者を指す
- 業務委託とは個人事業主が業務を請け負うときのひとつの契約形態である
- 業務委託は成果物に、準委任契約では業務遂行のための作業に報酬が発生する
- 個人事業主は契約・報酬・税金・社会保障などさまざまな面で会社員と違いがある
- 業務委託で働くときは契約内容をよく確認し、成果物の著作権の所在を確認しよう
業務委託と個人事業主の違い
業務委託とは、個人あるいは企業が仕事を請け負う際の契約形態のひとつです。
個人事業主は個人が独立して事業をおこなう形態のひとつです。それぞれ解説します。
業務委託とは
業務委託とは、企業や個人が、業務の一部またはすべてを外部委託することを指します。業務委託は契約形態の一呼称です。したがって、企業の業務を個人が請け負うこともあれば、企業間で業務委託を請け負うこともあります。また、個人の業務を別の個人が請け負うことも業務委託にあたります。
業務委託を個人が請け負う場合、会社員のような雇用契約ではなく、業務委託契約を締結します。業務委託契約はおもに2つの形態があります。
- 請負契約
成果物に対して報酬が発生する形で委託者と受託者が結ぶ業務契約を指す。
- (準)委任契約
業務の遂行を目的に、作業に対して報酬が発生する契約形態である。委任契約、または準委任契約と呼ばれる。
- → 委任契約
弁護士や税理士など法律に抵触する業務をおこなう者に業務を委託し、受託者が遂行する
- → 準委任契約
法律に抵触しない業務を委託、受託者が遂行する。たとえば、ITの業務請負は準委任契約となる。
- → 委任契約
個人事業主とは
個人事業主とは、法人をつくらずに個人で事業を営む人のことです。税務署に開業届を提出することで個人事業主となります。
個人事業主の職業の例としては、飲食店や服飾店などの店舗経営、弁護士や税理士といった士業、開業医、独立して仕事を請け負うコンサル業やエンジニア、漫画家やイラストレーターといったクリエイターなどです。成果物や商品を納品して報酬を得るため、働き方については自分で自由に決められます。
個人事業主と会社員の違い
この項では個人事業主と会社員との違いを詳しく解説します。
報酬の違い
会社員は、企業と雇用契約を結んで業務に従事する働き方です。企業の業務指示に従って働き、賃金が定期的に支払われます。契約で決められた時間に働き、残業をする場合には労働基準法で決められた割増賃金が支払われます。
個人事業主は、企業に提供した成果に対して報酬を得ます。能力が高ければ、会社員と比較してかなりの高収入を得られる可能性があります。
税金の違い
個人事業主は、税金の面で会社員とは違いがあります。
- 所得税の納税方法が違う
個人事業主は、会社員と違って年末調整や所得税天引きの仕組みはない。したがって、個人事業主は毎年自ら確定申告をおこない、所得税を支払う必要がある。
社会保障における違い
社会保障の面においても、会社員と比較して個人事業主は大きな違いがあります。
- 社会保障面
社会保険とは、会社員に加入義務がある健康保険(および介護保険)・厚生年金・労働保険・雇用保険のこと。ただし、個人事業主として生計を立てている場合は一部の社会保険に加入できない。
- 健康保険
日本では国民皆保険制度をとっており、国民はいずれかの健康保険に加入しなければならない。
会社員は、所属企業が運営する組合健保、または中小企業のために運営される協会けんぽという健康保険のどちらかに加入する。個人事業主は国民健康保険に加入する。
また、会社員と個人事業主では、健康保険の保険料にも違いがある。会社員の保険料は所属企業と本人との折半となるが、個人事業主は全額負担である。 - 年金
年金制度は、いわゆる2階建てのつくりになっている。国民全員が加入する国民基礎年金と、会社員が国民基礎年金に加えて加入する厚生年金のふたつが運用されている。
つまり、個人事業主は国民基礎年金のみに加入するが、会社員は、国民基礎年金と厚生年金の両方に加入することになる。このため会社員は、納める年金の額は大きいが、その分将来のもらえる年金の金額も増える仕組みだ。
厚生年金に加入している会社員と比較して、国民基礎年金のみの個人事業主では将来もらえる金額がかなり少なくなるので注意しよう。 - 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業し収入がなくなったときに、失業手当をもらえる国の制度だ。
会社員は、一定の基準を満たすと雇用保険への加入義務が生じる。加入期間が通算12か月以上あれば、失業時に失業手当がもらえる。しかし、個人事業主は、雇用保険に加入できないため、もし失業しても失業手当はもらえない。 - 労災保険
労災保険は、労働者が通勤または業務中に怪我・病気などをした際に保険金が給付される制度で、会社員は加入必須である。一方、個人事業主は原則として労災保険に加入できないが、労働者と同様に保護されるべき立場として、一人親方など一部の個人事業主には、特別加入制度による任意加入が認められている。さらに、2024年11月からは「フリーランス新法」の施行により、特定のフリーランスも特別加入の対象に加わった。
- 健康保険
参考:厚生労働省 – 令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました
- 法律面
個人事業主は労働基準法の適用外となる。なぜなら、労働基準法は会社員を守るための法律だからだ。つまり、個人事業主には最低賃金や残業の概念は適用されず、6時間以上の労働には休憩が義務付けられることもない。 また、なかには悪質な企業(委託者)も存在し、なかなか報酬が支払われないなどのトラブルも頻発している。しかし、こういったトラブルの解消を目的に2024年11月からフリーランス新法という法律が施行された。詳しくは厚生労働省のページを確認しよう。
参考:厚生労働省 – フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
業務委託の注意点
業務委託で仕事を請け負う際、注意すべきポイントを解説します。
偽装請負に気を付ける
準委任契約は、委託者と受託者の契約であるため、会社員のように上司の指示に従って動く必要はありません。
しかしながら、実際の現場では、委託者である企業から、仕事のやり方をまるで部下のように指示されるケースがあります。これはいわゆる偽装請負にあたり、違法行為となります。このような働き方をするのであれば、会社と雇用契約を結ばなければいけません。
法律では実際の業務形態を重視するため、契約書上は準委任契約となっていても実態が上司の指示に従うような働き方であれば法律違反とされます。
業務内容をよく確認する
業務委託を請け負う場合、どこからどこまでが自分の業務範囲かは、契約書に記載されている内容に準じます。この点をあいまいにすると、自分の仕事の範囲がどこまでかがわからず、トラブルにもつながりかねません。
業務範囲はきちんと相談の上で決定し、契約書にも業務内容の範囲を明確に記入することが大変重要です。
2024年11月に施行されたフリーランス新法を確認しておきましょう。
参考:公正取引委員会 – 公正取引委員会フリーランス法特設サイト
著作権が誰に帰属するか必ず確認をする
著作権とは、その作品をつくった人が持つ権利です。著作権を持たない者は、その作品を勝手に使用したり、販売して報酬を得たりすることはできません。これらの行為をおこなうためには、著作権者の承諾が必要です。
業務請負は完成した成果物として納品し、対価に報酬をもらいますが、この成果物について著作権はどちらものものかという問題があります。
結論からいうと、業務請負の場合は、契約により、依頼した企業(委託者)に成果物の著作権が帰属することが多いようです。しかし、双方相談の上、制作者(受託者)に著作権が帰属する契約にすることも可能です。
とくにクリエイター系フリーランスの間では、著作権物の問題でよくトラブルになっています。著作権について認識があいまいな場合は、成果物の著作権が誰に帰属するのか、契約締結のときに契約内容をよく確認するようにしましょう。
まとめ
個人事業主とは、法人をつくらずに個人で事業を営む人のことです。業務委託とは、企業や個人が、業務の一部またはすべてを外部委託することを指します。
つまり、個人事業主が業務を請け負うときの契約形態のひとつが業務委託です。
個人事業主は、会社員と比較して、報酬面、税金面、社会保障面でさまざまな違いがあります。会社員は毎月安定した収入を得られ、手厚い社会保障があります。対して個人事業主は、契約単位で報酬が発生するため月々の収入は不安定になりやすく、社会保障も薄いです。ただし、個人事業主の権利を保護する目的で、2024年11月にフリーランス新法という法律が施行されました。
個人事業主は、トラブルが起きても自分ですべて対応しなければならないため、契約書の内容をきちんと把握しておくことは非常に重要です。とくに業務委託契約では、偽装請負という違法な労働形態に陥る可能性があるので、契約書の業務内容はよく確認しておきましょう。