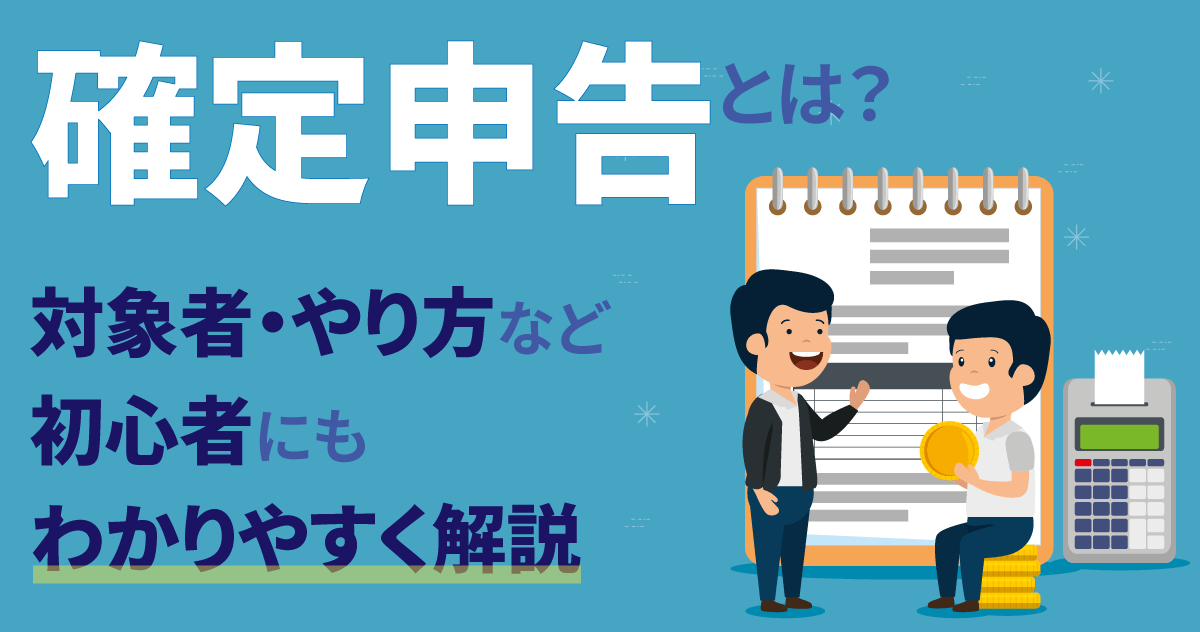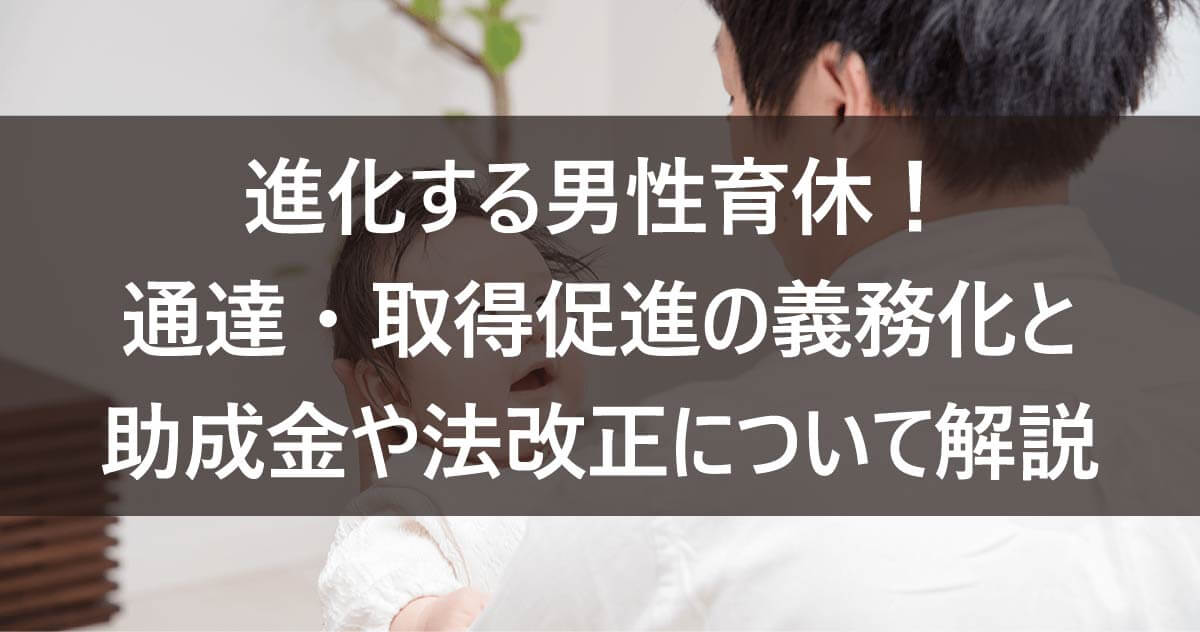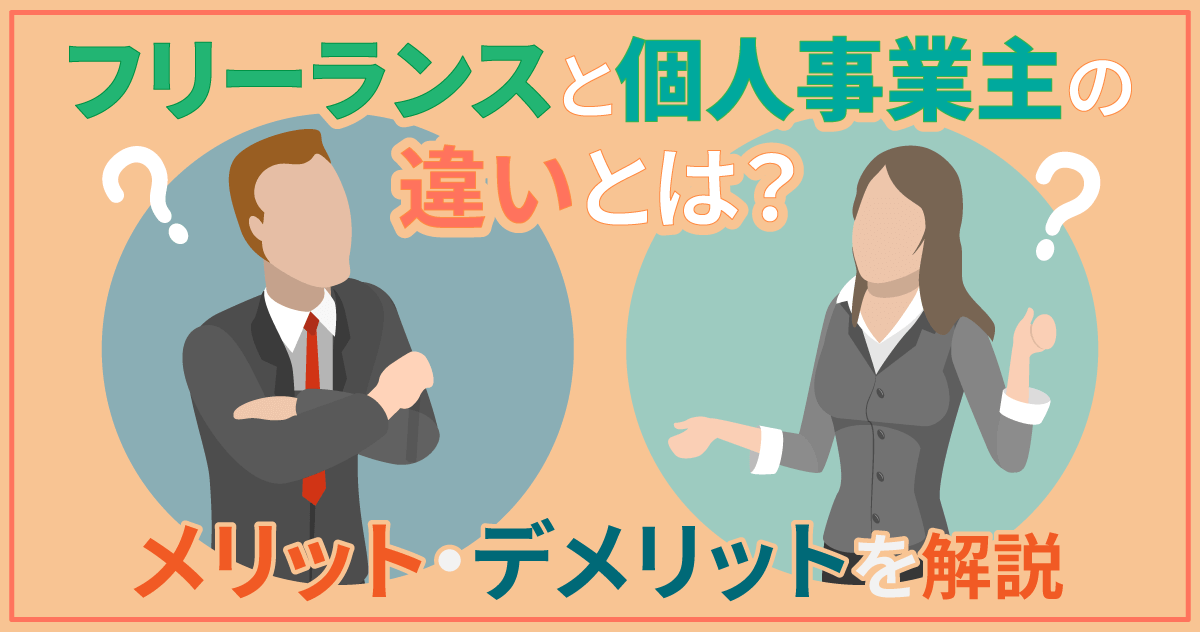個人事業主が活用できる補助金とは?種類や申請方法を解説


はじめに
- 補助金とは、国や地方自治体が企業・個人事業主に支給する資金のこと
- 社会問題の解消や、経済活性化を推進することが目的
- 補助金にはさまざまな種類があり、対象者・受給要件・申請方法などが異なる
- 国だけでなく、地方自治体ごとにも補助金制度が実施されている
- 申請したからといって、必ずしも採択されるとは限らない
補助金とは?
補助金とは、国や地方自治体が、企業や個人事業主を支援するために支給する資金のことです。補助金の支給により、社会問題や環境問題の解消・経済活性化を推進することが目的です。
多くの補助金は、申請・審査を経て採択された場合のみ受給できます。採択件数や金額などは、はじめから決まっている場合が多いため、申請しても受給できるとは限りません。
また、多くの補助金は所得税・法人税などの課税対象となるため、基本的には確定申告を行う必要があります。
助成金・給付金との違いは?
助成金と補助金は、意味も目的もほぼ同じです。
助成金は補助金と同じく、国や地方公共団体が企業や個人事業主などに支給する資金のことです。
社会問題や環境問題の解消・経済活性化の推進を目的としています。
補助金と異なる点は、基本的に、要件を満たせば受給できることです。
一方、給付金とは、国・地方公共団体が個人・世帯に対して支給する資金のことです。
主に、貧困家庭への生活支援や災害時の救済措置など、特定の条件を満たす場合に支給されます。
給付金は、事業活動を支援する補助金・助成金とは異なり、一時的な救済措置として給付されるケースが一般的です。
個人事業主も利用できる代表的な補助金
以下では、個人事業主も利用できる代表的な補助金を6つ紹介します。
1.小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)とは、小規模事業者・個人事業主などが販路開拓に必要な経費の一部を国が補助する制度のことです。
通常枠と特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)があり、いずれか1つの枠のみ申請できます。
通常枠とは、自らが作成した経営計画に沿って、販路開拓や事業拡大の取り組みを行う小規模事業者への支援枠のことです。通常枠の補助上限額は50万円ですが、インボイス特例の要件を満たせば、補助上限額に50万円を上乗せして申請できます。
2.IT導入補助金
「IT導入補助金」とは、中小企業・小規模事業者・個人事業主などが、ITツール(ソフトウェア・サービスなど)を導入する際に国が補助する制度です。主に、業務の効率化やDX推進を目的として設立されました。
IT導入補助金のなかでも、「インボイス枠(インボイス対応類型)」は、パソコン・タブレット・ハードウェアなどの導入にも利用できるため、人気があります。
ただし、ITツールの導入もセットで行うことが条件ですので、申請を検討している方は覚えておきましょう。
補助金を申請する際には、IT導入支援事業者とパートナーシップを組む必要があります。IT導入支援事業者とは、生産性向上を目指す中小企業・小規模事業者等へ、ITツールの導入を支援する事業者のことです。
また、補助金対象のITツールは、事前にIT導入補助金事務局のホームページに公開されているものに限ります。
3.中小企業省力化投資補助金
「中小企業省力化投資補助金」とは、中小企業・小規模企業・個人事業者などが、省力化製品(IoT・ロボットなど)を導入する際に国が補助する制度です。省力化製品を活用して、人材不足の解消につなげることを目的としています。
中小企業省力化投資補助金には「カタログ注文型」と、2025年から新設された「一般型」があります。
カタログ注文型とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページにあるカタログに登録された省力化製品のなかから、自社に合った製品を選び、販売事業者と共同申請する方式です。
一方、一般型は、カタログに登録されていない省力化製品やオーダーメイド製品などを活用できる点が特徴です。
4.事業再構築補助金
「事業再構築補助金」とは、コロナ後に事業の再構築を目指す、中小企業・小規模企業・個人事業者などを支援する国の補助制度です。
「事前着手制度」が廃止されてからは、補助金交付決定前に支出した経費は補助対象外となりましたので、注意が必要です。
事業再構築補助金を利用するための基本要件には、事業再構築指針の定義に該当する事業を行うことや、事業計画について金融機関や認定経営革新支援機関等の確認を受けることなどがあります。
事業再構築指針の定義は、「新市場進出」や「事業転換」「業種転換」などです。
たとえば、飲食業であれば、自社商品のテイクアウト販売を行うスペースの設置や、デリバリーサービス事業の立ち上げなどが該当します。
また、航空機の部品を製造する企業が、ロボットや医療機器の部品開発事業に乗り出した例もあります。
事業再構築補助金の申請手続きには、GビズIDの取得が必要です。
GビズIDの取得には一定期間を要するため、手続きは早めに行いましょう。
5.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」とは、中小企業・小規模事業者・個人事業主などが、今後直面する制度(働き方改革・賃上げ・インボイス導入など)へ対応できるように、国が補助する制度です。
また、日本国内に本社及び補助事業を行う場所(工場・店舗など)があることも条件の1つです。
補助対象事業には、以下の2つの事業枠があります。
- 製品・サービス高付加価値化枠:
新製品や新サービスの開発に、必要な設備・システム投資などを支援する事業枠
- グローバル枠:
海外事業を実施している企業の支援枠。主に、必要な設備・システム投資などを構築して、国内事業と海外事業の双方を強化し、国内の生産性向上に努める企業が対象
6.中小企業新事業進出補助金
2025年に新設されたばかりの制度に「中小企業新事業進出補助金」があります。
中小企業新事業進出補助金とは、既存事業とは別に、新市場・高付加価値事業への進出を行う企業や事業主に対して、設備投資等にかかる費用を国が補助する制度です。中小企業・小規模事業者だけでなく、個人事業主も対象となります。
企業や事業主の生産性向上だけでなく、賃上げを促進させることも目的の1つです。
また、同じく2025年に新設された補助金に「中小企業成長加速化補助金」があります。
こちらの補助金は、売上高100億円を目指す中小企業に対して国が補助する制度ですので、比較的事業規模が大きい事業者や企業でなければ対象にはなりません。
補助金の申請方法・流れ
補助金の申請方法や流れは補助金ごとに異なります。申請する際は、その都度要綱を確認しましょう。
以下では、補助対象者の申請方法・流れを解説します。
一般的な補助金の申請方法・流れ
以下の表では、一般的な流れをご説明しています。
-
事前準備
各補助金サイトから公募要領を確認する。郵送、またはネットのどちらから申請するかを決める
ネットから申請する場合は、法人・個人事業主向けの共通認証システムアカウント(GビズID)を取得すると便利 -
公募申請
公募要領・申請書を確認のうえ、必要書類一式を事務局に提出する
提出書類:応募申請書・事業計画書・経費明細書・事業要請書など -
交付申請・交付決定 → 補助事業の開始
採択後は交付申請(補助金を受け取るための手続き)を行う。申請が認可されたら交付決定(補助事業の開始)となる
受取書類:選定結果通知書・補助金交付規程・交付申請書・交付決定通知書など
提出書類:交付申請書・経費の相見積もりなど -
変更申請手続き
交付決定にあたり、事業内容を変更する都合があれば、計画変更申請手続きを行う
提出書類:計画変更申請(必要な場合のみ) -
報告書の提出・補助金交付
事業内容や経費を報告して補助金を受け取る。補助金の対象となる経費に関しては、領収書や証拠書類など、すべて保管しておく
提出書類:実績報告書・経費エビデンス・請求書など
受取書類:補助金額確定通知書・請求書様式など
補助金の公募期間は一か月前後であることが多いため、期間内に所定の書類を揃える必要があります。
その際に、きちんと補助金の必要性をアピールできないと採択されないため、注意しましょう。
補助金を受け取るためのポイント・注意点
以下では、補助金を受けるためのポイント・注意点を8つ解説します。
1.申請する補助金が個人事業主も対象かどうかを確認する
補助金を申請する前には、自社が対象となるかを確認しておきましょう。
補助金のなかには「個人事業者向け」と記載されていないケースもあり、自社が適用されるかどうかがわかりにくいこともあります。
そのため、補助金ごとの詳細要件を確認する前に、前提条件が当てはまるかを大まかに確認しておきましょう。
具体的には、以下の4項目の確認をオススメします。
- 補助対象者かどうか(事業規模・法人格・改行年数・開業実績など)
- 補助対象事業かどうか(補助金の趣旨にあった事業を展開しているかどうか)
- 補助対象経費のものを購入・投資予定か
- 補助対象期間に事業を実施しているか(支出した経費を含む)
2.補助金を受け取るまでは資金計画を立てておく
補助金を申請して採択された場合でも、受け取るまでの期間は、資金計画を立てておく必要があります。理由は、多くの補助金が後払い制であるためです。
たとえば、総額100万円の機械導入に1/2の補助が適用される場合でも、最初に自社で100万円を用意する必要があります。
50万円だけ自社で用意しておき、購入時に残りの50万円を補助金で支払うことはできませんので注意しましょう。
3.補助金を受け取る際の提出書類はきちんとチェックしておく
補助金を受け取る際に提出する書類(報告書・支払証憑類など)はきちんとチェックしておきましょう。提出書類の内容が適当であったり、目的外のモノに経費を支出していたりした場合、支払いを拒否されることがあります。
過去の例では、試作品をつくるために導入した機械に対する補助金が支払われなかったケースもあります。こちらは、試作段階で量産用の機械を購入したとして補助金の支払いが拒否されました。
4.補助事業開始前に支出しないよう気を付ける
一般的に、補助金は補助事業期間内のものに適用されます。そのため、補助事業開始前に支出した経費は補助金の対象外となるケースが多いです。
結果として、補助が受けられない事態を避けるためにも、支出時期には気を付けましょう。
たとえば、事業期間が6月1日から2月28日までの場合、5月31日や3月1日に支出したものは補助を受けられない可能性が高いです。
また、事業期間の最終日に関しては、年度末よりも少し早めに設定されているケースが多いため、こちらも注意が必要です。
5.国だけでなく地方自治体からの補助金の情報もチェックしておく
補助金の支給は国からだけではありません。
地方自治体でも実施していますので、各自治体の情報もチェックしておきましょう。
たとえば、大阪府では、「中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金」を実施しています。
中小事業者に補助金を支給して、脱炭素化や電気料金の削減を促したり、経営力強化を促進させたりすることが目的です。
また、神奈川県では、「ロボット導入支援補助金」を実施していました。こちらは、「ロボットと共生する社会」を実現していくことを目的として設立されました。主に「さがみロボット産業特区」で商品化したロボットを導入する事業者への補助金です。※令和6年度の募集は2025年2月で終了しています。
両者ともに、企業だけでなく、個人事業主も補助対象です。
6.補助金の対象となる領収書・証拠書類などは指定期間保管しておく
補助金の対象となる領収書・証拠書類などは、補助事業終了後、5年間は保管しておく必要があります。
また、「補助金等交付申請書等」には、補助対象外経費も含めて記載する必要があるため、事業期間に発生した補助対象外費用の領収書・証拠書類なども残しておきましょう。
さらに、補助金が支払われた企業は会計検査院の検査を受ける可能性が高いため、必要書類の保管だけでなく、事務処理手続きも正確に行うことが重要です。
7.補助金の不正行為・不正受給が発覚した場合は処罰されるリスクがある
補助金の不正行為・不正受給が発覚した場合、処罰される可能性が高いです。
たとえば、虚偽の申請を行って補助金を受給したり、補助金を目的外に使用したり、補助金の受給額を不当に釣り上げて関係者へ報酬を配賦したりするなどの行為が不正に該当します。
これらの行為が判明した場合、交付決定取消・補助金の返還だけでなく「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、処罰されるリスクがあります。
8.補助金の申請・活用などに迷ったら国が認定する相談機関を活用する
補助金の申請・活用に迷った際は、国が認定する相談機関の活用をオススメします。
国が認定する支援機関は、主に「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」と「よろず支援拠点」です。両者は個人事業主も利用できます。
認定支援機関では、中小企業を支援するうえで、一定以上の専門知識や実務経験がある税理士・公認会計士・金融機関などの支援機関が、相談に応じてくれます。
一方、よろず支援拠点とは、国が設置した無料の経営相談所です。経営上のあらゆる相談に対して何度でも無料で相談を受けられます。
まとめ
補助金の対象者は、受給要件に該当する企業・事業者・個人事業主などです。
補助金にはさまざまな種類があり、対象者・受給要件・申請方法なども異なります。なかには、個人事業主が利用できないものもあるため、事前に受給要件を確認しておきましょう。
また、国だけでなく地方自治体が実施している補助金もありますので、日頃からあらゆる情報をチェックしておくことが大切です。