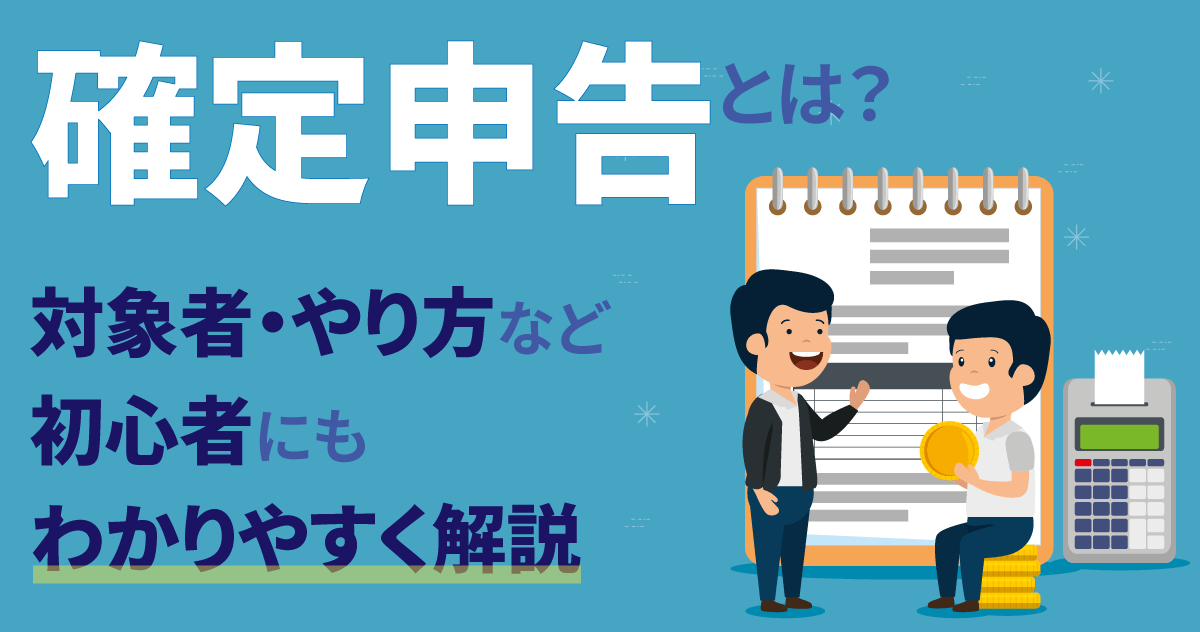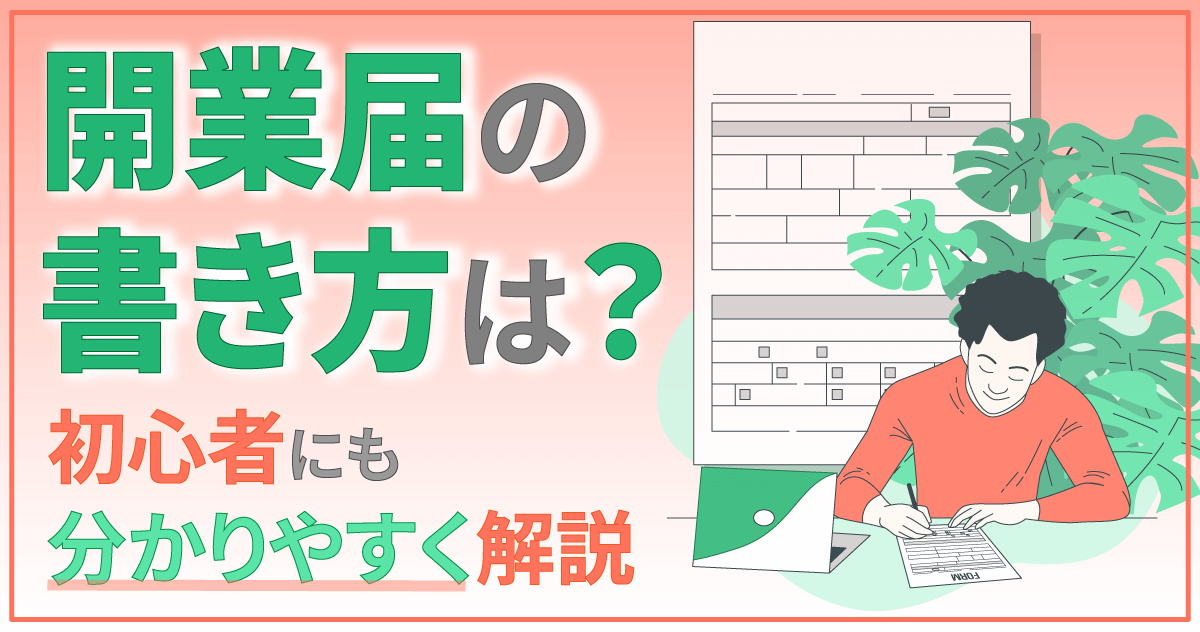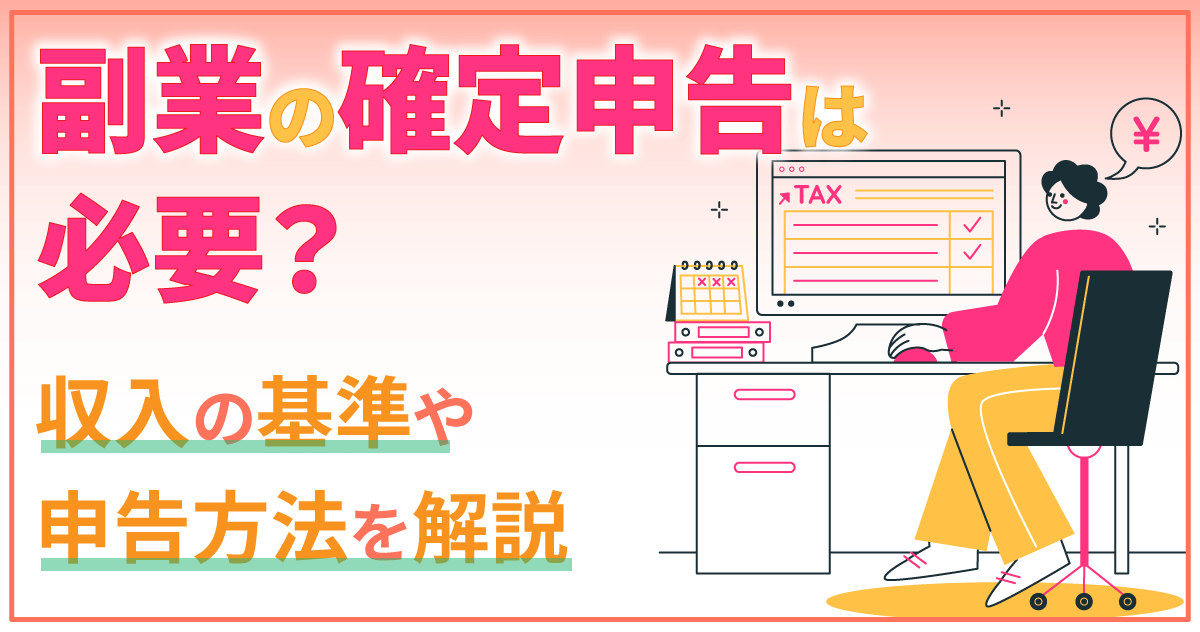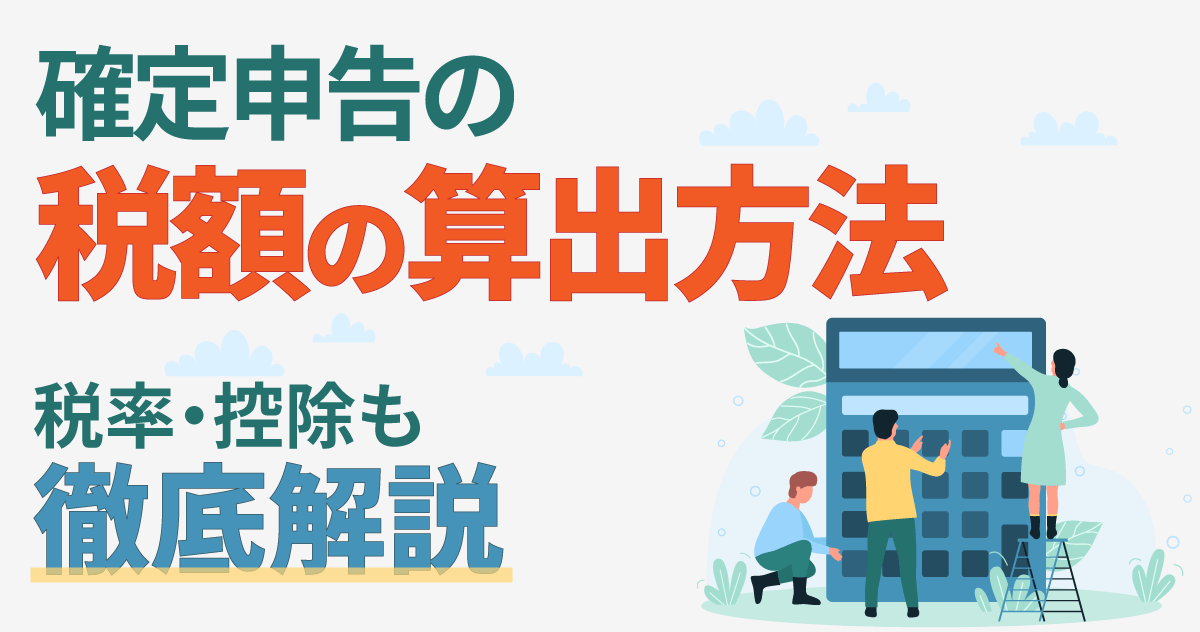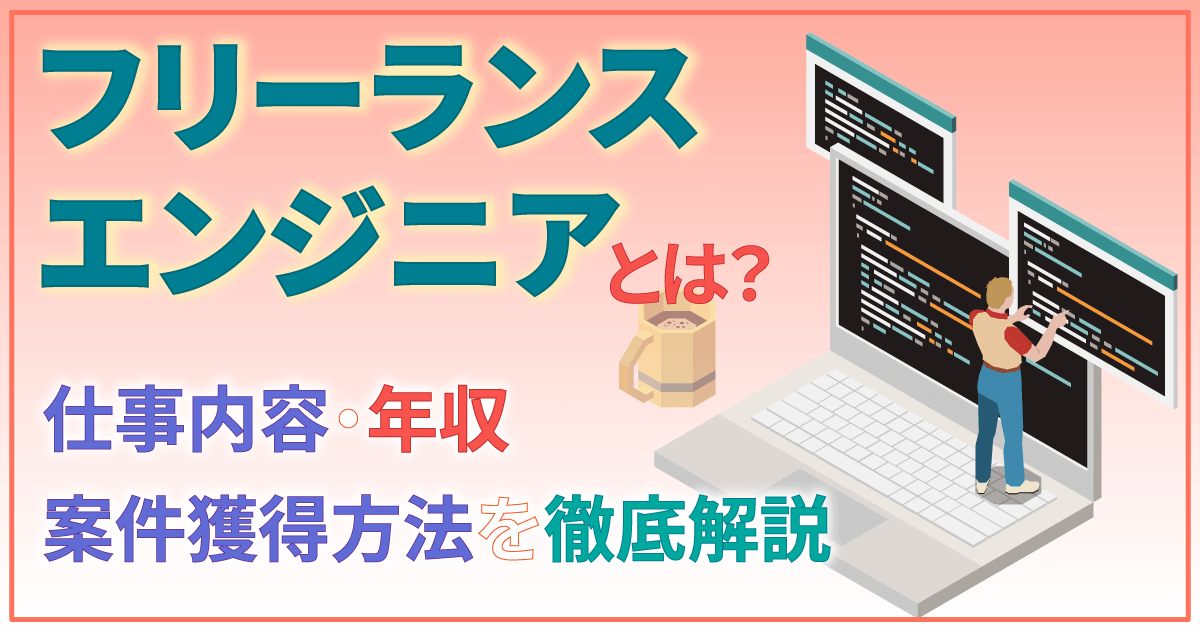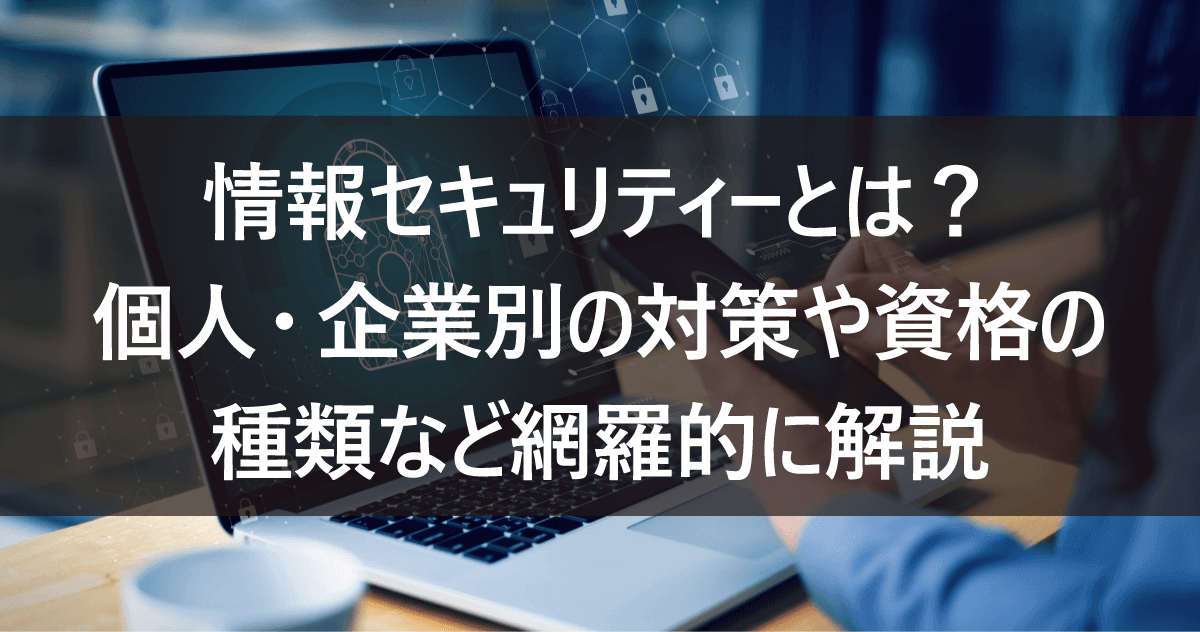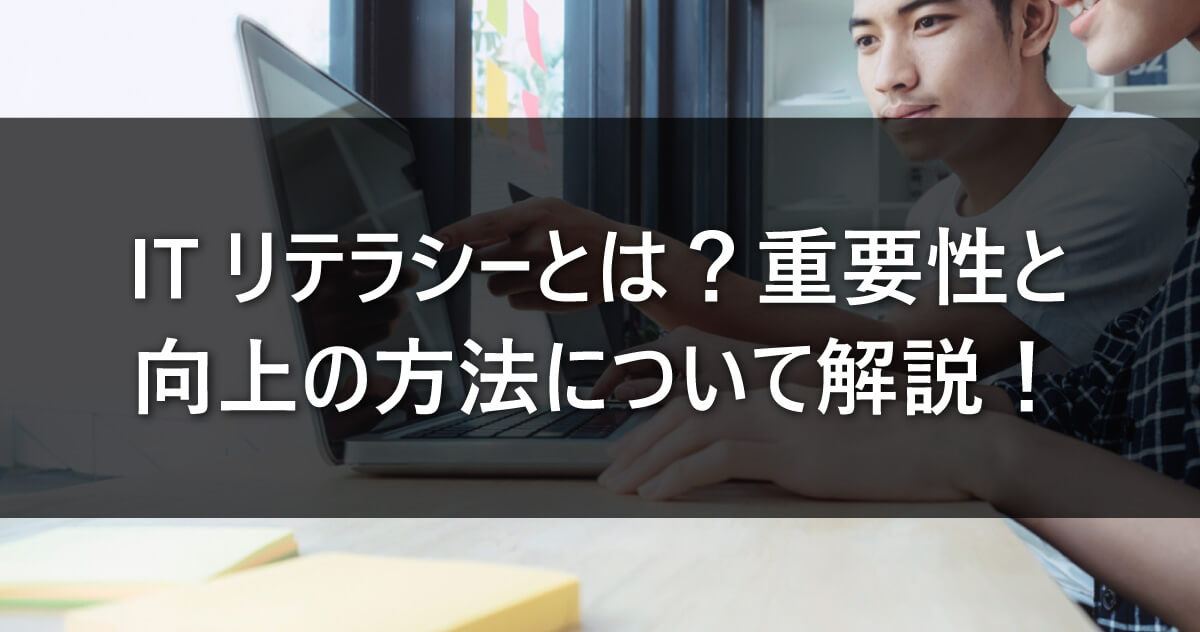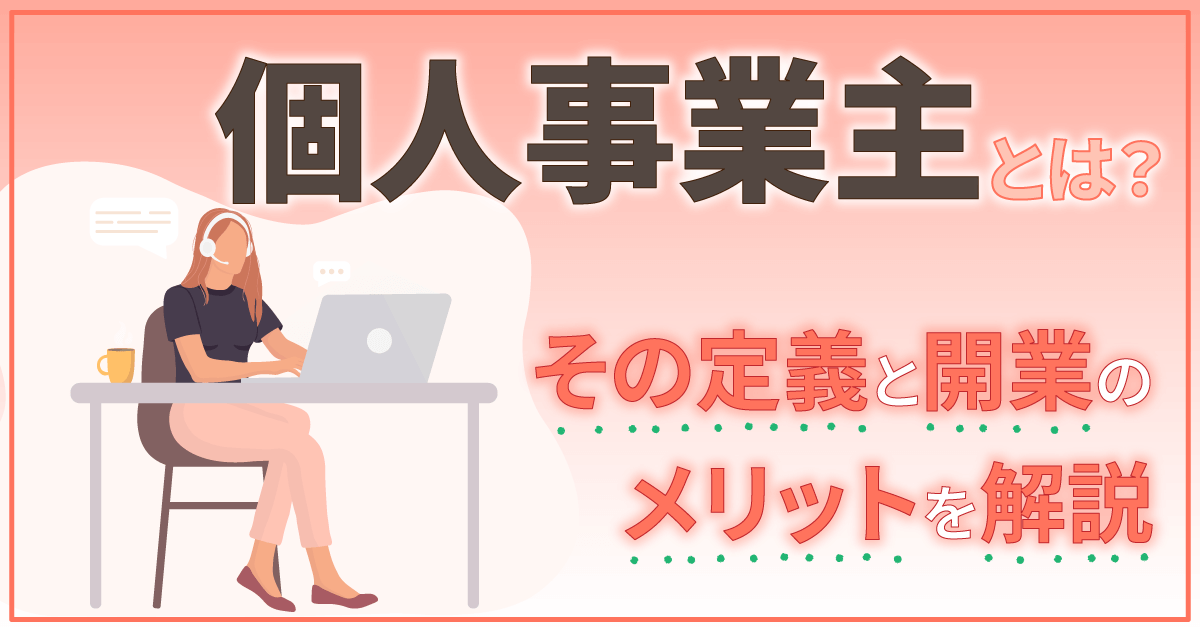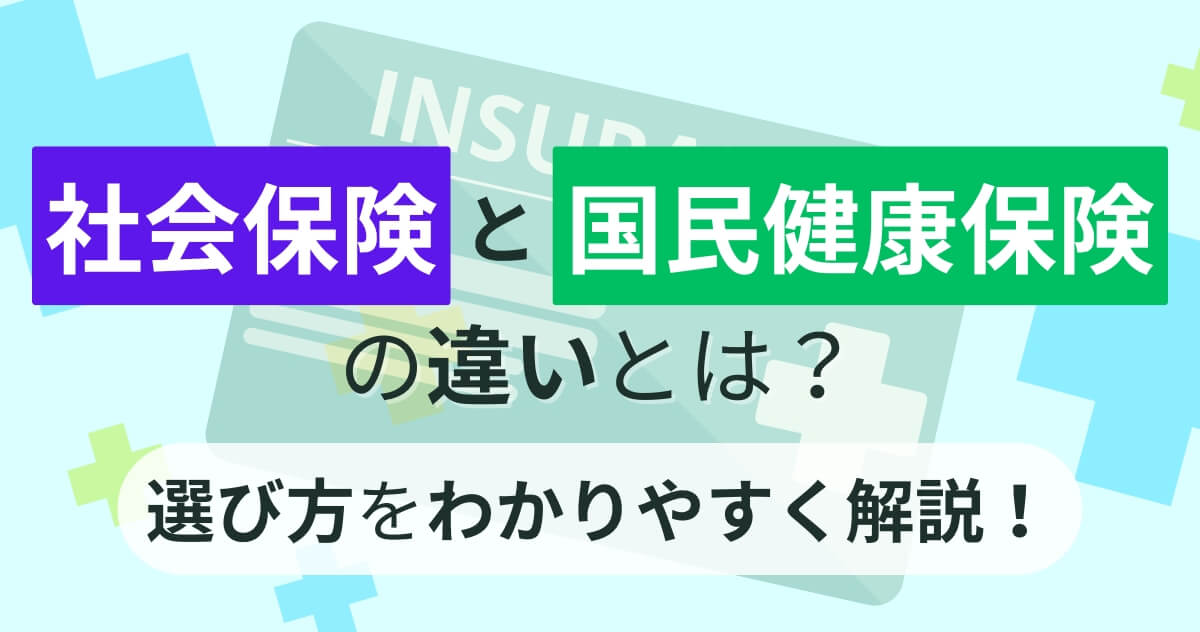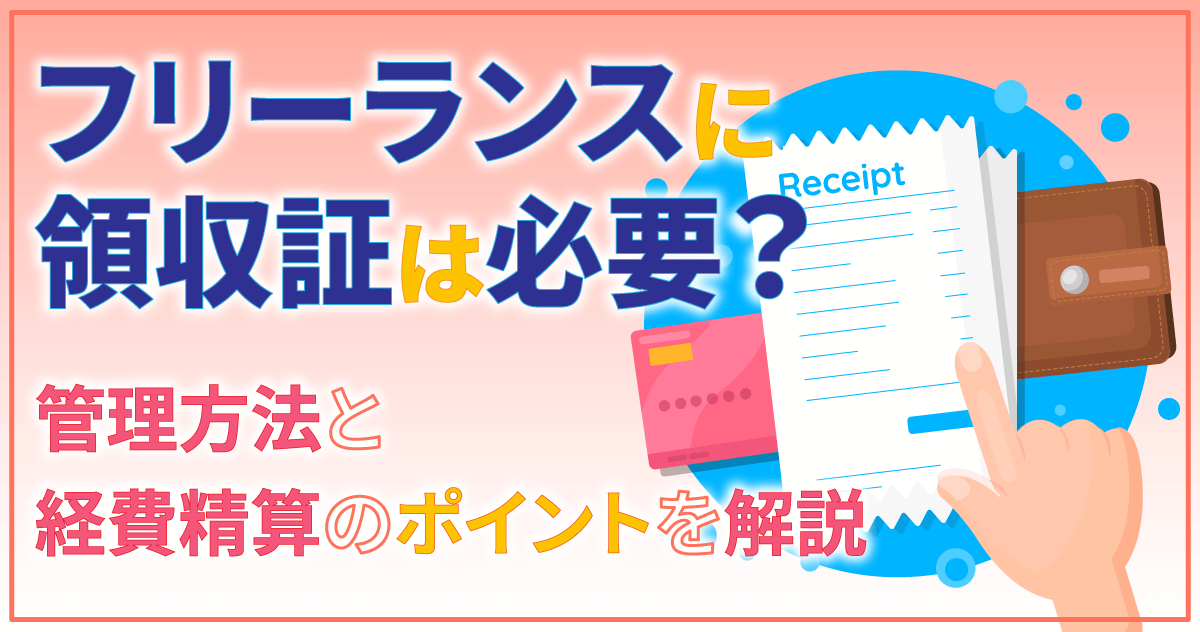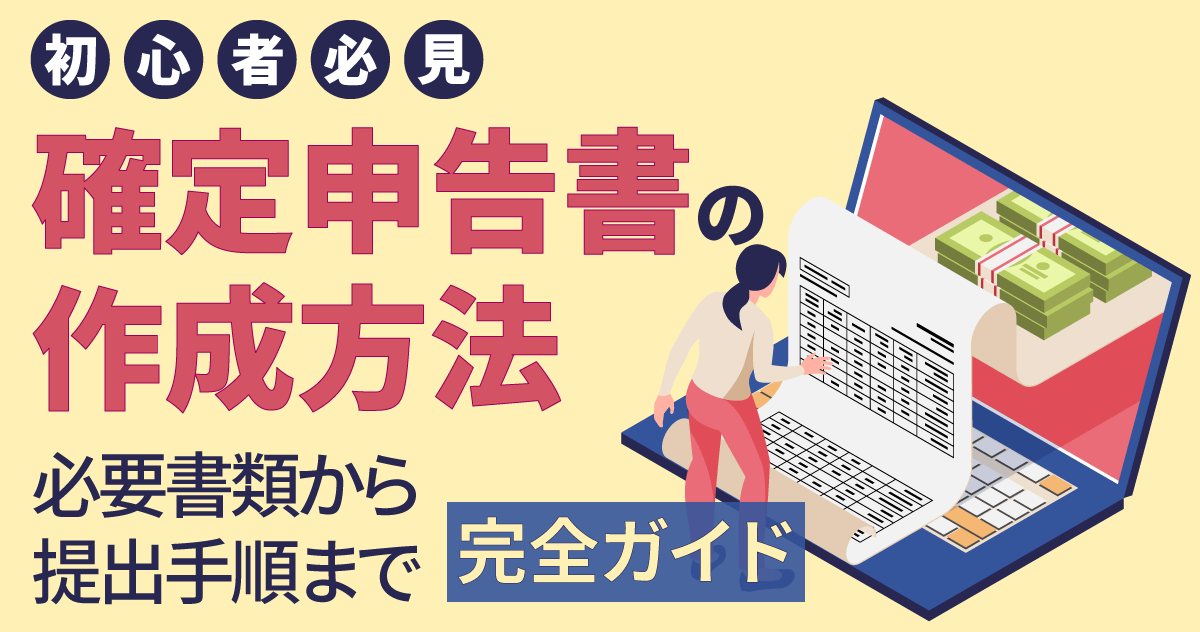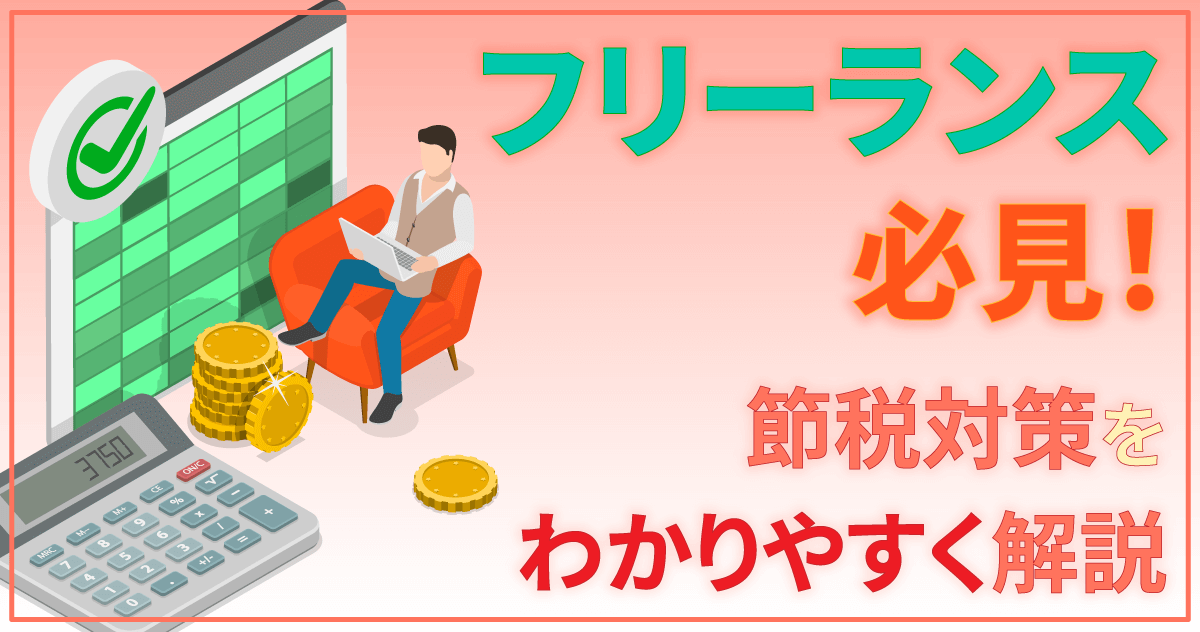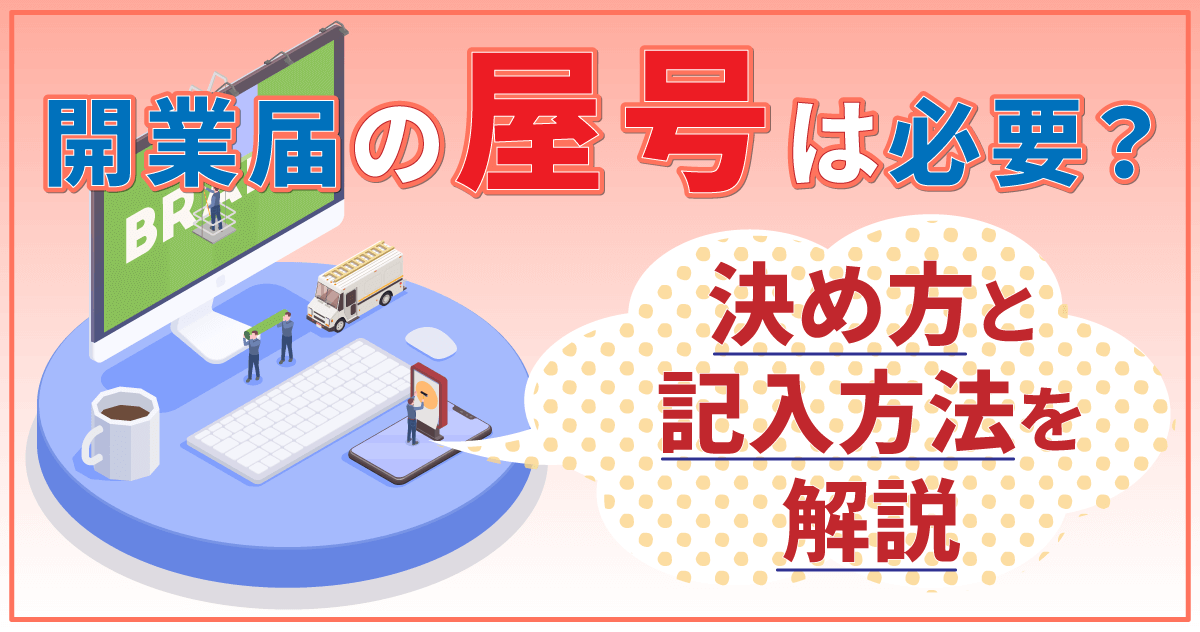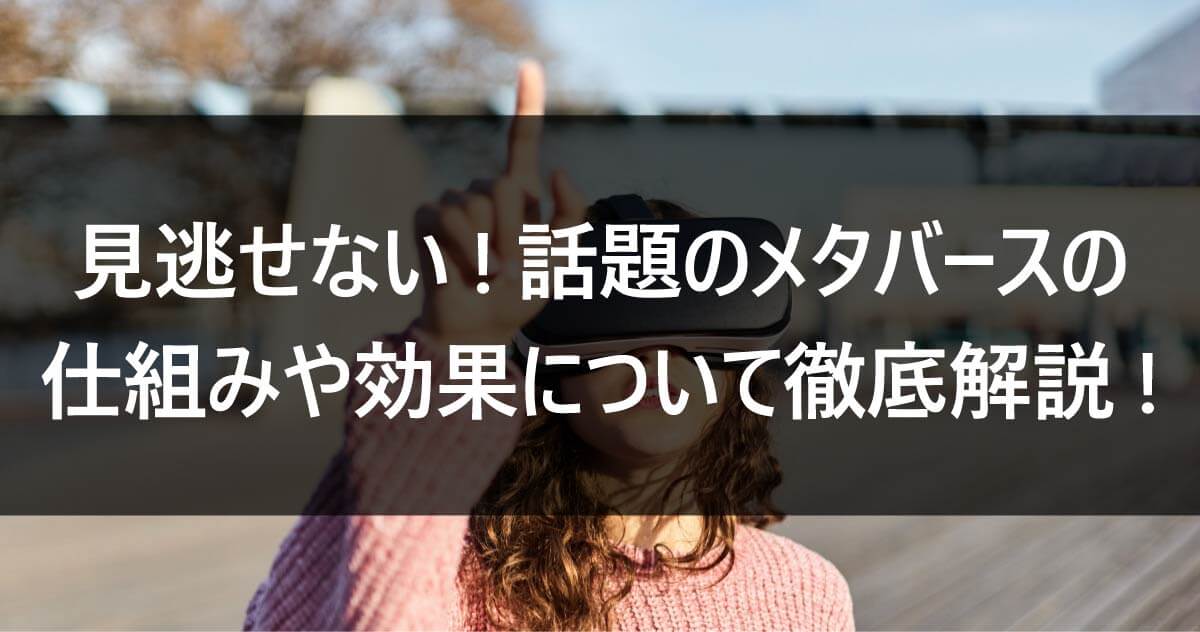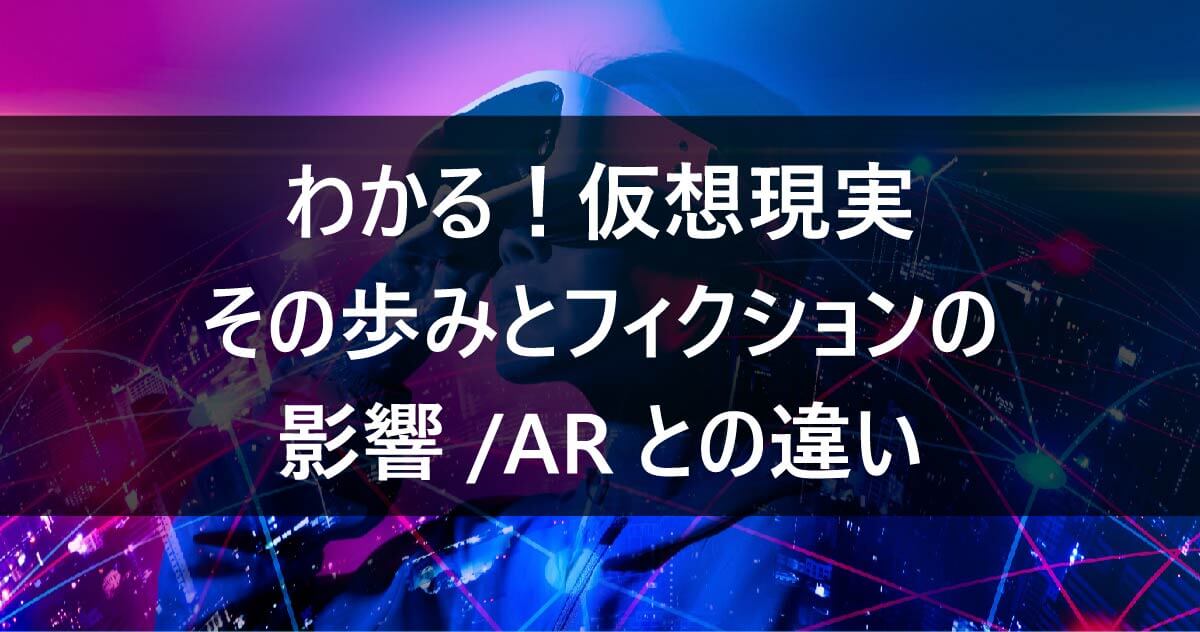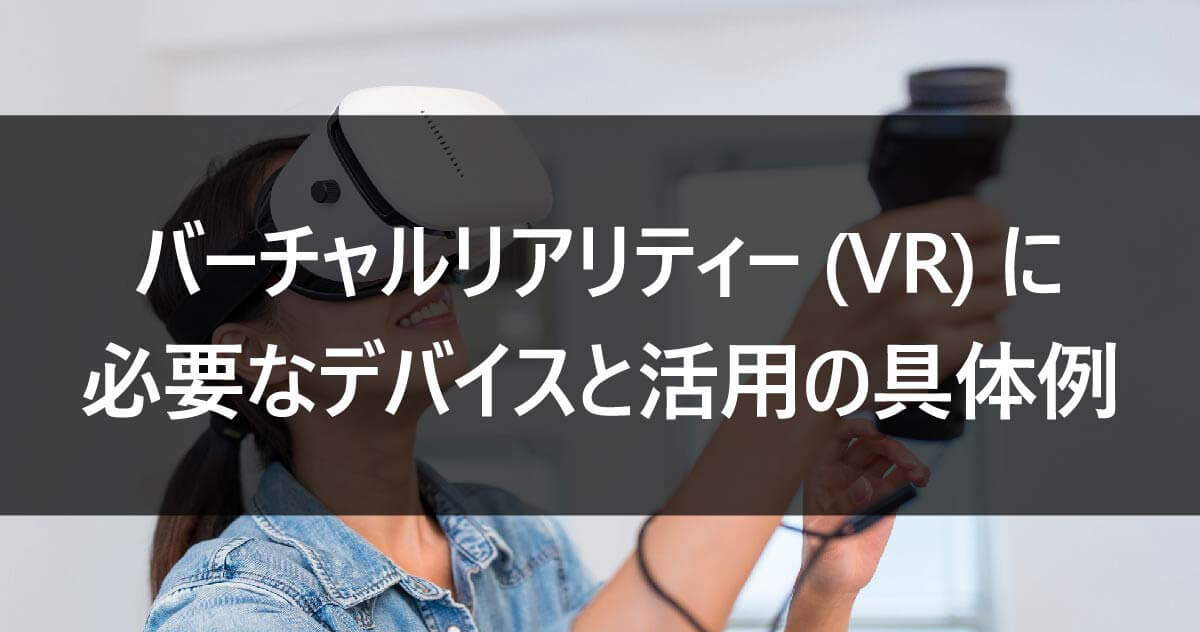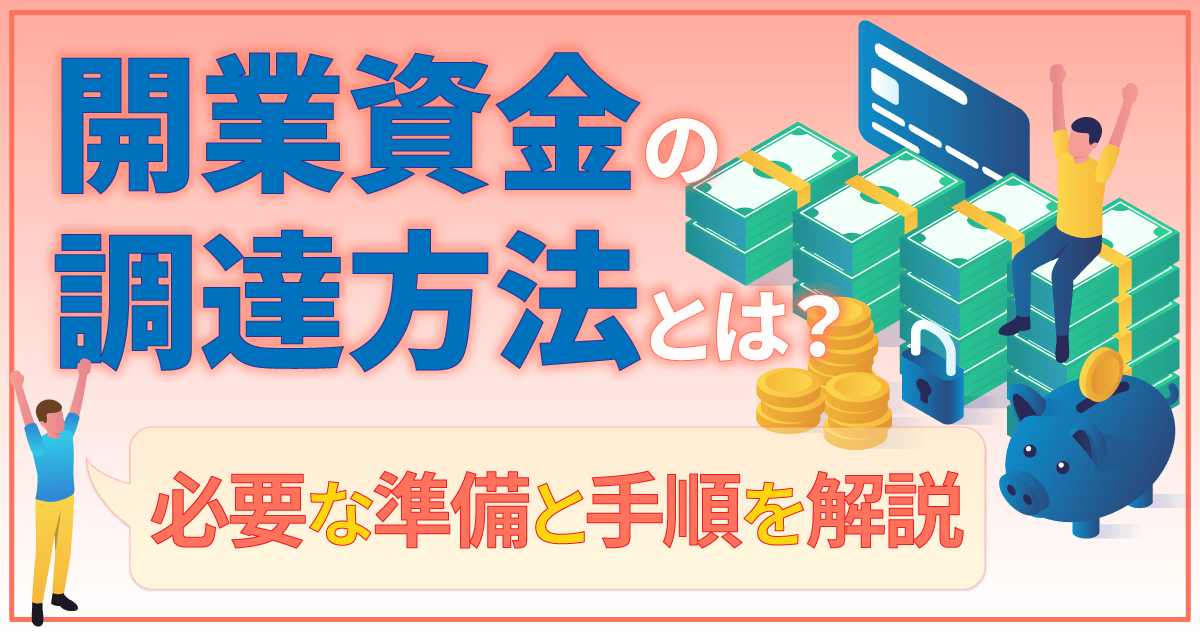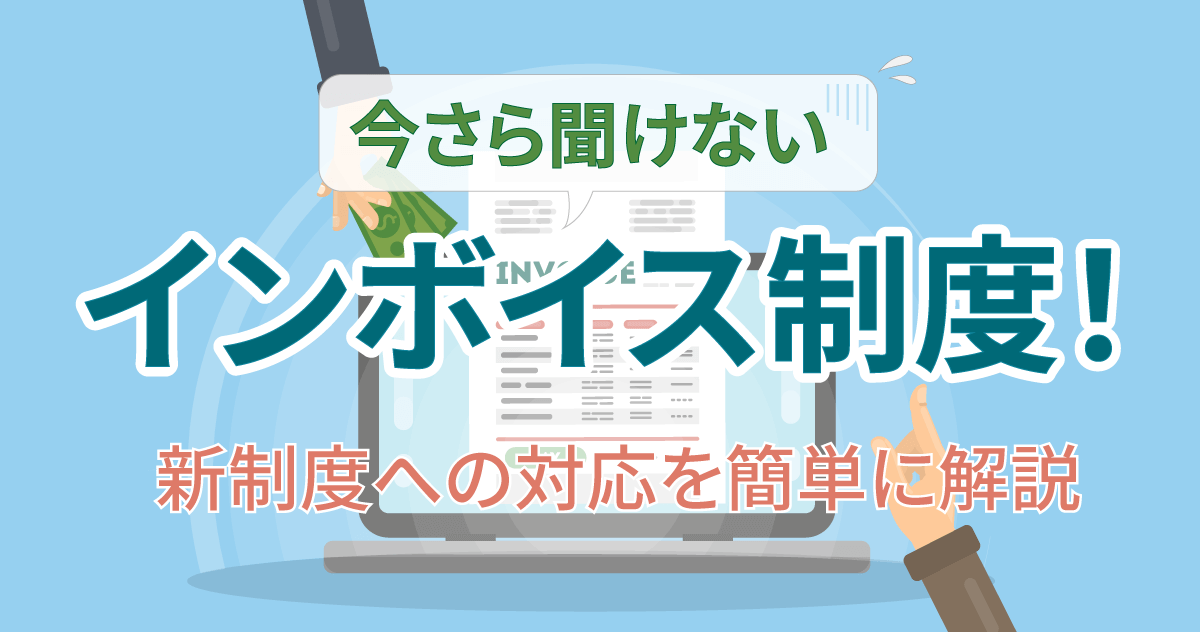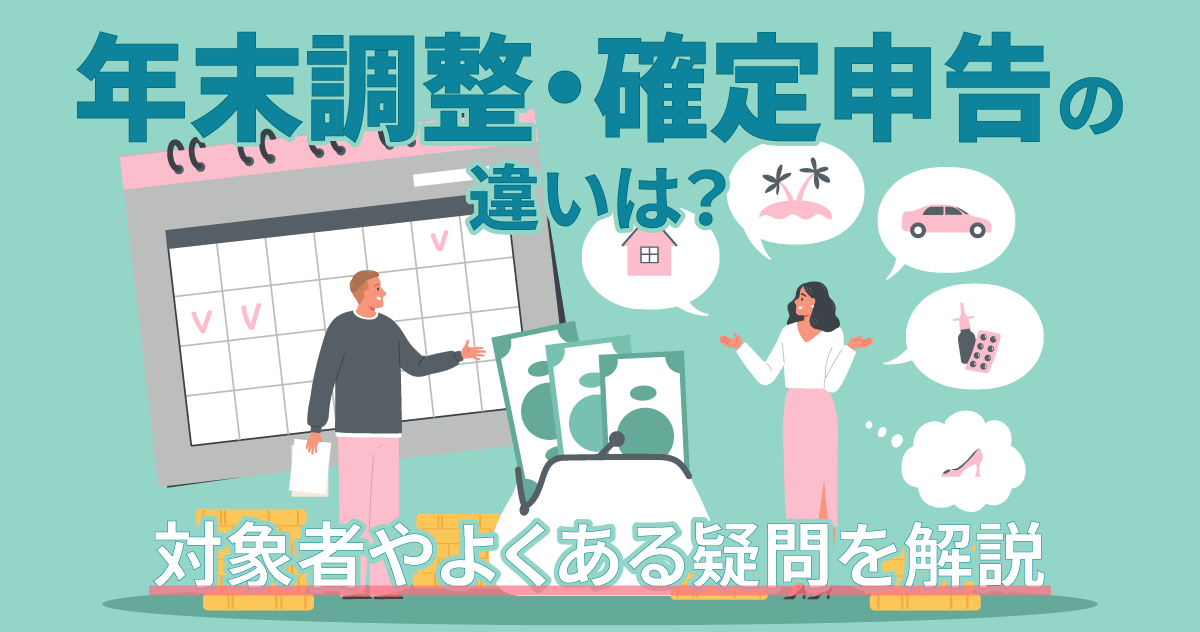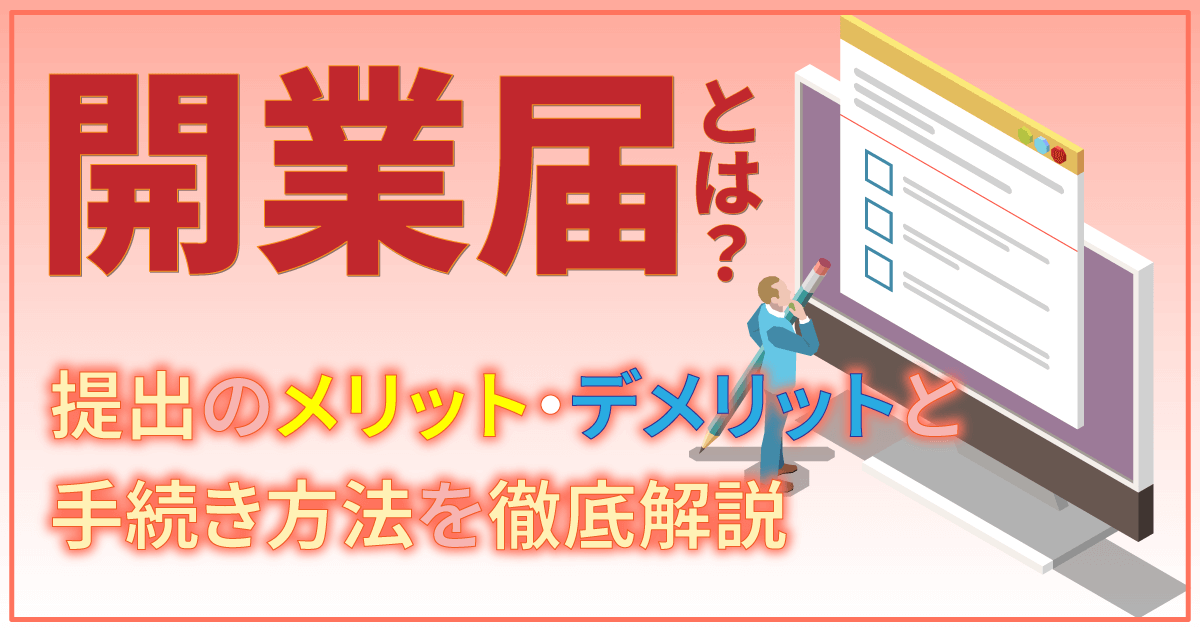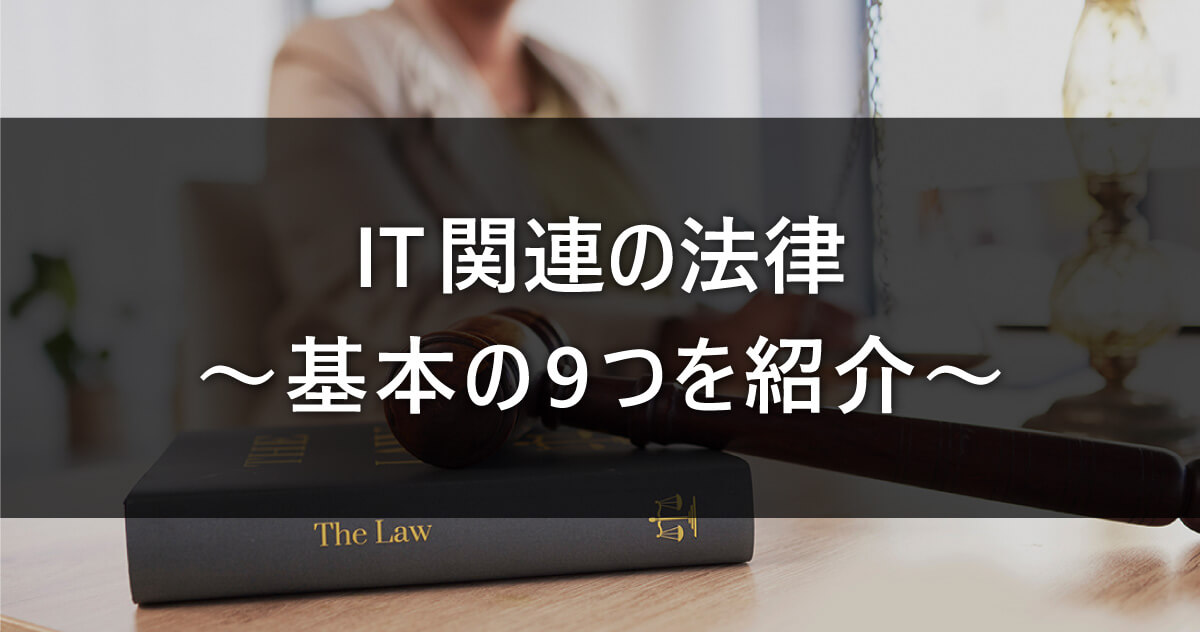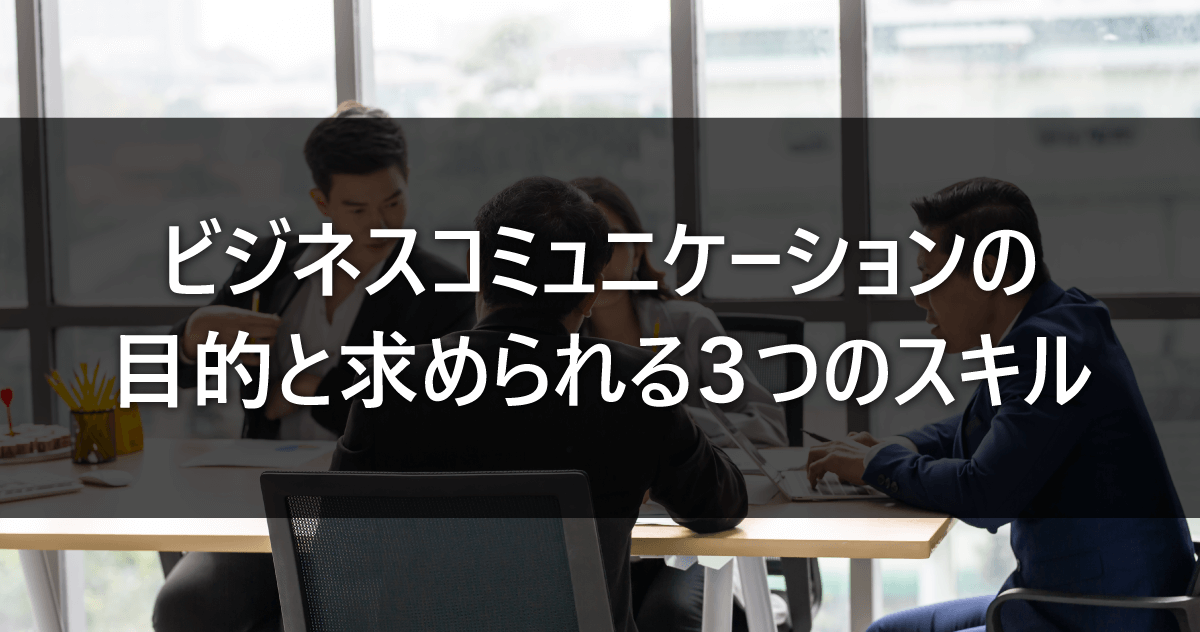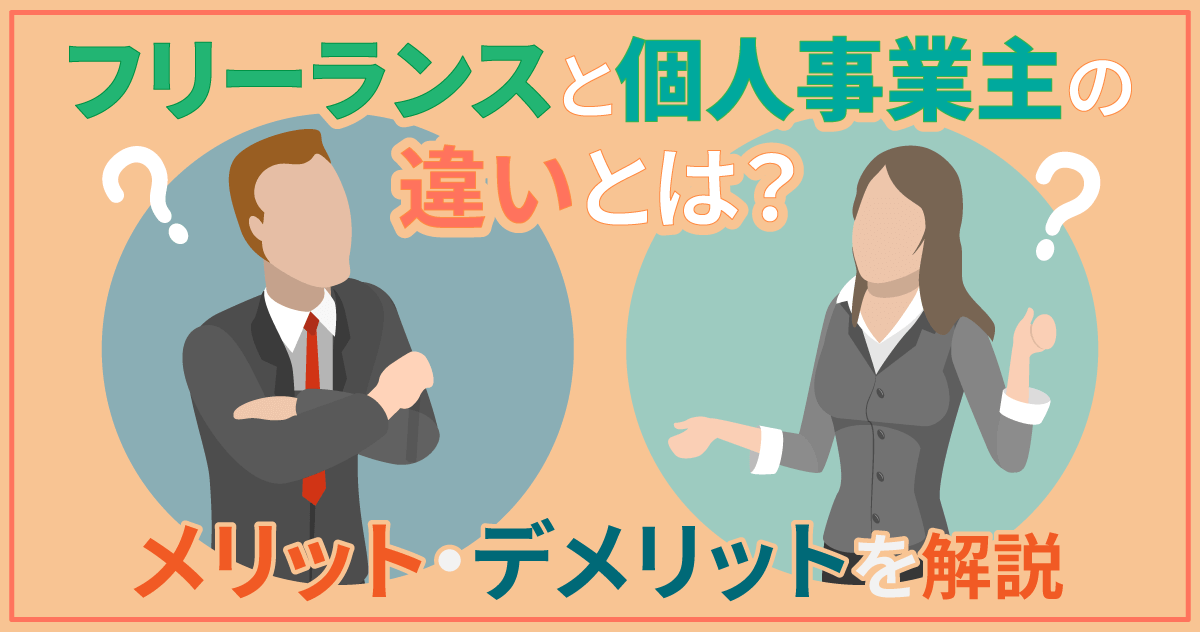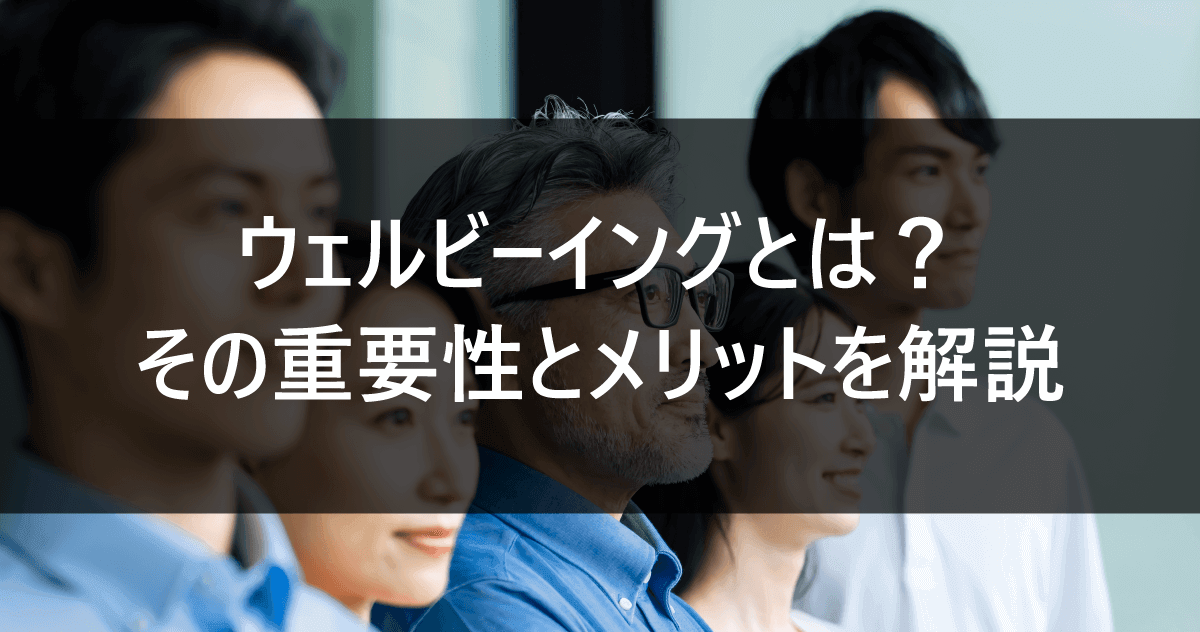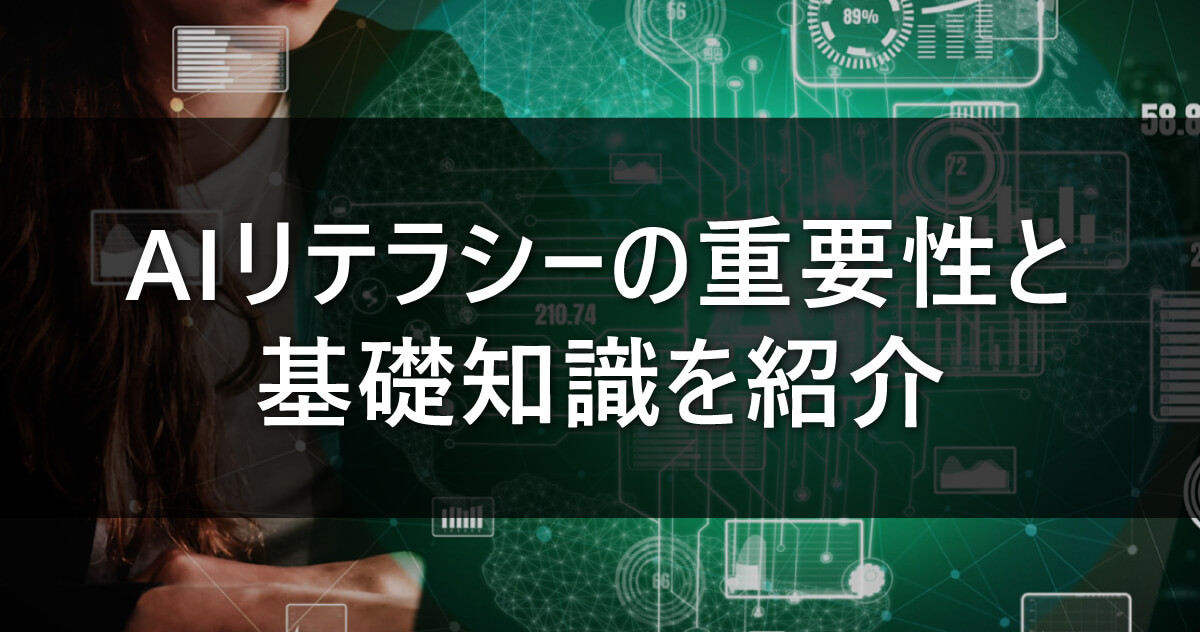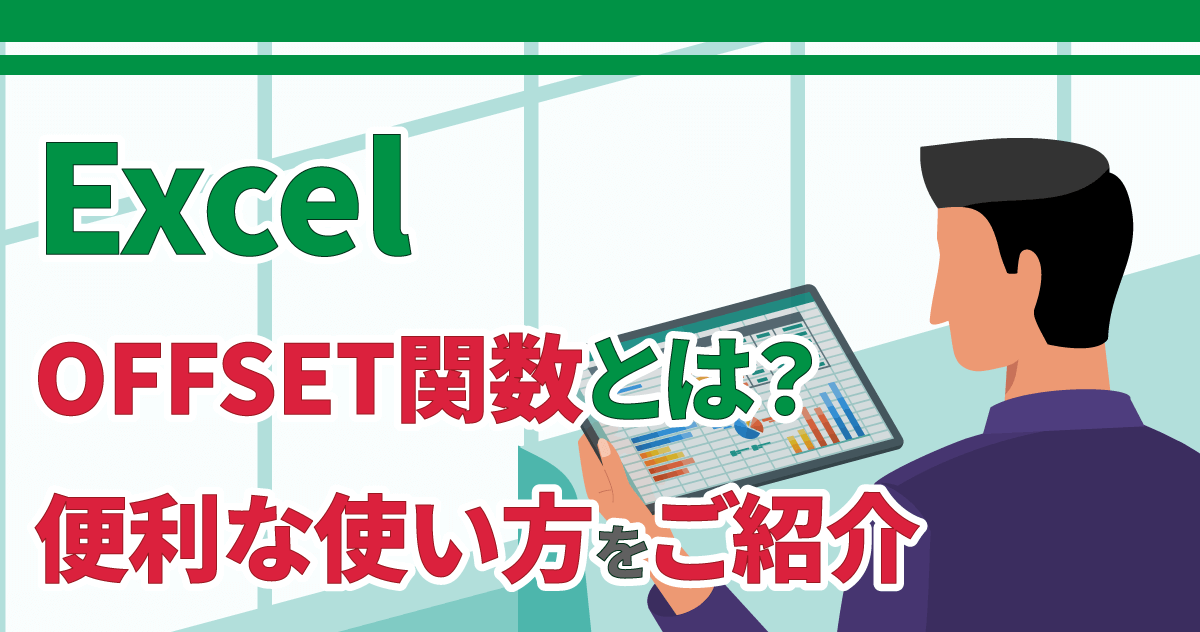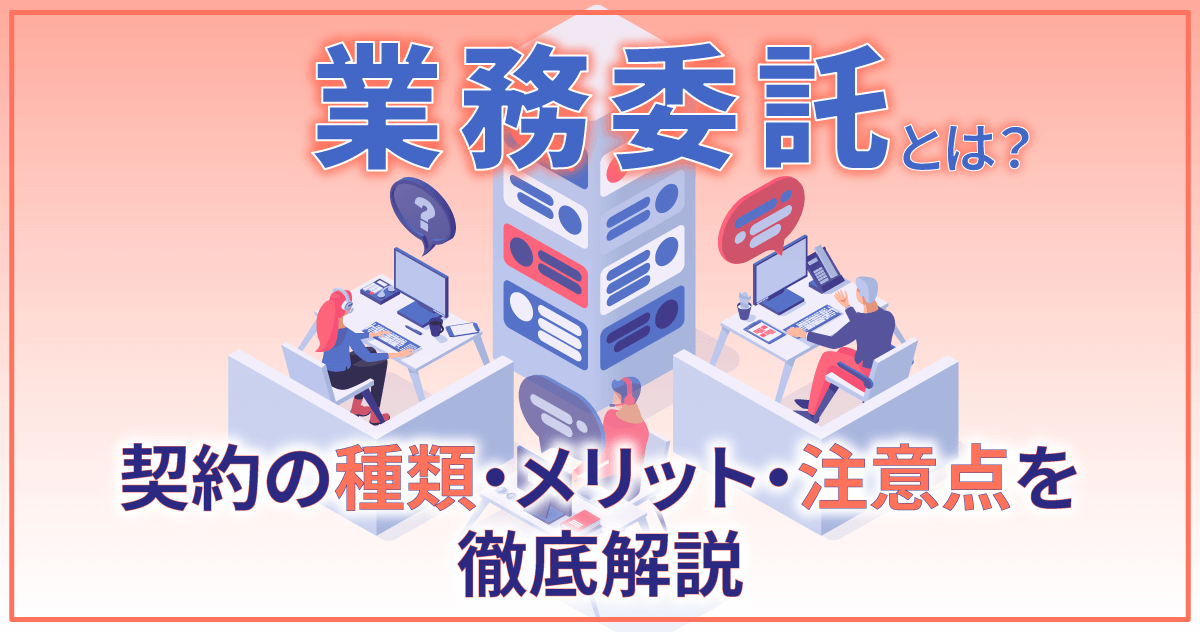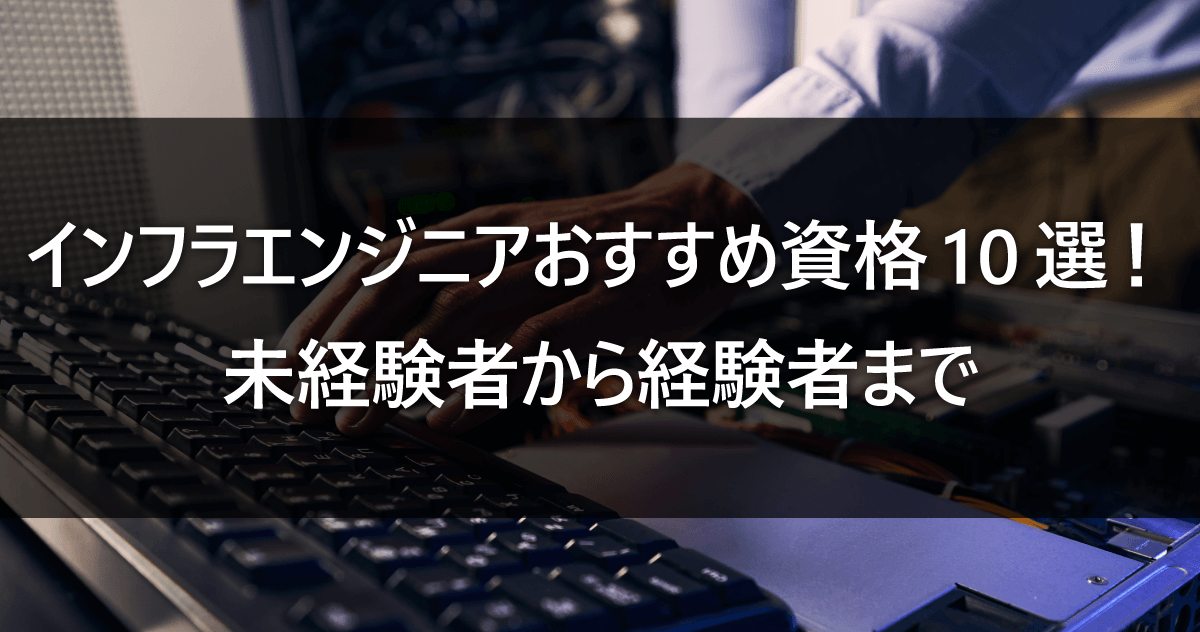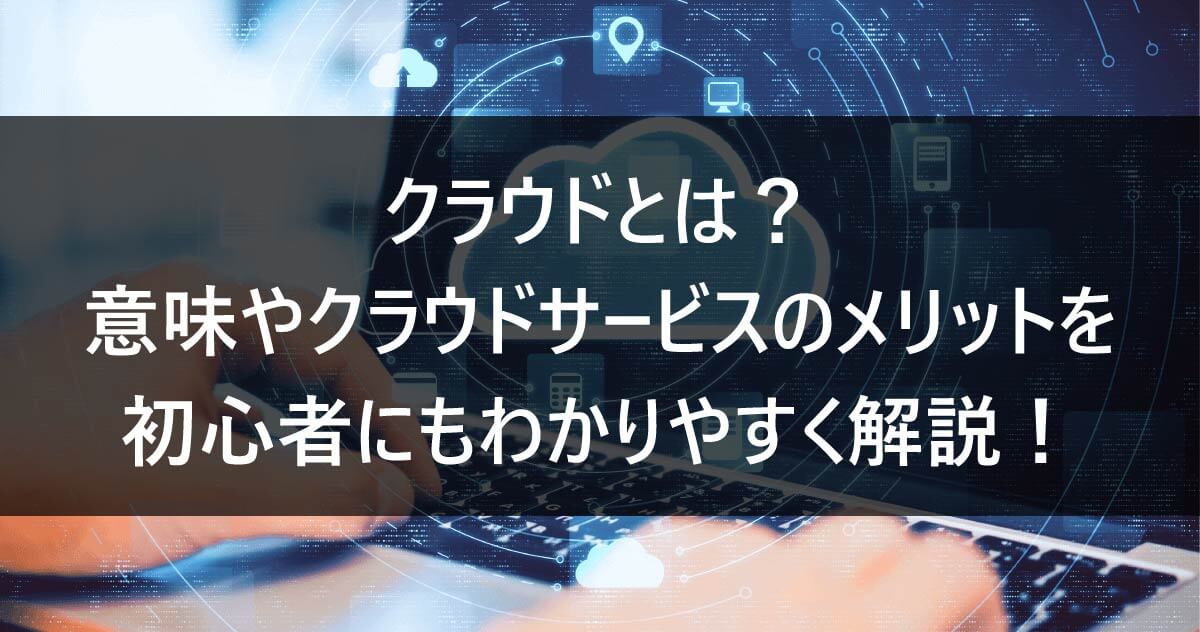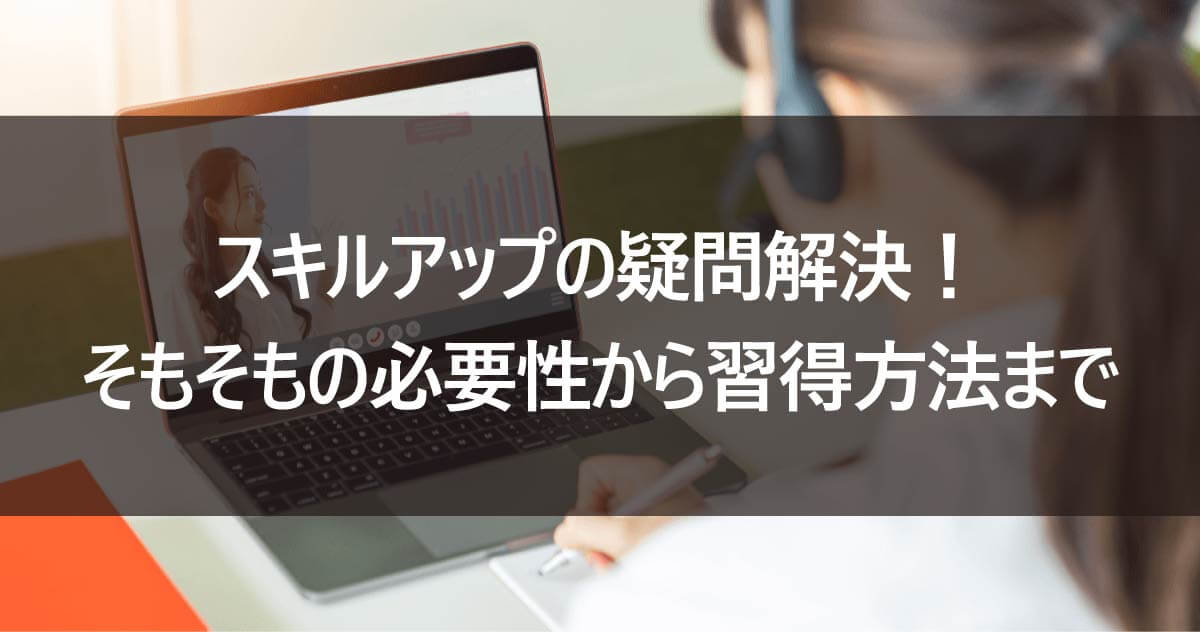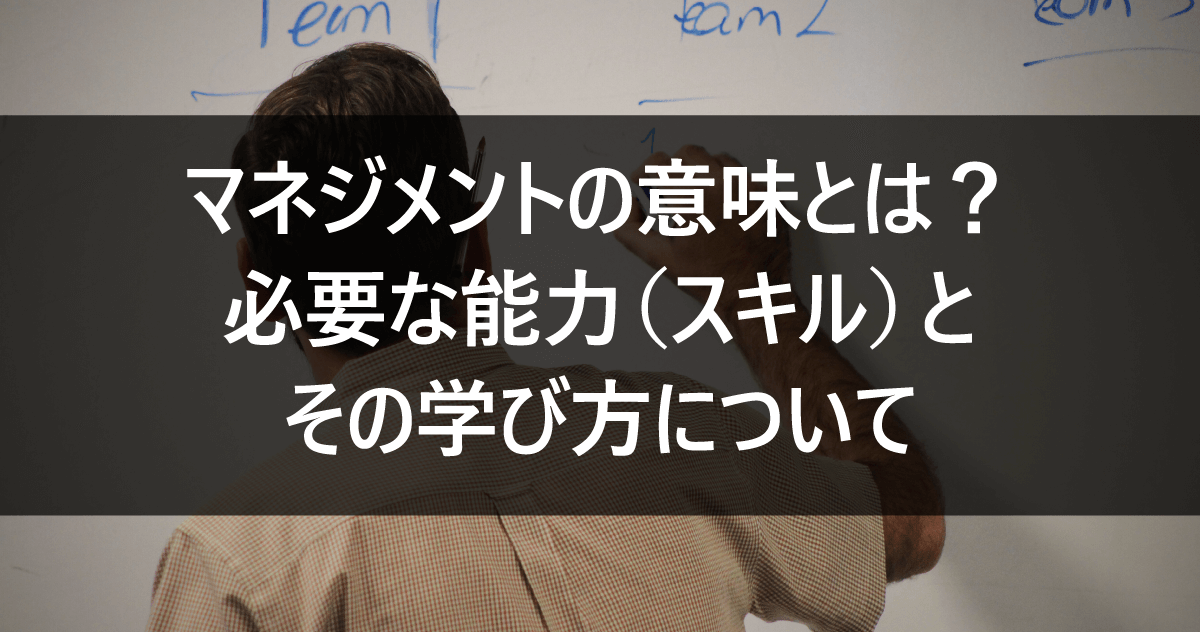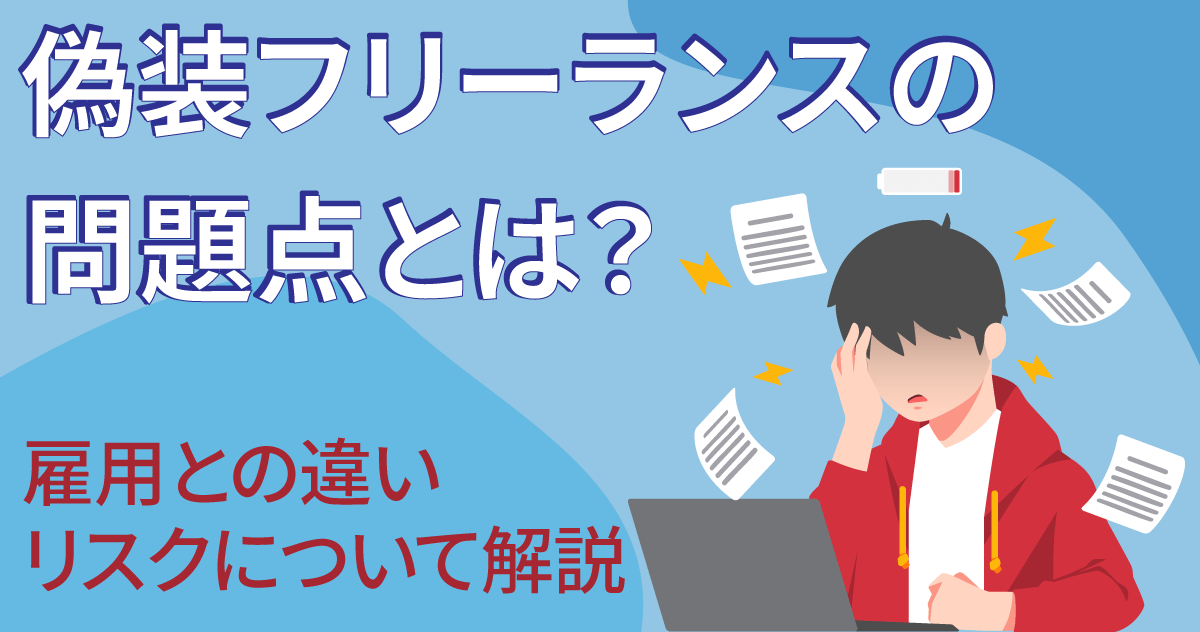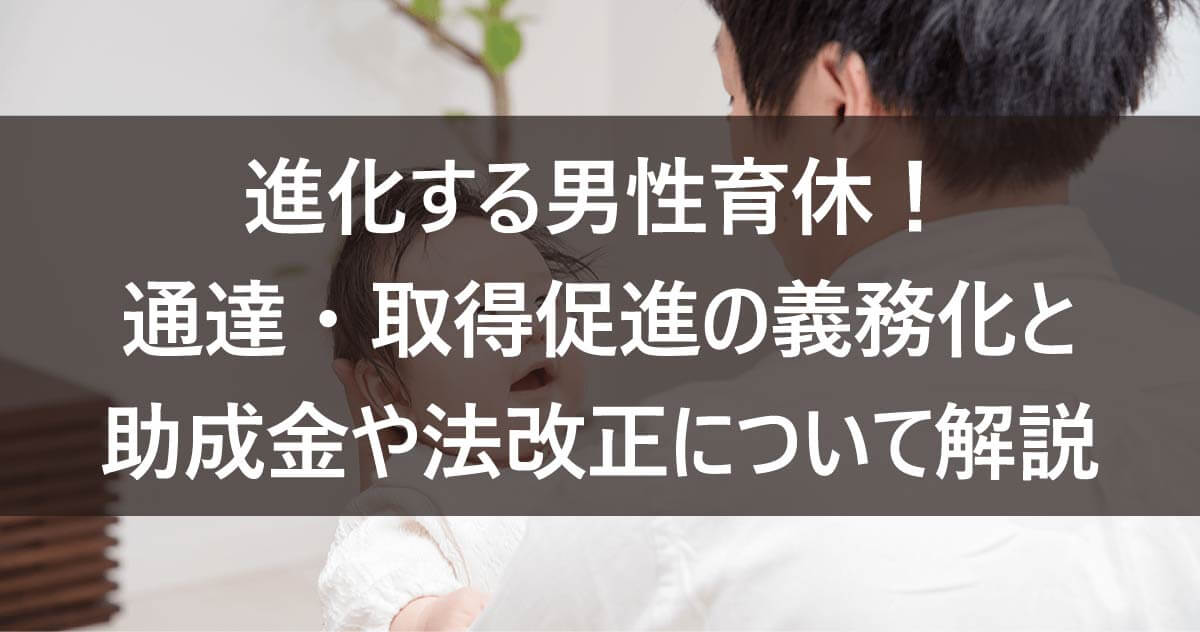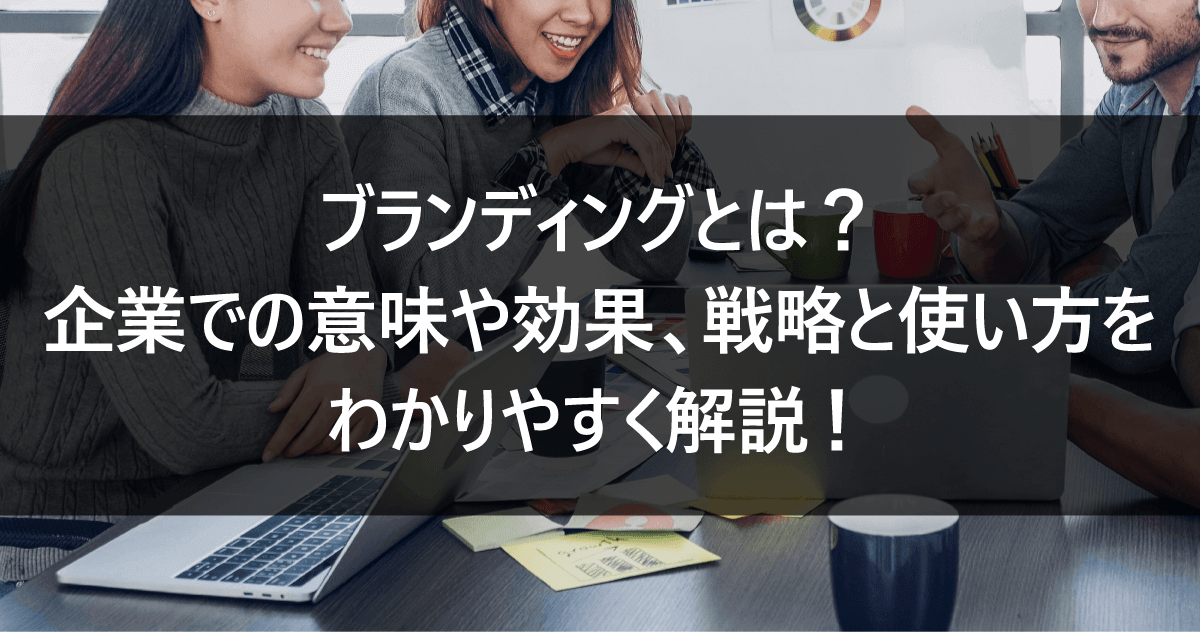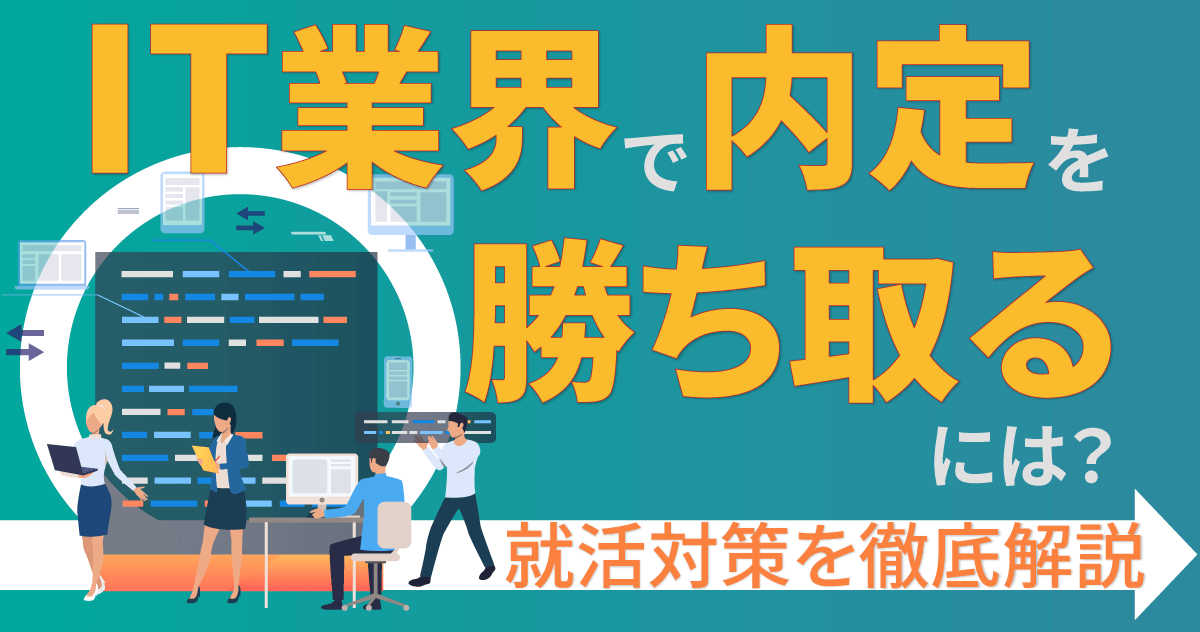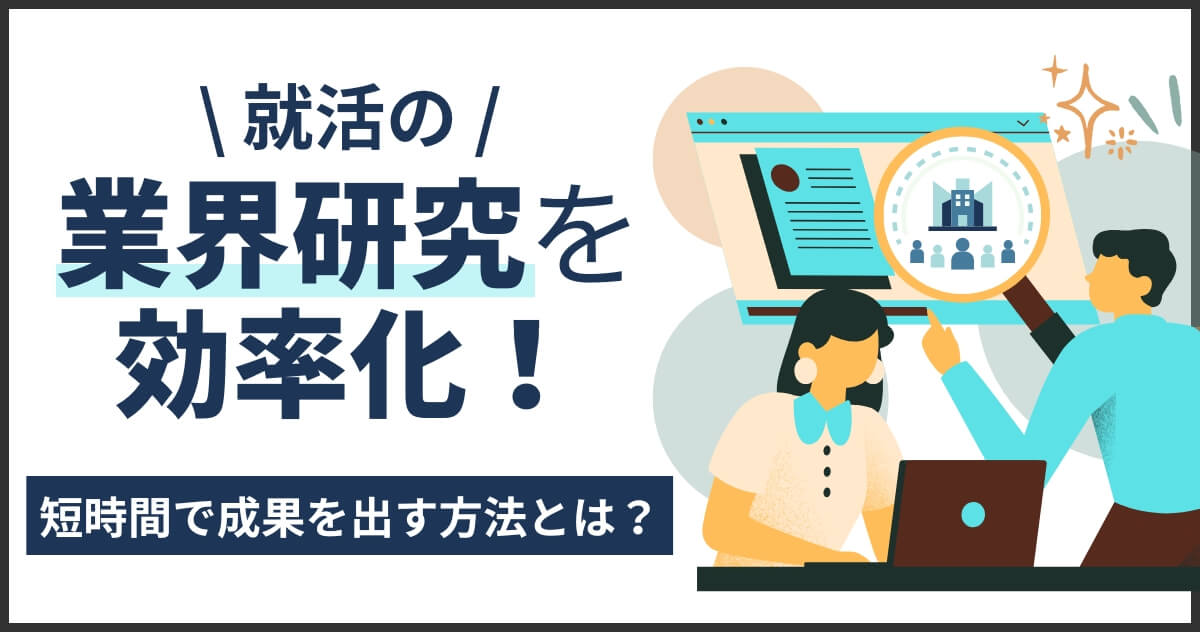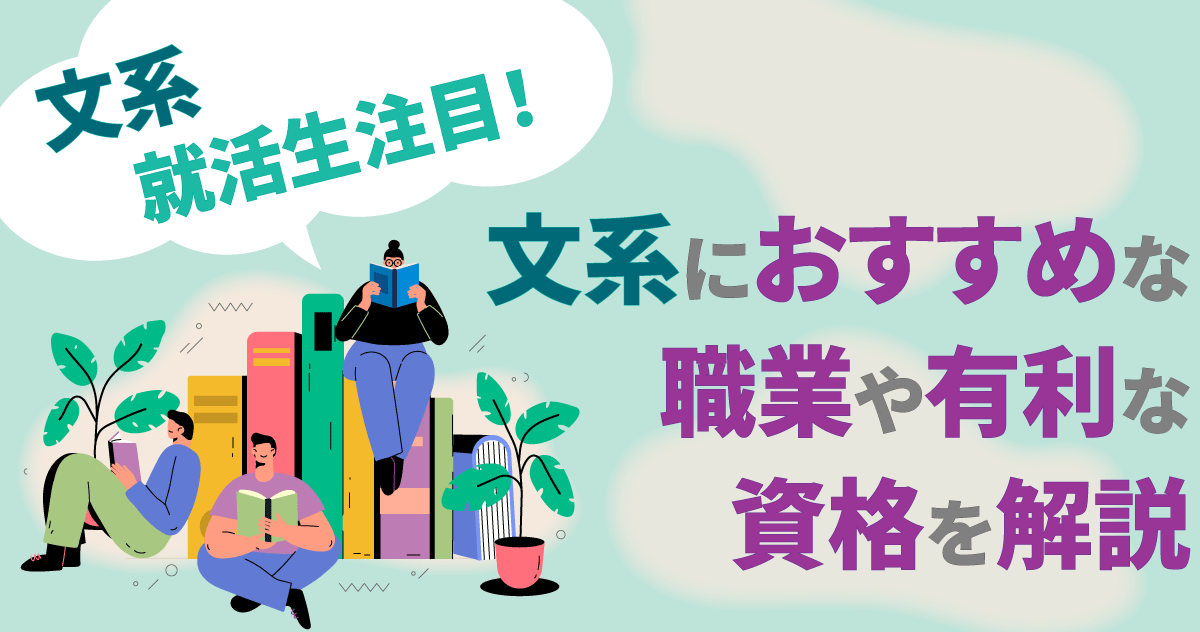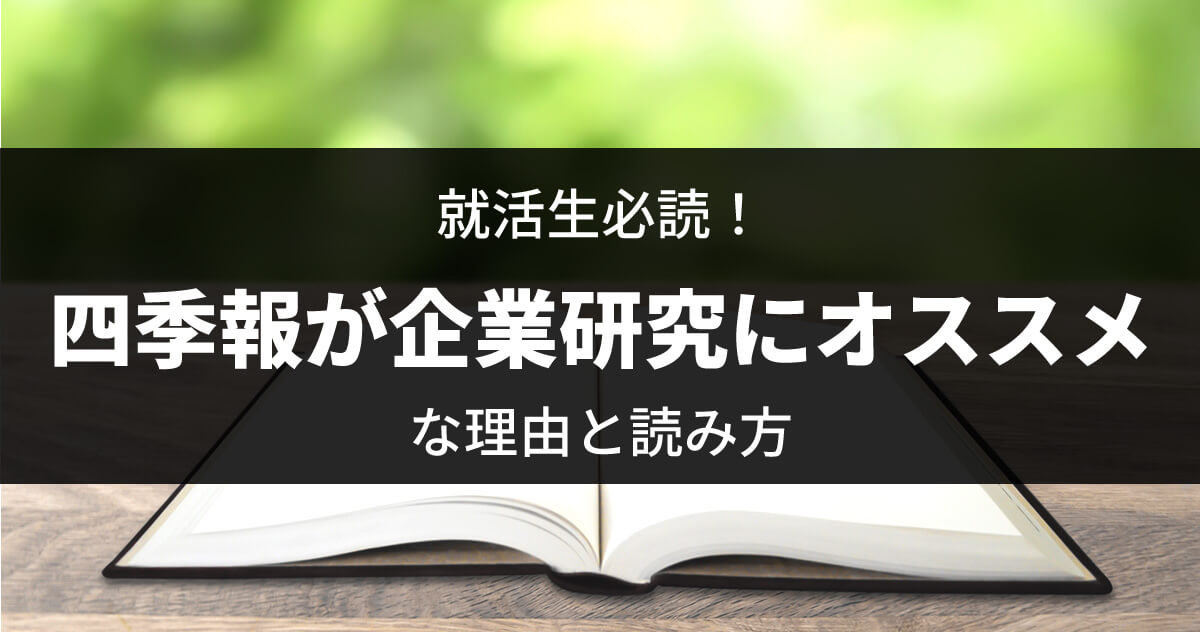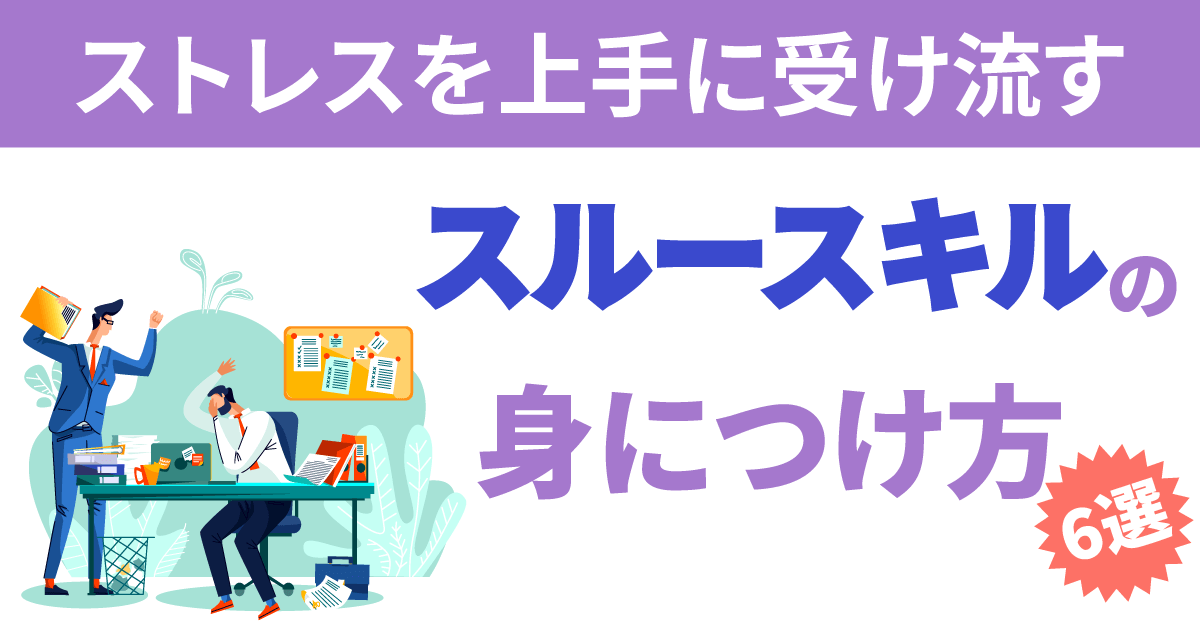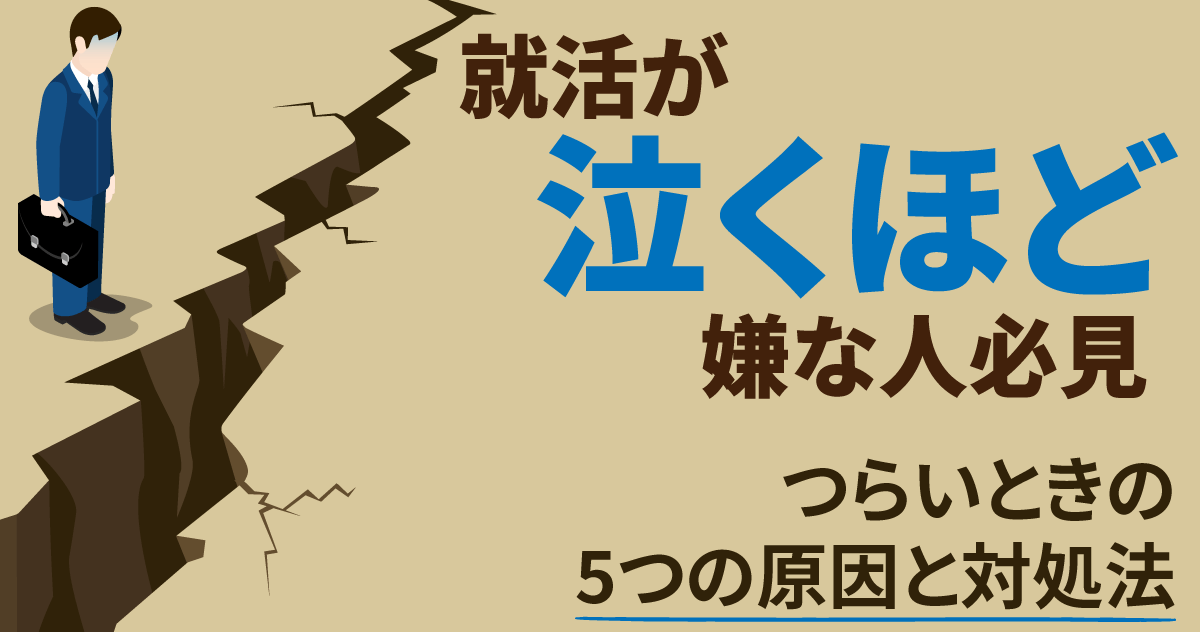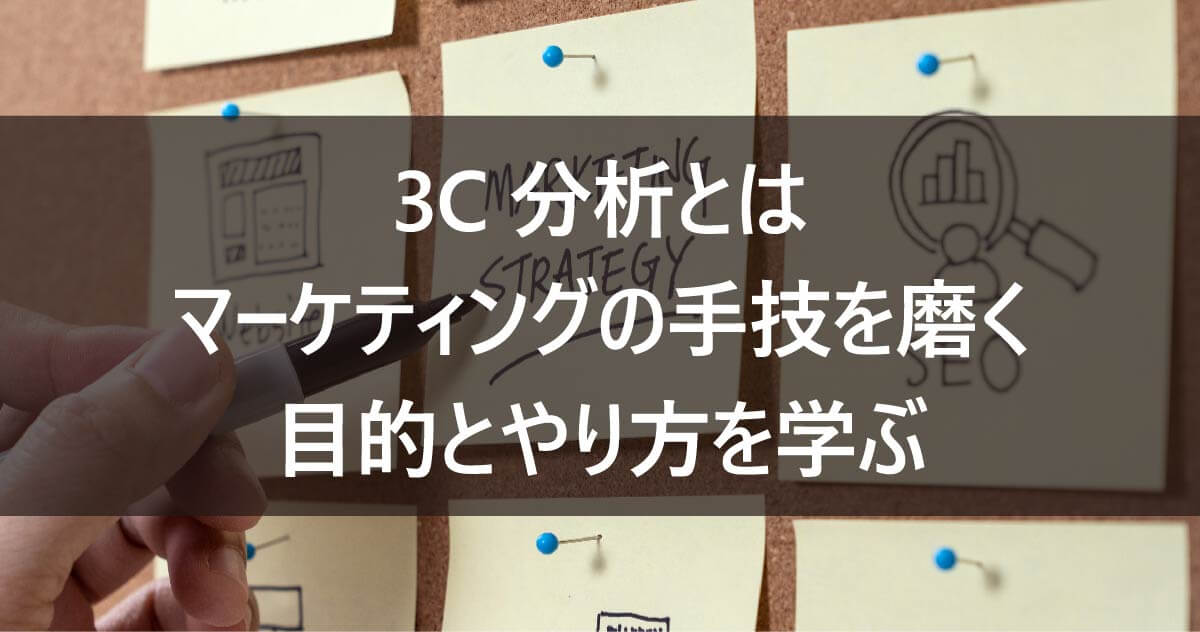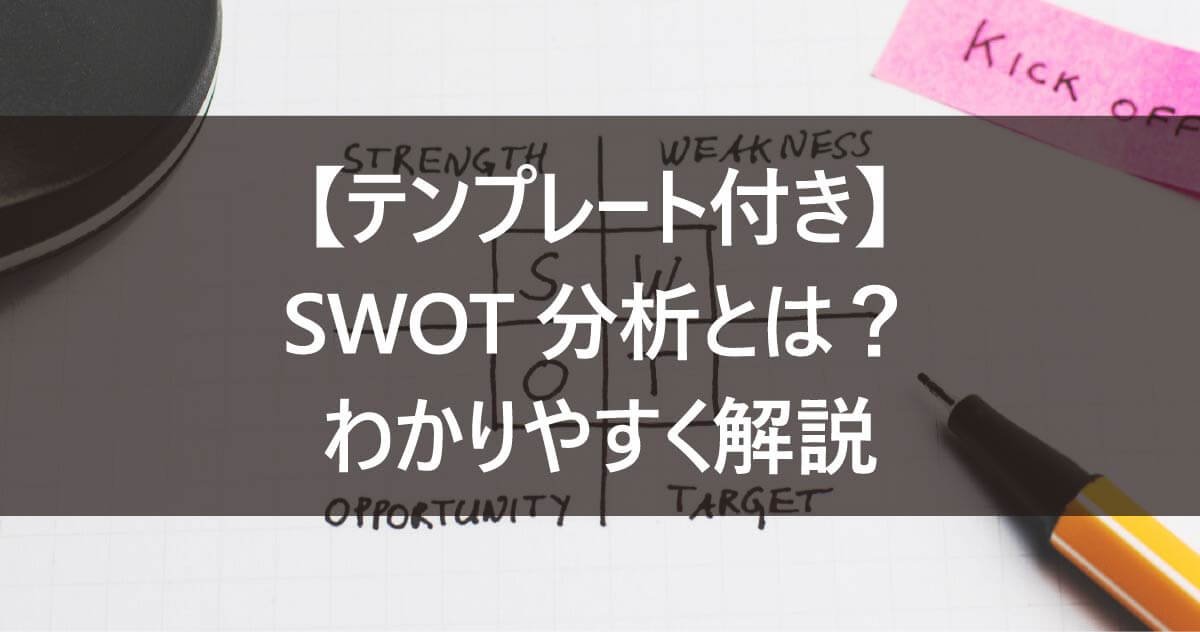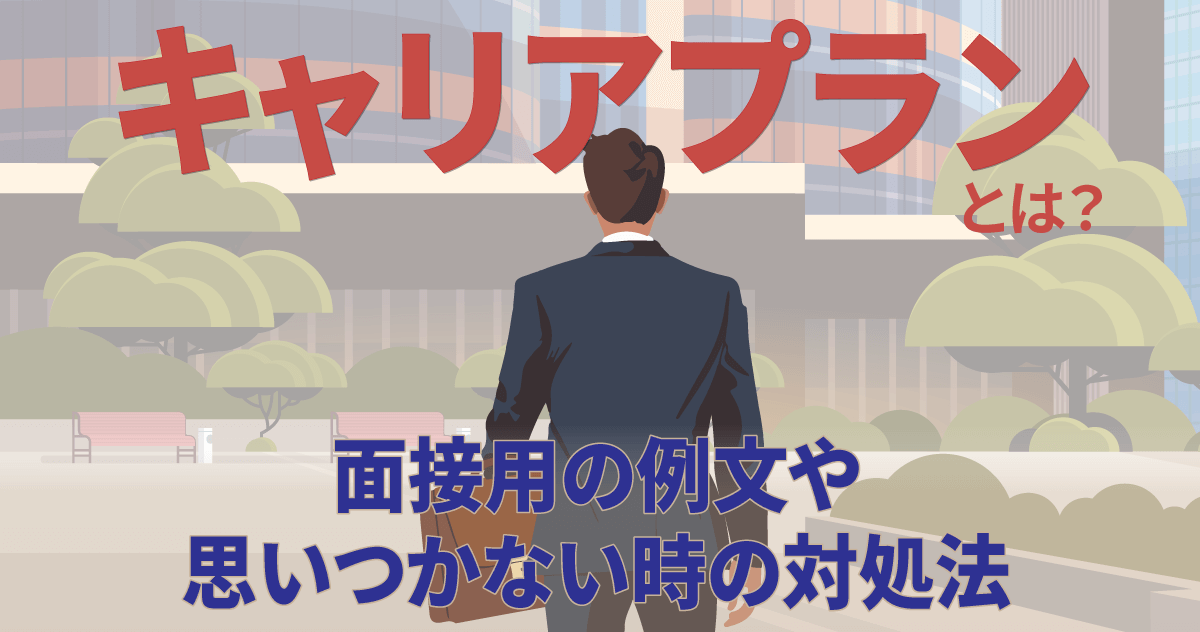- 青色申告は確定申告の一種である
- 青色申告には最大65万円の控除などの特典ある
- 青色申告をおこなうには事前申請と複式記帳が必要である
- 記帳が難しい場合は会計ソフトを利用するか税理士に依頼する方法がある
- 青色申告の疑問点は放置せず税務署窓口などに相談しよう
青色申告とは
青色申告とは、確定申告の方法のひとつです。確定申告は、1年の所得金額を確定し、そこから所得税を算出する手続きです。青色申告は個人事業主やフリーランス、法人が選択できる確定申告の方法であり、最大65万円の控除などの特典をうけることができます。
ただし、青色申告をするための事前申請が必要だったり、複式記帳をおこなう必要があったりと、手間も発生します。
この記事では青色申告のやり方やメリット・デメリットについてくわしく解説します。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。それぞれの違いは以下の通りです。
- 白色申告
白色申告は、帳簿の付け方が簡単だがあまり節税効果がない確定申告の方法だ。青色申告をしない場合、白色申告で確定申告をすることになる。
- 青色申告
個人事業主や法人が選択できる確定申告の方法が青色申告だ。ただし、青色申告をする場合は事前の申請が必要である。青色申告をするためには、1年の収支記帳と決算を複式記帳という複雑な方法でおこなわなければいけないが、最大65万円の控除を受けられたり、その他にも特典があったり、節税効果が大きい確定申告の方法である。
青色申告は、前述の通り帳簿のつけ方が複雑になって白色申告よりも難易度があがります。帳簿ソフトを利用して記帳したり 、仕事に関わるレシートや領収書をすべて保管したりする必要がでてきます。収支が大きかったり複雑すぎたりするような場合は、税理士への依頼が必要になることもあり得るでしょう。しかし手間がかかる分、大きな節税効果があります。
青色申告できる条件
青色申告は、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがある個人が対象です。たとえば、個人事業主・フリーランスで事業所得がある人や、所有している不動産によって所得がある人です。給与所得や雑所得のみでは青色申告対象者とならない(白色申告となる)ので注意しましょう。
青色申告が向いている人
青色申告に向いている人は以下の通りです。
- フリーランス・個人事業主で白色申告をしている人
- これから事業を始めようとしている人
- 事業が赤字になりそうな人
それぞれ解説します。
フリーランス・個人事業主で白色申告をしている人
フリーランス・個人事業主で今まで白色申告をしていた人は、青色申告にした方が大きく節税できるでしょう。
なお、これまで白色申告において記帳は必要なかったのですが、2014年1月より、白色申告でも簡易記帳の義務が生じました。したがって現状は、白色申告でも青色申告でも確定申告の手間は以前より減っている状況です。このため、似たような手間がかかるのであれば、青色申告をした方が節税できるのでオススメといえます。
これから事業を始めようとしている人
青色申告で確定申告をおこなうためには、税務署に事前の届け出が必要になります。このため、税務署で開業届の提出をするとき、同時に青色申告の申請も済ませてしまうと大変便利です。
事業が赤字になりそうな人
青色申告で確定申告をすると、決算時の赤字を3年間繰り越せるため、白色申告よりも節税効果があがります。とくに事業の開始直後は赤字になることが予想されるため、開業と同時に青色申告をはじめるのはやはりオススメといえます。
サラリーマンで副業している場合は?
サラリーマンで副業をしている場合、確定申告は、副業分を雑所得として白色申告で申請するパターンがほとんどです。しかしながら、事業規模や事業金額によっては青色申告ができることもあるため、青色申告が可能かどうか迷ったときは、税務署で相談するとよいでしょう。
青色申告のメリット
青色申告で確定申告をおこなう主なメリットは、以下の5つです。
- 青色申告特別控除が受けられる(最大65万円)
- 家族の給与(青色事業専従者給与)を経費扱いできる
- 赤字を3年間繰越ができる
- 減価償却の特例を受けられる
- 貸倒引当金を計上できる
それぞれ詳しく解説します。
青色申告特別控除が受けられる(最大65万円)
青色申告では、一定の要件を満たしたときに、65万円、55万円、10万円の特別控除を受けることができます。
まず、最大の控除額である65万円の青色申告特別控除を受けるには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 不動産所得または事業所得があること
- 複式簿記で帳簿をつけていること
- 帳簿をもとにした貸借対照表を確定申告書に添付する
- e-Taxで青色申告をおこなうか、もしくは2の帳簿を電子保管する
55万円の控除は、この要件のうち1~3までを満たすと受けられます。
65万円・55万円の要件を満たさなかったとき、または確定申告の期限までに提出が間に合わなかったときは、10万円の控除になります。
まとめると、次の通りです。
| 青色申告特別控除を受けるための要件 | |
|---|---|
| 65万円控除 | 次の条件をすべて満たすことが必要である ・不動産所得または事業所得があること ・複式簿記で帳簿をつけていること ・帳簿をもとにした貸借対照表を確定申告書に添付する ・e-taxで青色申告をおこなうか、もしくは帳簿を電子保管する |
| 55万円控除 | 次の条件をすべて満たすことが必要である ・不動産所得または事業所得があること ・複式簿記で帳簿をつけていること ・帳簿をもとにした貸借対照表を確定申告書に添付する |
| 10万円控除 | 65万円・55万円の要件をみたしていないときや、確定申告の提出期限日に間に合わなかった場合、最大10万円の控除となる。 |
なお、実際の所得税の計算方法はルートテックでも詳細に解説しています。
家族の給与(青色事業専従者給与)を経費扱いできる
青色申告では、配偶者や家族に支払った給料を経費扱いにすることが可能です。ただし経費扱いにするためには、事前に管轄の税務署に青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。なお、事前に届けた給与額より大きい額の給与は経費とすることができないので注意しましょう。
参考:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
赤字を3年間繰り越せる
青色申告では、3年間にわたって赤字の繰り越しができます。つまり、決算で赤字が出た翌年以降に黒字が出た場合、そこで赤字の清算ができるということです。
減価償却の特例を受けられる
減価償却とは、固定資産の購入費用を使用期間にわたり分割して費用として計上する処理のことです。
青色申告では、通常分割して計上する減価償却を取得価格が30万円未満であれば一括して計上することが可能です。分割計上しなくてよくなるため、節税できる範囲が広がります。
貸倒引当金を計上できる
青色申告では、貸倒引当金を計上できます。貸倒引当金とは、取引先の倒産などで売掛金が回収不可となるリスクを見越して、あらかじめ計上しておく勘定科目のことです。
つまり、貸倒引当金を計上することで、将来の貸し倒れリスクに備えつつ、所得の圧縮が可能です。
なお、金額の設定には上限があり、年末時点における売掛金などの債権残高の5.5%以下(金融業では3.3%以下)を貸倒引当金繰越として計上できます。
青色申告のデメリット
確定申告を青色申告でおこなうデメリットとしては、以下のものが挙げられます。
- 事前申請が必要
- 複式簿記で帳簿をつける必要がある
- 65万円の控除を受けるにあたりe-Taxによる電子申請が必須
それぞれ解説します。
事前申請が必要
確定申告で青色申告をおこなうためには、事前に「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。なお、白色申告をおこなうための申請はとくにないため、比較してデメリットといえるでしょう。
なお、青色申告をしたくても、青色申告承認申請書の提出をしていなければ、白色申告しかできません。
複式記帳をおこなう必要がある
青色申告をおこない65万円・55万円の控除をうけるためには、1年の収支について、複式記帳をおこなわなければなりません。複式記帳は二重で記帳する複雑な記帳方法であるため、かなり手間がかかります。これは青色申告でよくいわれるデメリットです。
対策としては、会計ソフトを利用して確定申告する、税理士に依頼するといった方法があります。
65万円の控除を受けるにあたりe-Taxによる電子申請が必須
青色申告で65万円の控除を受けるには、e-Taxによる電子申請か、または、複式記帳の帳簿を電子保管する必要があります。デジタルが苦手な人やPCを所有していない人には、大きなデメリットといえるでしょう。
青色申告の方法と期限
確定申告での青色申告は、以下の順番でおこないます。
- 事前に税務署に申請をする
- 申告に必要な書類を準備する
- 確定申告書を作る
- 確定申告をおこなう
なお、確定申告できる期間は決まっており、確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。ただし、初日や最終日が土日祝日の場合は、翌平日になります。青色申告の提出が最終日に間に合わない場合、ペナルティとして控除額が減る可能性があります。期間中に余裕をもって提出できるようにしましょう。
1.事前に税務署に申請をする
前項で解説した通り、青色申告をおこなうためには、事前に青色申告承認申請書を管轄の税務署に提出する必要があります。申請期限は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(ただしその年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをしたりした場合には、その事業開始等の日から2か月以内)です。提出を忘れた場合、その年は白色申告しかできません。
2.申告に必要な書類を準備する
申請を終えて、確定申告の期日が近づいてきたら、青色申告に必要な書類を準備します。必要な書類は以下の通りです。
- 青色申告決算書
- 確定申告書
- 添付資料
帳簿による決算書を作成し、付随する資料があれば添付します。これらをもとに、確定申告のための所定の用紙である「確定申告書」を記入することになります。
青色申告決算書
1年間の事業収支を表す重要な書類です。複式記帳による決算書を作成するには簿記の知識が必要ですが、近年では有料の会計ソフトに収支を入力するだけで自動的に複式記帳をしてくれるサービスが登場しています。個人事業主の方は、有料でもこちらを利用すると容易に青色申告できるのでオススメです。
添付資料
青色申告決算書の収支を証明する資料を添付します。
例:レシートや領収書、生命保険やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの控除証明書・掛金払込証明書、ふるさと納税の受領証明書など
確定申告書
確定申告には専用の用紙があります。以前は白色申告と青色申告は別の用紙でしたが、今は同一の様式に統一されています。電子申請(e-Tax)の場合は紙の申告書は必要ありませんが、記入したものを郵送する場合は、紙の申告書で提出することになります。事前に税務署などで確定申告用の申告書用紙を入手するか、国税庁のサイトからテンプレートをダウンロードして印刷しておきましょう。
参考:国税庁|所得税の確定申告
3.確定申告書を作る
決算書をもとに、確定申告書の作成をします。確定申告書の作成方法は複数あります。
- e-Tax(確定申告書作成コーナー)
- 会計ソフトによる出力または申告
- 手書き
e-Taxは、確定申告書作成コーナーというインターネットのWebページにアクセスして、オンラインで確定申告する方法です。
会計ソフトや確定申告ソフトは、複式記帳を自動でおこなってくれますし、e-Taxと連携してオンラインで確定申告がおこなえるものも多いので大変便利です。
手書きの場合は、確定申告用の用紙を使って記入します。
4.確定申告をおこなう
確定申告書が完成したら、確定申告をおこないましょう。申請方法は複数あります。
- 電子申請(e-Tax)
- 税務署の確定申告書作成コーナーで作成する
- 手書きの確定申告書を持参して税務署に提出する
- 手書きの確定申告書を税務署に郵送する
なお、郵送の場合は、消印の日付が提出日となります。
青色申告の際の注意点
確定申告を青色申告でおこなう際に注意すべきポイントを解説します。
保管が数年必要な書類がある
確定申告の際につけた帳簿やレシートなどの書類は、数年間の保管義務があります。白色申告と青色申告でそれぞれ保管期間が決められています。
青色申告の場合は次の通りです。
- 帳簿
保管期間:7年
- 決済関係書類
貸借対照表、損益計算書といった決算関係書類のこと。保管期間:7年
- その他関係書類
現金などのやり取りが記載されたレシート・領収書や生命保険の控除証明書など、通帳のコピーなどといった関連書類のこと。保管期間は原則7年だが、前々年分の事業所得・不動産所得が300万円以下のときは5年。
遅延や不正はペナルティがある
確定申告の遅延や不正は、追徴課税や青色申告承認の取り消しといったペナルティを受けることがあり得ます。
主な例は以下の通りです。
- 確定申告をしなかった場合、無申告加算税が課され、通常より納税金額が増える
- 期限後に確定申告をした場合は延滞税が課される
- 故意に所得を隠した場合、重加算税が課される場合がある
- 脱税や隠ぺいなどの行為をおこなった場合、青色申告の承認取り消し、さらには刑事罰(罰金・懲役)を受けることがある
- 2事業年度連続で期限内に申告が行われなかった場合、青色申告の承認が取り消しになることがある
参考:国税庁|法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)
疑問点がある場合は相談を
疑問点がある場合はそのままにせず、税務署や税理士による無料相談などの相談可能な窓口に相談しましょう。確定申告の内容が不正確な場合には追徴課税がかかることもあり、本来の金額より大きな金額が後から課される可能性もあるからです。
なお、相談窓口は複数あり、特に確定申告期間中は出張相談などが増えます。疑問点がある場合は積極的に利用を検討するとよいでしょう。
相談できる主な窓口や、参考になるWebサイトは以下の通りです。
- 所轄の税務署窓口(対面または電話)
- 青色申告会(相談するには有料会員になる必要があるので注意)
- 利用中の会計ソフトサポートサービス
- 税理士による無料相談会(確定申告期間中に商工会議所などでおこなわれる)
- インターネットのQ&Aサイト
まとめ
個人事業主やフリーランスは毎年確定申告をおこない、所得税を確定させる必要があります。確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、個人事業主やフリーランスは青色申告が可能です。
青色申告では、最大65万円の控除を受けられるほか、家族の給与を経費として計上できる、赤字の清算や減価償却の特例が利用できるなど、数多くのメリットがあります。ただし、青色申告にはデメリットもあり、手間がかかる複式記帳をおこなう必要があったり、青色申告をするための事前申請をしなければいけなかったりというデメリットもあります。
記帳が手間である場合は会計ソフトを利用する方法がオススメです。事業規模が大きかったり会計処理が複雑だったりという場合は、有料で税理士に依頼する方法もあります。
また、青色申告で不正や遅延をした場合はペナルティが課されます。そのため、疑問点は放置せず税務署窓口や税理士による無料相談会で相談したり、インターネットのQ&Aサイトを参考したりして正しく申告をおこなうようにしましょう。
- フリーランスの仕事とは、企業に所属せず自分のスキルや技術を活かして収入を得る
- 働き方の多様化が進む中で、働き手も企業もフリーランスという働き方にメリットを見いだし注目が高まった
- フリーランスの仕事は多々あるが、働く場所を選ばず、自己完結できたり時間の制約がなかったりするものが向いている
- フリーランスの仕事を継続するためには、案件獲得や自己管理、スキルアップを続けるなどの注意点がある
フリーランスとして働きたいと考えたとき、フリーランスにはどのような仕事があり、自分にできるのだろうか?と不安に感じている方へ。この記事ではおススメの職業16選と、フリーランスという働き方の魅力や、向いている職種について詳しく解説します。
フリーランスの仕事とは
フリーランスは、企業に所属せずに自分のスキルや技術を生かして働く人々のことです。この働き方は、さまざまな業種や職種に広がっています。時間や環境の制約があっても、空き時間を利用したり、自分の技術を高く評価してくれる案件に参入したりすることで仕事が成り立ちます。
なぜ今注目されるのか?
政府が副業や兼業、リモートワークを推奨し、働き方の多様化が進む中で、フリーランスへの注目が高まっています。
働き手は、自分の空き時間を活用できるメリットを享受し、企業は深刻な人材不足の中で人材確保にコストをかけるよりも、必要な業務に応じて契約できるフリーランスを活用することで、スキルや技術面でも頼れる人材を得られるようになりました。
参考:厚生労働省|副業・兼業
参考:厚生労働省|生涯における出来事と職業キャリア
参考:厚生労働省|フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
フリーランスに向いている仕事内容
フリーランスは、自分の工夫次第で、どのような業種でも実現可能な働き方といえます。ここでは特にフリーランスに向いている職種と仕事内容を紹介します。
ITエンジニア系の仕事
IT系の仕事はネット環境さえあればどこでも働けます。資格取得によるスキルやプロジェクト参加実績により経験値を示しやすい特徴があり、一旦企業に就職して一定以上の実績を積むことで、フリーランスとして独立しやすい職種といえます。
- プログラマー
- エンジニア
- Web制作
プログラマー
プログラマーは、プログラミング言語を用いて顧客の要望を実現するためのプログラムを作成する仕事です。いくつかのプログラミング言語を習得し、幅広いプロジェクト参加経験を通じて、フリーランスとして案件を獲得できる可能性が高いです。初心者でも参入しやすい職種ですが、常に新しい情報を収集し、スキルアップを心がけましょう。
エンジニア
エンジニアにはさまざまな専門分野があり、専門性を活かした働き方ができます。企業と契約し大きなプロジェクトに参加するほか、中小企業でもIT化が進んでいるため、エンジニアの需要は多く、幅広い働き方の選択肢があります。技術力に裏付けられた高収入も見込める仕事です。
Web制作
Web制作は、ホームページなどのWebサイトを作成する仕事で、フロントエンド技術を習得する必要があります。初心者でも案件を獲得できる分野です。高度な技術力やデザイン分野へスキルを広げることで、収入アップも期待できます。
クリエイティブ系の仕事
クリエイティブ系の仕事は、デザインや映像、画像などを成果物として納品します。個人で完結できる職種といえるため、フリーランスとして働く人材の多い分野となります。
クライアントが望む内容を提供するためには、傾聴力やコミュニケーション力は必要で、完成度の高い成果物の提供をすることで高収入が期待できる仕事です。
- デザイナー
- 映像クリエイター
- カメラマン
デザイナー
デザイナーはデザインを作成する仕事です。WebデザイナーはWebサイトに関連するデザインを作成しますが、グラフィックデザイナーやCGデザイナー、衣類や建築関連など、関わる媒体によって専門性があります。クライアントの要望をかなえることや、デザイン性や独自性の評価を得ることで収入につながります。
映像クリエイター
映像クリエイターは動画や映像制作にかかわる仕事です。テレビ・CM・映画・ネット・ゲーム・ミュージックビデオ・YouTubeなど、さまざまな業界で需要があります。映像制作の過程で仕事内容も細分化されており、得意分野で活躍できる仕事といえます。
カメラマン
カメラマンは撮りためた画像を販売したり、クライアントの要望する画像を撮影したりすることで収入を得ます。関わる業界も多く、得意な被写体によって専門性をアピールすることも可能です。人気のカメラマンになると高収入も望めます。
マーケティング系の仕事
マーケティング系の仕事は、さまざまなデータを分析して商品の販売戦略や企業の経営戦略の一端を担います。分析力だけでなく、論理的思考力も求められます。
- Webマーケター
- ブロガー・アフィリエイター
- データサイエンティスト
Webマーケター
WebマーケターはWeb対策に特化したマーケターです。SEO対策の知識をもち、SNSやサイト運用時の戦略を立てる仕事です。昨今、需要が増えている分野といえます。企業やインフルエンサーなどと契約して報酬を得ます。
ブロガーやアフィリエイター
ブロガーやアフィリエイターは自分のブログやWebサイトで記事を掲載し、商品やサービスの魅力を伝えます。自分が書いた記事を通じて商品やサービスが売れた際に収入につながる仕事です。読者が何を求めているのかを正確に分析し、購買力を刺激する魅力を伝えるためのライティング力が必要です。
データサイエンティスト
データサイエンティストは、ビッグデータを分析し、解析して課題を立案する仕事です。商品やサービスの開発、経営、ビジネス戦略においてもビッグデータの活用は重要であり、フリーランスへの需要も多い分野といえます。即戦力を求められる場合が多いため、知識と経験が必要です。
接客・経営系の仕事
接客や営業といった集客に工夫の必要な職種も、スキルや資格を活かし工夫次第で、フリーランスとして活躍できます。
- 営業代行
- 理美容師
- トレーナーやカウンセラー
- 士業
- インフルエンサー
営業代行
営業代行は、企業や営業の苦手なフリーランスなどの営業の一端を担い利益につなげます。企業は新人を育てるよりも、即戦力となるフリーランスの活用が増えています。営業が得意で培った経験を活かした営業代行は、安定した収入が見込める職種といえるでしょう。
理美容師
理美容師は国家資格を持ち、フリーランスとしての活動の場が広い仕事です。店舗をもつ理美容院や病院、福祉施設などと契約し、自分の空き時間に赴いて技術提供することで収入を得られます。
トレーナーやカウンセラー
トレーナーやカウンセラーは、相談者の要望の聞き取りからアドバイスをしたり、課題解決に向けたプログラムの提供をしたりする仕事です。スポーツトレーナーや心理カウンセラーなどがこれにあたります。幅広い知識や資格を担保に、Webサイトを活用しSNSなどで顧客を集めたり、店舗展開する事業主と契約したりと働き方はさまざまです。
士業(税理士・司法書士等)
士業は国家資格を持つ職業で、税理士や司法書士などがあります。事務所を構えて顧客を集めるという働き方が一般的ですが、SNSやWebサイトを活用して企業と契約したり、個人客からの依頼を受けたりすることで、フリーランスとして働くことも可能です。
インフルエンサー
インフルエンサーは企業やブランドから報酬を得て、商品やサービスのPR、レビュー、ライフスタイルの提案などを、SNSを通じて発信します。フォロワーの購買行動に強い影響力を与えるためのコンテンツ作成や、フォロワーとのコミュニケーションを通じてマーケティング活動を行う仕事です。
その他
他にも自分の得意分野を活用した、こんな働き方もあります。
- 料理代行
- ペットシッター
料理代行
料理代行は忙しい主婦に代わって、お客様宅に行き朝食・昼食・夕食の調理や作り置きおかず・お弁当の下ごしらえ、ホームパーティー用の料理などを調理する仕事です。女性もフルタイムで働く現代では料理代行の需要は増えています。調理師免許があると信頼されやすくなり、保健所への届け出や食品衛生に関する知識を求められるケースもありますが、得意な料理を作ることで収入を得られる仕事です。
ペットシッター
ペットシッターは家族の一員であるペットの世話を代行する仕事です。散歩や餌やり代行、1日預かりなど、好きな動物と触れ合いながら収入を得られます。
フリーランスの仕事の探し方
フリーランスにとって最も重要なことは案件の獲得です。継続して活動するために必須となる仕事の探し方を紹介します。
友人や知人の紹介
友人や知人、前職の関係者など自分を理解している人たちからの紹介です。人となりを理解している人からの紹介は、最初のハードルを下げてくれる効果があります。堅実な結果を残すことで、さらに紹介してもらえる可能性も高まるため、人とのつながりを大切にすることが近道といえます。
クラウドソーシングの利用
クラウドソーシングでは、企業が求める業務内容を提示し、フリーランスは自分のしたい業務に応募します。クラウドソーシングは、企業とフリーランスを結ぶ架け橋のような存在です。インターネット上で完結できるため、営業が苦手なフリーランスにとっても利用価値の高いサービスといえます。
SNSの活用
情報発信手段の豊富な現代では、それを活用しない手はありません。SNSやブログ、X(旧Twitter)
などで、自分の仕事を知ってもらう工夫をしましょう。問い合わせや依頼が来る可能性もあります。
フリーランスになるための注意点
フリーランスとして仕事をはじめたら、できるだけ長く継続したいものです。そのための必要なことや注意点を紹介します。
フリーランスは自由である以上の自己管理が必要になる
フリーランスは働く時間や場所を自由に選択できますが、自由の意味を履き違えると、収入が先細りになる可能性があります。決められた時間や条件と約束事を守り、仕事の成果や仕上がりのレベルを確保する必要があるからです。自由とは、自分の好き勝手にできることではなく、正しい自己管理のうえに成り立つと認識しましょう。
フリーランスになると仕事以外の諸事を自分で行う必要がある
フリーランスは全て自分で行うという覚悟が必要です。営業による案件獲得、確定申告に必要な書類や金銭管理、仕事の進捗を確認するためのタスク管理、さらに、自分が健康でないと継続できないので健康管理も重要となります。
フリーランスを継続するにはスキルや経験をあげる努力を続ける
フリーランスにとって、「ここまでは任せられるが、それ以上は難しい」とクライアントに思われた場合、案件の継続が難しくなり、先細りのリスクが生じます。常に新しい情報に触れ、スキルや経験をあげる努力を続ける必要があります。
まとめ
フリーランスに向いている仕事を紹介してきましたが、どのような業界・職種でも工夫次第でフリーランスとして働くことは可能です。自分のしたい仕事でフリーランスとして活躍するために、何が必要かを考えるきっかけにしていただければ幸いです。
]]>- 偽情報とは事実ではない、もしくは誤解を招くような情報のこと
- インターネットの普及にともない偽情報が社会問題化しており、早急の対策が必要
- 企業の偽情報リスクはブランドイメージの低下、顧客離れ、株価の暴落、訴訟リスク
- 生成AIの急速な普及で偽情報は増加・高度化しつつある
- 偽情報の対策はファクトチェック・クロスチェック、情報リテラシーの向上、信頼できる情報源の利用、SNSプラットフォームのフィルタリング機能の活用
近年のインターネット普及社会では、SNSやニュースサイト・動画配信などを介して膨大な量の情報が存在し、その中には偽情報もあるのです。偽情報は、企業や個人の判断を狂わせるリスクがあり大変危険なものですので、ここで偽情報のリスク・対策をしっかりと知っておきましょう。
偽情報とは
偽情報(ぎじょうほう)とは、事実ではない、もしくは誤解を招くような情報のことを指します。単なる悪意のない間違った情報とは違い、世論操作・特定の目的達成のために故意に流布されるという点が大きく異なります。
たとえば、誰かが誤ったニュース記事を真実だと信じて広めてしまった場合、それは誤情報です。しかし特定目的のため意図的に虚偽のニュース記事を作成・拡散した場合は、偽情報あるいは悪意のある情報となります。
情報の種類
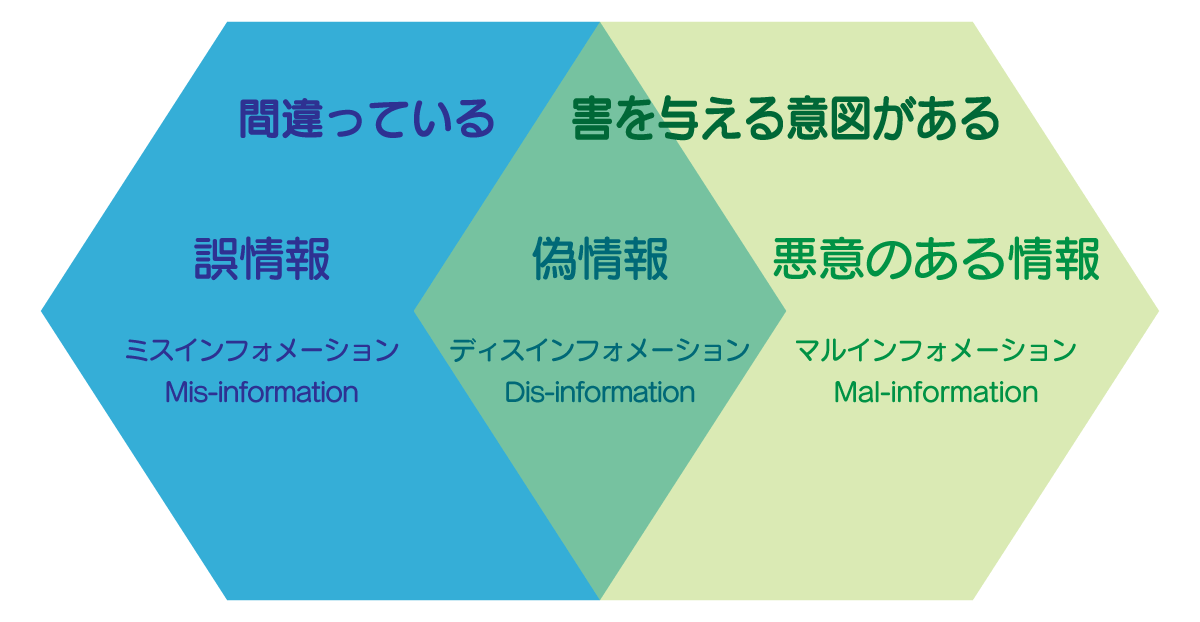
ここからは情報の種類について3つ解説します。それぞれについて混同しないようしっかりおぼえておきましょう。
1 ミスインフォメーション(誤情報・Mis-infomation)
ミスインフォメーション(日本語では誤情報と訳されることが一般的)とは、意図せず広められる不正確な情報のことで本人は正しいと思っていても実は間違っていることが多いという特徴があります。
悪意がない場合でも個人・企業の判断を誤らせたり社会に混乱を招いたりする可能性があります。
- 意図:だますつもりはない
- 内容:事実とは異なる
2 ディスインフォメーション(偽情報・Dis-information)
ディスインフォメーション(日本語では「偽情報(ぎじょうほう)」と訳されることが一般的)は意図的に作られ、誤解や混乱を引き起こす目的で広められた虚偽の情報のことです。
1で解説した誤情報が、単に間違った情報であるのに対して、偽情報は特定の目的をもって故意に流布されるという点が異なります。意図的に人をだますために作られた虚偽の情報で最初からウソとわかっていて、誰かを誤解させるために流される情報のことです。
- 意図:だますつもりがある
- 内容:事実とは異なる
3 マルインフォメーション(悪意のある情報・Mal-information)
マルインフォメーションは真実に基づいていながら悪意のある意図をもって公開または拡散される情報のことで、個人・組織・国家などに危害を与えることを目的としています。
ミスインフォメーションやディスインフォメーションとは違い、マルインフォメーションはウソやねつ造された情報ではありません。問題となるのは、情報の公開の仕方、タイミング、そしてその意図です。
- 意図:悪意がある
- 内容:内容自体は事実
偽情報セキュリティの必要性
近年インターネットの普及により、情報が瞬時に世界中に拡散されるようになりました。
その一方で意図的に作り出された虚偽の情報、いわゆるフェイクニュース、ディープフェイクの存在が社会問題化しています。
偽情報セキュリティでは 、デマやウソ情報を見抜くことだけではなく、偽情報が個人・企業・社会に与える深刻なリスクを防ぐための対策が必要です。
企業に対する偽情報の脅威
企業に対する偽情報の脅威を4つ解説します。企業に対する偽情報の脅威は、現代社会において無視できないリスクとなっていますが、どのようなものがあるのか見ていきましょう。
1 ブランドイメージの低下
偽情報によって、企業の信頼性・ブランドイメージが低下させられる可能性があります。
たとえば、企業に関する虚偽や誤解を招く情報が社会に広まり、それによって企業や製品・サービスに対する消費者や社会全体の信頼や好感度が損なわれるなど、が考えられます。
2 顧客離れ
偽情報によって、顧客が離れてしまう可能性があります。
ブランドイメージの低下が潜在的な顧客や将来の顧客に影響を与えるのに対し、顧客離れは既に企業との関係性を築いていた既存顧客が離れていくという影響を企業に与えます。
3 株価の暴落
偽情報によって、企業株価が暴落してしまう可能性があります。
企業に関する虚偽や誤解を招く情報が投資家や市場参加者に広まり、それが原因で企業の株価が急激に下落するリスクが存在します。株式市場は投資家の期待や信頼によって大きく左右されるため、ネガティブな偽情報はパニック売りを引き起こし、株価を大きく変動させてしまう力をもっています。
4 訴訟リスク
偽情報によって、企業が訴訟されてしまう可能性があります。
企業に関する事実に基づかない情報が広まることによって、企業が法的責任を問われ訴訟を起こされるリスクが存在します。
生成AIによって高度化する偽情報の現状
昨今の生成AIの急速な普及は、偽情報の増加・高度化に拍車をかけています。
偽情報はより巧妙かつ大量に生成・拡散されるようになり、企業・政府・一般社会に深刻な影響を及ぼしつつあるのです。以下は偽情報の作成に、生成AIがどう使われているかの例になります。
- リアルなテキスト生成:自然で説得力のある文章、特定の文体やトーンの模倣など
- 高精度な画像・動画生成:実在しない人物・場所・出来事のねつ造、ディープフェイク動画の進化など
- 音声合成によるなりすまし:自然な話し方の再現など
- 複合的な偽情報の生成と拡散:テキスト・画像・動画の組み合わせ、ソーシャルメディアでの拡散を最適化など
偽情報の対策
偽情報対策は、個人、企業、政府、プラットフォーム事業者など、社会全体で取り組むべき重要な課題です。偽情報の拡散を防ぎ、リスクを軽減するための対策を4つ解説します。
1 ファクトチェック・クロスチェックの習慣をつける
偽情報対策の1つ目はファクトチェック・クロスチェックの習慣をつけることです。信頼できる情報源を確認し、同じ情報が他ニュースソース・公式機関でも報じられているかを確認するということです。
ファクトチェックはもちろんのこと、ひとつの情報に頼らず、他の信頼できる情報源でも確認するクロスチェックをおこなうことが、 偽情報に惑わされないための強力な防波堤になります。
2 情報リテラシーの向上
偽情報対策の2つ目はインターネットに対する情報リテラシー教育をおこなうことです。
情報リテラシーとは情報を適切に理解・評価・活用する能力のことです。ただ情報に詳しいというわけではなく、流されずに正誤を判断し、自分で考える力のことを指します。
企業が情報リテラシー教育をおこなうメリットを3つ挙げます。
- 社員が偽情報にだまされない。誤った判断や行動を避けられる
- 企業としての誤発信・誤対応のリスクが減る
- 社内外からの信頼性が高まり、ブランド価値が向上する
3 信頼できる情報源の利用
偽情報(フェイクニュース、誤報、意図的なミスリードなど)は、個人の判断を誤らせるだけでなく社会全体の混乱や不信感の原因となります。これを防ぐには、情報を受け取る際に出所を確認し、信頼できる情報源を意識して選ぶことが欠かせません。以下に、信頼できる情報源の例を5つ挙げます。
- 公的機関:内閣府、厚生労働省など
- 大手報道機関:NHK、BBC、大手新聞など
- 国際機関:世界保健機関(WHO)、国際通貨基金(IMF)など
- 学術機関:大学、研究所、学術論文など
- 専門家の発言:有資格者(医師、研究者など)による情報など
4 SNSプラットフォームのフィルタリング機能の活用
社会に普及しつつあるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は情報発信の自由度が高い一方で、偽情報の拡散源となるリスクもあります。そのため、多くのSNSプラットフォームでは偽情報対策として「フィルタリング機能」「コンテンツ管理機能」を導入しています。必要に応じて設定・利用するといいでしょう。
まとめ
ここまで「偽情報セキュリティとはなにか?/偽情報の脅威・対策など」というテーマで解説してきました。
そもそも偽情報とは、事実ではない、もしくは誤解を招くような情報のことです。
偽情報セキュリティとは偽情報(フェイクニュース・誤情報・操作された情報など)から個人や組織、社会を守るためのセキュリティ対策全般を指します。
近年、インターネットの普及にともない偽情報が社会問題化しており、早急の対策が必要です。
企業に対する偽情報リスクとして4つ解説しました。
- ブランドイメージの低下
- 顧客離れ
- 株価の暴落
- 訴訟リスク
また社会へ生成AIが普及しつつあり、偽情報の増加・高度化してきています。
偽情報への対策として4つを解説しました。
- ファクトチェック・クロスチェックの習慣をつける
- 情報リテラシーの向上
- 信頼できる情報源の利用
- SNSプラットフォームのフィルタリング機能の活用
社会の変化に対応して、平時から偽情報の発生に備える必要性があります。
]]>- 扶養に入ることで健康保険料や年金保険料の負担がかからないメリットがある
- 扶養には社会保険上の扶養と税法上の扶養の2種類がある
- 社会保険における扶養の条件は年収130万円未満が原則である
- 税法上の扶養控除を受けるには合計所得金額が48万円以下でなければならない
- 扶養条件を維持するには年間収入を常に意識するようこころがける
フリーランスを始める際に、扶養内で働けるのか気になったことはありませんか? 近年、働き方改革の時代により、フリーランスとして働く人が増えました。中には配偶者の扶養内で働く人も少なくありません。しかし、年収の壁に対して、フリーランスが働く上でどのような基準や条件で見ればいいのか、不安や疑問を抱えたことはあると思います。本記事で扶養に入るための手続き方法と流れを理解し、年収基準や所得を超えないためのコツとともにポイントを見ていきましょう。
フリーランスが扶養内で働くとは?
そもそも扶養内で働くとは、生計を立てていくのが難しい場合に、配偶者や親など身内からの経済的な援助を受けながら働くことです。扶養に入ることで社会保険料や税金などの負担を経済的に減らすといった目的があります。
扶養内で働くメリット・デメリット
扶養に入る上でのメリットやデメリットとは一体どのようなことなのでしょうか? 以下、それぞれについて説明します。
メリット
健康保険料や年金保険料を自分で負担しなくとも良いというメリットがあります。たとえば国民健康保険に加入した場合、毎月数万円の支払いを必要とします。しかし、配偶者の扶養に入れば、国民健康保険や国民年金に加入する必要がなくなり、毎月の保険料負担が大幅に軽減されます。仕事と収入が不安定なフリーランスにとって、税金や社会保険料を節約できるという点では大きなメリットでしょう。
デメリット
逆に、扶養に入ることで年収に制限がかかるため「もっと働きたい」と思っていても、仕事量を扶養範囲内に収めるよう制限しなければならないことがあります。こうした収入制限が扶養内で働くフリーランスにとって、デメリットに感じる人も少なくありません。もし、順調に収入が増えて軌道に乗ってきた場合は、扶養から外れることも検討すると良いかも知れません。
フリーランスが入れる2種類の扶養と条件
フリーランスであっても扶養条件を満たせば、問題なく扶養に加入できます。扶養には大きく分けて社会保険上の扶養と税法上の扶養の2種類があります。
以下、それぞれに分けて見ていきましょう。
社会保険上の扶養の場合
社会保険上の扶養は、健康保険や年金の負担を免除するための制度です。条件として配偶者(扶養者)が「厚生年金」に加入していることが必須とされています。また、配偶者が個人事業主またはフリーランスの場合は対象外となるため注意が必要です。年収制限として、フリーランスの年収が130万円未満であることが求められます。
税法上の扶養の場合
一方で税法上の扶養は所得控除を受けられる制度で、所得金額が48万円以下であることが条件です。フリーランスの場合は売上から必要経費を差し引いた所得が対象になるのです。所得が48万円を超えると配偶者控除を受けられなくなるため、確定申告の段階できちんと調整する必要があります。両方の扶養で基準が異なるため、同時にクリアするには所得と収入のバランスに注意しなければなりません。
フリーランスが扶養に入るための手続き方法
フリーランスが配偶者の扶養に入るための手続き方法について、見ていきましょう。
書類の提出先
フリーランスが扶養に入るためには、まず配偶者の勤務先の人事担当部署、または健康組合を経由して年金事務所に提出します。
必要書類
事前準備として、被扶養者は「健康保険被保険者(異動)届」に必要な事項を記入します。その後、申請に必要な添付書類の準備もしなければなりません。詳細は以下をご参考ください。
- 【提出書類内容】
- 健康保険被保険者(異動)届
- 収入を証明する書類(次のいずれか)
- 確定申告書のコピー
- 所得証明書
- 給与証明書
- 離職票のコピー
- 続柄を証明する書類(次のいずれか)
- 戸籍謄本(あるいは戸籍抄本)
- 世帯全員が記載された住民票
申請時のポイントとよくある落とし穴
収入見込みを少なく見積もって申請してしまうと、扶養認定後に収入額が基準を超えた場合、過去に遡って保険料を徴収される可能性があります。申請の際は現実的な収入見通しを提示しておくことが重要ポイントです。また収入増加が予想される場合は、必ず、早めに配偶者の勤務先へ連絡するようにしましょう。
扶養内で働きながらフリーランス活動を続けるコツ
フリーランス活動を続けていく上で、扶養範囲内に収めるためのコツやポイントはどのようなことでしょうか? 以下、2つを見ていきましょう。
年間収入の管理をする
扶養条件を維持するには、年間収入を常に意識することが不可欠です。特に、年末に駆け込み受注をしがちなフリーランスは注意が必要です。ノートやExcelの表などを利用し、収入の記録をつけておくと収入の集計にも大変便利です。さらに、経費の管理もしやすくなり、収入と経費の差を定期的に見直せます。また、月次で収入管理を行うことで、繁忙期でも計画的にセーブできるでしょう。
必要に応じた契約・案件選びをする
高単価案件や長期契約案件を受けた場合、収入額をオーバーしてしまう恐れがあります。扶養内を意識するのであれば、単発案件中心に受注し、収入調整をしやすくしておくことがコツです。どのように案件を受注したいか、具体的に目標を決めておきましょう。案件のリサーチで内容や報酬、納期をきちんと確認して、自分の希望条件をリストにあげておくと無理のない契約・案件選びができるでしょう。
フリーランスが扶養から外れる際のポイント
万が一、収入が扶養基準を超えて、扶養から外れてしまった場合、どのようにしたらよいでしょうか? いざという時のために困らないように、事前に手続きや保険料負担をシミュレーションしておくと良いでしょう。扶養から外されてしまった際のポイントは以下の通りです。
配偶者から扶養元に申告する
まず、配偶者が勤めている会社へ扶養を外したい旨を申告することから始めます。担当から必要な手続きなどを説明してもらえるので、指示に従って速やかに手続きをしましょう。健康保険と年金をセットで手続きをしますが、加入先によって手続きも異なりますので、受け取った書類をよく確認して手続きを進めることがポイントです。
国民健康保険・国民年金への切り替えを行う
一般的には扶養基準を超えて扶養を外されてしまった場合は、国民健康保険および国民年金への切り替えを考えるのが賢明です。国民健康保険料は収入額が多ければ多いほど保険料は高くなりますが、収入額が少ない場合は軽減措置があります。ただし、国民健康保険料の軽減や国民年金の免除は、基本的に世帯全体の所得が少ないことが条件です。もし、本人のみの収入が少なくても、世帯内に高所得者がいる場合は適用されないことがあります。また国民年金の保険料については定額ですが、収入が少ない場合は特例措置(免除申請)についてお住まいの市区町村の役場へ相談してみると良いでしょう。
所得や税金の管理(確定申告の準備)をする
フリーランスは時給で働く従業員とは違って、収入のコントロールが難しいのが特徴です。そのため、自分自身で1年間にどのくらい稼いだかを、確定申告する必要があります。確定申告することによって、どのくらいの税金を支払うのか決定します。
まとめ
フリーランスが扶養内で働くための条件や手続き方法についてご理解いただけたでしょうか? 扶養内で働くメリットとして健康保険料や年金保険料の負担が軽減しますが、年収制限がかかるデメリットもあります。また年収と安定性のバランスが重要ポイントとなるため、社会保険上と税法上それぞれの条件に注意しなければなりません。フリーランスが扶養内で働くために年間収入を管理することを意識しながら、バランスよくコントロールしていきましょう。
]]>- 個人事業主の経費とは、事業活動に伴って必要となる支出のこと
- 適切な経費の計上は、節税効果が期待できる
- 経費は領収書等を整理して、勘定科目ごとに金額をまとめる
- 個人事業主が経費にできないものは、事業とは関係のない個人的な費用や支出である
- 自宅兼事務所利用の場合は、個人と共有する費用の家事按分(かじあんぶん)が必要になる
確定申告で何が経費として計上できるのか、必要なものや対応する勘定科目は何かから、計上できないものや、個人事業主ならではの判断に迷う経費について詳しく解説します。経費計上は節税対策につながりますが、計上しすぎるとリスクも伴います。どのように経費を計上すればよいか、上手な経費計上の方法をお伝えします。
個人事業主の経費とは
個人事業主の経費とは、事業活動に伴って支払った費用のことを指します。個人事業主の場合、個人的な費用と混同されがちなので、しっかりと区別する必要があります。経費を正しく認識し管理することで、適切な節税効果を得られます。
個人事業主の経費はどこまで計上できる?
計上できる経費に上限はありません。事業に関連する経費であれば、いくらでも計上することが可能です。しかし、収入と経費のバランスが悪いと税務署に不信感を抱かせる要因となります。たとえば、収入よりも多額の経費が続いたり、個人の費用を計上したりが疑われる場合です。経費は事業で生じたものであることを明確に示す必要があります。
経費計上が節税になる?
確定申告で納税額算出の基本となる課税所得金額の求め方は以下の通りです。
課税所得金額の求め方
※課税所得金額とは、確定申告で納税額を求める基本となる金額
課税所得金額=収入-経費-所得控除額
この計算式からもわかるように、経費を漏れなく計上することで、節税効果が期待できます。
経費と認められる判断基準は?
個人事業主の経費を認められるための判断基準は以下の3つです。
- その支出が事業と関連しているか
- 事業にとって必要なものか
- 支払額が一般的判断で妥当な範囲内か
認められない例には、完全在宅のWebライターが通勤用として自家用車の使用している場合や、実際に利用していない自宅の一室を事務所として申告している場合があります。
経費率に目安はある?
経費率の目安は業種や事業規模によってさまざまで、一概に提示することは難しいのが実情です。しかし、以下のみなし仕入れ率を参考にすることは可能です。
- 第1種事業:90%(卸売業)
- 第2種事業:80%(小売業、飲食料品の譲渡に係る林業・農業・漁業)
- 第3種事業:70%(第2種事業を除く林業・農業・漁業や製造業・建築業)
- 第4種事業:60%(飲食業など)
- 第5種事業:50%(サービス業・金融・保険など)
- 第6種事業:40%(不動産業)
参考:国税庁|No.6509 簡易課税制度の事業区分
個人事業主が経費にできるもの一覧
個人事業主が経費にできる経費項目は、事業形態や事業内容に応じて異なる場合があります。以下の経費一覧は、主な勘定科目をまとめたものです。
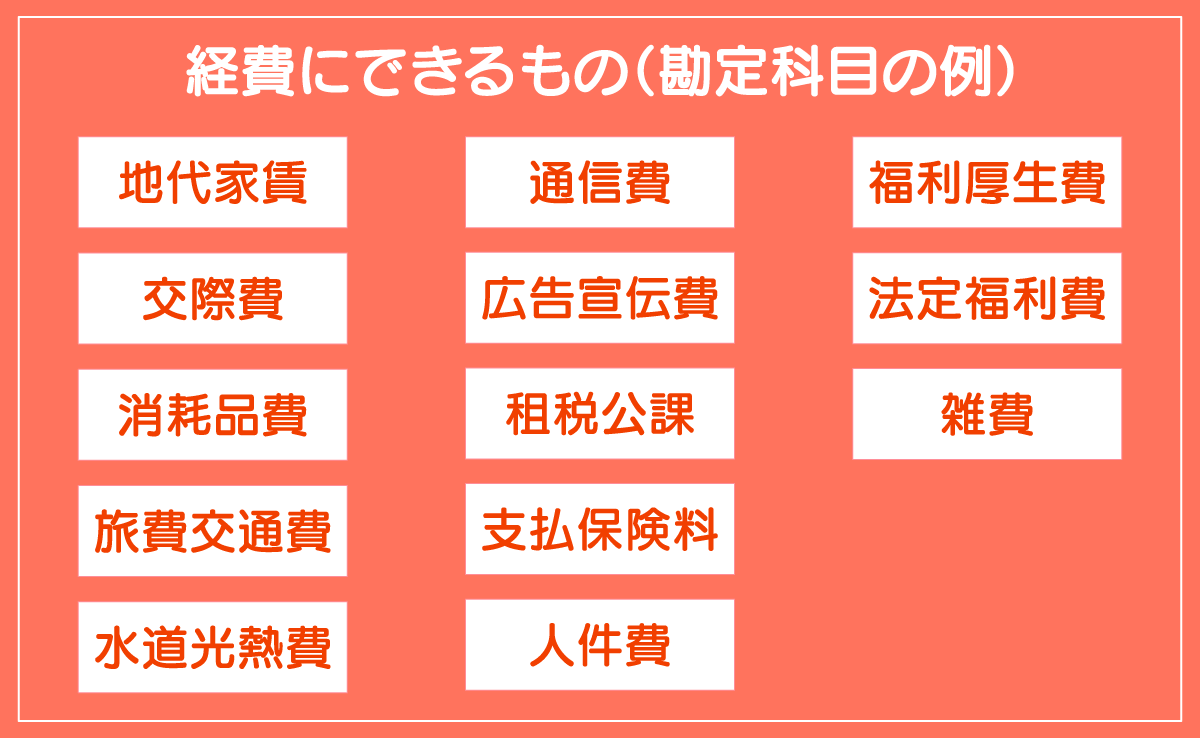
地代家賃
地代家賃は、事業用の土地や建物を借りる際の費用を計上する項目です。事務所や店舗を借りている場合の家賃・管理費・共益費や、社用車の駐車場代、新規に借りる際の契約に関する費用等が計上できます。ただし、自宅用の駐車場代等には利用できません。
交際費
交際費は、取引先との打ち合わせやミーティング等にかかった食費や、ゴルフ等の接待にかかった経費を計上する項目です。家族や友人など個人的な会食には利用できません。
消耗品費
消耗品費は、法定耐用年数が1年未満で、固定資産にならない10万円未満の事務用品や電化製品等を計上する項目です。文房具やコピー用紙、名刺、パソコン周辺機器など少額物品も含まれるため、領収書を保管し経費計上することが重要です。
旅費交通費
旅費交通費は、事業に必要な移動に係る電車・バス・タクシー等の交通費や、出張時の宿泊・交通費・日当、高速道路料金(ETC利用料)やガソリン代等を計上する項目です。出張時の食事代は基本的には含めませんが、食事付きの宿泊プランでの食費は経費に含められます。
水道光熱費
水道光熱費は、店舗や事務所運営に必要な、電気・ガス・水道等の公共料金を計上する項目です。事務所兼自宅の場合は、事務所として利用している分を家事按分して計上します。家事按分については、以下で詳しく解説します。
通信費
通信費は、インターネットの回線使用料・電話代・切手代・ファックス代等の、事業で利用する通信費用を計上する項目です。こちらも事務所兼自宅の場合は、家事按分が必要です。
広告宣伝費
広告宣伝費は、事業や商品を宣伝する費用を計上する項目です。Webサイトやチラシ、看板の製作費や広告の原稿料等が含まれます。少額の来店記念品代も計上できます。
租税公課
租税公課は、事業に関連する税金や公的な負担金を計上する項目です。個人事業税・印紙税・固定資産税・社用車の自動車税等が含まれます。個人に係る税金は計上できません。
支払保険料
支払保険料は、従業員や事業に関わる財産の保護を目的とした保険料を計上する項目です。事故や火災等の損害保険料・自動車保険料・自賠責保険料などがあげられます。個人事業主本人に関わる生命保険料や年金型保険料等は対象外です。
人件費
人件費は、従業員に支払う給与や手当、雇用する際にかかる費用を計上する項目です。生計を一にする家族を雇っている場合、基本的に経費計上できません。しかし、青色申告で専従者給与特別控除の申請をしている場合は経費計上できます。
福利厚生費
福利厚生費は、従業員の健康診断費用や慶弔費、社員旅行や忘新年会の費用等、従業員の福利厚生のために支出した費用を計上する項目です。
法定福利費
法定福利費は、従業員を雇っている場合に係る健康保険料や厚生年金保険料等の、社会保険料の企業負担額を計上する項目です。
雑費
雑費は、勘定科目を設けるほど使用頻度のないものや、ほかの経費にあてはまらないものを計上する項目です。たとえば、支払手数料の勘定科目がないときの銀行の振込手数や、新聞図書購読費の勘定科目がないときの書籍代等の少額の経費をまとめて計上できます。
勘定科目は一度設定したら、毎年同じ項目に同じ経費を計上する必要があります。
仕入は経費とは別の勘定科目になる
商品や原材料の仕入れにかかった費用は、事業にかかった経費として計上することが可能です。ただし、経費とは別扱いで「仕入」や「商品」の勘定科目を使って処理します。確定申告でも仕入金額は「売上原価」として、経費とは別に記載します。
また、まだ販売していない仕入れにかかった費用は、その期の費用として計上せずに、在庫として資産に計上する必要があります。
個人事業主が経費にできないもの
個人事業主が経費にできないものは、事業とは関わりのない個人的なものや、株式会社では適用されても、個人事業主であるがゆえに適用されないものなどがあります。
私的な交際費や旅費交通費
事業と関わりのない費用は経費として認められません。たとえば、家族や友人との食事や飲み会、旅行などは私的に利用されたものになります。個人事業主の場合、明確に区別する必要があります。
個人事業主本人の福利厚生費
福利厚生費は従業員の保険・医療・慰安等に適用される経費です。個人事業主は従業員ではなく事業主なので、本人の福利厚生費は経費には適用されません。
個人事業主本人の健康診断費用
従業員の健康維持のため、定期的に健康診断を行う企業は多いです。従業員の健康診断費用は経費計上できますが、事業主本人は福利厚生費同様に適用されません。自己負担で実施しましょう。
個人事業主個人に課せられた税金
事業運営に関わる税金や公的負担金は租税公課として計上可能です。しかし、個人事業主が自分で支払う所得税や住民税など、個人に課せられた税金は経費とは認められません。
10万円以上の物品購入
10万円未満の物品は、消耗品費として一括で経費計上できます。しかし、10万円以上の物品は固定資産として扱われるため、減価償却が必要になります。減価償却資産については、後ほど詳しく解説します。
事業主や家庭のための支払い
個人事業主が個人的に支払ったものや家族のために購入したものなどは、事業活動と関係ないものなので経費計上できません。たとえば、子供が塾に通うための交通費や個人的な友人におくった慶弔費、家族のための買い物などは、税務署に疑問を抱かせないためにも明確に分ける必要があります。
家事按分で個人と共有するものの経費を明確にわける
事務所兼自宅の場合、水道光熱費や通信費、事業として占有する面積分の家賃、自家用車を事業に利用する場合などは経費割合を定める必要があります。使用時間や使用面積、走行距離(車の場合)等の、合理的な基準に基づいて按分しなければ税務署に否認されるリスクもあります。
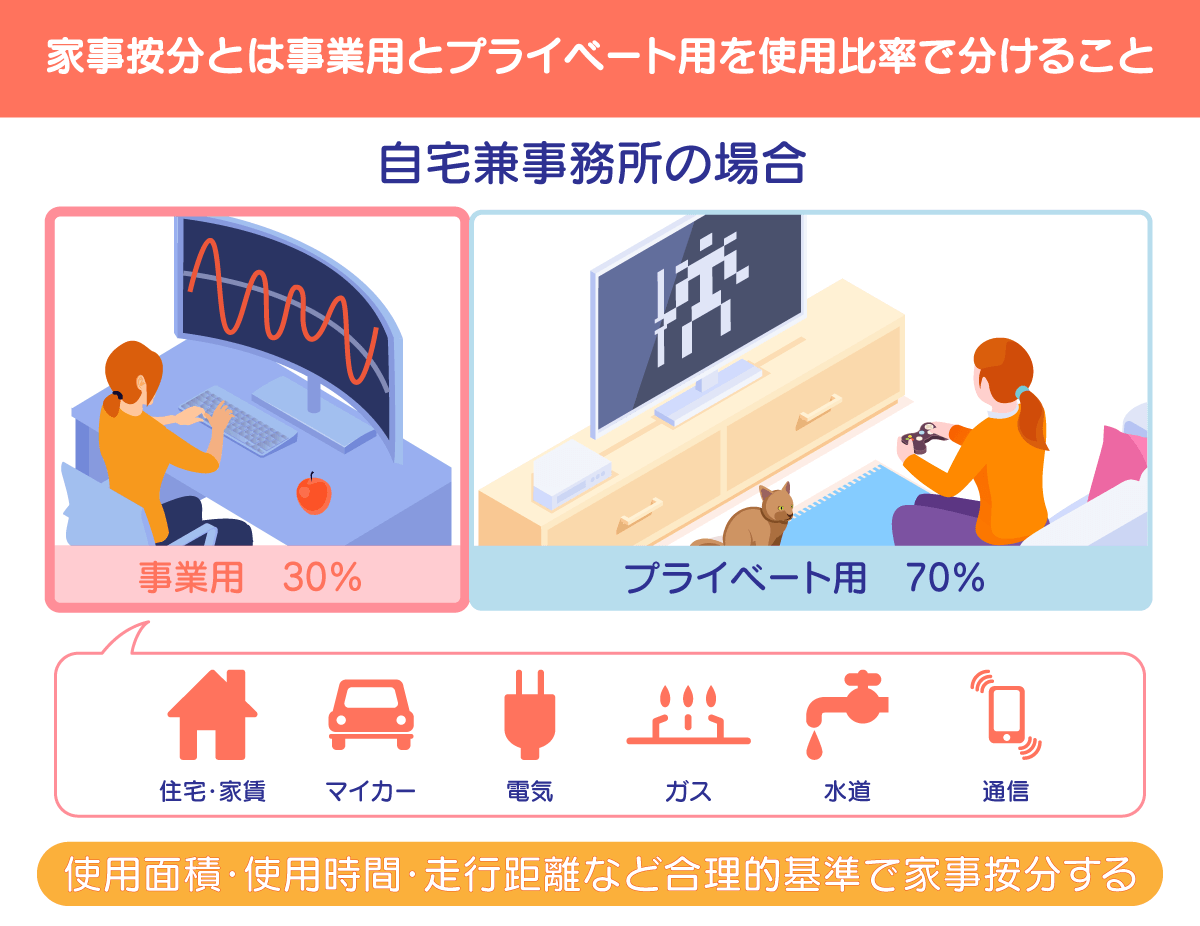
白色申告では「事業で利用する割合がおおむね50%超の家事関連費」が対象となっています。しかし、「所得税法 法令解釈通達45-2」では、50%以下でも必要性が明らかであれば経費算入できるとも記しています。明確な合理性の証明が必要ということです。
参考:国税庁|法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係
減価償却費の扱いに注意する
10万円以上30万円未満の減価償却資産は、一括で全額を経費計上することができません。各資産の法定耐用年数に応じて分割で経費計上します。
しかし、青色申告を行っている場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産で、年間の取得価額の合計額が300万円までの範囲内であれば、「少額減価償却資産の特例」を利用して一括で経費計上することも可能です。
参考:国税庁|主な減価償却資産の耐用年数表
個人事業主の経費計上のやり方
経費計上のやり方と注意点を解説します。
必要な書類
経費を証明する書類には、いつ・誰が・どこで・何を・いくらで購入したかが記載された領収書が一般的に利用されます。取引の都度、領収書を受け取り保管しましょう。領収書以外では、レシート・クレジットカードの明細書・出金伝票・電子データも利用できます。以下に注意点をまとめましたので、参考にしてください。
- いつ(日付)
- 誰が(購入者)
- どこで(購入先)
- 何を(購入品目)
- いくらで(金額)
- 領収書:最も利用される書類
但し書きがあることで購入品目や購入目的が理解できる
- レシート:領収書に代わる証明書類となる
裏面に購入者や購入目的などのメモを記載するとよい
- クレジットカードの明細書:領収書に代わる証明書類となる
事業専用のクレジットカードを利用するとよい。購入目的などメモするとさらによい
- 出金伝票:証明書類がない場合に利用できる
自動販売機の飲み物や電車・バスの乗車料金など領収書がないときに利用できる
- 電子データの領収書:ネット注文で購入した物品の領収書や納品書も証明書類となる
電子領収書は電子データのまま保存する
参考:国税庁|電子帳簿保存法が改正されました
青色申告の場合
青色申告では、正規簿記による書類の作成が必要になるため、青色申告決算書の損益計算書に勘定科目ごとに合計した金額を記入します。
青色申告は、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、青色専従者給与の経費計上、赤字の3年間繰越計上等の経費にできる項目が多く、節税効果を最大化できる可能性があります。
白色申告の場合
白色申告では簡易簿記で対応できるため、収支内訳書の経費の項目に、勘定科目ごとに合計した金額を記入し、確定申告書とともに提出します。青色申告に比べ簡易ですが、正確な計上が求められます。
経費計上が多すぎるとリスクにつながる
多くの経費を計上することで、節税対策になるため適切な経費計上が必要です。しかし、多過ぎる場合は、以下のようなリスクもあります。
税務調査の対象になる
経費計上が多すぎると、税務署から脱税を疑われ、税務調査の対象となる可能性があります。とくに赤字が続く場合は注意が必要です。税務調査で脱税と判断された場合の罰則は大変厳しいものになります。適切な経費管理が求められます。
銀行からの融資が受けられない
事業拡大のために銀行から融資を受ける場合、決算書や収支内訳書の提出が求められます。このとき、経費が多すぎて利益が極端に少ない、または赤字となっていると、融資が受けられない場合があります。
そればかりか、経営改善が優先だと苦言を受けるかもしれません。経費計上は慎重に行うことが重要です。
まとめ
事業を行ううえで、節税効果のある経費は重要な要素です。漏れなく正確に計上する必要があり、多すぎても少なすぎてもよいことはありません。日々の業務においては、細かい金額でも領収書を受け取り保管しましょう。さらに、個人事業主は事業者と個人の区別を明確にすることが、節税への近道となります。
]]>- 物価高や人手不足を背景に、初任給を引き上げる企業が増えている
- 中には10万円といった大幅引き上げを行う企業もある
- 初任給の引き上げを行っているのは大企業が中心である
- 新入社員の給料が先輩社員の給料を上回ることのないよう配慮が必要である
- 非正規従業員の給料についても賃上げを行う企業がある
初任給引き上げの背景
近年、初任給を引き上げる企業が増えています。2025年もその動きは進み、多くの企業が初任給の大幅引き上げに踏み切りました。その背景には何があるのでしょうか。以下に見ていきます。
物価高
食料品や光熱費をはじめ、生活に関係するあらゆる品目の価格が上昇しています。一方で賃金の上昇率は鈍く、物価高に追いついていません。これでは生活が圧迫されてしまいます。実質賃金を上げるためには物価高を上回るだけの給与の引き上げが必要です。
人手不足
日本では少子化に歯止めがかからず人手不足は深刻な問題となっています。採用競争が激化するなか、企業は初任給を引き上げることで優秀な人材を確保しようとしています。学生に自社を選んでもらうメリットとしてわかりやすいのが初任給の高さなのです。
賃上げムードの高まり
政府は経済界、労働界に2025年春闘での賃上げ協力を求め、経団連、労働組合はともに人への投資を起点とする経済の好循環を力強く回していくとしています。30年続く不況からの脱却のために国や企業が一丸となって賃上げに取り組む必要があります。
初任給引き上げ最新事例(2025年最新版)
どのような企業で初任給の引き上げが行われているか、業界別に見ていきます。
商社
丸紅
丸紅は2026年4月に入社する大卒新入社員の初任給を、月30万5,000円から33万円に引き上げます。院卒は36万5,000円となります。引き上げ幅は2万5,000円です。同社が初任給を引き上げるのは2年ぶりのことです。
伊藤忠商事
伊藤忠商事は、2025年より大学卒の初任給を30万5,000円から32万5,000円に引き上げます。引き上げ幅は2万円となります。同社は2024年にも一律5万円引き上げています。
金融
明治安田生命
明治安田生命は、2025年度の大卒初任給を24万円から27万円に引き上げます。全国転勤のある総合職が対象で、固定残業代を含めると33万1,660円となります。初任給の引き上げにより、若手先輩社員の給与が新入社員より低くならないよう、入社5年以内の従業員について平均8%以上の賃上げも行います。
住友生命
住友生命は2026年4月に入社する大卒新入社員の初任給を、26万円から29万円に引き上げることにしました。20時間相当の固定残業代を含めると、月額で33万5,000円となります。海外を含めた全国転勤のある総合キャリア職員が対象です。また、大卒営業職員の初任給も、現在の24万円から28万円に引き上げます。
住友生命の初任給引き上げは3年連続で行われています。先に入社した社員の給与よりも新入社員の給与のほうが高くならないように、入社2年目以降の従業員の給与も引き上げる方向です。
第一生命ホールディングス
第一生命ホールディングスは、2025年4月から、営業職員も含めた国内従業員に対し一律1万円(平均7%)のベースアップを行います。固定残業代も含めると、大卒総合職の初任給は、32万1,410円から33万5,560円に引き上げとなります。同社の賃上げは3年連続で実施されており、初任給の高さは大手生命保険業界の中でもトップクラスです。
りそな銀行
りそな銀行は、2026年4月入社の新卒社員より、10種類ある応募コースのうち、8つの専門コースの初任給を引き上げます。大卒初任給は25万5,000円から28万円となり、引き上げ幅は2万5,000円となります。専門コースでは、能力に応じてさらに高い初任給を適用されることもあり、特に優れた人材の場合、30万円を超えるケースも出てくる可能性があるそうです。
SBIホールディングス
SBIホールディングスは、2025年4月より、新卒初任給を30万円から34万円に引き上げます。引き上げ幅は4万円です。
また、入社3年目までの従業員の給与を一律で10%引き上げるほか、人事評価が高い従業員の給与をすべての年次において平均10%程度引き上げます。
みずほフィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループは、2024年の新卒初任給について、20万5,000円から26万円に引き上げます。引き上げ幅は5万5,000円となります。同社が初任給の引き上げを行うのは13年ぶりです。
また、新卒初任給の引き上げにより若手従業員の給与が逆転しないよう、若手を対象とした賃上げも実施します。
住信SBIネット銀行
住信SBIネット銀行は、2025年4月に入社する新卒の初任給を3万円引き上げて33万円としました。平均的な時間外勤務手当も入れると40万円を超える見込みです。同社は2023年4月にも初任給を8万円引き上げており、この3年間でトータル11万円もの引き上げを実施しています。
建設・不動産
大和ハウス工業
大和ハウス工業は、2025年4月の総合職新卒社員の初任給について、一律で10万円引き上げました。
大卒は25万円が35万円に、院卒は26万2,000円から36万2,000円に、高専・専門学校卒も23万2,000円から33万2,000円に、それぞれ引き上げとなります。
10万円という大幅初任給引き上げは業界の内外から注目されています。
大成建設
大成建設は、2025年4月入社の総合職大卒初任給について、28万円から30万円に引き上げました。引き上げ幅は2万円です。同社の初任給の引き上げは4年連続となります。
オープンハウス
オープンハウスは2025年4月入社の新卒の総合職初任給を33万円から36万円に引き上げます。引き上げ幅は3万円です。初任給の引き上げは3年ぶりで、年収は初年度から500万円を超える見込みとなります。
大東建託
大東建託は、2024年4月入社の新卒社員の初任給について一律2万円引き上げました。
大学卒は22万円から24万円に、大学院卒は23万円から25万円に、高専・専門学校卒は20万7,000円から22万7,000円となりました。
積水ハウス
積水ハウスは、2025年4月に入社する大卒新入社員の初任給を24万円から約30万円に引き上げます。この引き上げ率は25%という大幅引き上げです。また、総合職の全社員の月給も平均約18%引き上げます。
清水建設
清水建設は、2025年度の新卒初任給について一律2万円引き上げました。同社のグローバル職の初任給は、大学卒で30万円、修士了で32万円です。これで同社の初任給の引き上げは4年連続となりました。
小売り
ファーストリテイリング
ファーストリテイリングは、2025年3月以降に入社する新卒従業員の初任給を30万円から33万円に引き上げました。引き上げ幅は3万円で、年収は500万円を超える見込みです。
アシックス
アシックスは、2025年の新卒初任給について27万5,000円から30万円に引き上げました。引き上げ幅は2万5,000円です。大学院修士修了も3万円引き上げ32万円とします。
同社では、2024年度にも初任給を5万円以上引き上げており、2年連続の大幅引き上げとなりました。
ノジマ
ノジマは、2025年度の新入社員について、初任給を1万円引き上げ、現場手当も支給します。これにより、家電量販業界の大学卒初任給としては、最高水準の30万円となります。大学院修了は31万3,000円です。
食品
サントリー
サントリーは、2025年4月入社の大卒新入社員の初任給を27万8,000円から29万円に引き上げました。引き上げ幅は1万2,000円です。また同時に、組合員についても一律月1万2,000円の賃上げを行います。
味の素
味の素は、2025年春入社のグローバル型の新卒社員の初任給について、学歴を問わず一律1万6,000円の引き上げを実施しました。これにより、大卒の場合初任給は27万5,000円となります。
モスフードサービス
モスフードサービスは、2025年4月分から新卒社員の初任給を24万7,500円としました。前年に比べ7,500円の引き上げとなります。また、同社の全社員の給与もベースアップを含めて約5%引き上げます。
インフラ系(電力・資源・運輸)
東北電力
東北電力は、2025年度の初任給を最大で約10%引き上げます。
大学卒で16,000円増の24万円、大学院修士修了で19,000円増の26万3,000円、博士了では9,000円増の27万3,000円となります。
初任給の引き上げはこれで2年連続です。
四国電力
四国電力は、2025年度の初任給を、全学歴で一律1万2,000円引き上げます。これにより、大学院卒は25万8,000円、大学卒は23万6,000円、高校卒は18万8,000円となります。初任給の引き上げはこれで2年連続です。
JR東日本
JR東日本では、2025年4月から新入社員の初任給が全学歴一律1万2,000円引き上げられます。これにより総合職の博士卒は32万4,565円、院卒が28万2,315円、大卒が26万2,075円、高専卒が24万4,595円となります。
メーカー
ソニーグループ
ソニーグループは、2025年4月から新卒正社員の初任給を引き上げます。引き上げ後の初任給は大卒で31万3,000円、大学院卒で34万3,000円です。引き上げ幅は大卒で14%と、大幅な増額となります。
三井化学
三井化学は、2025年7月から、新卒総合職の初任給を一律2万4,000円引き上げると発表しました。同年4月入社の新入社員の給与は、7月から同水準に引き上げられます。これにより、学部卒の初任給は28万円、修士は30万2,000円、博士は35万2,000円となります。
エンタメ
オリエンタルランド
オリエンタルランドは、2025年4月より大卒・大学院卒の初任給を一律27万2,000円としました。引き上げ幅は17,000円です。また、パート・アルバイトといった従業員に対しても平均約6%の賃上げを行います。
バンダイ
バンダイは、2025年4月から新入社員の初任給を29万円から30万5,000円に引き上げます。引き上げ幅は1万5,000円となります。
- 【2025年最新】初任給を引き上げた企業の業界別一覧|30万円超えも
https://edenred.jp/article/hr-recruiting/251/#top
(2025年6月12日閲覧) - 2025年の賃上げ企業、大手メーカーも続々【3月19日更新】
https://www.businessinsider.jp/article/299909/
(2025年6月12日閲覧)
まとめ
近年続いてきた物価と賃金のアンバランスを埋めるように初任給の引き上げが相次いでいます。日本経済復調のためにはこの傾向が続くことが望まれます。また、現状ではこの初任給の引き上げは大企業中心となっています。人材の偏りを防ぐために、中小企業にまでこの流れが波及することが必要です。
]]>- メールアドレスは、仕事用とプライベート用で使い分けるのがおすすめ
- 用途別に複数のメールアドレスを持つと、メール内容の整理がしやすい
- 複数のメールアドレスを管理することは、セキュリティ強化にも効果的
- 独自ドメインのメールアドレスは、信頼性やブランドイメージの向上につながる
- メールアドレスは短くシンプルで、分かりやすくすること
個人事業主が使用するメールアドレスは、普段使用しているメールアドレスでいいのか、仕事用に新しく作成するべきか、悩む人も多いのではないでしょうか。また、独自ドメインとフリーメールの違いがわからず、作成方法に悩むこともあるでしょう。
この記事では、メールアドレスの使い分け理由やメリット、独自ドメインとフリーメールの違い、メールアドレスの取得方法などについてご紹介します。
個人事業主のメールアドレスは使い分けが大事!
個人事業主が仕事をするためには、仕事用とプライベート用でメールアドレスを使い分けることが大切です。使い分けずにメールでのやり取りを行った場合、業務上で重要な連絡や情報などを見逃す可能性があります。開業当初など、仕事が少ないうちは使い分けなくても対応できるかもしれませんが、忙しくなってからの作成は難しいため、あらかじめ作成しておくことがおすすめです。
仕事用メールアドレスを持つメリット
仕事用とプライベート用のメールアドレスを別に持つことで、さまざまなメリットが得られます。大きなメリットは、以下の4つです。
- 複数のメールアドレスが取得可能になる
ビジネス用にドメインを取得することで、事業の成長や用途に応じて新しいアドレスを追加できるため、複数のメールアドレスを柔軟に使い分けて対応できる。メールアドレスを用途別に分けられ、業務中に集中力を維持しやすくなる。
- プライベートと仕事用を分けてメール内容を管理しやすい
プライベート用と業務用を使い分けることでメール内容の整理がしやすくなり、重要な情報の見逃し防止や、管理業務の効率化が図れる。業務メールの間にプライベートな内容のメールが挟まらず、作業がスムーズに進められる。
- セキュリティの安全性を強化しやすい
複数のメールアドレスを使い分けて管理することで、特定のメールアドレスが漏えいした場合でも、他のアドレスへの影響を最小限に抑えられる。メールアドレスごとに個別セキュリティ設定を適用することで、スパムやフィッシングメール対策のフィルタリングを強化できる。
- ブランドイメージや信頼性の向上につなげやすい
独自ドメインのメールアドレスを使用することで、専門性を強調できるため、取引先にプロフェッショナルな印象を与えられる。ブランドイメージの向上にもつなげやすく、取引先との信頼関係の構築・強化ができる。
ビジネスに適したメールアドレスの選び方とは?
個人事業主にとって、メールアドレスはビジネスにおいて重要なコミュニケーションツールであり、事業の展開を左右する重要な要素の一つです。適切なメールアドレスを選ぶことは非常に大切で、顧客との関係構築やブランドイメージの向上に直結するため、どのように選べばいいか、迷う人もいるでしょう。
ここからは独自ドメインとフリーメールの違いや、個人事業主におすすめの選択肢についてご紹介します。
独自ドメインとフリーメールの違い
独自ドメインとフリーメールには、取引先からの信頼性やセキュリティ面、コスト面などに大きな違いがあります。大きな違いを以下の表にまとめました。
| 独自ドメイン | フリーメール | |
|---|---|---|
| 取引先からの信頼性 | 信頼を得やすく、仕事も得やすくなる | 信頼性が下がりやすく、仕事が得にくくなる |
| セキュリティ・サポート | セキュリティやサポートの充実性が高い | サポートが限定的で、セキュリティ面に不安がある |
| ドメイン | “~@”以降のドメインを好きな文字列で設定できる | “~@gmail.com”など、 選択したフリーメールのドメインのみ利用できる |
| 利用コスト | 利用する機能やサポートに合わせて使用料を払う | 基本的に無料で使用できる |
| 機能面 | プラン内であれば、あらゆる機能が使用できる | 簡単に設定できるが機能は限定的で、広告が入る場合がある |
| ブランディング | 事業の専門性やブランドイメージを強調できる | 事業内容などのイメージが伝えにくい |
| 複数のメールアドレス | 新しいメールアドレスが必要になった時、すぐに作成できる | 新しくアカウントを作る必要があり、アドレス管理が煩雑になりやすい |
ビジネス用のメールアドレスを独自ドメインにすることは、個人事業主としての専門性や信頼性を強調できるポイントです。フリーメールの利用が禁止されている訳ではありませんが、取引先によっては信頼性が低くなり、仕事が得にくくなる可能性があるため、選択する際には注意した方がいいでしょう。
個人事業主のメールアドレスは独自ドメインがおすすめ
個人事業主が事業用のメールアドレスを作成する時は、独自ドメインで作成することをおすすめします。仕事を得るためには、取引先との信頼性や事業イメージが重要です。独自ドメインであれば信頼性やイメージの向上に加え、情報漏えい対策のセキュリティや必要に応じたメールアドレスの作成・管理が行えます。また、ドメインに業種や事業名、屋号などを入れて作成できるため、取引先が判断しやすくなり好印象にもつながるでしょう。
Gmailなどのフリーメールをおすすめしない理由
GmailやYahoo!メールなどのフリーメールは、初期費用がかからず手軽に利用できるため、起業したばかりの時には魅力的に見えるでしょう。しかし、誰でも取得可能なフリーメールは、信頼性に欠けるとみなされることが多く、取引先との関係構築に悪影響となる可能性があります。また、フリーメールでは広告が表示されることもあるため、セキュリティ面の脆弱性(ぜいじゃくせい)に懸念が残ります。事業の安定や信頼獲得、セキュリティ強化を進めるのであれば、独自ドメインのメールアドレスを使用するといいでしょう。
個人事業主が独自ドメインのメールアドレスを作成する方法
個人事業主が事業のために独自ドメインのメールアドレスを作成することは、安定かつ長期的なビジネスのために非常に重要です。独自ドメインのメールアドレスは、事業への信頼性やプロフェッショナルな印象、ブランドイメージの向上に大きな影響があります。
ここからは、独自ドメインのメールアドレスを作成するためのステップをご紹介します。
1.独自ドメインを取得する
まずは、ビジネスの内容に適したドメイン名を選び、独自ドメインを取得します。ドメイン名を決める際には、事業名や活動内容を簡潔に示せるものがおすすめです。職種やご自分の名前、屋号などを入れてみてもいいでしょう。
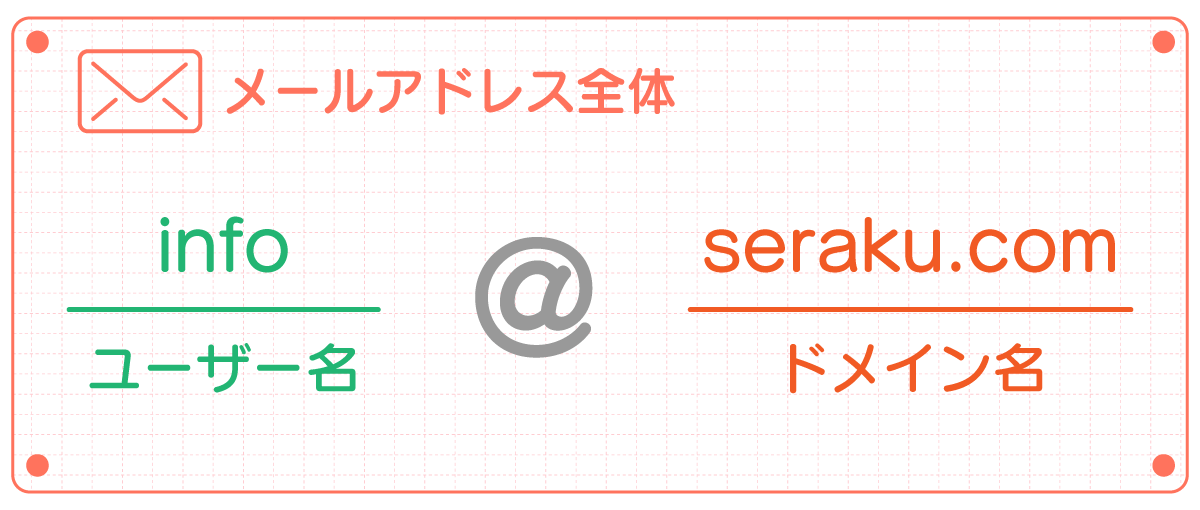
ドメイン取得する際は、信頼できるドメインレジストラ(ドメインを登録し、データベースを管理する業者のこと)を利用することが大切です。初心者でも簡単に取得手続きができ、サポートも充実している点では「Namecheap」や「GoDaddy」などのサービスをおすすめします。ドメインは年間契約が一般的となっており、長期間契約することで割引が受けられる場合もあります。ドメイン取得後は所有権をしっかりと確認し、必要に応じてプライバシー保護のオプションを検討するといいでしょう。
2.メールサーバを契約する
独自ドメインを取得したら、次はメールサーバの契約に進みます。メールサーバは、メールの送受信を管理するために必要なサービスです。さまざまなプロバイダから多様なサービスが提供されており、豊富な選択肢があります。契約する前にはプロバイダが提供しているサービスを確認し、信頼性とサポートの質が高いものを選びましょう。
選ぶ際のポイントは、ご自身のビジネスに必要な機能や容量を事前に確認しておき、ニーズに合ったプランを見つけることです。例を挙げると「Gmail for Business」や「Microsoft 365」は、信頼性が高くビジネス向け機能が充実しており、おすすめです。
メールサーバの選び方
メールサーバを決める方法はレンタルサーバやクラウドサービス、独自サーバの設置の三種類があります。それぞれの特徴をメリット・デメリットとともにご紹介します。
- レンタルサーバの利用
レンタルサーバは初期費用が低く、コスト効率は高く利用できる点は大きなメリット。多くのレンタルサーバは簡単に導入できるよう設計されており、導入や運用に関するサポートも受けられるため、初心者でも利用しやすい特徴がある。ただし、機能やセキュリティ面では制限がかかりやすいデメリットがある。
- クラウドサービスの導入
クラウドサービスは、ビジネスの成長に合わせて必要な容量や機能を増やせる柔軟性が大きな特徴。定期的な更新やパッチ運用を自動で行うため、セキュリティ対策が充実している点はメリットと言える。サービスの多くは従量制の料金体系が一般的で、使用量が増えると維持費などのコストも増える点に注意。
- 独自サーバの設置
独自サーバはハードウェアやソフトウェアを自由にカスタマイズでき、自身のニーズに合わせて完全なカスタマイズ設定が可能。セキュリティ対策も独自強化できるため、機密情報保護のために高いセキュリティを構築できる。ただし、物理的なハードウェアに依存するため、容量や性能に制限がかかる場合がある。初期費用も高く、高度な専門知識がないと管理しにくいデメリットがある。
3.独自ドメインとサーバを紐付ける
独自ドメインとメールサーバの紐付けを行うことを、DNS設定と呼びます。この設定はメールアドレスを正常に機能させるために必要不可欠です。DNS設定が完了すると、ビジネス用のメールアドレスとして利用可能になります。
DNS設定の手順は以下の2ステップです。
- 契約したメールサーバの管理画面にアクセスする
- 管理画面から必要なDNSレコードを設定する
上記の手順を行うことで、メールの送受信ルートが適切に設定されます。通常、プロバイダからガイドが提供されるため、ガイドに従って設定を行うとスムーズに進められるでしょう。
4.サーバでメールアドレスを発行する
独自ドメインとメールサーバの紐付けが完了したら、いよいよメールアドレスの発行です。メールサーバの管理画面から、新しいメールアドレスが作成できます。
- メールアドレス例
- info@seraku.com
- support@seraku.com
発行する際は、ビジネス内容や役割など、用途に応じて設定すると業務の効率化が図れます。また、メールアドレスの発行と同時に、パスワードの設定やセキュリティ設定も行い、アカウントの安全性を確保するといいでしょう。
独自ドメインのメールアドレスを作成する際のポイント
ビジネスにおいて、独自ドメインのメールアドレスは信頼性の構築に重要なツールです。個人事業主が取引先にプロフェッショナル、または専門的な印象を与えるためには、適切なメールアドレスの作成が必要です。ここからは、独自ドメインのメールアドレスを作成するために重要なポイントをご紹介します。
職種・名前・屋号を入れる
メールアドレスに職種・名前・屋号を入れることで、あなたが誰か、どのようなビジネスをしているかを瞬時に伝えられます。
- メールアドレス例
- hanako.yamada@seraku.it.com(名前+ビジネス名)
- sales.yamada@seraku.com(名前+職種)
組織内での役割を入れるのも、何を担当しているかを伝えられるため、おすすめです。分かりやすいメールアドレスは、顧客や取引先が誰に連絡を取るべきかが理解しやすく、コミュニケーション効率の向上につながるでしょう。
サービス名を入れる
メールアドレスにサービス名を入れると、提供しているサービスや商品を明確に伝えることが可能です。複数のサービスを展開している場合、非常に便利です。
- メールアドレス例
- support@seraku.com
- info@seraku.com
上記のような形式にすることで、メールの内容がどのサービスに関連しているのか一目で理解しやすく、受取人がメール内容を迅速に把握して対応できます。また、サービス名を含めることでブランド認知度を高め、ビジネスの専門性を強調することにもつながるでしょう。
短くわかりやすくシンプルにする
メールアドレスは短く、わかりやすく、シンプルであることが重要です。長すぎるアドレスは入力ミスを招きやすく、覚えにくいため、受取人にとって不便と言えます。
- 覚えやすいメールアドレス例
- k-yamada@seraku.com
- it-support@seraku.com
上記のような短くシンプルなアドレスは覚えやすく、誤入力のリスクを減らすと同時に、プロフェッショナルな印象を与えます。また、アドレスに記号や数字を多用すると、スパムフィルタに引っかかる可能性があるため、避けた方がいいでしょう。
ビジネスの信頼性を高めるためには、簡潔かつ明瞭なメールアドレスが大切です。
商標や類似名称をチェックする
メールアドレスを作成する際には、商標の事前チェックが重要です。特に、ビジネス名やサービス名を含める場合、他社の登録商標を侵害しないよう細心の注意が必要です。もし商標を侵害してしまうと法的な問題に発展し、ブランドイメージを損なう可能性があります。
商標侵害を避けるには、特許庁のホームページや商標データベースで検索することが重要です。また、法的リスク回避のためには専門家による確認を通じて、使用予定の名称が保護されていないか、類似の商標が存在していないかをチェックもしておくと安心です。
まとめ
個人事業主はメールアドレスを仕事用とプライベート用で使い分けることで、重要な業務連絡を見逃すリスクを減らし、効率的な管理を可能にします。仕事用のメールアドレスに独自ドメインを使用すれば、取引先への信頼性を高めて専門性をアピールできます。フリーメールは信頼性やセキュリティ面で懸念があり、複数のメールアドレスを管理することも難しいため、独自ドメインの利用がおすすめと言えるでしょう。独自ドメインでメールアドレスを作成する際は、職種や名前を入れて短くシンプルにまとめるよう意識することがポイントです。
]]>- 空間コンピューティングとは物理空間とデジタル世界を融合させる技術・概念
- 物理空間とデジタル情報を結びつけ直感的で没入感のある体験を可能にすることが特徴
- Apple独自の空間コンピューティング構成要素はウィンドウ・ボリューム・スペースの3つ
- 空間コンピューティングは今後数年間で私たちの生活やビジネスを劇的に変革すると予測されている
近年、空間コンピューティング(Spatial Computing)は私たちの社会に大きな変革をもたらしています。すでにさまざまな業界で導入が始まっていますが、一般ユーザへの浸透や標準化はまだこれからという段階です。この機会に、基礎知識や将来・課題などについての知識を学んでおくのはいかがでしょうか。
空間コンピューティングとは?
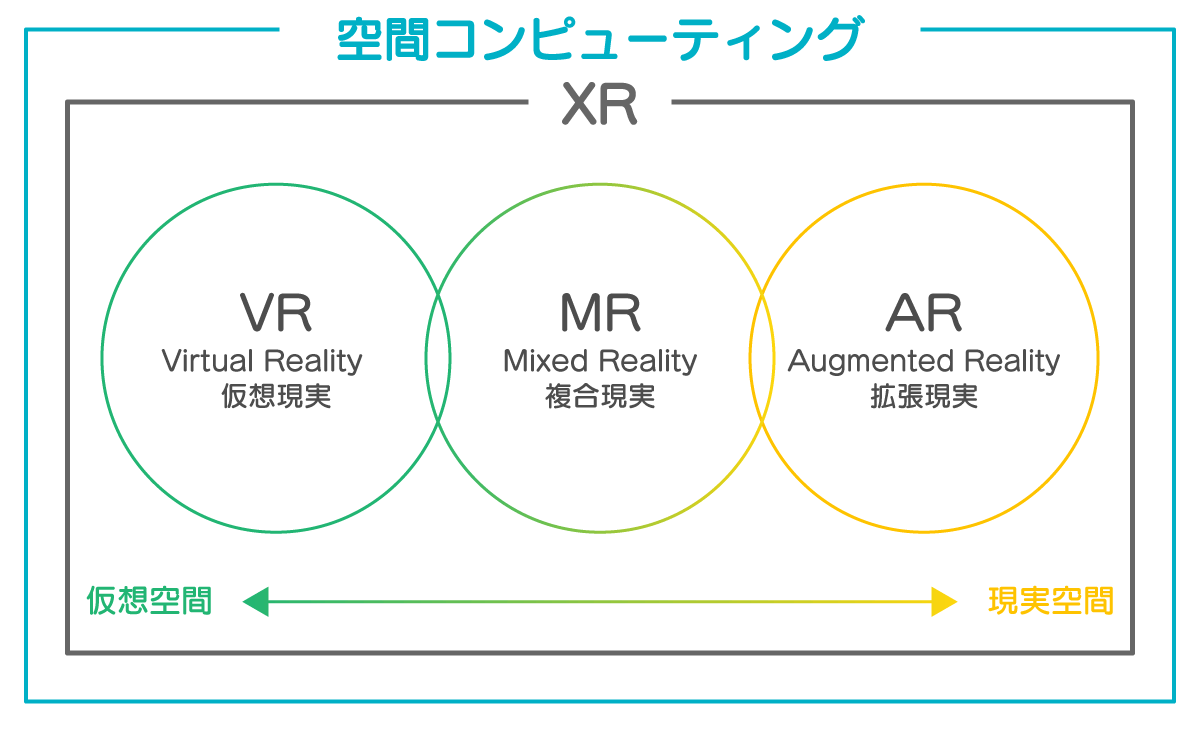
空間コンピューティングは、現実空間とデジル空間を融合させ、まるでデジタル情報が現実世界に存在するかのように体験・操作を可能とする技術のことです。2003年にアメリカのサイモン・グリーンウォルド氏によって「機械が実際のオブジェクトや空間への参照を保持し、操作する機械との人間の相互作用」と定義されました(参考元:サイモン・グリーンウォルド「Spatial Computing」)。以下のようなテクノロジーを組み合わせています。
- AR(拡張現実)
- VR(仮想現実)
- MR(複合現実)
- ハンドトラッキング、アイトラッキング、音声認識
- 3Dモデリング
AR・VRと空間コンピューティングの違い
AR(拡張現実)は、現実の景色を見ながら、その上にデジタル情報を重ねて表示する技術です。一方、VR(仮想現実)は、現実の景色をすべて覆い隠し、まったく別の仮想空間だけを見せる技術です。
| AR・VR | 空間コンピューティング | |
|---|---|---|
| 役割 | 特定体験実現のための技術 | 包括的な概念・技術 |
| 範囲 | 一部(表示・体験など) | 全体(認識、操作、統合、インタラクション全般など) |
| 関係 | 空間コンピューティングの応用形態 | 包括的な技術体系 |
空間コンピューティングの特徴
空間コンピューティングの特徴は大きく以下の4つになります。生活・仕事・学習などのさまざまな場面で活用される可能性があります。
- 二次元コンピューティングから三次元への進化
現実空間やバーチャル空間全体をコンテンツの表示などに活用する
- コンピュータの操作方法の変化
現より身体的で直感的なコンピュータ操作体験を実現させる
- デジタルと現実の融合への対応
現デジタルオブジェクトを現実空間に重ねて表示、物理空間そのものをデジタルで補完・拡張する、などの要求に答える
- 空間情報の取得と利用・活用
現空間コンピューティング型デバイスを活用して、ユーザのデータを詳細に取得・分析し効率化をはかる
空間コンピューティングの構成

Appleの空間コンピューティング体験では、「ウィンドウ」「ボリューム」「スペース」といった概念が導入されており、主要な構成要素として位置づけられています。3つそれぞれについて解説します。
1 ウィンドウ
1つ目の構成要素は「ウィンドウ(Windows)」です。
見た目は従来のPCで使われていたウィンドウとほとんど同じ、平面的な表示領域です。
ユーザは表示サイズや配置を自由に調整できます。また、複数のウィンドウを同時に操作することも可能です。
2 ボリューム
2つ目の構成要素は「ボリューム(Volumes)」です。
立体的な体積を持った表示領域で、3Dオブジェクトや相互作用的なコンテンツを空間内に配置するための要素です。ユーザはこれらのボリュームを360度から観察・操作でき、より没入感のある体験を提供します。
3 スペース
3つ目の構成要素は「スペース(Spaces)」です。
スペースはユーザの視界全体を領域とし、「ウィンドウ」「ボリューム」も含まれます。現実世界とデジタルコンテンツをシームレスに融合させ、自由にカスタマイズされた作業環境を構築可能です。
空間コンピューティングで可能になること
空間コンピューティングは現実空間とデジタル情報をシームレスに融合させ、直感的な操作を可能にする技術です。現実世界を操作可能なデータ空間に変え、デバイスの画面に閉じ込められていたデジタル体験を空間全体へと拡張することが可能です。以下のようなことができるようになります。
- 直感的な操作
現手のジェスチャー・視線・音声認識などを使い、デジタルオブジェクトを直感的に操作可能
- 2Dディスプレイからの解放
現従来の小さな画面に縛られることなく、目の前の空間全体をディスプレイとして利用可能
- 現実空間への情報重ね合わせ
現実の風景にデジタル情報を重ねて表示可能
- 空間共有
現コンテンツなどの共有をした場合、複数人で同じ情報をリアルタイムで空間共有・共同作業をすることが可能
多様な分野での利用
空間コンピューティングは、その汎用性の高さから非常に幅広い分野での活用が想定されています。4つの分野での利用について解説します。
1 教育分野での応用
教育現場での空間コンピューティング活用で「見て・触れて・動かして学ぶ」体験が可能になり、学習の理解度・定着率向上に貢献します。以下に利用例を挙げます。
- 歴史・科学・工学などの立体的な教材のAR表示
- 安全訓練や緊急対応トレーニング(災害、火災など)
- 職業教育におけるシミュレーション型実習
- 言語・文化教育でのインタラクティブ環境体験
2 ビジネス分野での応用
ビジネスでの空間コンピューティング活用は、空間上での情報共有・製品表示・業務効率化を進め、新しい働き方・営業スタイルを可能とします。以下に利用例を挙げます。
- 現場作業員へのARナビゲーションや作業手順表示
- リモートワークの環境を仮想オフィスとして提供
- 製品デザインやプロトタイプの3Dモデリングを利用しての作成
- 家具やメイクなどのAR試着・試し置き
- ARを使ったプロモーション演出やクーポン表示
- ECサイトでの仮想商品展示室
3 医療分野での応用
医療現場での空間コンピューティング活用は、人体の内部構造や手術計画を空間上で可視化・共有することが可能で、安全性・精度を大幅に向上させます。以下に利用例を挙げます。
- 手術支援AR(臓器の3D表示・位置ガイド)
- 医学生向けの仮想解剖トレーニング
- リハビリ支援の動作トラッキングとフィードバック
- 遠隔診療や支援における空間的情報共有
4. エンターテインメント分野での応用
エンターテインメントでの空間コンピューティング活用は、空間全体を演出装置として使い従来にない没入体験を創出します。また、ユーザが自宅にいながら臨場感あふれる体験を楽しむ・現実の空間と連動した新しいタイプのゲーム体験も可能となります。以下に利用例を挙げます。
- 空間を利用したMR/VRゲーム
- ライブイベントでの仮想演出(ホログラムやARエフェクト)
- ユーザの部屋を使った没入型AR体験
- バーチャルタレントやメタバースライブ
空間コンピューティングのこれから
空間コンピューティングは、今後の社会・産業・日常生活を大きく変える次世代の基盤技術として注目されています。今後の展望としては、以下の点が挙げられます。
- デバイスの進化と普及
軽量化・小型化・性能向上・低価格化・汎用化
- ユーザーインターフェースの革新
より直感的な操作・AIアシスタントとの融合
- インフラストラクチャの整備
5G/6Gネットワークの普及・IoTデバイスなどの進化・現実世界をデジタル空間に再現するデジタルツイン技術の進化
- アプリケーションとコンテンツの充実
キラーアプリの登場・対応したコンテンツやアプリケーションを開発するクリエイターの増加
空間コンピューティングの課題
空間コンピューティングは現実空間とデジタル空間を融合させ直感的で自然な操作などを可能にする画期的な技術ですが、その普及と発展にはいくつかの課題が存在します。以下に4つを挙げます。
- コストと導入障壁
初期導入コストの高さ・投資対効果証明の難しさ(導入に踏み切りにくい)など
- 高度な技術と専門知識の必要性
空間コンピューティング専門人材の不足がスムーズな導入を妨げる可能性など
- セキュリティとプライバシーのリスク
個人情報の漏洩リスク・データの適切な管理と活用など
- インフラ環境の整備とメンテナンス負荷
高性能なインフラ環境の整備と継続的なメンテナンスが必要など
まとめ
ここまで「空間コンピューティングとは?/基礎知識・将来・課題など」というテーマで解説してきました。
空間コンピューティングとは、現実空間とデジタル空間を融合させ、まるでデジタル情報が現実世界に存在するかのように体験・操作を可能とする技術のことです。
空間コンピューティングは次のコンピューティングパラダイムとして注目されており、今後数年間で私たちの生活やビジネスを劇的に変革すると予測され、その応用範囲は無限に広がっていくでしょう。
皆さんも、この記事を読んで空間コンピューティングについての知識を深めるきっかけにしてみてください。
- iDeCoは老後の資金を毎月コツコツ積み立てながら資産形成する制度
- 掛け金は所得税控除の対象になり、運用益も非課税になる
- 60歳まで途中引き出し・解約は原則不可能
- iDeCoの運用には手数料がかかり、元本割れのリスクもある
- 無理なく長期運用できるように負担のない掛け金にすることが重要
20歳から65歳までの方なら職業問わず、誰でも加入できるiDeCo。個人事業主は将来受け取れる年金が少ないため、iDeCoの加入を考えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、個人事業主がiDeCoを利用する際のメリット・デメリット、iDeCoの上限額や気になる節税対策についてもあわせて詳しく解説していきます。
「個人型確定拠出年金」iDeCoとは
iDeCoとは、自分でコツコツと掛け金を積み立て、60歳以降に老後資金として受け取ることができる私的年金制度です。公的年金だけでは将来の生活が不安な個人事業主にとって、iDeCoは有力な選択肢のひとつです。
個人事業主で公的年金だけでは将来が不安な方は、iDeCoについて詳しく知っておくと視野が広がることでしょう。以下で、iDeCoの特徴を押えておくと安心です。
iDeCoの特徴
iDeCoの特徴として節税効果が期待できます。掛け金を支払うと、所得税・住民税の負担が減りますし、運用益はすべて非課税です。そして受取時は、控除制度を利用でき所得税を軽減できるという特徴があります。以下では更に詳しくiDeCoのメリットやデメリットについて解説しています。
iDeCoの個人事業主の上限額は月額6.8万円
2025年5月時点で、個人事業主のiDeCoの掛け金額の上限は、月額68,000円と他の職種よりも高めに設定されています。しかし、国民年金基金や国民年金付加保険料と合算されているため、iDeCoの掛け金とあわせて月額68,000円を超えないように注意が必要になります。なお、年1回までなら現在の掛け金を変更することが可能です。無理のない範囲での運用を心がけましょう。
| 加入区分 | 掛金の月額上限 |
|---|---|
| 第一号被保険者 自営業者 | 月額6.8万円 |
| 第二号被保険者 会社員・公務員 | |
| 会社に企業年金がないケース | 月額2.3万円 |
| 企業型確定拠出年金に加入しているケース | 月額2万円 |
| 確定給付企業年金と企業型確定拠出年金に加入しているケース | |
| 確定給付企業年金にのみ加入しているケース | |
| 公務員等 | |
| 第三号被保険 主婦・主夫 | 月額2.3万円 |
参考元:iDeCoの拠出限度額について
個人事業主のiDeCoのメリットや節税対策とは?
個人事業主は会社員と異なり、退職金や企業年金といった制度がないため、自分で老後の資金を積み立てて準備しておく必要性があります。更に個人事業主は他の職業と比べて上限額も高く設定されているため、より多くの資産形成が可能になるでしょう。
ここではiDeCoを利用開始するとどのようなメリットや節税効果があるのか解説しています。iDeCoの運用開始前にメリットをしっかりと把握しておくことをおすすめします。
- 運用利益は非課税になる
- 掛け金は所得税控除の対象になる
- 受取時に税制の優遇措置が受けられる
個人事業主iDeCoのデメリットや注意点とは
メリットばかりにもみえるiDeCoですが、デメリットや注意点もあります。これらも事前に把握しておくと安心です。
- 途中引き出し、途中解約は原則不可能
- 価格変動リスクがある
- 手数料がかかる
- 毎月の掛け金が負担になることも
途中引き出し、途中解約は原則不可能
iDeCoは長期的な老後の資金形成を目的とした制度であるため、原則60歳まで引き出しや解約ができません。iDeCo利用中に事業不振になり、実生活が厳しくなったとしても途中引き出しや途中解約はできませんので、あらかじめ注意しておきましょう。
ですので、iDeCoだけに頼らず、流動性の高い資産の形成もあわせて行うことが重要です。
価格変動リスクがある
iDeCoは、価格変動のある投資信託などの金融商品を用いて資産を運用します。タイミングにより運用益が増えたり減ったりし、積み立てた金額よりも少なくなる元本割れが起こることもあります。このように価格変動のリスクがあるので注意が必要です。元本確保型の商品も選べますが、利回りは低めです。
手数料がかかる
iDeCoには加入時手数料・毎月の口座管理料・信託報酬・給付手数料・還付手数料など手数料がかかります。iDeCoを長期間運用するほどコストが積み重なり、運用益を圧迫してしまうことがデメリットです。老後資金を貯蓄する制度ですが、利用するにあたり一定の手数料がかかることを、あらかじめ押さえておくと安心です。
毎月の掛け金が負担になることも
iDeCoは毎月決まった額を積み立てていくため、事業の収入が不安定な時期には掛け金が負担に感じてしまうことがあるでしょう。それに加えて途中引き出しや、途中解約もできないため、事業の資金繰りが厳しいときに頼れないこともデメリットと言えます。しかし、毎月無理のない金額で運用できれば、将来心強い味方になってくれることでしょう。
iDeCoと小規模企業共済を併用しての運用はできる?
iDeCoは、小規模企業共済と併用が可能で、どちらも掛け金が全額所得控除の対象となるため、節税効果も期待できます。今後、iDeCoと小規模企業共済を併用して運用をしようと考えている方はあらかじめポイントを押さえておきましょう。
併用時のメリットと注意すべきポイントとは
iDeCoは投資で資産を増やすことができ、小規模企業共済は将来の退職金として受け取ることができます。併用して運用することで、節税しながらバランスよく将来の貯蓄を準備できます。
ただし、iDeCoは原則60歳まで引き出しができず、小規模企業共済も原則として廃業や退職など一定の事由がない限り途中解約が難しいため、流動性には注意が必要です。 iDeCoと小規模企業共済は運用方法やリスクの性質が異なるため、併用することで資産全体のリスクを分散することができます。iDeCoでの運用成果が振るわない場合でも、小規模企業共済による安定的な貯蓄効果が期待できる点は、安心材料といえるでしょう。
まとめ
iDeCoとは、自分で老後の資金を毎月積み立てていく制度です。iDeCoの掛け金は全額所得控除になり、運用益も非課税です。長期で運用した場合、この非課税のメリットは大きく、老後資金の形成に効果的です。しかし、途中引き出しや途中解約ができず、急な事業不振の資金繰りには当てられません。また、手数料もかかるため毎月の掛け金も無理のない範囲で決めておくことが重要です。ですが、iDeCoを無理なく運用していければ、節税をしながらもしっかりと自分の老後の資産形成ができる、心強い制度です。
]]>- 法人化することで個人事業主よりも信用力が高まるメリットがある
- 個人事業主の法人化には維持管理の複雑化とコスト増加のデメリットも伴う
- インボイス制度により消費税の免税期間が失われる可能性もあるため要注意
- 法人化するタイミングはメリットとデメリットを比較してよく見極める必要がある
- 法人化には法令遵守の取り組みや長期の事業計画策定といった継続的な努力が必要
本稿ではフリーランスをはじめとした個人事業主が、事業を拡大するために法人を設立する法人化について、メリット・デメリット、手続きの流れや最適なタイミングについて詳しく解説します。
個人事業主の法人化とは?
ここで述べる法人化とは、個人事業主から事業形態を法人に変更することを指します。法人とは個人と同様の独立した人格を持つ組織であり、例としては株式会社や合同会社、社団法人やNPO法人などがあります。
個人事業主の法人化では、事業は個人の所有から独立した法人に継承して運営され、法律上の権利と義務が法人に伴います。これにより事業の信用力が向上し、対外的なイメージの向上も期待できます。
個人事業主が法人化するメリット
法人には個人事業にはない、さまざまなメリットが存在します。以下の項目では、代表的な3つのメリットについて解説します。
信用力とイメージの向上につながる
法人は法律によって倒産時などの責任を、出資額を限度とした責任とする有限責任で守られるため、無限責任である個人事業主よりも信用力が高くなります。これは取引先や金融機関との関係構築において大きなメリットです。法人名義の契約を結ぶことで、ビジネスの信頼性や事業に対するイメージを高められます。
節税効果が期待できる
個人所得と法人所得では税率が異なるため、法人化によって所得税の負担を軽減できる可能性があります。法人の方が個人よりも所得税率が低くなる場合があるため、所得額によっては節税効果が期待できます。また、経費として認められる範囲も広がるため、経費計上の幅にも余裕ができます。
資金調達の手段が増える
法人化により、資金調達の手段が増えます。株式や社債の発行による資金調達が可能となり、融資を受ける際の融通性も期待できるため、事業拡大に必要な資金を集めやすくなります。
個人事業主が法人化するデメリット
法人化にはデメリットも存在します。以下の項目では、代表的な3つのデメリットについて解説します。
手続きと管理の負担が伴う
法人化には複雑な手続きが伴います。設立登記や定款作成など、初期段階での手続きが複雑で大きな負担が伴います。また法人としての管理業務も増えるため、事業の内容や形態によっては専門的な知識が要求されることもあります。
事業の維持費が増加する
法人を維持するためには個人事業よりも多くの費用がかかります。例えば、法人税や社会保険料、会計監査費用など、事業の規模に比例して多くの支出が発生します。
経理業務が複雑になる
法人化すると、経理業務がより複雑になります。毎月の給与管理業務をはじめ、出入金の管理も複雑化するため、事業規模によっては専門の担当者が必要です。また定期的な決算報告や税務申告が必要となるため、これらの作業には専門的な知識が求められます。
法人化する手続きの流れ
法人化の手続きでは、複数の役所に専門的な書類を提出するため、手続きの完了には2~3週間ほどかかります。表内の流れが手続きの手順です。
-
会社形態の選択
株式会社や合同会社など、適切な会社形態を選ぶ
-
定款の作成
会社の基本ルールを定めた定款を作成する
-
設立登記
法務局で設立登記を行い、法人としての認定を受ける
-
税務署への届出
法人としての税務手続きを税務署に届け出る
-
社会保険への加入
従業員を雇う場合は社会保険に加入する義務がある
これに伴い、個人事業として開業している場合には廃業の手続きが、法人に引き継ぐ資産がある場合には引き継ぎや名義変更の手続きが必要になります。複雑な手続きになりますので行政書士や司法書士、税理士との連携も視野に入れると、より確実です。
法人化の最適なタイミング
法人化の最適なタイミングは、事業の成長に応じて判断します。具体的には事業拡大を計画するタイミングや、所得税が高くなり始める頃が適していますが、消費税の課税に関するタイミングも目安になります。以下の項目で詳しく見ていきましょう。
事業拡大や資金調達を検討するとき
事業が成長し、人材採用や設備投資が必要なタイミングは法人化の好機です。法人化することで、採用や事業に対する支援や助成が受けられるようになります。資金面でも社債や株式を使った資金調達ができますし、個人に比べて社会的信用も高まるため、銀行からの融資も受けやすくなります。
事業所得が900万円を超えるとき
個人の所得税率は累進課税のため、課税所得695万円以上で23%、900万円以上で33%に上がりますが、法人の所得税率は800万円を境目に15~23.2%です。そのため事業所得が900万円を超える際は、法人化による節税が期待できます。
ほかにも法人であれば役員報酬による所得の分散や、生命保険・退職金といった経費の幅が広がることで、一層の節税対策が期待できます。そのため事業所得が900万円を超えるタイミングが法人化の好機と言えるでしょう。
参考:国税庁|タックスアンサー No.2260 所得税の税率
参考:国税庁|タックスアンサー No.5759 法人税の税率
事業売上が1000万円を超えるとき
個人事業で事業売上が1,000万円を超えると、2年後から消費税の納税義務が生じます。一方、新設法人で資本金1,000万円未満かつインボイス発行事業者でない場合は※、最長で2年間消費税が免除されるため、その直前の法人化は節税上有利なタイミングと言えます。
※但しインボイス発行事業者となる場合は、申請時点で消費税の課税事業者となり、免税期間がなくなるため注意が必要です。
個人事業主が法人化を検討する際の注意点
法人化を検討する際は手続きやメリット・デメリットの理解のほかにも、注意すべきことがあります。以下で代表的なものを簡単にまとめました。
- 専門家との連携
事業の内容や規模によっては、税理士や弁護士といった専門家との連携が必要になる
- 長期的な事業計画の策定
法人化後の資金調達や経営戦略といった、長期的な事業計画が必要となる
- 法令遵守への取り組み
法人化後は企業の法的な義務を理解するとともに、適切な取り組みを継続する必要が伴う
- 個人事業主に戻ることが難しい
法人から個人事業主に戻るには登記簿から法人格を消し、残った純資産を株主へ返金する手間がかかる
まとめ
個人事業主の法人化には、信用力の向上や節税効果への期待といった多くのメリットがあります。一方で法人化には、手続きの負担や事業管理コストの増加といったデメリットも伴います。法人化を検討する際は、これらをよく比較して最適なタイミングを見極めましょう。
法人化の前後には事業規模の拡大とともに複雑な手続きが伴いますので、これを一人で行うことが難しければ、専門家との連携を視野に入れるとより確実です。本稿が後悔のない選択と法人化を成功させる一助となることを願っています。
]]>- 副業で確定申告が必要となるのは、副業所得が20万円以上の場合
- 副業所得が20万円以下でも、所得控除や税金の還付を受けるときは確定申告をした方がよい
- 確定申告は、所得を得た方法により10種類の所得区分がある
- 副業で確定申告をする場合、本業の源泉徴収税額も記載する必要がある
- 副業でも確定申告を行わないと法的な罰則が科される可能性がある
副業とは
副業とは、主職以外の時間を活用して収入を得る働き方を指します。リモートワークでのライター業務や、深夜のバイト、スキルを活用した成果物の販売などが含まれます。
2018年に厚生労働省が作成した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」により、副業を推奨する動きが広がりました。しかし、モデル就業規則第70条記載の理由に該当する場合、企業は副業を禁止および制限できるとしています。
- 労務提供上の支障がある場合
- 業務上の秘密が漏えいする場合
- 競業により自社の利益が害される場合
- 自社の名誉や信用を失う行為、信頼関係を破壊する行為がある場合
参考:厚生労働省|「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定・令和4年7月改定)
副業で得た収入の確定申告はいくらから必要?
副業をしていても確定申告をしてない人も多いようですが、所得によっては、確定申告を行い所得税の納付義務が生じます。
確定申告とは一年間に得た収入等に対して、所得税を自分で計算して申告・納税を行うことを指し、正しく実施するためには理解が必須です。いくらから確定申告が必要か詳しく解説します。
副業所得が20万円以上
確定申告が必要な判断基準は、所得額が20万円を超えた場合です。副業で得た収入ではなく、収入から経費を引いた所得額なので区別しましょう。以下は会社員と個人事業主(副業収入によっては個人事業主の場合と同様に考える)の収入と所得の違いをまとめました。
収入と所得の違い
| 収入 | 所得 | |
|---|---|---|
| 会社員の場合 | 1年間に受け取った給与・報酬・賞与など総額 | 収入から給与所得控除を引いた金額 |
| 個人事業主 | 1年間に受け取った現金や経済的価値のあるものの合計額 | 収入から経費を引いた金額 |
副業所得が20万円以下でも確定申告をした方がよい場合
副業で確定申告をしなくていい金額は、副業所得が20万円以下の場合です。しかし、20万円以下だから確定申告不要と考えるのは損かもしれません。確定申告をすることで、所得控除を受けたり税金の還付を受けたりできる場合があるからです。以下に確定申告をした方がよい例をまとめました。
| 確定申告をすることで還付や減税を受けられる | |
|---|---|
| 医療控除 | 1年間に支払った医療費が10万円を超えた |
| 雑損控除 | 災害や事故・泥棒などで資産に損害があった |
| 寄付金控除 | ふるさと納税等寄付をした |
| 住宅借入金等特別控除 | 住宅ローンを契約した初年度である |
| 退職所得控除 | 年の途中で退職した |
| 経常利益が赤字の事業主 | 青色申告では3年間の赤字繰越計上ができる |
副業の確定申告における所得区分とは
確定申告ではどのような方法で収入を得たかに応じて所得区分が定められています。以下は10種類の所得区分の概要です。所得区分によって必要書類や申請が異なる場合があるので、詳しく見ていきましょう。
| 各所得区分の内容 | |
|---|---|
| 所得区分 | 所得の内容 |
| 事業所得 | 商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得 |
| 不動産所得 | 土地や建物、船舶や航空機などの貸付から生ずる所得 |
| 雑所得 | ・公的年金等の所得 ・原稿料、講演料やシェアリングエコノミーなどの副収入による業務所得 ・その他、他の所得に当てはまらない所得 |
| 給与所得 | 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得 |
| 配当所得 | 法人から受ける剰余金の配当や上場株式等に係る配当等の所得 |
| 利子所得 | 国外で支払われる預金等の利子や特定公社債の利子、預貯金の利子などの所得 |
| 山林所得 | 所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 |
| 譲渡所得 | ゴルフ会員権や金地金、機械などの譲渡、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得 |
| 一時所得 | 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金、一時払の養老保険や損害保険などによる所得 |
| 退職所得 | 退職所得 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法および確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得 |
事業所得
副業の収入源が事業所得に該当する場合は、事業所得として申告しますが、売り上げや経費などを帳票に残す必要があります。事業所得は青色申告の対象であり、帳簿の作成や帳票の保存により、節税対策に役立つ場合があります。
2022年の所得税基本通達の一部改正では、帳簿や書類を作成し保存していれば、本業・副業に関係なく、概ね事業所得として認められるとしています。
参考:国税庁|「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
雑所得
雑所得とは、公的年金や副業による臨時的・単発的な収入など、他9つの所得区分に該当しない所得を指します。上記事業所得で記載したように、帳票の作成や保存等があれば、事業所得に区分される場合もあります。
また、法改訂により3年にわたる副業による雑所得が年間300万円を超える場合は、書類の保存が義務付けられましたので、帳票類の作成や保存を習慣づけることが必要です。
参考:国税庁|No.1300 所得の区分のあらまし
参考:国税庁|雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説
給与所得
給与所得とは、会社や組織と雇用契約を結び、労働の対価として受け取る給与・賞与などの所得を指します。本業とアルバイト等副業の両方で年末調整した場合は、確定申告により再計算され、過払い分の税金の還付を受けられる場合があります。
参考:国税庁|No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの貸付等により得た収入を指します。本業以外でアパート経営等をしている場合は、本業の源泉徴収税額とあわせて不動産所得の申告が必要となります。
参考:国税庁|No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
所得区分に応じて、できる確定申告の種類は異なる
確定申告には青色申告と白色申告があります。青色申告は事業所得・山林所得・不動産所得がある方が対象です。副業で青色申告を受ける場合の方法と青色申告のメリットを見ていきましょう。
副業で青色申告する場合
青色申告を受けるには、事前に「青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。青色申告は、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、専従者給与の経費算入や赤字の3年間繰越計上など、節税効果が大きい申告方法といえます。ただし、正規の帳簿作成など条件があり、副業の場合でも帳票整理を習慣づける必要があるでしょう。
副業では雑所得に区分される場合も多いですが、雑所得ではなく事業所得と認められた場合は、青色申告という大きなメリットを受けることができます。
参考:国税庁|始めてみませんか?青色申告
副業の確定申告のやり方
ここからは、確定申告のやり方を手続きの流れにそって解説します。
副業の確定申告に必要な書類
副業の確定申告には、次のような書類が必要です。他にも、状況に応じて申請書や必要書類がありますので、確認しながら漏れのないように準備しましょう。
| 確定申告に必要な基本的な書類 | |
|---|---|
| 書類 | 内容 |
| 確定申告書 | 所得金額・控除額・税額等を記載したもの |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、または、以下の①②から1点ずつ ①通知カード、個人番号が記載された住民票 ②運転免許証、健康保険証、パスポート 等 |
| 雑所得 | ・公的年金等の所得 ・原稿料、講演料やシェアリングエコノミーなどの副収入による業務所得 ・その他、他の所得に当てはまらない所得 |
| 源泉徴収票 | 本業で源泉徴収をした場合(提出は不要) |
| 所得税額がわかるもの | ・事業所得の内訳を記載した収支内訳書等 ・その他、収入を証明する書類 |
| 各種控除申請に必要な書類 | 各種控除ごとに必要な書類 (ただし、年末調整で申告済の書類は添付不要) |
| 銀行口座がわかるもの | 預金通帳やカード等(還付金受取りの窓口となる口座) |
確定申告書の作成方法を決める
次に確定申告書の作成方法を決めます。手書きやWeb上での作成などもあり、自分の得意な方法を選びましょう。
手書きで作成する
確定申告書を最寄りの税務署までもらいに行くか、国税庁のホームページからダウンロードして取得します。1年間の収入や経費等をまとめておき、各項目に記入します。本業の源泉徴収税額も忘れずに記入しましょう。
手書きの場合は、全体の収支状況が見やすいメリットもありますが、計算ミスや書き間違い等に気をつける必要があります。
確定申告書作成コーナーを利用する
国税庁が運営するサイトを活用する方法で、ガイドにそって入力することで、確定申告書の作成が可能です。マイナンバーカード等で個人を確定し、印刷したりそのままe-Taxで送信(申告)したりもできます。スマートフォンにも対応しているので、手軽に確定申告書の作成ができます。
参考:国税庁|確定申告書等作成コーナー
会計ソフトを活用する
日々の会計状況を管理できるソフトを活用する方法です。ソフトによっては確定申告書の作成もでき、e-Taxに連動させ申告ができるものもあります。年末に計算してみたら、確定申告が必要な収入に達していたが、経費を証明できる書類がないなどと慌てることがないように、会計状況を把握することが重要です。
専門家へ相談・依頼する
税理士に依頼すれば、複雑な税務処理や節税対策も含めて正確な申告が可能です。費用はかかりますが、会計が苦手な人や時間がない人にはおススメです。
確定申告書の書き方
最初に1年間の収入や経費、控除金額等を取りまとめて合計金額を出しておきます。確定申告書のそれぞれの欄に対応する金額を記載し、確定申告書内にある指示に従い計算します。詳しくは以下の記事をご覧ください。
参考:国税庁|給与所得者(年末調整済)の記載例
確定申告書の提出方法
確定申告書の提出には、税務署に持参・郵送・e-Taxの利用などがあります。郵送では、特例として投函日が提出日扱いにできるので、期限がギリギリの際は便利です。しかし、書類不足や記載ミスがあると差し戻される場合もあり念入りな準備が必要です。
それぞれのメリットとデメリットを以下にまとめましたので、自分にとってどの方法がよいか参考にしてください。
| 各提出方法のメリット・デメリット | ||
|---|---|---|
| 方法 | メリット | デメリット |
| 税務署へ持参 | 不明点や記載ミスの確認ができる | 開庁時間内に持ち込まなければならない |
| 郵送 | 遠方の税務署へ行かずとも最寄りの郵便局から投函できる | 不明点や記載ミス、書類不足等があった場合、2度手間になる |
| e-Tax | 24時間利用でき、効率よく申告できる | 操作に不慣れな人にとって初期設定に時間がかかる |
参考:国税庁|スマホで確定申告(副業編)
副業で確定申告しないとどうなるか
副業だから確定申告をしなくていいわけではありません。収入を得たならば、正しく申告し納税をしましょう。以下は確定申告や納税をしなかった場合のデメリットです。
確定申告をしないと罰則もある
確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税、重加算税などのペナルティが科されます。これらの税率は非常に高く、青色申告特別控除の減額などもあり、よいことは一つもありません。以下はそれぞれの罰則の詳細です。
| 確定申告・納税をしない場合の罰則 | |
|---|---|
| 無申告加算税 | 申告期限が過ぎても申告しなかった場合 原則、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%、300万円を超える場合は30%の割合を乗じて課される |
| 延滞税 | 所得税が定められた期限までに納付されない場合 無申告加算税に加え、延滞税もかかる |
| 重加算税 | 重加算税は税務署から調査を受けた際、悪質と判断された場合 無申告加算税等に代えて課される場合の重加算税の税率は40% |
その他副業する際の税の疑問
副業には、所得税の確定申告以外にも、住民税や消費税が関わる場合があります。これらの疑問について解説します。また、納税することで本業企業にバレるのではないかという疑問にもお答えします。
確定申告しなくていい金額でも住民税はかかる
副業所得が20万円以下の場合、特例として確定申告はしなくてもよいとされています。しかし、居住地域の市県民税にあたる住民税は、収入を得た場合、20万円以下でも申告しなければなりません。住民税の申告は、区役所や市役所など市区町村の役所で行います。ただし、確定申告を行っている場合は、そのデータをもとに市区町村が住民税を決定するため、住民税の申告は不要です。
副業によっては消費税の申告が必要な場合がある
適格請求書発行事業者は、消費税の納税が必要です。例えば、インボイス制度に対応している取引先と契約した場合や、自分が適格請求書発行事業者への登録申請を行っている場合、副業でも消費税を納める義務が生じます。確定申告をしなくていい所得金額でも、赤字でも、課税売上があれば消費税の納付が必要です。課税事業者である場合は、消費税分の余力を残す必要があるでしょう。
本業企業が副業禁止の場合バレる可能性がある
副業禁止の企業に勤めている場合、副業がバレる心配があるでしょう。その可能性があるのは、所得税の源泉徴収と住民税の月割税額が毎月の給与から差し引かれる際に、企業が支払う給与の税率よりも多い場合です。副業の住民税等を、別途自分で納税するように申請することで解消できます。確定申告や住民税の申告を正しく行い、バレる可能性を回避できる申請を講じれば安心です。
まとめ
副業で得た収入についても確定申告が必要な場合があります。納税だけでなく、節税対策や還付金を受け取るためにも重要です。申告や納税を行うためには、確定申告への理解が必要ですので、この記事を参考にしていただけると幸いです。
]]>- 事業開始等申告書は、個人事業主が新規事業を開始する際に必要な書類
- 地方税である個人事業税に関係している
- 提出先は各都道府県の税事務所
- 未提出でも罰則やペナルティは特にないが、なるべく提出しよう
- 開業時に提出が必要な書類を整理しておこう
事業開始等申告書とは?
事業開始等申告書とは、個人事業主が新しく事業を始める際に地方自治体へ提出する書類です。
国や自治体が新しく始まる事業について正確に把握して、税金や法令を管理するためにこの手続きが必要となります。提出期限は事業所の所在地によって違うため、いつまでに提出しなければいけないのかきちんと調べておきましょう。
また、事業所得が290万円を超えると、個人事業税の納税義務が発生します。毎年、前年の所得について、3月15日までに各都道府県の税務署へ申告が必要です。
ただし、所得税の確定申告をする場合には、個人事業税のために別途申告をする必要はありません。「事業税に関する事項」の欄に必要事項を記入して、確定申告書を提出しましょう。
開業届との違い
開業届と事業開始等申告書の主な違いは以下の通りです。
| 開業届 | 事業開始等申告書 | |
|---|---|---|
| 税金の種類 | 国税 | 地方税 |
| 書類の提出先 | 税務署 | 各都道府県税事務所 |
| 提出期限 | 開業日から1か月以内 | 都道府県によって異なる |
開業届は国税である所得税に関する書類で税務署に提出するのに対し、事業開始等申告書は地方税である個人事業税に関する書類で、提出先は各都道府県税事務所です。
個人事業税は個人事業主が得た収入に対してかかる税金で、地域のインフラや公共サービスの維持に使われます。
開業届は所得税法第229条で、事業開始から一か月以内に提出しなければならないと定められています。もし開業届を出し忘れてしまった場合でも、古い日付に遡って提出が可能です。
事業開始等申告書の書き方
ここでは東京都の事業開始等申告書を元に、書き方を解説します。
都道府県ごとに申告書のレイアウトは違いますが、基本的には事業所や事業主の情報、開始年月日などを記入します。各都道府県の税事務所ホームページにある申告書記載例も確認してみましょう。
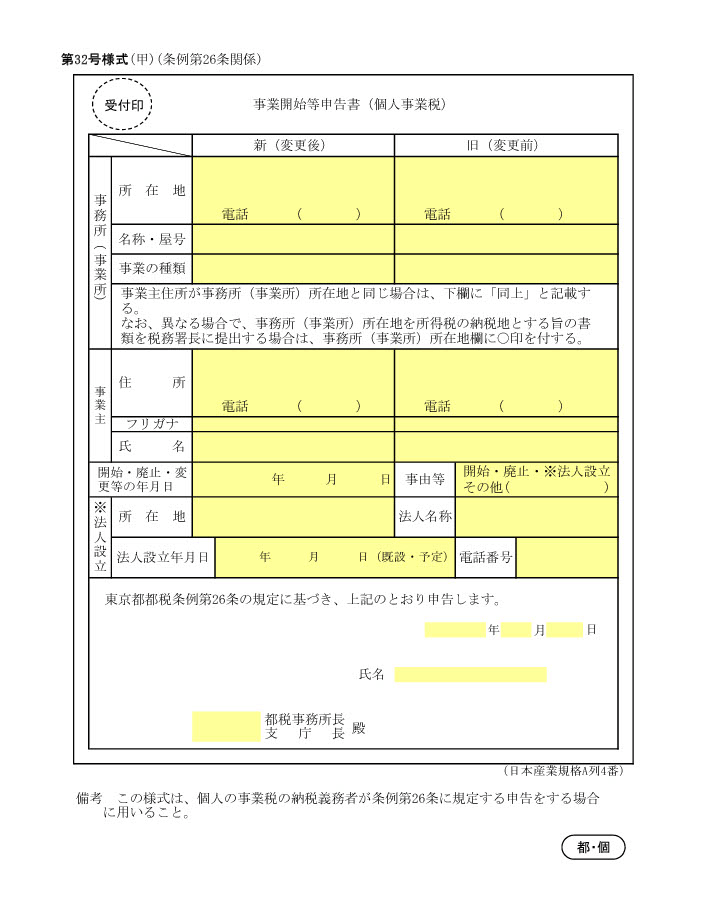
※クリックで画像を拡大できます
出典:東京都主税局|事業を始めたとき・廃止したとき
事務所・事業所の所在地
事業を行う場所の住所と電話番号を記載します。市区町村や番地、建物名などは省略せずに正確に書きましょう。
名称・屋号
事業を行う際に使用する名称および屋号を記載します。ない場合は空欄でも問題ありません。
事業の種類
事業の内容や業種を記載します。
たとえば飲食店の場合は「飲食店業」、生花店の場合は「花・植木小売業」となります。
事業主の住所・氏名
事業を行う本人の住所と氏名を記載します。
自宅で事業を行う場合は、事業所の住所と同じになるので「同上」と書きます。
開始・廃止・変更等の年月日
開業した日付を記載します。開業日は個人事業税の課税期間や納税額に関係してくるので、正確に書きましょう。
事由等
申告書を提出する理由に丸をつけます。開業する場合は「開始」を丸で囲みましょう。
申告日・申告者氏名
提出日を記入し、署名と捺印をします。
提出日は申告書を持参する日、もしくは郵送する日です。
宛先の税事務所
事業開始等申告書の提出先となる税事務所名を記入します。
事業開始等申告書の提出方法・期限
事業開始等申告書の提出方法や期限について解説します。
提出期限
事業開始等申告書の提出期限は、都道府県ごとに異なります。
たとえば東京都の場合は、個人事業を始めた日から原則15日以内が提出期限です。一方、大阪府では開業した日か事務所・事業所を設けた日から2か月以内の提出と決められています。
提出期限を知りたい場合は、自治体に問い合わせるか、各自治体のホームページを確認してみましょう。「事業開始等申告書 ○○県(都道府県名)」と検索すると情報が出てきます。
提出方法
所轄の税事務所へ届け出ます。税事務所窓口で手続きするほか、郵送での受付や電子申請を行っている場合もあります。
事業開始等申告書を提出しないとどうなる?
事業開始等申告書には提出期限が定められているものの、期限を超過したり提出をしなかったりしても、特に罰則やペナルティはありません。
ただし、個人事業税の課税対象となった場合は、事業開始等申告書提出の有無に関係なく、都道府県から納税通知書が届くため、内容を確認し期限内に納付を行ってください。課税対象となるのは、地方税法で定められている法定業種70種に該当している事業で、事業所得や不動産所得など290万円を超える所得があった場合です。
事業開始時に必要な書類
開業時に提出を求められる書類は、事業開始等申告書のほかにも複数あります。事業規模や事業内容によって提出すべき書類が変わるので、事前に確認しておきましょう。
開業届
前述の通り、事業開始時に届け出が必要な書類のひとつです。開業届を提出すると事業者名義の銀行口座を開設したり、確定申告で青色申告を選べたりと、メリットも複数あります。
青色申告承認申請書
税金計算上で有利になる青色申告制度を利用したい場合、こちらの申請も忘れずに行いましょう。要件を満たすと最大65万円の控除を受けられ、節税になります。青色申告制度では、事業で発生した赤字を翌年以降の利益から差し引いて節税できる「損失の繰越控除」や、一定の条件を満たした家族への給与を必要経費として計上できる「青色事業専従者給与」など、さまざまなメリットがあります。
青色事業専従者給与に関する届出書
事業を手伝う配偶者や親族に支払う給与を経費に計上したい場合、青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。家族への給与が経費になることで節税になるほか、収支が明確になり財務管理をしやすくなるメリットがあります。ただし、青色事業専従者給与は扶養控除や配偶者控除と併用できない点に注意しましょう。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
役員や従業員を雇用する際に必要な書類です。開業時に従業員がおらず、後から雇い入れることになった場合にも提出が求められます。提出期限は役員や従業員を雇用する日から一か月以内です。期限を過ぎてもペナルティはありませんが、忘れずに提出しておきたい書類のひとつです。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は、給与を受け取る際に天引きされる所得税です。企業や個人事業主が給与から事前に差し引いて、従業員本人に代わって納付をします。
原則毎月納付となりますが、従業員常時10人未満の場合には半年ごとにまとめての納付が特例として可能となります。この申請をすると納付回数が少なく済むため、事務負担を軽減できるのがメリットです。
適格請求書発行事業者の登録申請書
インボイス制度は、複数税率があっても事業者が消費税を正確に納められるように、消費税の金額などを記載した請求書や領収書(インボイス)を基に計算する仕組みのことです。
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出すると、仕入税額控除を受ける際に必要となるインボイスの交付が可能となります。多くの事業者がインボイスの発行を求めるため、登録することで取引の機会が増える可能性があります。
まとめ
事業開始等申告書は、新たに事業を開始する際に必要な書類のひとつです。提出を忘れてしまっても特にペナルティは発生しませんが、税務処理を滞りなく進めるためにも、期限内に申告するのが望ましいです。期限や書類のレイアウトが都道府県ごとに異なるため、所轄の税事務所のホームページなどで確認しておきましょう。
]]>- 開業届はオンライン提出が可能
- オンライン提出のメリットは、時間や手間が省けること
- e-Taxや無料のWebサービスからオンライン提出できる
- オンライン提出時は、ICカードリーダやスマートフォンが必要
- オンライン申請には、マイナンバー情報が必要
開業届はオンライン提出できる?
開業届とは、個人事業主として事業を開始するときに、税務署へ提出する書類のことです。開業届はオンラインから提出が可能です。
開業届をオンライン提出する際は、主に「国税庁のオンラインサービス」を利用します。
昨今では、開業届の作成・提出を支援するWebサービスの提供を無償で行っている企業も増えています。
開業届をオンラインで提出するメリット
以下では、開業届をオンライン提出するメリットについて解説します。
時間や手間が省ける
オンラインから開業届を提出するメリットは、他の手段と比べて時間や手間が省けることです。これは、開業届の作成から提出までが、すべてオンライン(パソコン・スマートフォン)のみで完結するためです。
一方、郵送で開業届を提出する場合は、書類の作成・封入作業のあとに、郵便局へ行ったりポストに投函したりしなければなりません。また、税務署の窓口で手続きを行う場合は、書類の作成・記入にかかる時間だけでなく、待ち時間も考慮しておく必要があります。
24時間365日いつでも提出が可能
自分の都合がつく日時に開業届を作成・提出できるのが、オンラインのメリットです。時間や場所にとらわれず、いつでも開業届を提出できます。
郵送や税務署の窓口で手続きする場合、税務署や郵便局の開庁時間に自分の都合を合わせなければなりません。また、税務署や郵便局の窓口の受付時間は、基本的に平日の日中のみですので、限られた方しか来庁できないのがデメリットです。
履歴が残る
オンラインで開業届を提出した場合、開業届の控えは発行されません。
ただし、オンラインでは、提出履歴が残るため、それを控えの代わりとして活用できます。
たとえば、e-Taxでは、開業届の提出後に受理したことを知らせるメッセージが届きます。メッセージには、開業届の受理日や提出書類の状況などが記載されているため、きちんと保存しておきましょう。
開業届のオンライン提出時に準備が必要なもの
以下では、開業届のオンライン提出時に必要なものや準備について解説します。
マイナンバーカード
オンラインから開業届を提出する際は、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードとは、マイナンバー(個人番号)が記載されている顔写真付きの身分証明書のことです。
また、マイナンバーカードにはICチップが内蔵されており、なかには個人情報が記録されています。オンラインから開業届を提出する際は、ICチップ内の個人情報をWebへ読み込む必要があります。
マイナンバーカードがない方は開業届のオンライン申請ができませんので、注意しましょう。
ICカードリーダまたはスマホ
先述した通り、開業届のオンライン申請時にはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの情報を読み込むには、ICカードリーダ・スマートフォンなどの専用機器や端末を準備しましょう。
ICカードリーダとは、ICカードに記録された電子情報を読み取る機器のことです。ICカードリーダは、パソコンへ接続して使用する機器のため、スマートフォンから手続きを行う方には必要ありません。
オンラインで開業届を提出する方法
オンラインから開業届を提出する際は、国税庁のサービス(e-Tax)や無料のWebサービスを利用できます。
以下では、それぞれの方法について解説します。
e-Taxで申請する場合
e-Taxとは、国税庁の電子手続きシステムのことです。e-Taxから開業届を提出する際は、マイナンバーカードの用意や利用者識別番号・電子証明書の取得が必要です。
事前に取得・インストールしておくもの
e-Taxから開業届を提出する前に、利用者識別番号や電子証明書の取得およびe-Taxソフトのインストールが必要です。すべて、パソコンやスマートフォンから取得・インストールができます。
- 利用者識別番号とは
利用者識別番号とは、e-Taxの申告時に使用する16桁の番号のことです。
利用者識別番号をすでに取得している方が再取得すると、以前の番号は使えなくなります。古い利用者識別番号に関する情報(メッセージボックスや通知書等一覧の内容など)は確認できなくなるため、注意しましょう。利用者識別番号の取得は以下のサイトから行えます。
参考:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)|作成・送信する開始(変更等)届出書の選択
- 電子証明とは
電子証明書とは、オンライン申請時に用いる身分証明書のことです。
取得にはマイナンバーカードが必要ですので、持っていない方は以下のサイトから申請しましょう。
参考:マイナンバーカード総合サイト|申請・受取方法/申請状況確認
パソコンから電子証明書を取得する場合はe-Taxソフトのインストールが必要です。また、ほかの民間認証局等が発行する電子証明書のなかにはe-Taxで利用できるものもあります。各認証局に関しては、以下のサイトをご参照ください。
※1:政府共用認証局が作成する電子証明書および、地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)の認証局が作成する電子証明書は、個人利用不可
※2:商業登記認証局が発行する電子証明書は個人事業主の利用不可。
参考:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)|電子証明書の取得
スマートフォンから電子証明書を取得する場合は、マイナポータルアプリから手順に従って申請します。
※マイナポータルアプリから電子証明書を取得できるスマートフォンは、2025年4月現在Android機種のみ
参考:マイナポータル|スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォンを教えてください。
- e-Taxソフトのインストール
e-Taxソフトは、国税庁のホームページからインストールできます。
※OSはMicrosoft Windowsのみ対応(Macは非対応)
参考:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)|e-Taxソフトのダウンロードコーナー
e-Taxから開業届を提出する手順
e-Taxから開業届を提出する手順を解説します。
-
e-Taxを起動する
-
メニューボタンの「作成」をクリックする
-
「申告・申請等」をクリックする
-
右下にある「新規作成」をクリックする
-
手続きの種類は「申請・届出」を選択、作成する申告・申請等の税目は「所得税」を選択する
-
「個人事業の開業・廃業等届出書」にチェックを入れる
-
申告・申請等名を記入する
-
利用者識別番号・個人番号などを入力する(マイナンバーカードを読み取る) 提出先の税務署を設定する
-
基本情報の入力が完了したら「OK」をクリックする
-
「作成」→「申告・申請等」→「個人事業の開業・廃業等届出書」→「帳票編集」をクリックする
-
所定の項目を記入して「作成完了」をクリックする
無料のWebサービスから提出する場合
無料のWebサービスからも開業届の提出が可能です。
無料のWebサービスを利用する場合も利用者識別番号と電子証明書の取得は必要ですので、マイナンバーカードは忘れずに準備しておきましょう。
開業届のオンライン提出におけるポイント・注意点
以下では、開業届をオンライン提出する際のポイントと注意点について解説します。
ネット環境やセキュリティ対策を整える
オンラインから開業届を提出する際は、ネット環境の整備やセキュリティ対策を講じる必要があります。
また、ネット環境次第では、ソフトのインストールや開業届の手続きなどが、スムーズに進まない可能性もあります。
不測の事態に対応できるよう、事前にバッファ(余裕時間)を設けておくと安心です。
マイナンバーカードやICカードリーダが必要
オンラインで開業届を提出する際は、マイナンバーカードやスマートフォン・ICカードリーダなどが必要です。持っていない方は事前に準備しておきましょう。
とくに、マイナンバーカードの取得には時間を要することがあります。開業届の提出日が迫っている方は、早めに行動しましょう。
オンライン以外で開業届を提出する方法
開業届は郵送や税務署の窓口でも提出できます。
以下では、オンライン以外で開業届を提出する方法について解説します。
郵送で開業届を提出する方法
開業届は、所轄の税務署(納税者の納税地を管轄する税務署)宛に郵送で提出できます。
- 個人事業の開業・廃業等届出書の原本
国税庁のホームページからダウンロードが可能
- 切手を貼付した返信用封筒
日付や税務署名を記載したリーフレットの送付を希望できる。リーフレットの希望者のみ、切手を貼付した返信用封筒を同封する
- 本人確認書類の写し
「運転免許証」「パスポート」「マイナンバーカード」などのコピー
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類
マイナンバーカード以外の身分証を提出する場合は、マイナンバーを確認できる書類が別途必要(マイナンバーカードの場合は、マイナンバーの確認と本人確認が同時に行えるため不要)
- 青色申告承認申請書(任意)
青色申告を希望する方のみ必要
郵送時には追跡や記録が残る配送方法をオススメします。
その際は「第一種郵便物」または「信書便物」として送付しましょう。宅配便では信書(差出人の意思や事実を受取人に伝える文書)が送れないため注意が必要です。
税務署の窓口で開業届を提出する方法
開業届は、所轄の税務署の窓口でも提出できます。
- 個人事業の開業・廃業等届出書の原本
税務署にある用紙を使用可能
- 本人確認書類
「運転免許証」「パスポート」「マイナンバーカード」など
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類
マイナンバーカード以外の身分証を提出する場合は、マイナンバーを確認できる書類が別途必要(マイナンバーカードの場合は、マイナンバーの確認と本人確認が同時に行えるため不要)
- 印鑑(認印でOK)
訂正が必要な場合にあると便利
- 青色申告承認申請書(任意)
青色申告を希望する方のみ必要
まとめ
開業届はオンラインから提出可能です。オンラインで提出する際は、国税庁や民間企業が提供しているサービスを利用できます。
オンラインのメリットは、自分の都合にあわせて開業届を提出できることです。そのため、近年ではオンラインから開業届を提出する人が増えています。
ただし、オンライン提出時は、マイナンバーカードやマイナンバーカードを読み取るための機器が必要です。
また、マイナンバーカードは取得に時間がかかります。準備や申請方法などに関しては、事前に調べておきましょう。
- 個人事業主の印鑑は実印、銀行印、認印を最低限用意しておけば問題ない
- 個人用の印鑑と併用可能だがセキュリティの観点から分けて印鑑を作るのがオススメだ
- 請求書など書類の信頼度をあげるために事業用の角印を作り運用するのもよい方法だ
- ペンネームや屋号をもつ場合はその名称で事業用の印鑑を作るのも一つの手だ
- 税務署に提出する開業届や確定申告といった書類に印鑑を押す必要はない
個人事業主に印鑑は必要?
個人事業主は重要な契約を結ぶときや、銀行口座の開設などにおいて印鑑が必要になります。この記事では、個人事業主に印鑑はなぜ必要か、最低限持つべき印鑑はどれか、持っていると便利な印鑑などを解説します。
印鑑の種類
印鑑にはいくつか種類があります。
- 実印
- 銀行印
- 認印
- 角印
- 丸印
- 住所印(ゴム印)
- 電子印鑑
このセクションでは印鑑の種類と特徴や役割を解説します。
実印
実印とは、住民登録をしている自治体で印鑑登録を行い、公的に証明される印鑑です。賃貸契約や不動産購入、車の購入といった正式な契約をかわすときには、実印の使用とともに印鑑登録証明書が必要になることがほとんどです。
なお、実印の作成には、チタンや牛角といった壊れにくい高級素材がよく使用されます。実印登録のあとに印鑑が欠けてしまって使えなくなると、再登録が必要になるため、破損しにくい丈夫な素材を選ぶとよいでしょう。
銀行印
銀行印は、新規口座の開設や小切手・手形の手続きといった、銀行・金融機関の手続きに必要な印鑑のことです。
個人の銀行印は苗字またはフルネームで、認印よりやや大きめの丸印で作成するのが一般的です。個人事業主の場合は、名前に屋号を加えて作成する方も見受けられます。ただし、屋号入りの印鑑が個人事業主用の銀行口座の開設に使えるかどうかは、銀行によって違いがあるため、注意しましょう。
お金に関する重要な印鑑であるため、セキュリティの観点から、普段使う印鑑や実印とは別に銀行印を作るのが基本の考え方です。また、銀行印と口座の通帳は別々に保管することも非常に大切です。この2つが盗難にあうと、銀行窓口で預金を引き出されてしまうトラブルがあり得ます。
認印
認印とは、簡易的な印鑑のことです。宅配便の受取や社内回覧の確認印などといった、日常での簡易的な手続きで頻繁に使用されるので、見たことがある人、普段使っている人が最も多い印鑑といえるでしょう。100円ショップやはんこ屋などで販売されている三文判やシヤチハタのようなスタンプタイプの印鑑が認印として使われることが多いです。
ただし、認印は実印や銀行印に比べて法的効力が低いため、重要な契約などには別途、実印や銀行印を用意することがほとんどです。
角印
角印とは、社印のことです。法人で使われる角印は、印影が正方形の印鑑で、社名が彫られているのが大きな特徴です。見積書や納品書、請求書、領収書といったお金に関する書類によく使われます。
個人事業主にとって角印は必ずしも必要な印鑑ではありませんが、とくに屋号がある個人事業主は、公私混同を避けるために屋号で角印を作っておくとよいかもしれません。
丸印
丸印とは、法人では代表者印を指しますが、個人事業主の場合は実印のことです。
住所印(ゴム印)
個人事業主の氏名や屋号、住所、電話番号をスタンプで押せるゴム印は、事業をするにあたって必須ではないものの、意外と重宝するシーンがあります。
たとえば複数の取引先に請求書を送るときや、大量のDMを送付するときに、郵送物の差出人住所の記入を省略できるため、事務作業にかかる時間が大幅に短縮されます。ゴム印注文時にメールアドレスやURLなどを入れることも可能です。ひとつもっていると便利な印鑑です。
電子印鑑
電子書類やオンライン決済の普及によって、電子的に押印できる印鑑が登場しました。重要書類に使用する場合はオンライン上でのセキュリティ面に気を付けましょう。
個人事業主が最低限持つべき印鑑は?
個人事業主が法人と同じ印鑑をそろえなくてはいけない、ということはありません。では、最低限用意しておくべき印鑑はどれなのか、と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
このセクションでは、個人事業主が最低限用意すべき印鑑とその理由を解説します。
実印、銀行印、認印を用意しておけばOK
結論からいうと、個人事業主が持つべき最低限の印鑑は、実印・銀行印・認印の3つで問題ありません。個人事業主は日常的な書類や請求書などには認印を使ってもとくに問題はなく、実印、銀行印も個人名で作成したもので問題はありません。
税務署に提出する確定申告などの書類も、個人事業主については基本的に押印が不要になりました。税務署に提出する開業届にも押印は不要です。詳しくは国税庁のページをご覧ください。
個人事業主が印鑑を使う場面とは
個人事業主が印鑑を使うのは、次のような場面です。
- 銀行口座の開設(銀行印)
- 融資の申し込み(実印)
- 不動産契約(実印)
- 日常の書類、請求書、領収書の処理(認印、角印)
これらの印鑑は個人のものと併用も可能ですが、セキュリティの観点から銀行印と実印は事業用に分けて、新しく作ることをオススメします。
個人事業主が印鑑を作るメリット
前述のとおり、個人事業主には事業用の印鑑が必ずしも必要というわけではありません。
しかし、個人事業主でも角印を作って使用している方は少なくありません。
では、個人事業主が事業専用の印鑑を作るメリットはなにがあるのでしょうか。このセクションでは、個人事業主が印鑑を作る理由やメリットについて解説します。
顧客や取引先からの信用度が上がる
顧客や取引先からみたとき、見積書や納品書に格式のある角印が押されているのと、三文判のような簡易な印鑑が押されているのでは信用度が大きく異なることがあります。格式のある印鑑が押されている書類は、確認をしたという事業者側からの意思表明になるため、書類の信用度を上げる効力をもちます。
そのため、個人事業主であっても、あえて事業専用の角印を作るのもよいでしょう。書類の格式を上げるほか、公私混同を避ける効果もあります。なお、個人事業主が角印を使用するにあたって、実務・法律面ともに問題はとくにありません。
相手に本名を知られずにすむ
漫画家やイラストレーターなどのクリエイター系職種では、ペンネームで活動している個人事業主も少なくありません。そのような場合は、ペンネームや屋号で印鑑を作っておけば、不必要に本名を知られるリスクを回避できます。
個人事業主としての意識が強まる
形式的なことではありますが、事業用のアイテムをきちんと用意しておくことで、事業に対するモチベーションがアップする効果が見込まれます。その一環として事業用の印鑑を用意しておくのもよいでしょう。
まとめ
個人事業主の印鑑は、実印、銀行印、認印を最低限用意しておけば問題ありません。これらの印鑑は、個人用の印鑑と併用可能ではありますが、セキュリティの観点から実印と銀行印については、個人用と別に印鑑を作るのがよいでしょう。
最低限必要な印鑑は先ほど挙げた3種類ですが、請求書などの書類の信頼性を高めたい場合は、事業用の角印を作成して活用するのも効果的です。また、ペンネームや屋号で活動している場合は、それらの名称で印鑑を作成することで、本名が不用意に知られるリスクを回避できます。
個人事業主は、重要な契約を結ぶときや銀行口座開設、融資を受けるために、認印以外の印鑑を使う機会が増えます。印鑑の作成および管理には注意を払い、適切な場面で使用できるようにしておきましょう。
]]>- 開業届を税務署に提出すれば誰でも個人事業主になれる
- 副業禁止の企業に勤めている場合は、上司への相談が必要不可欠
- 法律に触れている場合は、個人事業主になるための要件確認から行う
- 公務員は基本的に副業禁止のため、個人事業主にはなれない
- ただし、非営利活動なら副業と見なされず許可される場合もある
原則として誰でも個人事業主になれますが、この働き方が自分に向いているかどうかの判断は、慎重に行う必要があります。
この記事では、個人事業主になれないケースや、向いている人・向いていない人の特徴などをご紹介します。個人事業主になることを検討する際に、ぜひご参考ください。
個人事業主とは
個人事業主とは法人を設立することなく個人で事業を営む個人のことです。個人事業主になるための要件は特にないため、税務署に開業届を提出することで、原則誰でも個人事業主になれます。従業員を雇用していたとしても、法人でなければ個人事業主と見なされます。
個人事業主は事業者であり労働者には基本的に該当しないため、労災保険と雇用保険へ加入できず、労働法による保護が受けられない点は、大きな特徴です。
個人事業主になれないケースとは?
前述したように、開業届を提出すれば誰でも法的に個人事業主になることが可能です。しかし、以下の条件に当てはまる場合、個人事業主になれないケースがあります。
- 副業禁止の企業に勤めている
- なんらかの法律に触れている
- 本業が公務員である
特に、公務員は信用失墜行為の禁止・守秘義務・職務専念義務の三原則を守る必要があるため、副業は国家・地方公務員法で禁止されています。個人事業主になるということは、公務員でありながら事業を起こすことでもあるため、基本的に認められません。
【理由別】個人事業主になれない場合の注意点
個人事業主になれないケースでは、起業するためには一定の要件を満たす必要や、条件付きの許可を得る必要があります。どちらも満たすことなく起業した場合、法律違反となる可能性があるため、注意が必要です。
ここからは、理由別の注意点をご紹介します。
勤め先の企業が副業を禁じている
企業に勤めている場合、その企業の就業規則で副業が禁止されていることがあります。就業規則での副業禁止は、厳密に言えば法的な拘束力はありません。しかし、企業の機密情報を副業に利用したり情報漏えいの原因となったり、本業への悪影響があった場合は別です。企業内の処罰だけでなく、法律でも厳しく罰せられるでしょう。
どうしても本業と併せて副業を行いたい場合は、副業可の企業へ転職する方法もあります。ただし、副業が本業に悪影響を及ぼす場合には不可とされますので、注意しましょう。
法律の定めに触れている
国や自治体で定められた法律に該当する場合も、個人事業主になれないケースの一つです。ただし、絶対になれないわけではありません。それぞれのケースに該当する要件を満たすことが求められます。
| 対象者 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 18歳未満 | 未成年でも個人事業主になれるが、契約を締結する際には親や親族など、法定代理人による同意書が必要。協力が得られなければ開業できない。 親が法定代理人であることを証明するために、戸籍謄本の提出が求められる場合もある。 |
| 成年被後見人・被保佐人・被補助人 | 精神上の障害などによって判断能力が欠如しており、法律行為を適切に行うことが困難と見なされた場合、個人事業主になることを制限される可能性がある。 個人事業主になるには、法的な能力を補うために、適切な法定代理人が必要となる。 |
| 破産者 | 自己破産の経験がある人は信用情報機関に事故情報が登録されるため、金融機関から融資を受けることが難しく、資金調達が困難になる。一定の要件を満たせば事業の再開は可能だが、財務状況の改善策を講じることが求められる。 |
| 禁錮以上の刑に処された人 | 社会的な信用が低く起業も営業も困難になる可能性が高いが、一定の要件を満たせば個人事業主になれる。個人事業主を目指すのであれば、法的な制約内容を理解し、信用回復に努めることが重要。 |
上記にまとめた内容・注意点をおさえることで、個人事業主になれる可能性があるでしょう。ただし、要件を満たすためには本人の適性や能力だけではなく、家族や知人などの協力といった、社会的な状況も必要不可欠です。
本業が公務員である
前述したように、公務員は信用失墜行為の禁止・守秘義務・職務専念義務の三原則を守る必要があります。副業が国家・地方公務員法で禁止されていることから個人事業主にはなれません。
ただし、営利目的でなければ副業と見なされず、許可がもらえるケースもあるようです。以下の表に、副業例としてまとめました。
| 副業例 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 投資(株式・FX・仮想通貨など) | 株やFXなどの資産運用は副業に該当しないため、基本的には自由に行うことが可能だが、業務と重複した時間に投資を行うことはできない。三原則の範囲内で行うことが大前提。 ただし、業務で知り得た未公開情報をもとに株式売買を行って利益を得る行為は、インサイダー取引に当たり法律違反となるため、取引方法には要注意。 |
| 不動産 | 不動産は、売却目当ての投資は不可。あくまでも家賃収入を得る目的で、以下条件にあてはまる不動産賃貸業のみが認められる。 ・家屋の賃貸は、物件の数が5棟未満かつ10室未満であること ・土地の賃貸の場合は、10件未満であること ・賃貸する不動産が娯楽・遊戯目的または宿泊目的に使われていないこと(劇場・映画館・ゴルフ練習場・旅館・ホテルなど) ・駐車場の賃貸は、駐車台数が10台未満かつ平面で、機械設備を設けていないこと ・賃貸料収入の年収が500万円未満であること |
| 講演・執筆活動 | 講演や執筆活動は、単発で発生する講演や執筆の場合には許可が必要ないとされている。ただし、定期的または継続的に行う場合は、申請をした上で許可を得る必要がある。活動時間は、他の副業と同様に公務員としての業務時間と重複しないことが重要で、本業に支障がある場合は活動不可となる。 講演における謝礼金は、営利目的でない場合のみ受け取れる。 |
| 農業(小規模・家庭菜園) | 農業をはじめとした牧畜・酪農・果樹栽培などは、自給自足を目的とした小規模農業であれば兼業として認められる。一定の規模を超える場合は承認を得る必要があるため、自己判断せずに勤務先に確認することが重要。 農業が盛んな地域では、公務員と農業の兼業も珍しくないことから、規模が大きい農業でも承認が得られやすい傾向にある。 |
| 家業手伝い | 家業の手伝いは無報酬であれば可能。しかし、国家公務員は非営利団体で自営に該当する副業は基本的に制限されており、地方公務員も自治体の制度や家業の内容などによって可否が異なる。自己判断で進めずに、勤務先の承認を得る必要がある。 やはり、三原則の範囲内であることが大前提。 |
| フリマアプリなどの処分売却 | 不用品を売るだけであれば問題ないが、転売・せどり目的であれば禁止行為に当たる。趣味のハンドメイド品を販売する場合も、作ったが使わない不用品であり、販売価格が原価程度であれば問題ないが、販売頻度が高い場合は禁止行為に当たる可能性がある。 本業に支障をきたさない範囲で行うこと。 |
一部の自治体では副業解禁に向けた動きがあります。本業に支障がなく社会貢献性があるなどの基準・条件がしっかりと定められた場合は、地方公務員の副業が可能となるかもしれません。
個人事業主に向いている人の特徴
開業届を提出すれば個人事業主になれるとはいえ、どういった人が向いているのか、自分の向き不向きが気になる人もいるのではないでしょうか。
ここからは、個人事業主に向いている人の特徴を5つ、ご紹介します。
責任感・責任を負う覚悟がある
個人事業主は、事業に関わるすべての責任を負う必要があります。企業勤めの頃は上司や会社が責任を負っていたことにも、自分で対処し責任をとらなければならないため、相応の責任感や覚悟がなければ務まりません。事業の成功・失敗のすべてが自分次第です。困難な状況下であっても、積極的に改善しようと行動できる人は、個人事業主に向いていると言えます。
責任感をもって仕事に取り組むことで、顧客や取引先とのスムーズな信頼構築につながり、人脈によって事業の発展にもつなげられるでしょう。
向上心・チャレンジ精神がある
個人事業主は、常に目まぐるしく変化する社会情勢や市場動向、顧客のニーズなどに臨機応変に対応する必要があります。そのためには新しいスキルや知識を積極的に学び続ける姿勢も重要となり、向上心やチャレンジ精神がある人には有利です。事業の競争力の維持や継続的な成長にもつなげられます。
さらに、新しいプロジェクトやアイデアに挑戦することで、事業の幅を広げることが可能です。失敗を恐れずに挑戦することで、成功への道を切り開くことができるでしょう。
営業・交渉スキルがある
自分で案件を獲得する個人事業主にとって、営業や交渉のスキルは必要不可欠です。
営業スキルが高い人は顧客のニーズを的確に把握して最適な提案ができ、交渉スキルがある人は取引条件を有利に進められます。営業・交渉スキルがある人は、顧客を獲得しつつ取引を成功へ導けるため、利益を最大化させることが可能です。スキルを磨きながら案件を受けることで、個人事業主としての信頼性が向上し、長期的な成功を収められるでしょう。
自分の裁量で業務を進めたい
自分の裁量で業務を進めたいという意欲は、業務の進行を自分のペースで管理しつつ効率的に成果を上げられるため、個人事業主にとって重要な要素です。裁量権を持つことで、創造的なアイデアを自由に試みることができ、事業の継続性や革新につながります。また、自分の裁量で業務を進めることでストレスを軽減し、充実した仕事環境を築くことが可能となるでしょう。
しっかり自己管理ができる
個人事業主にとって、自己管理能力は欠かせない要素です。自己管理ができる人は、目標に向かって計画的に行動し、時間を有効に使うことが可能です。スケジュール管理やタスクの優先順位付けを行うことで、効率的な業務の遂行や、成果につなげられます。これにより、事業の安定性を維持し、継続的な成長を実現します。また、自己管理能力が高い人は健康管理やストレス対策もしっかりと行えるため、個人事業主としての事業運営を長期的にセルフサポートできるでしょう。
個人事業主に向いていない人の特徴
個人事業主には、さまざまな変化への迅速な対応や、自ら事業を切り開く力が求められます。必要とされるビジネススキルの有無以外に、個人事業主に向いていない人の特徴を4つ、ご紹介します。
主体性・決断力がない
個人事業主が円滑に事業を運営するには、迅速かつ的確な判断が求められます。主体性と決断力が欠けていると、問題の解決に手間取ったり、新しいビジネスチャンスへの対応が遅れたり、重要な場面での選択に迷って機会を逃してしまう可能性があります。
主体性を高めるためには、自らの考えを明確にして、積極的に意見を発信する練習が効果的です。日々の小さな決断を積み重ねて、自信や決断力を養っていくといいでしょう。
コミュニケーションが不得意
コミュニケーション能力が低い場合、個人事業主としての活動に大きな支障をきたします。コミュニケーションが取れないだけでも顧客や取引先などの関係構築が難しく、信頼を得にくくなります。その結果、ビジネスチャンスを逃したり、顧客満足度を低下させたりする可能性があるでしょう。
コミュニケーションが不得意な人は、まず基本的な会話スキルを向上させることが重要です。具体的なポイントは以下の3点です。
- 相手の話をしっかり聞く
- 明確な言葉で自分の意見を伝える
- フィードバックを受け入れる姿勢を持つ
人と関わる機会を積極的に増やし、実践を通じてスキルを向上させると良いでしょう。
保守的・安定性を求める
保守的で安定性を求める人は、挑戦に消極的な傾向にあるため、個人事業主に向いていると言えません。新しい市場やビジネスモデルに対するリスクを恐れて、現状維持を選んでいては競争の激しいビジネス環境での適応が難しく、成長の機会を逃す可能性があります。安定性を求めること自体は悪いことではありませんが、事業を拡大させるためにはある程度のリスクを取ることも必要です。
対策として、リスク管理のスキルを身につけ、小さなリスクから徐々に挑戦していくことでリスクへの耐性を高めるといいでしょう。情報収集も怠らず、市場の変化に対応するための柔軟性が持てると、挑戦にもつなげやすくなります。
自己管理ができない
自己管理ができない人は、個人事業主として成功するのが難しいです。スケジュール管理が甘いと納期を守れず、顧客の信頼を失う恐れがあります。業務の優先順位がつけられなければ、効率的な仕事ができず、結果として事業の成長が妨げられます。
自己管理能力を高めるためには、まず目標設定を明確にし、それに基づいた計画を立てることが重要です。時間管理ツールやアプリを活用して日々のタスクを可視化したり、定期的に自分の進捗を確認したり、必要に応じて計画を見直していくといいでしょう。
まとめ
個人事業主は開業届を提出することで誰でもなれますが、副業禁止の企業に勤める人や法律に触れている人、公務員などは制約があります。特に公務員は副業が法律で禁止されており、個人事業主になることは基本的に認められません。個人事業主にも向き不向きがあり、責任への覚悟を持っていて、向上心やチャレンジ精神、営業・交渉スキルがある人には向いていると言えるでしょう。反対に、主体性や決断力の欠如、コミュニケーションが不得意で保守的な人には向いていないでしょう。
]]>- フリーランスが支払う税金は収入と所得から算出される
- フリーランスの節税には経費計上と各種控除の活用が重要となる
- 節税には資金管理とともに経費にできる税金を把握することも重要
- 青色申告による各種の控除はフリーランスにも大きな節税効果がある
- 控除にできる保険や共済は資産形成とともに節税効果をもたらす
フリーランスの事業では確定申告を通じて収入を申告し、税額を求めます。税額は収入(売上)と、そこから経費と各種控除を差し引いた課税所得から算出します。つまり経費と控除を増やすことが節税のポイントです。本稿ではフリーランスの税金と節税対策について、ポイントと合わせて解説します。
フリーランスが支払う税金の種類
フリーランスが支払う税金には、所得税や住民税、さらには個人事業税や消費税などが挙げられます。以下の表では、確定申告後にフリーランスが支払う税金について、解説とともにまとめました。
フリーランスの税金一覧
| 所得税 | 収入から必要経費を差し引いた所得に課税される税金 |
|---|---|
| 復興特別所得税 | 東日本大震災からの復興に必要な財源確保を目的として創設された税金 |
| 住民税 | 所得に応じて地方自治体から課税される税金 |
| 個人事業税 | 年間の事業所得が290万円を超えた事業者に課される地方税。業種によって税率が異なる |
| 消費税 | 前々年の売上が1000万円を超える事業者、また開業から2年以内でも前年1月1日~6月30日の売上が1000万円を超える事業者は、売上に対して消費税が課される |
| 固定資産税 | 家屋や土地などの固定資産に対する税金。所有する物件をオフィスとして使用する場合は、固定資産税を合理的な割合で按分できる |
フリーランスの節税対策
経費と控除は確定申告時に収入や所得から差し引かれるため、これを確保し、活用することがフリーランスの節税につながります。そのためには、年度末になって慌てて対策を始めるのではなく、年間を通じて経費や控除を意識した、計画的な資金管理が重要になります。これらのポイントについて、以下の項目で詳しく解説します。
経費計上が節税につながる
必要経費は確定申告時に収入から差し引かれ、その計算結果が所得となるため、経費の適切な計上こそ節税の基本といえます。フリーランスも他の事業者と同様に、事業に直接関連する出費を必要経費として申告できます。例えば、仕事用のパソコンやオフィスの家賃、通信費などがこれに該当します。注意すべきは、プライベートと事業の出費をきちんと区別することです。
経費項目の具体例
正しく経費を計上するためには、具体的にどのような費用が必要経費として認められるかを知っておくことが重要です。代表的な経費としては交通費・交際費・消耗品費・研修費などがあり、これらの費用は事業を円滑に進めるために必要な経費として計上できます。普段から領収書やレシートを保管し、記録をつける習慣をつけましょう。
経費にできる税金を把握する
フリーランスは自身の税金を経費にすることはできません。例えば所得税や住民税などはいずれも経費対象外です。ただし、事業に関わる税金であれば経費として計上できます。例えば、個人事業税や事業で支払った印紙税は経費の対象になります。また、自宅兼事務所として使用している不動産の固定資産税や自動車税は、家事按分後の金額を経費に計上できます。他にも、個人事業税や税込経理方式における消費税などが租税公課として経費に計上できます。
控除の活用も節税に有効
確定申告で扱う控除には所得金額を差し引く所得控除と、算出後の所得税額から差し引く税額控除が存在します。いずれも税金を減額させる効果があるため、控除を理解し活用することは節税にも有効に働きます。
所得控除の種類
売上から経費を差し引いて算出した金額を、事業所得と言います。この事業所得からさらに所得控除を差し引いた金額が課税所得となります。この所得控除について、以下の表にまとめました。
| 所得控除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下の納税者が受けられる控除 |
| 社会保険料控除 | 社会保険料を支払った際に受けられる控除 |
| 配偶者控除 | 控除対象の配偶者がいる場合に、一定の条件を満たした納税者が受けられる控除 |
| 配偶者特別控除 | |
| 扶養控除 | 16歳以上の親族を扶養に入れている場合に受けられる控除 |
| 勤労学生控除 | 学生であり、一定以下の所得がある場合に受けられる控除 |
| ひとり親控除 | ひとり親の場合に受けられる控除 |
| 寡婦・寡夫控除 | 寡婦・寡夫の場合に受けられる控除 |
| 障害者控除 | 納税者本人・配偶者・扶養親族などが障害者や特別障害者に該当する場合に受けられる控除 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料を支払った際に受けられる控除 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った際に受けられる控除 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済や個人型年金の掛金などがある場合に受けられる控除 |
| 医療費控除 | 納税者本人・配偶者・扶養親族などの医療費が一定額を超えた場合に受けられる控除 |
| 寄附金控除 | 国や地方公共団体への寄附やふるさと納税などを行った際に受けられる控除 |
| 雑損控除 | 災害・盗難・横領などによって損害を受けた際に受けられる控除 |
税額控除の種類
税額控除とは、確定申告で算出された所得税額から直接的に差し引ける控除です。そのため税額控除は直接的な節税効果があります。この税額控除について以下の表にまとめました。
| 税額控除の種類 | 控除を受けられる対象 |
|---|---|
| 特定増改築等住宅借入金等特別控除 | 住宅の新築・取得・増改築などを行った際に受けられる控除 |
| 住宅特定改修特別税額控除 | 住宅の省エネ改修工事をした場合に受けられる控除 |
| 住宅耐震改修特別控除 | 住宅の耐震改修工事をした際に受けられる控除 |
| 配当控除 | 株の配当金や投資信託の分配金を受け取ったときに受けられる控除 |
| 外国税額控除 | 海外で課税された所得税を日本の所得税額から控除できる制度(二重課税を調整するための制度) |
節税に生命保険や小規模企業共済を活用する
社会保険料・生命保険料・地震保険料の各種保険料は確定申告時に所得から控除できます。また小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)も有効な節税手段です。これらは、老後の資金を準備しながら所得控除を受けられる制度です。掛け金は全額所得控除の対象となり、節税と資産形成の両方に役立ちます。
青色申告には大きな節税効果がある
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、手続きがより複雑な青色申告では、最大65万円の控除を受けられるため、フリーランスにも大きな節税効果をもたらします。以下で詳しく見ていきましょう。
青色申告の条件
青色申告の特別控除を受けるには、管轄税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、以下の条件を満たす必要があります。
- 事業所得、または事業的規模の不動産所得がある
- 事業所得に関する取引を複式簿記で記帳している
- 作成した青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付して確定申告をしている
- 期限を守って確定申告をしている
- 現金主義による所得計算の特例を選択していない
- e-Taxで確定申告を行うか、仕訳帳と総勘定元帳などを電子帳簿保存法が定める「優良な電子帳簿」として保存している
※1~5を満たすと55万円控除、6も満たせば65万円の青色申告特別控除が受けられる
※65万円・55万円の控除要件を満たさない場合、控除は最大10万円となる
※10万円控除の場合は単式(簡易)簿記での帳簿作成が可能
青色申告のメリット
青色申告はフリーランスの節税にも大きなメリットがあります。それらについて以下の表にまとめました。
| 青色申告特別控除 | 所得金額から最大65万円の控除を受けられる |
|---|---|
| 赤字を繰り越せる | 赤字を翌年以降、個人事業主で最長3年、法人で最長10年※の所得から差し引ける ※平成30年4月1日より前に開始した事業年度の繰り越し期間は9年 |
| 青色事業専従者給与 | 事業主が生計を同じくする家族に支払う給与を経費にできる(申告する前年の3月15日までに届出が必要) |
| 貸倒引当金を経費にできる | 貸倒引当金とは、貸倒れの可能性がある債権(売掛金や貸付金など)に備えて、事前に計上する金額のことで、青色申告ではこれが、貸金の帳簿価額合計の5.5%以下であれば経費にできる |
| 少額減価償却資産の特例 | 30万円未満の資産を取得した場合、一度に経費に計上できる |
まとめ
今回はフリーランスの税金と節税のポイントについて解説しました。フリーランスとして事業を安定して継続するには、収入確保とともに節税も重要課題です。そのためには経費や控除について正しく理解し、青色申告の活用や計画的な資金管理を行うことが、税負担の軽減につながります。後になって慌てることがないよう、節税は日々の業務とともに積み重ねて対策しましょう。本稿が節税対策の一助となることを願っています。
]]>- 開業届とは、個人事業主が事業を始めた際に、所轄する納税地の税務署へ提出する届出書
- 記入の前に、マイナンバーカードや本人確認書類などを準備する
- 開業届に記載する住所は、納税地住所とその他の住所がある
- 開業届の提出は、開業から1か月以内のため注意が必要
- 開業に伴う届出書や、給与の支払状況に応じた源泉所得税の納期など、関連する提出書類の確認が必要
個人事業主が新たに事業を始めたとき、税務署に開業届を提出しなければなりません。どのような内容を記入するのか、必要書類は何か、さらに官庁への提出書類にありがちな独特の表現などに戸惑うことも多いでしょう。この記事では、開業届の書き方を、見本とともにわかりやすく解説します。
開業届とは
開業届とは、個人事業を開業した際、所轄する税務署に提出する届出書です。これにより納税や申告の意思を正式に示します。所得税法第229条において開業届の提出は義務付けられています。ただし、事業所得を得ていないフリーランスや副業の場合はこの限りではありません。
参考:国税庁|No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
開業届の入手方法と準備するもの
開業届の入手方法と、開業届の記入前に準備しておくものを解説します。この章では、基本的な準備について紹介しますが、記事後半の節税対策や従業員の有無など、開業届の記載内容によって他に提出する書類等もあります。最後までお読みいただくことで、開業に必要な手続をスムーズに進められるでしょう。
開業届の入手方法
開業届の入手方法は、最寄りの税務署に直接もらいに行く、もしくは、国税庁のホームページからダウンロードして印刷できます。手書きのほかにネット申請できるe-Taxなどを利用してWeb上で作成することも可能です。
参考:国税庁|個人事業の開業・廃業等届出書・控え
参考:国税庁|A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
入手前に準備しておいたほうがよいもの
開業届には、マイナンバーの記入が必要になるため、マイナンバーカードなど個人番号が確認できるものが必須です。また、住所の番地や丁目などを略さずに記入するためには、本人確認書類があると便利でしょう。さらに、事業所の住所や屋号、職業などの基本情報を整理しておくとスムーズに書き進められます。
開業届の見本と書き方
開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい各項目に正確な情報を記入することが求められます。開業届の書き方を、以下の書き方例(見本)にそって解説します。
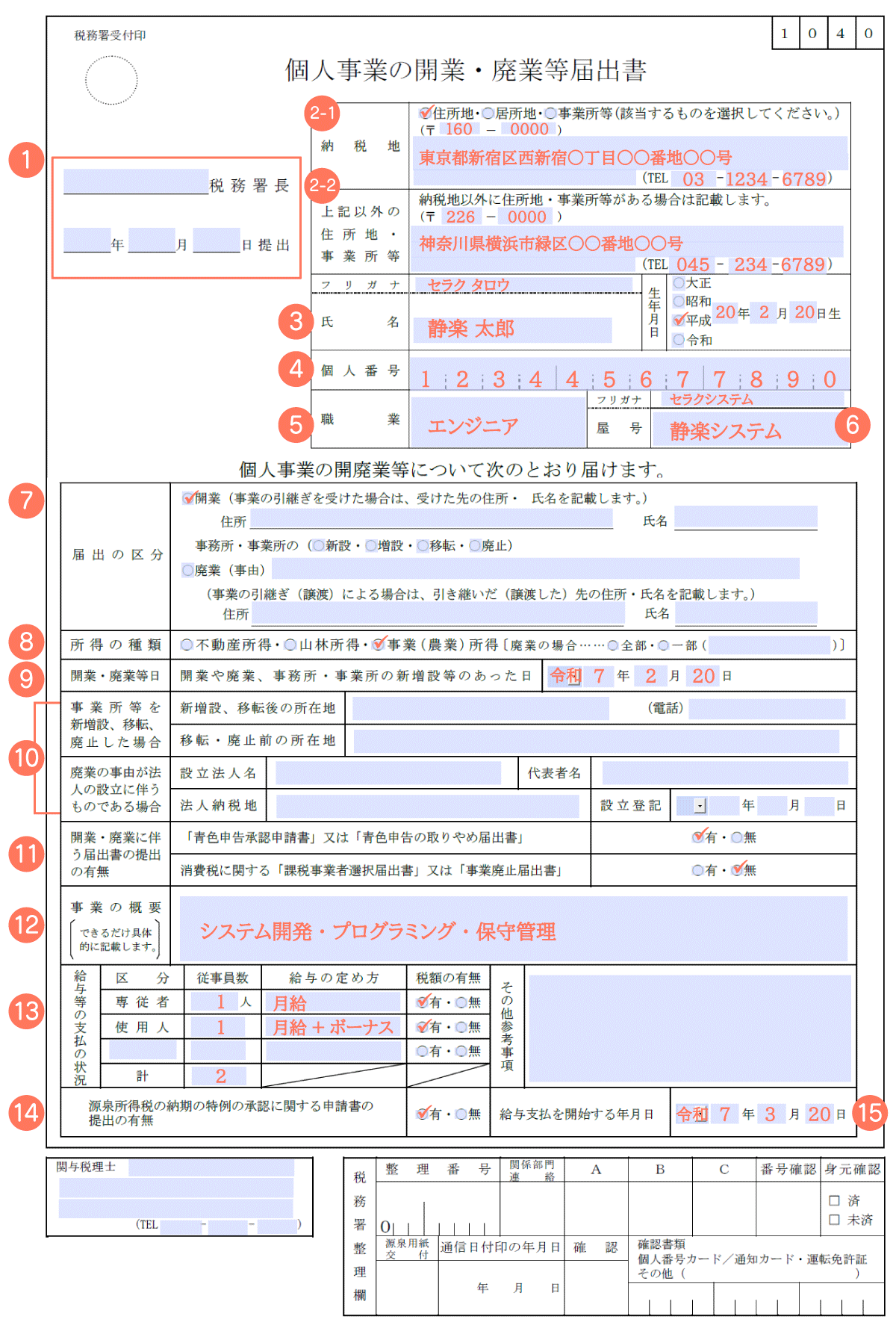
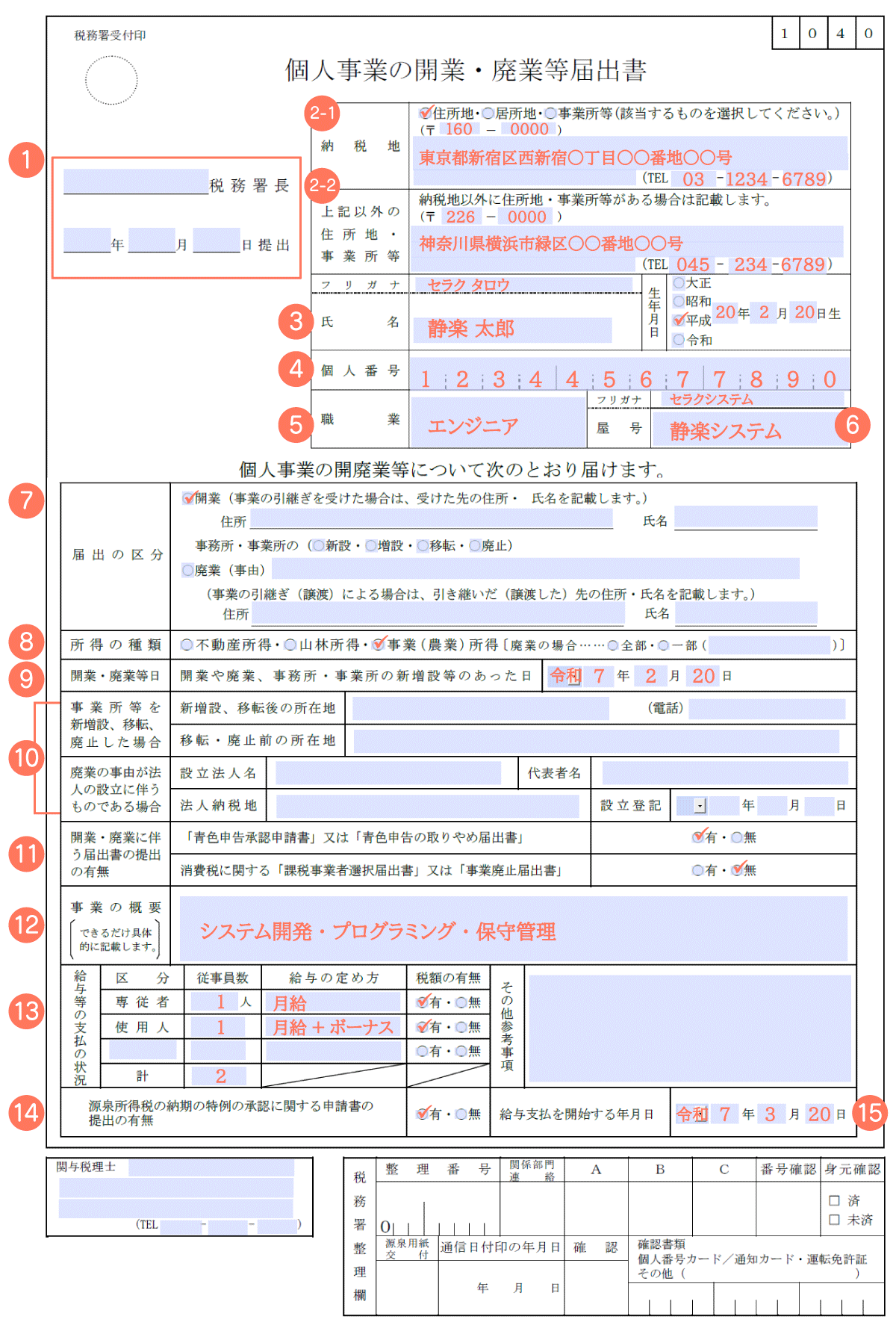
※クリックで画像を拡大できます
①提出先税務署名と提出日
所轄する(納税地の税務署)税務署名と提出日を記入します。提出日は和暦・西暦どちらでも構いません。ただし、提出期限が開業から1か月以内なので開業日からの期限を守ることが重要です。
納税地の税務署は国税庁のホームページから確認できます。
参考:国税庁|国税局・税務署を調べる
②-1納税地
納税地とは、個人事業主の場合、原則として自宅のある「住所地」となります。住民票に記載された住所ということです。ただし、納税地の特例として、店舗や事務所のある住所「事業所等」や「居所地」を納税地にすることも可能です。税務署からのお知らせは、この納税地の住所に届きますので正確に記入しましょう。
【住所地・居所地・事業所等の違い】
| 住所地 | 住民票に記載の住所 |
|---|---|
| 居所地 | 一時的に居住している住所で、ここで生活が営まれている客観的な根拠が必要 |
| 事業所等 | 店舗や事務所等の事業所のある住所 |
参考:国税庁|No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
②-2.上記以外の住所地・事業所等
上記以外とは、たとえば納税地に事業所等や居所地を選んだ場合、こちらには自宅の住所地を記入します。また、海外在住で日本国内に事務所等を開設して事業を開始する場合、納税地は日本国内の店舗あるいは事務所等の住所となり、こちらに自宅住所地を記入します。この項目は、事業運営の実態に合わせて正確に記入しましょう。
【納税地別の記入例】
| 例1:納税地を自宅にしたが、他に店舗がある | 2-1納税地:自宅住所(住所地) 2-2上記以外の住所地、事業所等:店舗のある住所 |
| 例2:納税地を事務所の住所にしたい | 2-1納税地:事業所等の住所 2-2上記以外の住所地、事業所等:自宅住所(住所地) |
| 例3:自宅と事務所を兼ねている | 2-1納税地:自宅住所(住所地) 2-2上記以外の住所地、事業所等:記載不要 |
| 例4:海外在住で、日本国内に事務所がある | 2-1納税地:事業所等の住所(日本国内の住所) 2-2上記以外の住所地、事業所等:自宅住所(住所地) |
③氏名/生年月日
事業を開始した本人の氏名と生年月日を記入します。氏名にはふりがなを忘れずに記入し、生年月日の和暦は、あてはまる箇所にチェックを入れましょう。
④個人番号
マイナンバーカードに記載された12桁の個人番号を記入します。この番号は、税務上の識別に使用されるため、正確な記入が必要です。間違いの無いように注意しましょう。
⑤職業
職業は誰が見てもわかるような職業名を記入します。記載にルールはありませんが、業種によっては個人事業税(地方税)の課税対象や、税率が変わる可能性もあるため注意が必要です。
個人事業税に関わる個人事業等の開始申告書は地方によって提出期限が異なりますので、お住まいの都道府県税事務所に確認しましょう。
⑥屋号
屋号がある場合に記入します。屋号を設定することで、屋号つき銀行口座の開設が可能です。さらに、事業の内容やイメージを明確に伝えることができ、ブランディングにもつながります。商標登録されていないか確認し、屋号を決めるのもよいでしょう。
⑦届出の区分
「開業」の項目にチェックを入れます。廃業の場合も同じ書式を使うので、記入漏れの無いように気を付けましょう。また、事業を引き継いで開業する場合は、元の事業者の住所、氏名を記入します。
⑧所得の種類
所得の種類は、「不動産所得」「山林所得」「事業(農業)所得」のうち、該当する所得にチェックを入れます。副業の場合も、その副業で得る所得の種類にチェックを入れましょう。
【所得とその内容】
| 事業(農業)所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得 |
|---|---|
| 不動産所得 | 土地や建物など不動産の貸付けや、借地権など不動産に関する権利の設定および貸付け、船舶や航空機の貸付けなどから生ずる所得 |
| 山林所得 | 山林を伐採して譲渡や、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 |
⑨開業・廃業等日
開業日には特に決まったルールがないため、事務所の開設日や店舗のオープン日、または仕入れや広告制作などの準備を始めた日などを開業日として設定することがあります。ただし、この開業日から1か月以内に開業届の提出が必要なので計画的に準備をしましょう。
⑩事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
基本的に新規開業の場合は、記入する必要はありません。
⑪開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業に伴って、「青色申告承認申請書」や「消費税の課税事業者選択届出書」を提出する場合は、それぞれの段の「有」にチェックを入れます。
開業した年から、青色申告や課税事業者を希望する場合は、「青色申告承認申請書」や「課税事業者選択届出書」を一緒に提出できます。なお、インボイス制度に対応するため「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しているなら、課税事業者選択届出書を提出しなくても課税事業者になることが可能なため、「無」にチェックを入れましょう。
【同時提出を検討したほうがよい書類】
- 青色事業専従者の給与に関する届出・変更届出書:
青色申告では、専従者給与を経費計上できるため、専従者があり青色申告を受ける際には一緒に提出できます
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書:
給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設・移転・廃止した場合に提出する届出書です
開業時に事務所等を開設した場合は開業届と一緒に提出できます
参考:国税庁|D1-4 消費税課税事業者選択届出手続
⑫事業の概要
職業欄に記載した事業の内容を詳しく記入します。たとえば、エンジニアなら、「システムの開発、設計、保守点検」など、飲食業なら、「ラーメン等の調理、販売」などのように、実際に行う業務内容を具体的に記入しましょう。
⑬給与等の支払の状況
家族「専従者」や家族以外の従業員「使用人」を雇用する場合、それぞれの人数と給与の支払方法(例:日給・月給)および、源泉徴収の有無を記入します。給与の支払が生じる場合、基本的に源泉徴収を行う必要があるため「有」にチェックを入れます。
【給与等の支払状況記入時のポイント】
| 従業員数 | 専従者:生計を一にする家族の従業員 使用人:家族以外で雇用した従業員 それぞれの人数と合計人数を記入する |
| 給与の定め方 | 「時給」 「日給」 「月給」 「月給+ボーナス」などの給与の支払方法を記入する |
| 税額の有無 | 源泉徴収する場合は、「有」にチェック しない場合は「無」にチェック ※給与の支払が生ずる場合、基本的には源泉徴収を行うため「有」になります。 |
⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書の提出の有無
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期です。しかし、給与の支給人員が常時10人未満であれば、年2回にまとめて納める特例を申請できます。これを申請する場合は「有」にチェックをして、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書」も一緒に提出します。
参考:国税庁|No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
⑮給与支払を開始する年月日
給与の支払が生ずる場合に記入します。新たに給与支払いを始める場合はその予定年月日を、すでに支払っている場合は開始した年月日を記入しましょう。
ここで注意することは、支払開始から源泉所得税の納期の特例(⑭参照)を受けたい場合は、給与の支払開始日の前月末までに申請書を提出する必要があります。
すでに給与を支払っている場合は、申請書を提出した翌月から特例の適用となります。これ以前に支払った給与に関しては、通常の納期限までに源泉所得税を納付しなければなりません。
【給与の支払状況別、記入例と注意点】
| 給与の支払予定がある:支払い始める年月日を記入する |
| すでに給与を支払っている:支払を開始した年月日を記入する |
| ※)開業当初から源泉所得税の納期の特例(⑭記載)を受けたい場合は、支払開始月の前月末までに、
開業届と共に申告書を提出する必要がある ※)すでに給与を支払っている場合は、申告書を提出した翌月からの適用になる |
まとめ
開業届に限らず、官公庁への提出書類の文言は、難しい表現や誤解を生じやすい表現もあり、戸惑うことも多いでしょう。この記事では、開業届の記入における注意点と文言の意味についてわかりやすく解説しました。開業届の記入の際に、お役立ていただければ幸いです。
]]>「AIエージェントとは何か?」と聞かれた時、なんとなくのイメージしかもたず具体的にはあまり正確に答えられない方も多いのではないでしょうか。この機会に、この記事を読んでAIエージェントについての基礎知識をたくわえておくことをオススメします。
AIエージェントとは?
AIエージェントとは、AIを使用してユーザの目標達成に向けて自律的に業務を遂行するソフトウェアシステムのことです。大きくわけると、個人が使用する「パーソナルエージェント」、企業が使用する「企業エージェント」という2つに大別されます。
- パーソナルエージェント:
ユーザ個人のニーズに合わせてサポートしてくれるAI
- 企業エージェント:
企業内の業務プロセスを最適化し生産性の向上やコスト削減、企業価値の向上をおこなう
これらのエージェントはいずれも、以下の4つの基本タイプに分類されます。
AIエージェントの種類
AIエージェントは、その意思決定の仕組みによって以下の4タイプに分類されます。これらの分類は、パーソナルエージェント・企業エージェントのいずれにも共通です。それぞれについて解説します。
1 反射エージェント
1つ目に解説するAIエージェントは「反射エージェント」です。
もっともシンプルな仕組みのAIエージェントで、単純反射エージェントとモデルベース反射エージェントの2種類に分かれています。
- 単純反射エージェント:
事前に定義された条件と行動のルールに従って動作します。たとえば、温度が一定値になったらエアコンをオンにするサーモスタット、人が近づくと自動的にドアを開くドア、壁にぶつかると方向を変えるシンプルな掃除ロボット など。
- モデルベース反射エージェント:
環境の内部モデルを保持し、現在の知覚と過去の経験に基づいて行動を決定します。単純反射エージェントとは異なり、環境が完全に観測可能でない場合でも、内部モデルを使って見えない部分の状態を推測します。たとえば、過去の運転経験に基づいて障害物を避けながら走行する初期の自動運転車、過去のユーザ行動履歴に基づいてオススメの動画を表示するレコメンデーションシステム など
2 目標ベースエージェント
2つ目に解説するAIエージェントは「目標ベースエージェント」です。
ただ目の前の状況に反応する反射エージェントとは異なり、どうすればゴールに近づけるかを判断し、その目標を達成するための一連の行動を推論し、選択するというものです。
- 活用事例:
ナビゲーションシステム(目的地を設定すると、現在の位置から目的地までの最適な経路を探索し、案内する)など
3 効用ベースエージェント
3つ目に解説するAIエージェントは「効用ベースエージェント」です。
目標ベースエージェントをさらに発展させたAIエージェントで、目標を達成することだけでなく、行動の結果として得られる効用を最大化するように行動を選択するところまで実行します。
- 活用事例:
医療診断支援システム(病気の診断に加えて、治療のリスクや効果・患者のQOLなどを考慮して最適な治療法を提案)など
4 学習エージェント
4つ目に解説するAIエージェントは「学習エージェント」です。
経験から学習し、自身の知識や行動の改善能力をもつAIエージェントです。与えられたタスクを繰り返す中で、徐々に最適な行動戦略を身につけていく特徴があります。
- 活用事例:
ゲームAI(囲碁・将棋・ビデオゲームなどで人間以上のパフォーマンスを発揮する)など
AIエージェントと生成AIの違い
生成AIとAIエージェントはよく混同されがちです。しかし、双方には明確な違いがありますのではっきりと区別できるようにしておきましょう。
| 生成AI | AIエージェント | |
|---|---|---|
| 特徴 | ユーザからの指示で受動的にコンテンツを生成できる | ユーザとのやりとりを通じて能動的に業務を自動化できる |
| 用途 | テキスト、画像、音声、動画などの「あたらしいコンテンツ」を生成する | データ分析、意思決定の支援など多岐にわたる用途で活用される |
| 運用方法 | 入力(プロンプトや参考画像など)を元に成果物を生成する(反応型) | 目的を達成するために、状況を認識しながら自律的に行動する(自律型) |
| 活用例 | ChatGPT(文章生成)、 DALL·E(画像生成)、 Midjourney・Stable Diffusion(画像)、MusicLM(音楽) など | カスタマーサポート、自動運転、チャットボット、音声アシスタント など |
生成AIは生成することに特化しており、基本的に指示がなければ動きません。一方、AIエージェントは目標達成に向かって自律的に動くため、必要に応じてタスクを分解・遂行する特徴があります。
AIエージェントが求められる理由
なぜ今、AIエージェントは社会に必要とされているのでしょうか。大きく3つの理由が挙げられますので、それぞれについて解説していきます。
業務の複雑化
AIエージェントは、複雑な業務内容・環境で価値を発揮します。
現在の社会は多様化しており、これに迅速・柔軟な対応をすることが求められています。AIエージェントは多くの情報源から得たデータを統合的に分析し、与えられた目標に対して最適な手段を自律的に選択し実行する能力を期待されているのです。
人材不足
AIエージェントは、人材不足を解消する役割が期待されています。
熟練人材の高齢化や採用難により業務の自動化・効率化が急務となっており、また属人化した業務知識を形式化し組織内の知的資産として活用可能にする点でも、AIエージェントは必要とされています。
働き方改革に対応するため
AIエージェントは、企業が働き方改革への対応をするために求められています。働き方改革が目標とする労働時間の短縮・生産性の向上・多様な働き方の実現・従業員の満足度向上、といった4項目について貢献をすることが期待されているのです。
AIエージェントに雑務・繰り返し・判断を任せれば、人間はより創造的な業務に集中できるようになります。また、リモートワークや時短勤務に対しても業務の継続性やカバーが24時間可能となり、頼れるデジタルパートナーとしてチームを支えることにもなるでしょう。
AIエージェントの課題
現在AIエージェントが抱えている5つの課題と対策について解説します。どのようなことが問題になっており、どういった対処方法があるのでしょうか。
1 セキュリティ・プライバシーの保護
AIエージェントは、業務や日常生活においてさまざまなデータを収集・分析・利用します。これらに含まれる機密情報や個人情報が適切に保護されなければ、深刻なリスクを引き起こす可能性があるのです。これの対策として以下の5つがあります。
- オンプレミスorクローズド環境で運用
- アクセス制御・認証の徹底
- 通信・APIの暗号化と監視
- データのマスキング・匿名化
- ログ管理・使用履歴の監査体制
2 倫理的・法的な問題
AIエージェントが間違った判断をした時に、誰が責任を負うのかが明確になっていません。また、どのようにその意思決定をおこなったのかがブラックボックス化しており、その理由を人間が理解できないなどの問題もあります。対策として、以下に挙げる2つの対策をしっかりおこなってください。
- 倫理原則・ガイドラインの策定:
AIエージェントの開発・利用に関する倫理的な原則やガイドラインを策定し、関係者間で共有する必要があります。
- 透明性と説明可能性の向上技術の開発:
AIの意思決定プロセスを可視化し、人間が理解できるようにする技術開発が重要です。
3 専門人材確保の難しさ
現在、AIエージェント向け専門知識をもった人材が不足しています。
AIエージェントの開発、実装、運用には高度な専門知識とスキルをもつ人材が不可欠です。しかし、その確保は非常に難しいのが現状です。以下に対策を挙げておきます。
- 社内育成・リスキリング:
社員に対して育成プログラムの構築
- 大学・研究機関と連携:
共同研究やインターン受け入れなど
- 副業・フリーランス人材の活用:
外部人材との協業
- 魅力的な職場環境の提供:
リモートワークやフレックスタイム制など
- 外部パートナーとの連携:
初期段階では外部のAIコンサル・SIer・AIベンダなどと連携し、 社内メンバーのシャドウイング(学びながら導入)を進める方法も有効。
4 リソースが限られていること
AIエージェントにおいて、限られたコンピュートリソースは、その開発・訓練・実運用において非常に重要な制約であり課題となっています。とくに高度な自律性や複雑なタスク処理能力をもつAIエージェントほど、より多くの計算資源を必要とする傾向があるのです。この課題への対策としては以下のものがあります。
- 軽量モデルの開発・活用
- オンデマンド処理に設計を切り替える
- 処理の分散化・非同期化
- ローカル/クラウドのハイブリッド運用
- インフラストラクチャへの投資
5 ハルシネーション
AIエージェントが、事実に基づかない、あるいは文脈と矛盾する情報を生成してしまうのは深刻な問題です。対策としては大きく以下の2つがあります。
- ファクトチェックとの統合:
外部知識ベースや検索エンジンと連携して、情報の正確性を検証する
- トレーニングデータの精査:
高品質なデータに基づく学習によって、誤情報の生成を減らす
まとめ
ここまで「AIエージェントとは?/種類・基礎知識・課題など」というテーマで解説してきました。
AIエージェントとは、AIを使用してユーザの目標達成に向けて自律的に業務を遂行するソフトウェアシステムのことです。あたらしく普及しつつあるAIエージェントについてはあまり知識のない方も多いのではないでしょうか。この記事を読んで、AIエージェントについて、生成AIとの違い、求められる理由、AIエージェントの課題についての知見を蓄えましょう。
最後のチェックポイント
- AIエージェントとはAIを使用してユーザの目標達成に向けて自律的に業務を遂行するソフトウェアシステム
- AIエージェントは能動的に業務をおこない、生成AIはユーザからの指示で受動的にコンテンツを生成する
- AIエージェントが求められる理由は業務の複雑化・人材不足の解決と働き方改革への対応のため、の3つ
- AIエージェントの課題はセキュリティ・プライバシーの保護、倫理的・法的な問題、専門人材確保の難しさ、リソースが限られていること、ハルシネーション
- 領収書は、発行側・受領側どちらも保管が必要
- 領収書は、経費処理時の証明書でもある
- 保管方法には、アナログとデジタルがある
- 一定要件を満たせば、領収書の電子保存が可能
- 経費精算を効率化するためには、ポイントを押さえて管理する
領収書の役割
領収書とは、金銭やその他の支払いが生じたことを証明する書類です。領収書を「領収証」と記載するケースもありますが、どちらも意味は同じです。
領収書の役割は、発行側と受領側で異なります。
発行側にとっては代金を受け取ったことの証明となり、受領側にとっては支払ったことの証明になりますので、二重請求や過払い防止の役割も果たします。従って、どちらの立場でも領収書の保管は必要です。
フリーランスが領収書を保管することの重要性
領収書は重要な書類ですので、きちんと管理をしておきましょう。
とくに、フリーランスの場合は、確定申告時に「経費として扱ったもの」を証明するのに役立ちます。
確定申告時に領収書の提出義務はありませんが、手元に領収書がないと経費として認められないこともあるため、注意が必要です。
また、納品書やレシートなども領収書と同様に扱われるため、捨てずに保管しておきましょう。
【アナログ】フリーランスが経費精算を効率化するための領収書保管方法・ツール
経費精算を効率化するには、領収書の保管方法や使用ツールも大切です。
アナログで管理する場合は、紙の領収書を定期的に整理しましょう。整理することで、現在必要な領収書が管理しやすくなります。
以下では、領収書のアナログ保管方法・ツールなどについてご紹介します。
ノートやスクラップブックなどに領収書を貼る
アナログで領収書を保管する方法の1つに、ノートやスクラップブックへ領収書を貼る方法があります。
こちらの方法は手軽ですが、デメリットもあるため、あわせて覚えておきましょう。
たとえば、感熱紙(とくにレシート)は熱や湿気に弱いため、夏場や梅雨時期の保管には気を付けましょう。また、感熱紙はのりの溶剤成分との相性も悪く、化学反応を起こして変色することがあります。
ほかには、印字面にセロハンテープを貼ると文字が消えることもあるため、注意が必要です。
封筒に領収書をまとめる
領収書のアナログ管理方法には、封筒にまとめる方法があります。とくに、領収書の数が少ない場合は、月や費目ごとに専用の封筒を用意して、その中に収納するのがオススメです。
反対に、事業規模が大きくなるにつれて、領収書の数は増えがちです。
その場合は「現金・振込等の支払い手段別」「勘定科目別」「取引先別」などに、分別してもよいでしょう。
クリアファイルやドキュメントファイルに領収書をまとめる
クリアファイルに領収書をまとめても便利です。
最近では、領収書や小物などを整理しやすいクリアファイルも販売されているため、そちらを活用してもいいでしょう。ファイルに収納する際は、インデックスを付けると、より管理がしやすくなります。
また、クリアファイル以外では、12仕切(13ポケット)のドキュメントファイルの活用もオススメです。
ドキュメントファイルとは、資料を入れるための見開きフォルダのことです。12仕切以上のドキュメントファイルを活用することで、1年間の領収書を月単位で収納できます。
デジタル】フリーランスが経費精算を効率化するための領収書保管方法・ツール
以下では、領収書のデジタル保管方法・ツールなどについてご紹介します。
クラウドサービスを活用して領収書を保管する
領収書の保管には、クラウドサービスの活用がオススメです。クラウド型ソフトのメリットは、業務効率化や作業のシームレス化につながることです。
最近では「領収書」「見積書」「納品書」「請求書」などに対応した、クラウド型のソフトが普及しています。
なかには、別のクラウド型請求サービスと連携可能だったり、領収書の作成から電子送付まで同じアプリ内で完結したりするものも存在しますので、大変便利です。
また、2022年に「電子帳簿保存制度」が見直されたことを契機に、一定要件を満たした「国税関係帳簿」や「国税関係書類」は、電子上で保存できるようになりました。領収書も国税関係書類の一種ですので、デジタル保存が可能です。
なお、電子帳簿保存制度は3つに区分されています。
以下では、領収書のデジタル管理方法やツールについてご紹介します。
紙の領収書をスキャナで読み取りデータで保管する
電子帳簿等保存制度では、紙で受け取った書類や紙で渡した書類の写しを、スマホやスキャナで読み取り、電子データとして保存できます。
この方法のメリットは、紙の領収書のファイリング作業や、物理的な保存スペースの確保が不要になることです。
スキャナ保存ができるものは、決算関係書類を除く国税関係書類です。国税関係書類は、「重要書類」と「一般書類」に大別されます。
重要書類と一般書類は、それぞれ以下の通りです。
- 重要書類:契約書・納品書・請求書・領収書など
- 一般書類:見積書・注文書・検収書など
重要書類と一般書類では、スキャナ保存を行う際のルールが一部異なります。
たとえば、領収書は重要書類に該当するため、帳簿との相互関連性の確保が必要です。
具体的には、スキャンした領収書のデータとそれに関連する帳簿との間で、相互に関連性を確認できるようにする必要があります。
また、紙の領収書をデータ化する際には、毎回帳簿や会計ソフトへ記帳・入力してから、保管するようにしましょう。
前回分の領収書を、どこまで入力したか確認する手間が省けたり、入力漏れを防げたりするのがメリットです。
電子上で作成した領収書をデータで保管する
電子帳簿等保存制度では、電子上(メールやチャットツールなど)で自身が作成した領収書を、パソコンやタブレット内に保管することが可能です。印刷する必要はありません。
ただし、保存時は指定の要件を満たす必要があります。
保存時の要件には、システム関係書類等を備え付けることや、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の条件から指定して検索できるようにするなどが挙げられます。システム関係書類等とは「システム概要書」「システム仕様書」「操作説明書」「事務処理マニュアル」などのことです。
なお、電子上で作成した領収書のデータ保管が任意であるのに対して、法人・個人事業者が電子上で送付・受領した領収書の保存(電子取引データ)は法律で義務付けられています。
これは、自社で作成した書類の控えとは異なり、外部と電子上で取引したデータは、改ざんリスクが高いためです。
以下の見出しでは、電子上で送付・受領した領収書の保管の重要性や保管方法について解説します。
電子上で取引した領収書にはデータの保管義務がある
2024年以降は、改ざん防止を目的として、電子上(メールやチャットツールなど)で送付・受領した領収書の保管が義務付けられました。
電子取引データをデータ保存する際は「可視性の確保」や「真実性の確保」を満たす必要があるためです。可視性とは「目に見える事実」を指し、真実性とは「真実と認められる事柄」を指します。従って、電子上で取引したデータは、誰が見ても正しい内容であることが重要です。
電子取引に関するルールには、一例として以下の項目が挙げられます。
- 改ざん防止措置をとること
- 保存データを確認するためにディスプレイやプリンタを設置すること
- 「日付」「金額」「取引先」の3つの要素で検索できるように設定すること(Excelやスプレッドシートなどの表計算ソフトで対応可能)
また、2025年度の税制改正では 、電子取引データの保存要件が見直されました。
今回の改正で、帳簿類の隠匿・破棄などの不正行為や期限後申告などがあった電子取引に対しては、10%の重加算税が加重されることとなりました。
一方、2027年からは、特定電磁的記録(保存要件にしたがって保存される電子取引データのこと)でかつ、財務省が掲げる要件を満たしている場合は、上記の罰則(重加算税の加重措置)が適用されない予定です。
従って、今後デジタル保管を選択する場合は、より電子帳簿保存法に準拠したシステムの導入が必要だといえます。
迷った場合はデジタル保管がオススメ
アナログ保管かデジタル保管か迷った場合は、デジタル保管をオススメします。
理由は、デジタル保管の方が、ファイルの管理やセキュリティ対策がしやすいためです。
たとえば、ファイル名に宛名や日付を設定すると、検索時に指定のファイルを見つけやすくなります。また、ファイルにパスワードを設定することで、情報流出の防止にも役立ちます。
フリーランスの領収書保管期間
領収書の保管期間は、申告者の立場ごとに異なります。
以下では、「青色申告者」「白色申告者」の保管期間の違いや、両者が「適格請求書発行事業者」の場合の保管期間や、適格請求書を保管する重要性について解説します。
青色申告者・白色申告者・適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)など立場ごとに異なる
領収書の保管期間は、青色申告者と白色申告者で異なります。
青色申告者の領収書保管期間は、通常7年です。
青色申告者とは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」が発生する業務を行う人で、かつ「青色申告承認申請書」を提出した方のことです。
ただし、以下の条件に該当する青色申告者は保管期間が5年間と定められています。
- 前々年分の事業所得および、不動産所得の金額が300万円以下の方
- 雑所得が発生する業務を行う方で、前々年分の業務の収入金額が300万円を超える方
一方、白色申告者とは、青色申告以外の方法で確定申告する方を指します。
白色申告者の領収書の保管期間は通常5年です。
また、青色申告者・白色申告者を問わず、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)も兼ねている場合は、領収書の保管期間が7年と定められています。
以下では、インボイス発行事業者が領収書を保管することの重要性について解説します。
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)が領収書を保管することの重要性
2023年10月より開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための仕組みです。
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)が、仕入税額控除の適用を受けるには、帳簿および適格請求書(インボイス)等を保存しておく必要があります。「請求書」「納品書」「領収書」などがインボイスに該当します。
インボイス発行事業者(売手)が買手に交付したインボイスの写しや、インボイスに関連する電磁的記録(デジタルデータ)の保管期間は7年です。また、交付されたインボイスを買手側が保存する期間も同様に7年です。
なお、上記インボイスの写しは、記載事項が確認できれば正式な書類のコピー以外でも構いません。
たとえば、納品書やレジのジャーナル(顧客に出力するときの名称はレシート)など簡易なものでもOKです。
まとめ
領収書は、金銭の授受を証明する重要な書類であり、発行側も受領側も保管が必要です。
確定申告時に慌てないためにも、フリーランスの方は、普段から領収書の保管方法を決めておきましょう。
管理方法には、アナログ保管やデジタル保管があります。
自分に合った方法で領収書を管理して、経費精算を効率化しましょう。
- 開業届は個人事業主が開業したことを税務署に知らせる書類のこと
- 事業開始後1か月以内に提出が必要、しかし未提出でも罰則はない
- 提出にはマイナンバーカード、本人確認書類、印鑑が必要
- 提出すると青色申告で特別控除が受けられ、屋号名義で銀行口座が作成できる
- 提出すると扶養から外れることや、失業保険が受けられないケースもある
個人事業主として活動をしていくにあたり、開業届を提出する必要があります。けれども、初めて開業手続きをするという方は、提出に必要なものや状況に応じて必要な書類などがたくさんあり、どうすればいいのか分からないという方もいることでしょう。今回は、その必要な書類や状況に応じて必要な書類、開業届を提出するメリット・デメリットについても解説していきます。
開業届とは
開業届とは、個人事業主が開業したことを税務署に届け出るための書類です。個人事業主として事業を行うと売上や経費が発生し、それに基づいて所得税の確定申告を行う必要があります。税務署は開業届をもとに納税管理を行い、個々に必要な申告書類の送付がされますので、それらに従い確定申告を行いましょう。
開業届は必ず提出が必要?
原則、事業開始後1か月以内に開業届を提出する必要があります。しかし、開業届を提出しなくても特に罰則や罰金などはありません。確定申告を正しく行っていれば問題ないと言えます。
開業届の提出時に必要なものは?
開業届を提出するにあたり必要なものがあります。提出時に忘れてしまうことがないように、あらかじめ用意しておきましょう。
- マイナンバーカード
- 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類(マイナンバーカードがない場合)
- 印鑑(訂正印で使用する為)
マイナンバーカードまたは本人確認書類
開業届を提出する際に必要なものは、開業届とマイナンバーカードです。マイナンバーカードが無ければ、個人番号通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証またはパスポートなどの本人確認書類が別途必要になります。
また、税務署に持ち込みで開業届を提出する場合、印鑑を持っておくと修正にもすぐに対応できるため安心です。
状況に応じて必要な書類
開業届の他にも、自身の状況に応じて別途必要な書類もあります。今一度自身の現状を確かめて必要であれば準備をしておくと、スムーズに開業手続きが行えることでしょう。
青色申告承認申請書
青色申告承認申請書とは、開業から2か月以内に提出することが望ましい書類です。
また、開業してから2か月を過ぎてしまった場合には、青色申告をする年の3月15日までに提出すれば問題ありません。
青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与に関する届出書とは、青色申告を行っている個人事業主が、家族・親族に支払った給与を必要経費にできる届出書のことです。家族・親族への給与の支払いを必要経費とすれば、所得が分散され節税効果が期待できます。
給与支払事務所等の開設届出
給与支払事務所等の開設届出書とは、個人事業主が従業員を雇用する際に税務署へ提出する届出書のことです。個人事業主は従業員の給与から所得税を天引きして、従業員に代わって納税をする「源泉徴収」を行う義務があります。従業員を雇った日から1か月以内に届出書を出しましょう。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
通常、従業員から天引きした源泉徴収税は、原則として翌月の10日までに納付しなければなりません。しかし、給与を支払う従業員が10人未満であれば、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、源泉徴収税を年2回にまとめて納付できます。
適格請求書発行事業者の登録申請書
適格請求書発行事業者の登録申請書とは、適格請求書(インボイス)を発行するために事業者が「適格請求書発行事業者」として税務署に登録するための書類です。事業者がインボイスに対応していないと、取引先は支払った消費税額の控除が受けられなくなります。
この登録申請書には期限はありませんが、登録日以降でなければインボイスの発行はできません。ただし、インボイス制度開始から2029年9月30日までは免税事業者との取引についても段階的に控除が認められる経過措置が設けられています。
事業開始等申告書
事業開始等申告書とは、各都道府県の税事務所に開業を申告する書類です。各都道府県によって提出期限や提出先がさまざまのため、事前の確認が必要です。しかし事業開始等申告書を提出しなくても、罰則には当たりません。開業届とは目的・提出先も違うため、混同しないように注意しましょう。
開業届を提出するメリット
開業届を提出すると主に以下のメリットが得られます。
- 青色申告で特別控除が受けられる
- 屋号名義で銀行口座を開設できる
青色申告で特別控除が受けられる
開業届と青色申告承認申請書を同時に提出した場合、最大65万円の特別控除が受けられます。個人事業主としてスタートしたばかりのころは、初期費用がかさんでしまうため赤字になってしまうこともあるでしょう。青色申告を行うメリットである特別控除や赤字繰り越しなどを活用して節税対策をするのがおすすめです。
屋号名義で銀行口座を開設できる
開業届を提出すると、自身の屋号名義で銀行の口座を開設できます。プライベートと事業のお金を区別でき、事業のお金の流れを把握することが可能です。また、開業届を提出することで、きちんと事業を行っているという証明書の代わりにもなり、顧客や取引先の方からの信用度もアップするでしょう。
開業届を提出するデメリット・注意点
一方で、開業届を提出するデメリット・注意点もあります。
- 扶養から外れてしまう場合もある
- 失業保険が受けられない
扶養から外れてしまう場合もある
現在、扶養に入っている方が開業届を提出するときは注意が必要です。開業届を提出することによって、たとえ収入が少なくても扶養から外されてしまうケースがあります。企業の健康保険組合の規定によりさまざまなので、一度健康保険組合のホームページを確認しておくと安心です。
失業保険が受けられない
一度、開業届を提出するとハローワークから「就職した」と判断され、失業保険の給付がストップする可能性があります。そのため、失業保険の受給を優先したい場合は、開業届を提出するタイミングに注意しましょう。
まとめ
今回は開業届を提出するにあたり、必要な書類や状況に応じて必要な書類などについて解説してきました。開業届は、マイナンバーカードと開業届さえあればすぐに提出できますが、自身の状況により他にも提出が必要になる書類もあります。また、開業届を提出すると青色申告などの税制上のメリットが受けられるほか、屋号名義付き銀行口座が開設でき顧客や取引先の信頼度もアップするでしょう。しかし、一度開業届を提出してしまうと、扶養から外れてしまうケースや、失業保険が給付されないというケースもあります。自身の状況を今一度よく確認し、メリット・デメリットをよく把握した上で開業届を提出しましょう。
]]>- フリーランスにとって営業は最も重要な業務のひとつ
- 効果的な営業経路には、知人や取引先からの紹介、SNSの活用、仲介業者からの紹介などがある
- 営業活動の前に、ポートフォリオや名刺、基本情報の整理を行う
- 営業効果をあげるスキルには、コミュニケーション力、プレゼンテーションスキル、傾聴力、自己分析力がある
- 営業を成功させるためには、人脈を大切にし、信頼と実績を積み重ね、諦めずに方法を変えて挑み続けることが重要
フリーランスを始めた、もしくはこれから始めようと考えている方にとって、案件の確保はおおきな不安材料かもしれません。この記事では、フリーランスの営業方法から効果的なアイテム、営業効果をあげるスキルなど、フリーランスが継続して収入を安定させるためのポイントを紹介します。
フリーランスにとって営業が重要な理由
フリーランスにとって最も重要な業務が営業だといっても過言ではありません。営業による案件獲得が収入に直結し、将来的に継続可能な事業体系を構築する基盤になるからです。
営業活動を通じて、クライアントとの信頼関係を築き、長期的な契約につなげることで、安定した収入と自由な働き方を実現できます。
フリーランスが効果的に営業を進めるには
以下のグラフは、他のフリーランスがどのような営業経路で案件を獲得しているかを表しています。多くのフリーランスが、知人を介して案件を獲得しており、人脈の重要性がわかります。また、SNSなどの発信や広告活動も有効です。自分にできる案件獲得方法の参考にしましょう。
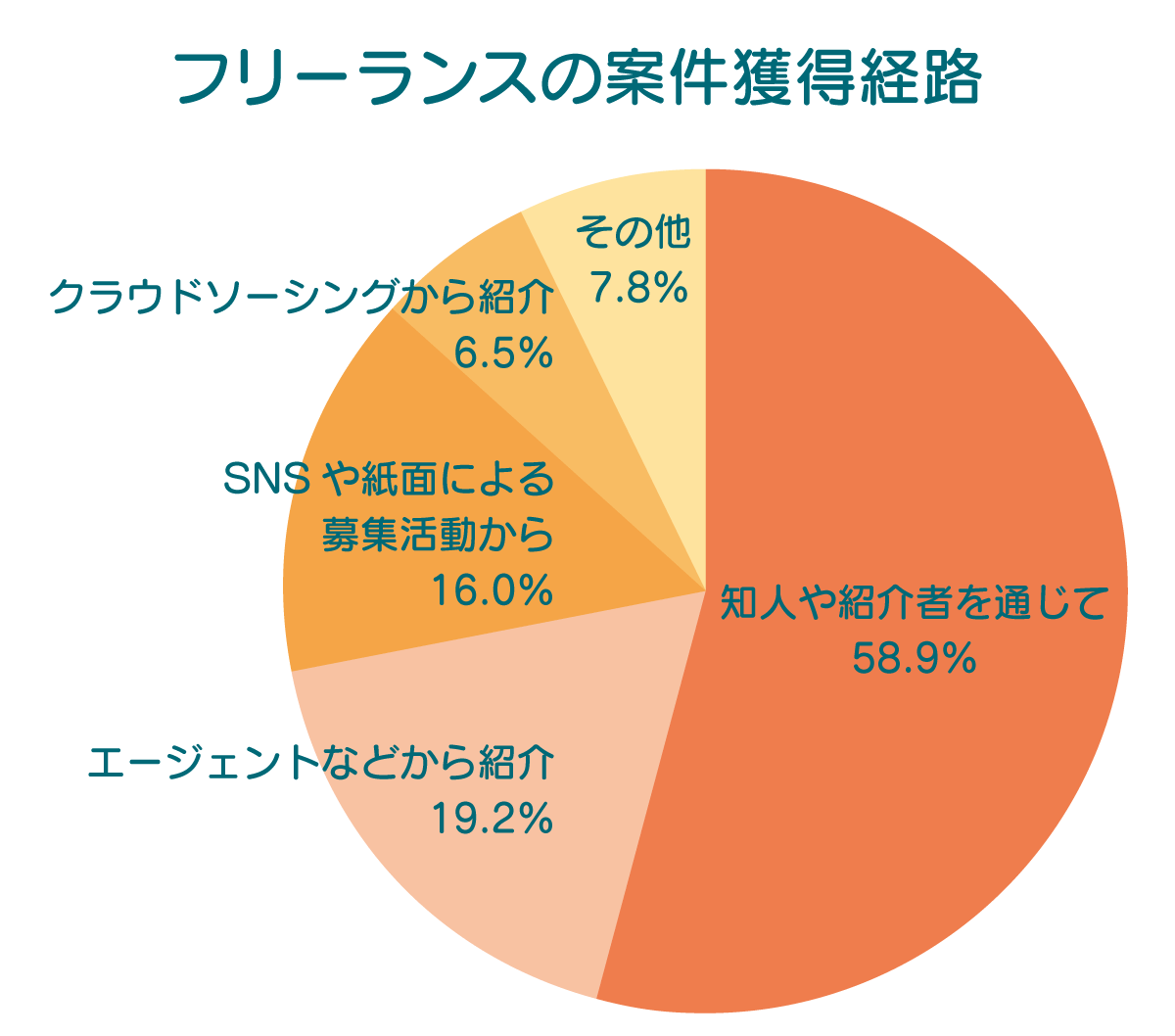
参考:内閣官房新しい資本主義実現会議事務局・公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁|令和4年度フリーランス実態調査結果
フリーランスの具体的な営業方法
ここからは、フリーランスがどのような営業方法を活用しているか、具体例を紹介します。
友人や知人に相談
案件獲得手段として最も多いのが、友人や知人からの紹介です。人柄を理解している人を介することで、信頼が担保され、スキルや技術をアピールするだけで案件が獲得しやすくなります。業界や業種にこだわらず、さまざまな人に相談してみましょう。思いもよらない縁が生まれる可能性があります。
取引先からの紹介
取引先からの紹介も、技術力の担保があるため、案件を獲得しやすい方法です。取引先との関係を良好にし、満足してもらえる仕事を提供することで、「この人なら任せても大丈夫」と思ってもらえます。紹介案件は信頼度が高く、案件獲得にもつながりやすいため、積極的に活用しましょう。
SNSの活用
不特定多数への情報発信も有効な営業方法といえます。FacebookやX(旧Twitter)、Instagramやブログなどを定期的に更新することで、興味をもった人からの依頼や問い合わせが期待できます。また、自社サイトの開設も、社会的信用度の向上につながるでしょう。
企業へ直接営業メールを送る
ターゲットとなる企業に直接営業する方法です。断られたりメールの返信がなかったりすることもありますが、挫けないことが大切です。相手のニーズを理解した提案内容を心がけましょう。
メール例文では、突然のメールへのおわびから始め、名のり、過去の実績例を紹介し、御社の○○分野で何ができるかを簡潔にアピールします。ホームページやSNSのアドレスも記載しましょう。
クラウドソーシングの利用
クラウドソーシングとは、業務を依頼したい人と受けたい人をつなぐオンラインのマッチングプラットフォームです。企業が業務内容を登録し、それを見た個人が自分のスキルや技術を活かせる業務に応募します。その後、業務委託契約を結ぶことで、案件を獲得できます。営業が不得手でも、案件獲得しやすいので活用しましょう。
フリーランスエージェント利用
フリーランスエージェントとは、営業や事務手続きを代行してくれるサービスです。営業の苦手なフリーランスにとって、企業の仲介と案件紹介、条件交渉や契約締結を手助けしてくれるため便利です。さらに、煩雑な事務手続きを代行してもらうことで、業務に集中できるメリットもあります。
セミナーやコミュニティ参加
フリーランスが営業する上で、人脈形成は非常に重要です。業界のセミナーや同業種のコミュニティに参加することで、情報収集ができるだけでなく、同じ分野の人々と交流することで人脈が広がり、新たなビジネスチャンスの可能性があります。
チラシ配布や広告活動
チラシは、企業だけでなく個人の目に留まり、興味をもってもらえる可能性があります。たとえば、「パソコン教室をやります」というチラシを、許可をとったカラオケボックスのフリースペースに置くことで、家族連れから高齢層までアピールでき、地域密着型の営業方法として有効です。どこに人の縁があるかはわからないため、広い視野をもつことが大切です。
営業活動に効果的なアイテム
実際に営業を行うまでに準備しておきたいアイテムを紹介します。知名度をあげたりトラブルを防止したりと、効率的に営業するために役立ちます。
- ポートフォリオ
- 名刺
- 時給や単価など基本情報
ポートフォリオ
ポートフォリオは、自分の実績を視覚的にまとめた資料のことです。成果や経験を集約し、実績やスキルをアピールする効果があります。営業時に見やすくまとめたポートフォリオを提示することで、技術力やスキル、経験値を理解してもらいやすく、相手に信頼感を与えることができます。作成して効率的な営業に活かしましょう。
名刺
ビジネスにおいて自分の顔となるのが名刺です。最初の接点となる重要なアイテムといえます。表面には住所、氏名、連絡先のほかに、SNSのアドレスを入れるのも効果的です。さらに裏面には、簡潔に自分のアピールポイントを表現しましょう。上手に裏面を活用することで、相手の記憶に残りやすくする効果があります。
時給や単価など基本情報
自分の業務に応じて、時給や成果物の単価を事前に設定しておきましょう。案件によって報酬形態が異なるため、柔軟に対応できるよう準備しておくことが重要です。これは案件獲得時の重要な指針になるため、正しい自己評価が求められます。また、単価や支払期日、契約期間などの契約条件を明確にするための資料を作成することで、透明性を保つことができ、円滑な契約が可能になります。
営業効果をあげるスキル
営業効果をあげるために身につけておきたいスキルを紹介します。どれもビジネススキルの基本ですが、フリーランスとして各スキルをどのように活かせるかも解説します。
- コミュニケーション力
- プレゼンテーションスキル
- 傾聴力
- 自己分析力
コミュニケーション力
営業にとって必須のスキルがコミュニケーション力です。フリーランスは、多くの人々と関わることで職種を継続できるため、的確で効率的なコミュニケーションは欠かせません。相手の立場に立って信頼関係を築くことが重要となります。
プレゼンテーションスキル
プレゼンテーションは自己アピールと相手のニーズを満たす提案を効果的に伝えるスキルです。何ができるかを考え、自分のスキルや技術で活用できる内容を伝えます。論理的な資料作成や説得力のある話し方を習得して、的確に伝えることがポイントになります。
傾聴力
フリーランスは、相手が何を求めているのかを正しく理解する必要があります。自己アピールに注視するあまり、どれほど高いスキルや技術をもっていても、相手のニーズと合わなければ案件は獲得できません。相手の話に耳を傾け、質疑応答を繰り返しながらニーズを把握して、自分にできることを考えましょう。
自己分析力
営業効果をあげるためには、正しい自己分析が重要です。営業を繰り返す中で上手くいったこと、いかなかったことを把握し、自分の強みや弱みを理解することで、営業方法の課題や営業戦略の問題点を把握できます。改善策を検討し実行することで、より効果的な営業活動が可能になります。
フリーランスが営業を成功させるポイント
フリーランスを継続するために営業は必須です。営業を行う際の注意点から対策までを紹介します。
- 人脈を大切にする
- 信頼と実績を積み重ねる
- 自分本位な営業は避ける
- 第一印象の重要性を知る
- 複数の営業方法を同時に行う
- 諦めずに方法を変えながら挑み続ける
人脈を大切にする
人脈はフリーランスにとって最大の資産です。人との出会いや縁を大切にし、真摯に向き合っていくことが肝要です。積極的に交流の場に参加し、新たな人脈づくりを意識しましょう。
信頼と実績を積み重ねる
時間や約束を守り、質の高い仕事を提供することで信頼と実績を重ねていくことが重要です。この案件は任せて大丈夫と安心してもらえることで、再契約や紹介案件へとつながります。その結果、営業に係る労力が少なくて済むようになるでしょう。
自分本位な営業は避ける
どれほど自分のスキルや技術、できることをアピールしても案件獲得につながらない場合もあります。自分本位の営業は避け、相手の求めることと自分のできることの一致点を見極めましょう。相手の視点に立って考える姿勢が重要です。
第一印象の重要性を知る
初対面の印象がその後の関係性に大きな影響を与えます。フリーランスだから何でも自由というわけではありません。礼儀正しく、清潔感のある身だしなみや立ち振る舞いはビジネスの基本と認識しましょう。
複数の営業方法を同時に行う
営業手段はさまざまあり、自分にとって不得意なものや業種によって異なる場合もあるでしょう。しかし、複数の方法を同時に行うことで、多方面へのアクションが可能になり、案件獲得の確率をあげることができます。自分にあった方法を見つけましょう。
諦めずに方法を変えながら挑み続ける
営業はすぐに効果が期待できない場合もあります。そこで諦めてしまっては、フリーランスとして継続できなくなってしまい、収入にも影響します。営業とは、失敗を恐れずに、さまざまな方法を試しながら、諦めずに挑み続けることで収入の安定につなげることです。
まとめ
フリーランスにとって、最も苦労する業務は営業かもしれません。苦手な方は営業代行を活用するのも選択肢の一つですが、自分に合った営業方法を試行錯誤しながら見つけていくことが、継続的な仕事の獲得と収入の安定につながります。本記事がその参考になれば幸いです。
]]>- 開業にかかる資金の平均値は985万円、中央値は580万円である
- 開業資金の調達方法は融資、補助金・助成金、出資、貯金など多岐に渡る
- 各手段にメリット・デメリットがあるので自分に適した調達方法を検討するのがよい
- 開業資金を把握し、何に使うか事業計画を具体的に話せるようになっておくのが資金調達を成功させるコツだ
開業資金の平均値は985万円
開業するにあたっては多額の資金が必要となります。たとえば店舗を構える場合は家賃や改装費用、商品を扱う場合は仕入れや設備投資、IT系業種であればパソコンや制作環境の整備費などが発生します。さらに、開業後しばらくの運転資金も必要です。
日本政策金融公庫総合研究所の「2024年新規開業実態調査」によると、開業費用の平均は985万円、中央値は580万円です。
以下は、開業費用の平均と中央値の推移をグラフにしたものです。
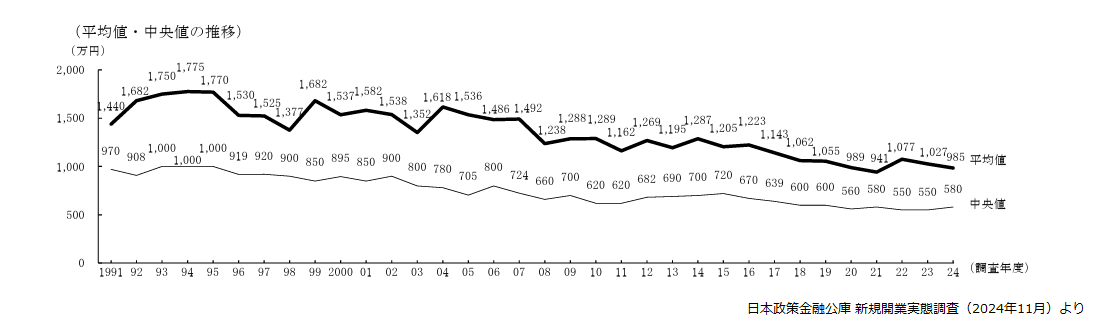
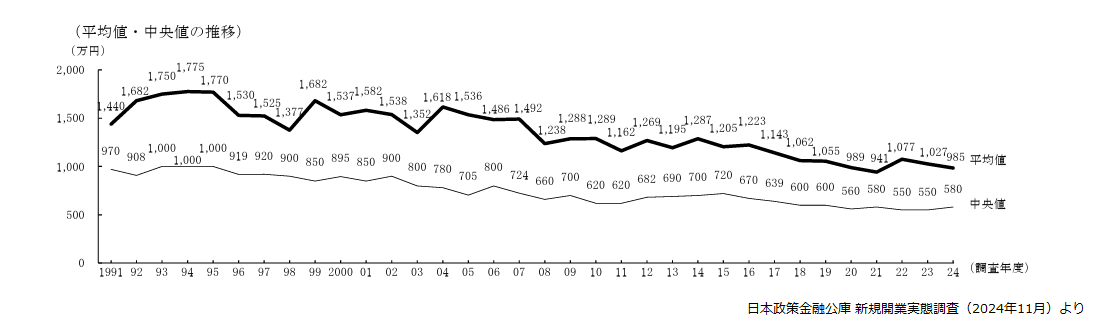
※クリックで画像を拡大できます
以前に比べて開業コストはやや低下傾向にあるといわれていますが、それでもある程度はまとまったお金が必要といえます。
開業にあてる資金調達の方法
開業したいと考えても、大きな金額をすぐに用意するのは難しい場合もあるでしょう。実は、開業のための資金を調達する方法は複数存在します。
このセクションでは、開業にあてる資金の調達方法をそれぞれ解説します。
開業時の資金調達(1)融資
融資とは、公的な機関や金融機関などからお金を借り受けることです。いわゆる借金・借入ですが、事業のための資金調達という性質上、単なる借入とは違い、開業のために低めの利子設定や審査基準を緩和してもらえるという点が融資の大きな特徴です。
国や自治体による融資制度、民間の金融機関など、開業のための融資をおこなっている団体は多くあります。代表的なものを紹介します。
日本政策金融公庫の融資
日本政策金融公庫とは、中小企業や小規模事業者向けに融資をおこなう国の政策金融機関です。他の融資機関と大きく違うのが、原則、無担保・無保証人で利用でき、金利も比較的低めです。
融資限度額は7,200万円で、若者・女性・シニアや開業に再チャレンジする人などに向けて、有利な条件で融資が利用できる制度もあります。詳しくは日本政策金融公庫の新規開業者に向けた資金融資のページで確認しましょう。
参考:日本政策金融公庫 – 新規開業・スタートアップ支援資金
地方自治体による融資制度
地方自治体でも、それぞれ独自で融資制度があります。自治体ごとに制度が違うので、まずは問い合わせをしましょう。
こちらは信用保証協会と連携し、低金利での融資が可能です。ただし、申請から融資までに時間がかかる点や、限度額が日本政策金融公庫より低い点は注意が必要です。
中小企業の開業や運営支援をする独立行政法人・中小企業基盤整備機構では、「J-Net21」というWebサイトで各自治体の開業における融資制度を紹介しています。こちらで制度を探すのもよいでしょう。
参考:J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト] – 創業者向け補助金・給付金(都道府県別)
民間の銀行や信用金庫による融資
民間金融機関でも開業融資を受けられますが、審査は厳しく金利も高めです。
通常、民間の機関が企業に融資するときは、これまでの売上や事業資本などが審査されるため、開業しようとする個人に対しては既存企業以上に審査が厳しくなると考えてよいでしょう。
しかし、融資が承認されれば、銀行の担当者から経営のアドバイスを受けられるなど、民間機関からの融資ならではのメリットもあります。
また、銀行・信用金庫には、使途自由のフリーローンという商品があり、これを開業資金にあてるという手もあります。この方法であれば、資金の用途目的に制限がないため非常に借りやすいです。半面、利子が割高になってしまうことが大きなデメリットです。
開業時の資金調達(2)補助金・助成金
融資とは別に、国や自治体が新規開業する人や団体に補助金・助成金を提供する制度も存在します。融資や借入と違い、返済義務がない点が大きなメリットです。
ただし、申請から助成金・補助金がもらえるまでに相当時間がかかる場合が多いため、今すぐにでも開業資金が欲しいときに頼りにするのはあまり向いていません。
ルートテックでは個人事業主が活用できる補助金制度の解説もおこなっています。
開業時の資金調達(3)出資
個人投資家やベンチャーキャピタルに出資してもらうのも開業資金を集める方法の一つです。とくに、起業して間もないスタートアップを支援する個人投資家はエンジェル投資家と呼ばれ、ビジネスの将来性や成長可能性に着目して出資します。
また、最近はクラウドファンディングを通じて商品のアイデアを紹介し、開発費用を募るという方法も出てきています。どちらの方法もお金をもらう資金調達方法なので、返済義務はありません。
ただし、投資家は将来のもうけのために出資するので、大きな魅力のある事業計画を提示しないと出資してもらうのはかなり難しいでしょう。
クラウドファンディングもいくつか注意点があります。たとえば「All-or-Nothing方式」の場合、目標金額に達しなければ一切資金を受け取ることができません。加えて、クラウドファンディングの手数料は一般的に20%~30%程度かかるため、手取り額にも注意が必要です。
開業時の資金調達(4)自己資金
自分で貯めたお金を開業資金にあてる方法もあります。開業には大きな金額がかかるため全額自分で賄うことは難しいですが、できるだけ自己資本金を用意することが重要です。
また、金融機関から融資を受ける際には、自己資金の額が融資の限界額決定に影響するため、この点でもできるだけお金を貯めてから開業するのがオススメといえるでしょう。
開業時の資金調達(5)親戚や知人に借りる
開業の資金調達のため、親や親戚、知人からお金を借りるという方法も存在します。しかし、近しい間柄でのお金の貸し借りなので、他の方法と比較してトラブルにつながる可能性が高いといえます。
親戚・知人から開業資金を借りるのであれば、借入したという事実をきちんと書面に残す、つまり契約書を交わすようにしましょう。近しい間柄だからこそあえて正規の方法をとることが、トラブルを未然に防ぐ重要なポイントです。
開業時の資金調達(6)ビジネスコンテストの参加
公的機関や民間団体などが定期的にビジネスコンテストをおこなっている場合があり、これも資金調達の方法のひとつです。新規事業の内容でコンペに参加し、優秀者には出資されるというものです。ただし、必ず入賞できるわけではないので、資金を得られないこともあります。反面、コンテスト出場の過程で他の起業を目指す人々と交流が持てるところは資金調達以外の点で魅力的なポイントでもあります。
開業のための資金調達を成功させるポイント
このセクションでは、開業のための資金調達を成功に導くコツを解説します。
開業届を出す
融資を受けるためには、開業届を出しておくことが必要です。開業する場所の管轄の税務署に開業後1か月までを目安に開業届を提出しておきましょう。
開業資金がいくら必要か理解する
開業資金と一言でいっても、事業形態で必要な資金の額は大きく変わります。たとえば、店舗経営なら、店舗の敷金や家賃、各種備品、商品の仕入れ、人員費など多額が必要になります。一方で、自分1人でスモールスタートが可能な事業であれば、必要なものは仕事道具と仕事の場所程度になり、開業資金の金額は店舗開店と比較するとかなり少なくすむことが多いです。
まずは事業に必要な費用を明確にし、どれだけの自己資本があるのか、外部からどの程度資金調達が必要なのかを洗い出すことが重要です。そのうえで、最適な資金調達の方法を検討するのが、開業の第一歩といえるでしょう。
自己資金を用意する
前述したように、自己資金は可能な限り用意できるほうがよいでしょう。無利子なうえ、返済の必要もないからです。まず何より、今後の事業を続けていくに向けてある程度の元手がないと、もし収入がない時期が続けば、すぐに食べていけなくなってしまいます。
それに加え、銀行・信用金庫の融資額は自己資金の額によって決定されることも、自己資金を可能な限り用意するべき理由のひとつです。企業が財務状況によって銀行からの借入額が左右されるのと同じように、個人が開業しても財務状況や返済能力といった信用を元に、借入の是非が決定されます。
全額自分で賄うのは無理でも、開業のための自己資金は可能な限り用意するのがよいでしょう。
事業計画、開業資金の使い道の計画をよく練っておく
これまでの事業の実態がない以上、融資を受けるためには「これから何をするのか」「何のために融資が必要なのか」「どうしてこの金額が必要なのか」をしっかり説明できるようになっておく必要があります。そのためには事業計画書をしっかりと作りこみ、融資担当者に開業資金をどのように使うかを具体的に説明できるようになっておかなくてはなりません。
返済の能力を証明する
これまで個人でクレジットカードを使ったり、ローンでお金を借りたりした人も多いでしょう。これらお金に関する貸し借りや返済の延滞といった個人の借入履歴は、信用情報として信用機関に登録されています。このため、開業前には信用情報を確認し、延滞などがある場合は改善に努めるのが望ましいでしょう。過去の返済履歴が良好であれば、金融機関に対して返済能力のある人物としての信頼性を示す材料になります。
まとめ
開業にかかる資金の平均値は985万円、中央値は580万円とされています。必要な金額は業種や事業規模によって変わってきますが、ある程度のまとまったお金が必要なのは確かです。
開業資金は自己資金で賄えることに越したことはありません。ですが、大きな金額のため、全額用意するのは難しいことが多いでしょう。
自己資金で賄う以外の資金調達方法は、融資、補助金・助成金、投資家などに出資してもらう、知人や親戚に借りる、クラウドファンディングに挑戦する、ビジネスコンテストに参加するなど、さまざまあります。それぞれメリット・デメリットがあるので、自分に適した方法を検討するとよいでしょう。ただし、親戚や知人に開業資金を借りる場合はトラブルになりやすいため、きちんと貸し借りを書面に残すよう注意しましょう。
どれだけ開業資金が必要かをきちんと把握し、何に使うか事業計画を具体的に話せるようになっておくのが資金調達をうまくするコツです。
]]>- 開業届は事業を開始してから1か月以内に税務署に届け出る
- 職業欄と事業の概要欄は具体的な内容でわかりやすいように記入する
- 職業欄は個人事業税の税率にかかわる
- 複数の事業がある場合は一番収入が高いものを職業欄に記入しよう
- 事業の変更があっても開業届の再提出は不要だが、確定申告書の職業欄に正しく記入する必要がある
開業届には職業欄・事業の概要欄の記入が必要
新しく事業をはじめたときは、開業届を提出する必要があります。届け出先は、納税地を管轄する税務署です。原則として、開業から1か月以内に、事業所が存在する場所の税務署へ開業届を提出します。
開業届では、職業欄および事業の概要欄について、どのように記入すればいいのかよくわからないという方が見受けられます。とくに記入方法の決まりはないものの、後述する個人事業税の税率に関わってくるため、何の事業をしているのかしっかり記入するのがポイントです。
この記事では、これらの記入方法や注意点などを解説します。
なお、開業届の用紙は税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードが可能です。
参考:国税庁 – A1-5 個人事業の開業届け出・廃業届け出等手続
職業欄には具体的な職業を記載する
開業届の職業欄は「フリーランス」「個人事業主」というような書き方ではなく、具体的にどのような職業を営んでいるかわかるように記入しましょう。たとえば「システムエンジニア」「個人小売店店主」などです。
なお、職業欄の書き方に迷った場合は、総務省が公開している「日本標準産業分類」という分類表を参考にするのもよい方法です。
事業の概要欄は明確に書こう
開業届における事業の概要欄は、職業欄の業務内容を詳しく記入する場所です。職業欄よりも詳しく、実際の仕事内容や事業内容を記入しましょう。
たとえばWebライターであれば「Webメディア記事の構成作成および記事執筆」、海外ブランド服のセレクトショップを営んでいるなら「インポート輸入服販売」のように記入します。
開業届における職業欄の書き方
ここまで、開業届の職業欄、事業の概要欄の基本的な書き方を解説しました。しかし、書き方にルールはないといっても、「自分の職業の場合はどのように書けばよいか」と戸惑う人も多いでしょう。
このセクションでは、いくつかの職業を例に挙げて、書き方の例を紹介します。書き方に困ったときは参考にしてください。
開業届:職業欄・事業の概要欄の例文
開業届の職業欄・事業の概要欄について、職業ごとに書き方の例を挙げます。
- システムエンジニア
職業:システムエンジニア
事業の概要:ソフトウェアの設計・開発・プログラミング、およびシステムの保守 - 商店街の個人商店店主
職業:文房具店運営
事業の概要:学生向けの筆記用具を中心とした文房具の販売、社会人向けの万年筆の販売 - Webデザイナー
職業:Webデザイナー
事業の概要:Webサイトのデザイン制作、LPのデザイン制作、コーディング - ラーメン店経営
職業:飲食店
事業の内容:ラーメン店の経営、ラーメンやサイドメニューの提供、メニューの開発 - YouTuber
職業:インターネット関連サービス業
事業の概要:YouTubeの企画・動画作成および編集、動画公開と管理、YouTubeコミュニティ管理
開業届作成、提出における注意点
このセクションでは、開業届の作成や提出に関する注意点を解説します。
複数の事業がある場合、収入がもっとも多いものを記入する
新しく事業をはじめるとき、最初から複数の事業を並行して開始する方も中にはいます。この場合、開業届の職業欄はどのように記載すればよいか迷うこともあるでしょう。
このような場合は、最も収入の多いものを代表として職業欄に記入すれば問題ありません。並行している事業は事業の概要欄に詳細を記載してください。
複数の事業がある場合は確定申告の記入に注意
個人事業税に直接関係してくるのは、確定申告書の職業欄です。したがって、事業内容に変更があっても開業届の再提出は不要です。
しかし、これはつまり、確定申告ではしっかりと事実を記入する必要があるということです。とくに複数事業をおこなっている場合は、事実関係が複雑になりがちであるため、しっかりと確定申告書の職業欄で、実際にどのような事業をおこなったのかきちんと記入することが肝要です。
事業内容を変更しても再提出は不要
事業を新しくはじめたものの軌道に乗らず、別の事業をはじめてみると本業より売上伸びたパターンは珍しくありません。このように、開業届の提出時に記入した職業と現在の主な職業は異なる場合でも、開業届を再提出する必要はありません。
ただしその代わりに、確定申告で「職業の詳細」を記入するときは、現在の職業と所得などを正確に記入する必要があることに十分注意しましょう。
開業届の職業欄は個人事業税にかかわる
個人事業税とは、個人が営む事業に対してかかる地方税の一種で、地方税法によって定められています。個人事業税は、開業届に記入された職業欄の業種によってかかる税率が違うことに注意が必要です。このため、職業欄はきちんと記入するようにしましょう。
このセクションで詳細を解説します。
職業により個人事業税の税率が違う
個人事業税とは、個人が営む事業のうち、地方税法などで定められた業種(法定業種)に対してかかる税金のことです。法定業種は70種類あり、ほとんどの事業が該当します。
個人事業税は5%であることが多いですが、事業の種類によっては3%または4%のものも存在します。
業種と税率は以下の通りです。
| 区分 | 税率 | 事業の種類 |
|---|---|---|
| 第1種事業 (37業種) | 5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業 |
| 第2種事業 (3業種) | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3種事業 (30業種) | 5% | 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業 |
| 3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
個人事業税がかからない職業もある
前項で紹介した法定業種に当てはまらない職業の場合、個人事業税は非課税となります。
たとえば、以下のような業種です。
- 漫画家、作曲家、作詞家、小説家などクリエイティブ関連の職業
- システムエンジニア、プログラマーなどIT関連職
- 林業や鉱物採掘業務
- プロスポーツ選手
- 翻訳や通訳
ただし、これらの職業であっても、業務の実態が「請負業」などの法定業種と判断されたら、個人事業税がかかるケースがあります。
たとえば、プログラマーや翻訳家などが、単なる作業の代行ではなく、成果物を納品する契約内容で報酬を受け取っている場合、「請負業」とみなされて課税対象になることがあります。ほかにも、イラストレーターなども同様のことが起こっているため、事業内容はきちんと記入することが肝心です。
また、事業所得290万円以下の方は個人事業税の対象外となり、非課税です。
開業届を出した当初と事業内容が変わっている方は、確定申告書の職業・事業内容の欄が税率の根拠となるため、きちんと記入して提出しましょう。
まとめ
開業届は、新しく事業を開始してから1か月以内に管轄の税務署に届け出をしなければなりません。
開業届の職業欄と事業の概要欄の書き方にルールはとくにありませんが、具体的な内容でわかりやすいように記入する必要があります。職業欄は個人事業税の税率にかかわるので、きちんと記入しましょう。
また、複数の事業をおこなう場合は一番収入が高いものを職業欄に記入すれば問題ありません。
事業内容が変わった場合でも、開業届の再提出は不要です。ただし、個人事業税にかかわるため、確定申告書の職業欄は正確に記入する必要があります。
はじめての開業で戸惑うこともあるかもしれませんが、適切に届け出や申告をおこない、事業を成功に導きましょう。
]]>- プラットフォーム・エンジニアリングとはアプリケーション開発者が使用する共通基盤を設計・構築・運用する手法
- 明確で一貫性のあるAPI、セルフサービス・エクスペリエンス、モジュール型、組み込みの優れたプラクティス、整合のとれたガイドラインという5つの原理原則がある
- 開発者の満足度を最優先することで負担軽減効果が得られビジネスの成功につながる
- 実行には、オンプレミスとクラウドの組み合わせ・クラウド連携・DevOpsベースの自動化関連・IaCとそのバージョン管理・インフラセキュリティが必要
最近では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の向上を目的として企業がプラットフォーム・エンジニアリングを積極的に採用しつつあります。みなさんもこの機会に知見を深化させてみてはいかがでしょうか。
プラットフォーム・エンジニアリングとは
プラットフォーム・エンジニアリングとは、開発者がアプリケーションを効率的に開発・運用できるようにするための共通基盤(プラットフォーム)を設計・構築・運用するエンジニアリング手法のことです。そもそもITにおけるプラットフォームとは、アプリケーションやサービスを動作させる基盤のことで、4種類があります。
- オンラインプラットフォーム
インターネット上で情報やサービスの共有をするプラットフォーム
- ソフトウェアプラットフォーム
ソフトウェアやアプリケーションの開発・提供を支援するプラットフォーム
- コンテンツ配信型プラットフォーム
ユーザに文章や動画、音楽などのコンテンツを提供するプラットフォーム
- クロスプラットフォーム
異なる環境やデバイス間でコンテンツやアプリケーションが共有・利用できるようにするプラットフォーム
プラットフォーム・エンジニアリング 5つの原理原則
プラットフォーム・エンジニアリングをおこなうために不可欠な原理原則が5つ提言されています。それぞれについて解説していきましょう。
1 明確で一貫性のあるAPI
「明確で一貫性のあるAPI(Application Programming Interface)」とは、設計が洗練され、一貫性のあるAPIのことです。
具体的には、利用者が容易に理解でき、期待通りに利用できるAPIです。これを利用する開発者は機能を効率的に活用し、より迅速にアプリケーションを開発することが可能になります。
現代のIT開発において明確で一貫性のあるAPIは、効率的で信頼性の高いシステム構築の基盤となっています。
2 セルフサービス・エクスペリエンス
ここでいう「セルフサービス・エクスペリエンス」とは、ユーザが自身のニーズや問題を自力で解決できる体験のことを指します。開発者は必要なリソース・ツールを迅速かつ効率的に利用できるということです。
プラットフォーム・エンジニアリング実現のためには、ユーザがより主体的かつ効率的に、サービスを利用可能なように設計された仕組みや環境が必要になります。
3 モジュール型
プラットフォーム・エンジニアリングにおける「モジュール型」とは、システム全体を一枚岩ではなく独立・再利用可能な機能単位(モジュール)に分割する設計アプローチのことを指し、以下に記載する特徴があります。
- 開発者の生産性向上
必要なリソースをすぐに利用可能
- システムの拡張が容易
新機能を追加する際に、影響範囲を最小限に抑えられる
- 保守がしやすい
モジュールごとに更新・修正が可能
4 組み込みの優れたプラクティス
プラットフォーム・エンジニアリングにおける「組み込みの優れたプラクティス(Built-in Best Practices)」とは、開発者が特別な知識や設定をしなくても、デフォルトで推奨される一番よいやり方が適用される仕組みのことを指します。セキュリティ・パフォーマンス・信頼性・コンプライアンスなどにおいて、専門的な知識や細かな設定を必要とせずに最初から最適な状態を保てるようにするといった具合です。
より安全・高品質・効率的なアプリケーション開発をおこなえるようにする基盤となる重要な要素です。
5 整合のとれたガイドライン
プラットフォーム・エンジニアリングにおける「整合のとれたガイドライン(Consistent Guidelines)」とは、開発者が、統一されたルールのもとでインフラ・アプリケーションを設計・運用できるようにする指針を指します。
これらのガイドラインは、プラットフォームの設計・利用方法・セキュリティ・運用・開発プロセス全体にわたって適用され、プラットフォームの効率性・信頼性・セキュリティ・開発者体験を向上させます。
開発者の満足度を最優先する理由
プラットフォーム・エンジニアリングにおいては、開発者の満足度を最優先することが最終的なビジネス全体の成功につながります。開発者がストレスなく効率的に作業できる環境を整えることで、開発スピード・品質・運用負担の軽減につながるためです。
- 開発者体験の向上がビジネス成果に直結する
- フラストレーションを減らしエンジニアの生産性を最大化する
- 優秀なエンジニアの定着率を向上させる
プラットフォーム・エンジニアリングに必要なスキル・知識
プラットフォーム・エンジニアリングの実行に必要なスキル・知識を5つ解説します。エンジニアにはどのようなものが求められるのでしょうか。
1 ハイブリッド・テクノロジーへの適応スキル・知識
プラットフォーム・エンジニアリングを担うエンジニアに求められるのは「ハイブリッド・テクノロジーへの適応知識・スキル」です。ハイブリッド・テクノロジーとは、複数の異なる技術やシステムを組み合わせてあたらしい機能や性能を実現する技術のことです。常に最新のハイブリッド技術動向を把握することで、組織のデジタルトランスフォーメーションを成功に導くための重要な役割を果たします。
オンプレミスとクラウドの両方を理解し、それらを効果的に融合させる能力は不可欠な能力といえるでしょう。
2 クラウド連携のためのアーキテクチャ設定や構成スキル・知識
プラットフォーム・エンジニアリングを担うエンジニアは「クラウド連携のためのアーキテクチャ設定や構成スキル・知識」を求められます。
具体的には、オンプレミス環境とクラウド環境を効果的に統合し、組織のニーズに合わせたITインフラストラクチャを構築・運用するための専門的な能力のことです。多くの企業が採用しているハイブリッドクラウド戦略(オンプレミスとクラウドを組み合わせてITインフラを最適化する戦略)を成功させ、クラウドの利点を最大限に活用するためには不可欠な要素です。
3 DevOpsベースの自動化関連のスキル・知識
プラットフォーム・エンジニアリングでは、手動での管理を減らし、一貫性・再現性・スケーラビリティを確保するために、DevOps(システム開発手法の1つで、開発(Development)と運用(Operations)が協力して開発を進めること)の考え方を取り入れた自動化が不可欠です。また、DevOpsベースの自動化は単なるツールの導入などにとどまらず、組織文化・プロセスを変革してより効率的で革新的なソフトウェア開発・運用体制を構築するためにも重要な要素です。
4 IaCとそのバージョン管理のスキル・知識
プラットフォーム・エンジニアリングにおいてIaC(Infrastructure as Code)とそのバージョン管理は、インフラの構成と運用の効率化を実現します。IaCには以下の主な特徴があります。
- 自動化
インフラのセットアップをコードで記述し、自動構築
- 一貫性化
環境ごとの差異(設定ミス・手作業ミス)を排除
- 再現性化
同じコードを適用すれば、どこでも同じ環境を作成可能
- スケーラビリティ
クラウド・オンプレミスを問わず大規模環境も管理
- 監査・コンプライアンス対応
誰が・いつ・何を変更したかを追跡可能
また「なぜIaCのバージョン管理をおこなう必要があるのか」については以下の理由があります。
- 変更の追跡
誰が・いつ・どのような変更を加えたかを管理できる
- ロールバック可能
問題が発生した場合、以前の状態に戻せる
- チームでの共同作業が容易
Gitを活用してブランチ管理ができる
- インフラの再現性向上
同じコードを適用すれば同じ環境を作れる
5 インフラセキュリティのスキル・知識
プラットフォーム・エンジニアリングにおいて、インフラセキュリティは非常に重要です。システムの可用性やデータの機密・完全を確保するためには、適切なセキュリティ対策が求められます。
また、スキル・知識を習得後も常に最新のセキュリティ動向を把握することで、安全で信頼性の高いプラットフォームを構築・運用し、組織全体のセキュリティレベル向上に貢献します。
運用に必要なスキル・知識
プラットフォーム・エンジニアリングにおいて、プラットフォームを円滑に運用し安定したサービスを提供するために必要なスキルと知識も重要です。以下に記載する分野についてのスキル・知識がとくに求められるのでしっかりと身につけておきましょう。
- CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery)への精通
- より早期での問題解決に向けたトラブルシューティング
- プロアクティブ(積極的または主体的な行動)な対応のためのモニタリング/可観測性
- 根本原因解析に向けたインシデント管理
- サービスリクエストの実現
まとめ
ここまで「プラットフォーム・エンジニアリングとは/基礎知識など」というテーマで解説してきました。
近年、企業のIT開発はインフラ管理やデプロイ(アプリケーションの機能やサービスをサーバ上に配置・展開し、利用可能な状態にする一連の作業のこと)の複雑さが増しており、こうした背景の中で注目されているのがプラットフォーム・エンジニアリングです。
開発者がアプリケーションなどを効率的に開発・運用できるようにするため共通基盤(プラットフォーム)を設計・構築・運用するエンジニアリング手法で、これにより開発チームの生産性を高め、運用負荷を軽減することが可能になります。
この記事を読んで、現在の開発環境の改善に役立つプラットフォーム・エンジニアリングについての理解を深めていきましょう。
- フリーランスエンジニアとは、企業に属すことなく自身で営業・交渉・業務を行うITエンジニアのこと
- フリーランスエンジニアは、収入面が不安定でセルフブラックになりやすい
- IT、プログラミングスキル・自己管理能力・コミュニケーション能力・営業力は必須で、英語力もあるとなおよい
- クラウドソーシングやフリーランスエージェントの活用で案件獲得が可能
- 普段から周囲にフリーランスとして活動しているという旨をアピールしておくとよい
働き方改革の一環で、フリーランス人口も増加しつつあります。フリーランスの中でも、今回はフリーランスエンジニアについて解説します。フリーランスエンジニアとはどのような職種・仕事内容なのでしょうか。また、案件の獲得方法や必須なスキルなども詳しく解説します。
フリーランスエンジニアとは
フリーランスエンジニアとは、企業に属さず、自ら案件を受注して業務を行うITエンジニアのことです。
フリーランスエンジニアの主な職種と仕事内容
フリーランスエンジニアの主な職種は以下の5つです。それぞれの仕事内容を解説しますので、参考にしてみて下さい。
- システムエンジニア
- インフラエンジニア
- フロントエンドエンジニア
- データサイエンティスト
- アプリケーションエンジニア
システムエンジニア
顧客の要望をもとにシステムの要件定義・設計、動作確認をすることが主な仕事です。ヒアリングした内容から汲み取り、開発を進めていきます。
インフラエンジニア
インターネットやシステムのベースを支えるために、設計から運用保守までを行うことが仕事です。作業する領域は幅広く、設計から運用保守だけでなくサーバやネットワーク、クラウド、セキュリティに関するものなどさまざまな知識が必須です。
フロントエンドエンジニア
Webでユーザが画面越しに触れる部分の設計や構築を行うことが主な仕事です。コーディングやSEOに関する知識も求められます。
データサイエンティスト
企業が持つ業務データ、Webなどから膨大なデータ分析をして企業の課題を解決する仕事です。統計学からデータ解析まで幅広い知識が求められます。
アプリケーションエンジニア
Webアプリやスマートフォンアプリの開発に携わる仕事です。業務向けや一般アプリ・Web系・組み込み系など種類は多岐にわたります。
会社員エンジニアとの違い
フリーランスエンジニアは自ら顧客に営業をして案件を獲得し、スケジュールを調節して自分のペースで働くことができます。しかし、仕事内容以外のこともすべて自分で行わなければならないため、事業に関する豊富な知識が必要です。
会社員エンジニアは、企業の就業規則に定められた勤務時間や仕事内容、勤務場所・勤務ルールに従って働く必要があります。仕事内容では、自身の業務以外にもさまざまな雑務を行うこともあるでしょう。しかし、フリーランスエンジニアと違って、事業に必要な全業務を担う必要がないことが大きな違いです。
フリーランスエンジニアがきついと言われる理由
フリーランスエンジニアはどのような面できついと言われているのでしょうか。フリーランスエンジニアとして独立を考えている方は、以下のデメリットもあらかじめ頭にいれておくとよいでしょう。
- 収入面が不安定になる
- セルフブラックになる
収入面が不安定になる
フリーランスエンジニアは、案件により報酬額の変動が激しいため、収入が不安定になる恐れがあります。また、会社員エンジニアと違い固定給制ではなく、働いた分収入につながるので、常に新規の案件を獲得しなければなりません。
セルフブラックになる
フリーランスエンジニアは労働時間を自分で決められるため、つい長時間作業をしていたということも珍しくありません。セルフブラックにならないためには、自分が受け持てる範囲内で仕事を受注し、納期まで余裕を持ったスケジュール調整が大切です。
フリーランスエンジニアになるメリット・デメリット
フリーランスエンジニアのメリット・デメリットを解説します。会社員から独立を考えている方は、あらかじめ押さえておきましょう。
フリーランスエンジニアのメリット
フリーランスエンジニアになるメリットは、働き方の自由度が高いことです。自分でスケジュールを管理でき、働く時間や場所を選べるため、自身のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また、働いた分が直接収入につながるため努力次第で高収入も目指せるでしょう。
フリーランスエンジニアのデメリット
フリーランスエンジニアになるデメリットに、長期間休むと収入がゼロになるという収入面での不安定さが挙げられます。会社員のように、失業保険や産休・育休という制度がないからです。また、つい長時間作業してセルフブラック化することや、仕事上トラブルが発生しても一人で対応する必要があり、プレッシャーと孤独を感じてしまうこともあるでしょう。
フリーランスエンジニアに必須なスキル
フリーランスエンジニアとして働いていくためには、必ず身に付けておきたいスキルがあります。自身の現在のスキルレベルを確かめながら見ていきましょう。
- IT・プログラミングスキル
- 自己管理能力
- コミュニケーション能力
- 営業力
- 英語力(あればなお良い)
IT・プログラミングスキル
フリーランスエンジニアとして働いていくためには、IT・プログラミングは必須スキルです。案件ごとに使用する言語も異なるため、複数の言語を扱えるようになると、その分より多くの案件にも対応できるようになり、業務の幅もさらに広がります。
自己管理能力
自己管理能力は、フリーランスエンジニアには必須のスキルです。案件のスケジュール管理や自身の体調管理、納期までのスケジュール調整など多岐にわたります。自己管理不足で、納期を守れないと顧客からの信頼がなくなり、フリーランスエンジニアとして活動することが難しくなる恐れもあります。
コミュニケーション能力
フリーランスエンジニアは、自分で案件を獲得しなければなりません。業務では、顧客とコミュニケーションを取りながら進めていく必要があります。コミュニケーションがうまく取れていないと、食い違いが発生したり相手に不安を与えたり信頼を失ってしまう恐れがあります。
営業力
フリーランスエンジニアは顧客の要望を聞いて、それに対して顧客が納得できるような提案をするという営業力が求められます。営業力を磨くためには、さまざまな人と会い、実績を積むこと積むことが非常に重要です。営業を経験していくなかで案件を獲得できれば、自信にもつながっていきます。
英語力
フリーランスエンジニアとして、国内だけでなく海外で活躍するためには、英語力が不可欠です。英語が堪能であると、海外企業と直接取引できるチャンスも生まれます。また、海外の最新技術情報にも触れる機会ができ、自身のスキルアップにもつながります。一朝一夕で身につく力ではないため、日頃から英語力を磨いておくと更なる高みを目指せることでしょう。
フリーランスエンジニアで案件を獲得する方法
フリーランスエンジニアとして活動を続けていくには、絶えず案件を獲得していくことが非常に大切です。案件を獲得するには、主に以下の3つの方法があります。
- クラウドソーシングサービスを利用
- フリーランスエージェントを利用
- 知人から紹介してもらう
クラウドソーシングサービスを利用
クラウドソーシングサービスとは、インターネットを通じて数ある案件の中から受けたい案件を選び応募する仕組みです。
毎日新しい案件が掲載されており、利用者は技術スキルを磨くことができます。これにより、自身の市場価値を高めることが可能になります。また、これまで挑戦したことのない案件を受けることで、自身の得意な分野を見つけることができるでしょう。
フリーランスエージェントを利用
フリーランスエンジニア向けのフリーランスエージェントとは、企業とフリーランスエンジニアのマッチングを支援するサービスです。個々のスキルや経験に沿った案件紹介や、顧客との契約交渉の代行や、税務関係・保険の手続きのサポートまでも可能です。そのため、フリーランスエンジニアは自身の仕事に集中でき、安定的に仕事を受注することができるでしょう。
知人から紹介してもらう
会社員時代のクライアントや、知人からの紹介でも案件獲得が可能です。知人からの紹介ですので、営業や交渉の手間もほとんどかからず、スムーズに案件を獲得できるでしょう。しかし、業務を進めていく中で問題が起きてしまった場合、今後の関係に亀裂が入る恐れがあります。そのため、自身のスキルや報酬の相場を事前にしっかりと把握しておくことが重要です。
まとめ
フリーランスエンジニアは会社員エンジニアと違い、働き方が自由になる代わりに、自身で案件を獲得していかなければなりません。また、顧客と信頼関係を築いていくためにも、フリーランスエンジニアに必須なスキルを事前に身に付けておく必要があります。クラウドソーシングやフリーランスエージェントをうまく活用しながら、周囲にもフリーランスとして活動している旨をアピールしておくと、思いがけないところから案件が舞い込む可能性があるでしょう。
]]>- 個人事業主は法人設立せず個人で事業を営む人のこと
- フリーランスと個人事業主の違いは、開業届を提出しているかどうか
- 法人と個人事業主の違いは、法人格の有無と信用の得やすさ
- 税務署に開業届を提出すれば、誰でも個人事業主になれる
- 必要経費の計上や青色申告の利用により、節税が可能になる
個人で事業を営み、企業や団体などに所属せずに利益を上げる人は「個人事業主」「フリーランス」など、いくつかの呼称があります。自身で事業を起こすと考えた際、自分がどのスタイルに合っているのか、どれを選べばよいのか困惑した人も多いのではないでしょうか。
本記事では、複数ある呼称のうち「個人事業主」についてご紹介します。
個人事業主とは
個人事業主とは、法人を設立することなく個人で事業を営む人のことを指します。従業員を雇用していても、法人を設立していない場合は個人事業主と見なされます。原則として個人事業主になるための要件はなく、税務署に開業届を提出することで誰でも個人事業主になることが可能です。
フリーランスとの違い
フリーランスとは働き方の一つであり、自身の経験や知識、スキルなどを活用し、個人で収入を得ている人たちを指します。一方、個人事業主はフリーランスの働き方のうち、税務署に開業届を提出して収入を得ている人たちのことを指します。
フリーランスは働き方を示す呼称で、個人事業主は税法上の事業主を示す呼称です。しかし、多くの場合でフリーランスは個人事業主を指しているため、開業届を提出しているか否かが大きな違いと言えるでしょう。
法人との違い
個人事業主は法人を設立せず個人で事業を営む人のことを指すのに対し、法人は法人格(法律で個人と同様の権利・義務をもつ資格が与えられる)をもった組織や団体を指します。個人事業主と比べて、法人は信用を得やすく一定以上の利益に対する税率が低いというメリットがある反面、会計・事務処理などの細かな業務が多くなるデメリットもあります。
個人事業主から法人化することは可能ですが、事業内容や利益率によってはメリット・デメリットが異なるため、事前確認が重要です。
個人事業主になるメリット
個人事業主になることで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。大きなメリットを3点紹介します。
自由な働き方が選べる
雇用契約を結ぶ正社員・契約社員などの働き方と比べると、雇用契約を結ばない個人事業主は働き方を自由に選択できます。勤務地・勤務時間はもちろん、業務の順番やペース配分など、すべて自身でコントロールが可能です。受ける仕事の取捨選択も判断できますし、店舗を運営する場合も営業時間や定休日の決定権があります。
必要な経費を計上できる
事業を運営・維持するためにかかる費用は必要経費と呼ばれます。必要経費は、個人事業主として申告を行う際に計上することで支払う税金額が抑えられ、節税が可能になります。
青色申告時には、材料の仕入れや人件費、業務に必要な道具・機器代や打ち合わせ時の飲食代などを必要経費として計上可能です。また、自宅の一部で事業を営んでいる場合は、家事関連費用の一部も計上できます。
青色申告特別控除が受けられる
上記で軽く触れた「青色申告」を行うことで、個人事業主は青色申告特別控除を受けられます。申告するためには、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出することが必要です。税務署に必要書類を提出した後、貸借対照表および損益計算書をあわせて確定申告を行うことで、青色申告特別控除が受けられます。e-Tax(国税電子申告・納税システム)や電子帳簿保存による申告の場合は、最大65万の控除が受けられます。ただし、期限を過ぎてしまうと青色申告特別控除が受けられなくなるため、確定申告は期限内に済ませることが重要です。
参考:No.2072 青色申告特別控除|国税庁
個人事業主に向いている人とは?
個人事業主として事業を営むうえで、受けた仕事を投げ出すことなく完遂できる、責任感が求められます。未知の分野にもかかわる場合も考えられるため、向上心やチャレンジ精神、しっかりとした自己管理が行える人は、個人事業主に向いていると言えるでしょう。
また、個人事業主として仕事を請けるためには、自身で営業や交渉を担う必要もあります。営業・交渉スキルがあり、自分の裁量で業務を進めたいと考えている人にとって、個人事業主という働き方が向いている可能性もあるでしょう。
個人事業主になるための4ステップ
個人事業主になるには、何から始めたらいいのか疑問に思う人もいるでしょう。ここからは、個人事業主になるために必要な4つのステップをご紹介します。
1.どの事業で生計を立てるか決める
個人事業主になるには、事業を始める必要があります。しかし、明確な開業理由や動機がないまま、無計画に事業を起こしていては大きな損害を出してしまう可能性があります。開業する前に、事業を起こす目的・理由・動機などを定め、どのように生計を立てていくかを決めることが重要です。
勤めていた企業を辞めて開業する場合、ワークライフバランスが大きく変化する可能性もあります。個人事業主になるメリットはさまざまにありますが、開業することで自身にどのような影響があるか、販路や資金の維持ができるか、といったことも想定しながら事業計画を立てましょう。
2.税務署に開業届を提出する
どの事業で開業するか定まったら、開業してから1ヵ月以内に、「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を税務署に提出します。開業届の提出がない場合、青色申告が行えなかったり、補助金や助成金の申請ができなかったりといったデメリットがあります。
併せて、居住地域の自治体に「事業開始等申告書」の提出も行うといいでしょう。これは都道府県に個人事業の開始を知らせる書類で、自治体によって「個人事業開業届出書」「事業開始届」など名称が異なる場合があります。提出先が自治体によって変わる場合もありますので、提出期限と共に各自治体のWebページで確認してから進めることをおすすめします。
3.青色申告承認申請書を提出する
開業届の提出に続いて「青色申告承認申請書」を税務署に提出することで、青色申告の承認が受けられ、最大65万円の特別控除を受けられるようになります。控除が受けられれば、事業の初期段階で財務面から準備が整えられるでしょう。
申請書の提出期限は、以下のように定められています。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
引用元:A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
期限を過ぎた場合は、青色申告できるのが翌年からになるため、提出期限に注意しましょう。
4.国民健康保険・国民年金への切り替え手続きをする
正社員から個人事業主に転身した場合は、国民健康保険・国民年金への切り替え手続きを行います。手続きは居住地域の役所で行います。切り替え手続きに必要な書類を準備し、窓口での手続きを迅速に進めることで、個人事業主としての活動に専念するための基盤が迅速に整えられるでしょう。
企業に雇用されていても、国民健康保険と国民年金に加入していた場合は、この手続きは不要です。
個人事業主として開業するためのポイント
個人事業主として事業を起こすには、資金調達や事務作業など、相応の準備が必要です。滞りなく開業するために、押さえておくといいポイントをご紹介します。
事業用の銀行口座を用意しておこう
個人事業主として活動する際には、プライベート用と別に、事業用の銀行口座を用意しておくことが重要です。事業用の口座があれば、個人の資金と事業の資金を明確に分けられるため、経理の透明性を確保できます。同時に収入と支出を一目で把握できるため、税務署や取引先に対して事業の信頼性を示す手段にできます。口座開設時には事業名義での開設を求められることもあるため、必要書類を準備しておくといいでしょう。
利用できる補助金・助成金を確認しておこう
個人事業主としての活動するために、利用可能な補助金・助成金制度を確認しておくことが重要なポイントです。利用できる制度があれば、新規事業の立ち上げや事業拡大の際に、資金面のサポートが得られます。補助金・助成金制度は地方自治体や国から提供されており、事業の種類や地域によってサポート内容が異なります。積極的に情報収集を行い、自分の事業に合ったものを探すことと、申請時に求められることが多い事業計画書や財務計画書の準備を進めるといいでしょう。
経費にできるもの・できないものを確認しておこう
個人事業主の経費に上限はありません。事業の継続や拡大などに必要不可欠なものであれば、原則として、どのような費用も経費として認められます。しかし、健全に事業を営むためには、個人事業主が経費として計上できるもの、できないものを正確に把握することが重要です。
- 経費にできるもの
- 事業に直接関連する支出(材料費・交通費・通信費など)
- 家賃や光熱費の一部(自宅の一部を事業に利用している場合)
- 経費にできないもの
- 個人的な支出(趣味・事業と無関係の交通費など)
- 売上に見合わない多額の支出
経費の適正な管理は、税務調査の際に重要なポイントとなります。売上が少ないにもかかわらず多額の経費を計上した場合、税務署から確認が入り、経費とは認められずに赤字となる可能性もあります。常に売上とのバランスを意識して、領収書や請求書の保存・記帳と、経費の証拠をしっかり確保しておくことがポイントです。
まとめ
個人事業主とは、法人を設立せず個人で事業を行う形態のことを指し、開業届の有無や法人格の有無で、フリーランス・法人との違いを分けています。個人事業主には、自由な働き方や必要経費の計上による節税効果、青色申告特別控除が利用可能など、さまざまなメリットがあります。開業には事業選択、開業届・青色申告承認申請書の提出、保険・年金の切り替え手続きが必要です。健全な事業運営のためには、事業用の銀行口座の開設や補助金・助成金制度の確認、しっかりとした経費管理が重要になるでしょう。
]]>- 開業届は郵送で提出可能
- 郵送は税務署が遠方にある場合や、提出期限が迫っていたり、開庁時間内に行けなかったりするときに便利
- 開業から1か月以内に、届出書を記入し、必要書類をそろえて同封する
- 郵送時は、税務署の住所を確認し、不備がないかチェックして信書便扱いで送る
- 開業届の控えは、コピーして必ず取っておく
開業直後はやることが多数あり、税務署に出向く時間の確保が難しいかもしれません。そのようなときに便利なのが開業届の郵送による提出です。この記事では、開業届の郵送方法から注意点、一緒に同封できる届出書を紹介します。
開業届とは
開業届とは、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人事業主やフリーランスが事業を開業または廃止した際に税務署に提出する必要がある書類です。
開業届の提出方法は3種類
開業届は以下の方法で提出できます。
- 郵送
- 税務署へ直接持参
- e-Taxによるオンライン提出
忙しい開業当初には、税務署へ行く時間がとれなかったり、慣れないe-Taxの設定に時間がかかったりすると、煩わしさを感じるかもしれません。そのようなとき、郵送は時間や労力を省ける便利な提出方法といえます。
開業届を郵送した方がよい場合
開業届を郵送した方がよい場合は、次の通りです。
管轄する税務署が遠方にある
都市部以外では、税務署の管轄範囲が複数の市区町村にわたる場合があります。税務署まで数時間かかる場合もあり、移動時間が大きな負担と感じることもあるでしょう。郵送なら最寄りの郵便局から投かんするだけなので、時間を節約し、移動の手間を省けます。
税務署の開庁時間内に行けない
税務署の開庁時間は、年末年始を除く平日の8時30分~17時です。開業当初の忙しいとき、この時間内に税務署に出向くことが難しい場合もあります。また、時間外収受箱に入れる方法もありますが、税務署が遠方にある場合、持参するのが困難になることもあるでしょう。
提出期限が迫っている
通常、税務署に提出する書類の収受日は、税務署に届出書を提出した日付となります。しかし、郵送の場合は例外的に、郵便局の預かり日(発送日)が収受日として扱われます。提出期限が迫っていて、税務署に行く時間もとれないときは、郵送することで提出期限に間に合わせることも可能です。
開業届の郵送の仕方
ここからは、開業届を郵送する手順にそって解説します。不備が出ないよう、入念に準備を行うことが大切です。
開業届を取得し記載する
開業届「個人事業の開業・廃業等届出書」は税務署でもらうか、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。記載内容は、屋号、所在地、連絡先、代表者名のほか、所得の種類や給与支払状況などがあります。必要項目に記載漏れがないように注意しましょう。
開業届の提出期限を確認する
開業届の提出期限は開業から1か月以内です。遅延による罰則はありませんが、青色申告の申請や銀行口座の開設など、諸手続きへの影響も生じるため速やかに行いましょう。
郵送一覧
開業届の送付書類は以下の通りです。
- 開業届 1通
- マイナンバーカードの写し、またはマイナンバー通知書の写し
- 身分証明書の写し
- 返信用封筒(必要な場合)
マイナンバーの記載があるためマイナンバーのわかる写しと、運転免許証などの本人確認書類の写しが必要です。
また、返信用封筒は、開業届を収受した日付や税務署名が記載されたリーフレットを受け取る場合に必要になります。リーフレットは、開業届の控えではないので、返信用封筒を入れ忘れても問題ありません。
郵送先税務署の住所を確認する
開業届を郵送する宛先は、 個人事業主の場合、原則自宅のある住所地を管轄する税務署になります。事業を行う事務所所在地と自宅が異なる場合は注意が必要です。
自宅住所地を管轄する税務署の住所は国税局のホームページから確認できます。
郵送時の封筒サイズと宛名の書き方
郵送時の封筒サイズに決まりはなく、折りたたんで封入しても問題ありません。
宛名の書き方は以下の図を参考に、税務署名の下には「御中」と記入します。税務署内で部署仕分けがしやすいように、左側に「個人事業の開業・廃業等届出書 在中」と記載しましょう。
裏面には、自分の住所、氏名、郵便番号を記入し送付者を明確にします。また、切手代不足などの場合、裏面住所に返送されることがあります。
【開業届送付用封筒の書き方】
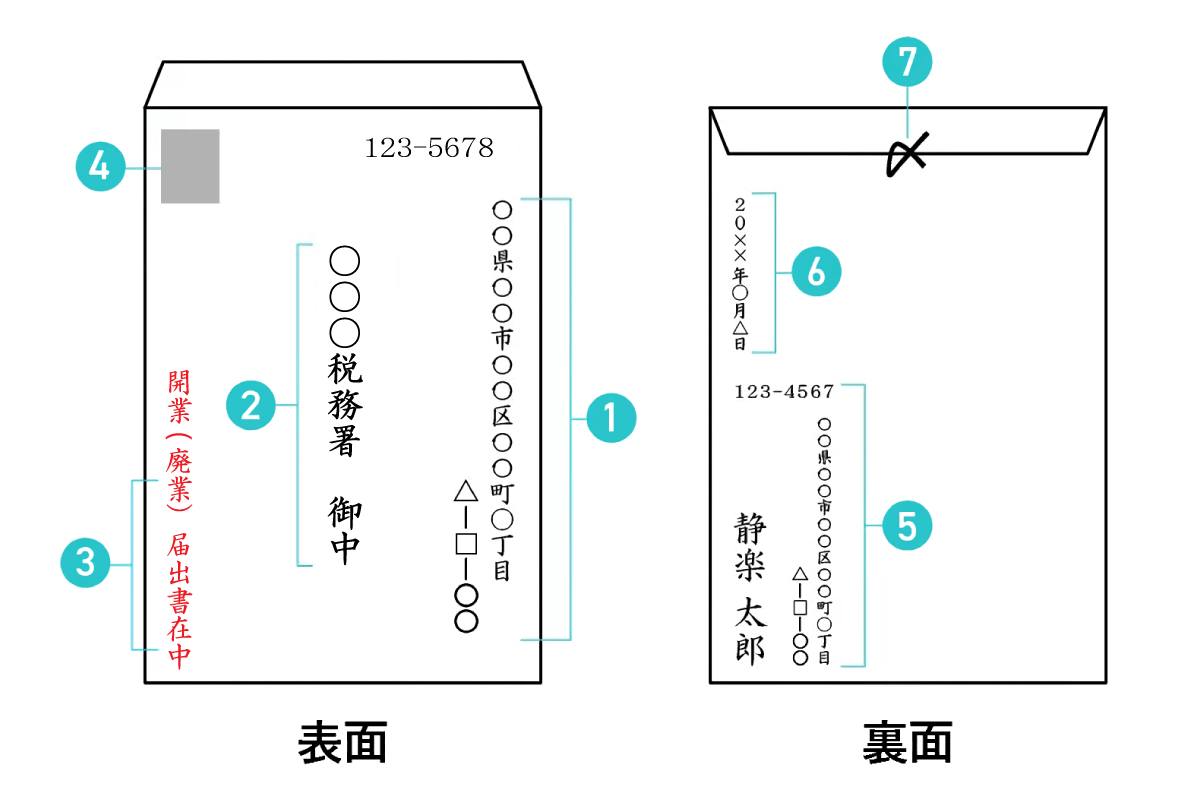
【同封する返信用封筒の書き方】
返信用封筒の表面には、自分の住所、氏名、郵便番号をと記入します。氏名の下には、「様」ではなく「行」と記入することを、ビジネスマナーとして覚えておいてください。さらに郵便切手も忘れずに貼りましょう。
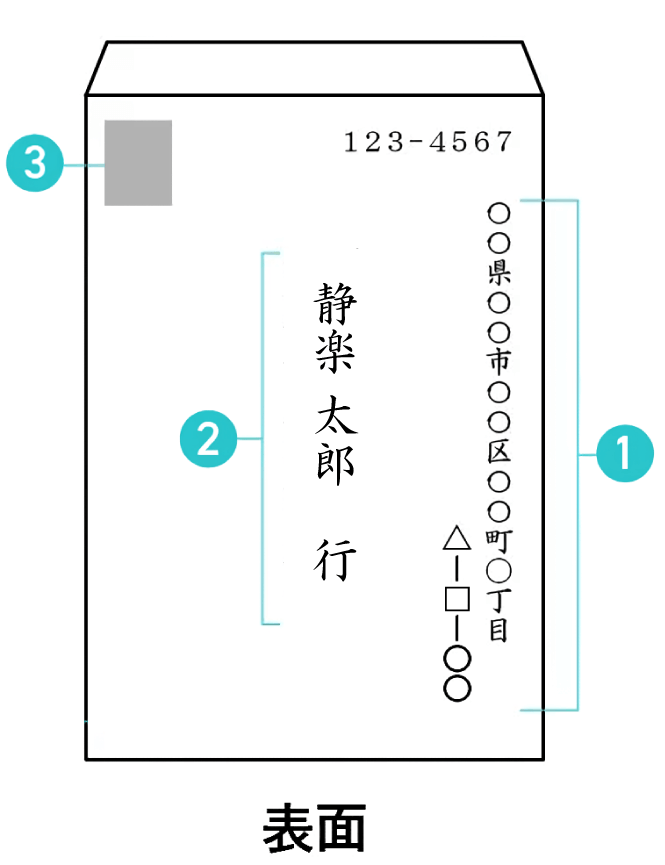
開業届を郵送する際の注意点
開業届を郵送する際は、書類に不備がなく、確実に税務署に届く方法を選ぶ必要があります。そのポイントを詳しく解説します。
郵送は信書扱いにする
開業届のような税務に関する書類には、個人情報の記載があるため、「郵便物」または「信書便物」として送付する必要があります。信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思や事実を通知する文書のことです。確実に税務署へ届けるため、追跡可能なレターパックなどの利用が安心です。また、宅急便での発送は、法律で禁止されているので注意しましょう。
控えを取っておく
これまでは、開業届を2部作成し提出することで、そのうちの1部に収受日付印と税務署名が押印されて開業届の控えとして返送されました。しかし、令和7年1月から押印がなくなり、申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したリーフレット(開業届の控え扱いが確立するまでの対処として)が返送されるようになりました。そのため、開業届のコピーを取っておき、リーフレットを受け取るための返信用封筒を同封します。
参考:国税庁|申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A
書類に不備がないようにする
開業届の記載内容に不明点があったり、添付書類に不備があったりした場合、問い合わせや差し戻されることがあります。その度に確認や再提出するための、無駄な時間と労力が必要です。忙しいときだからこそ落ち着いて、必要項目の記載と必要書類を確認し不備のない準備が重要です。
開業届と同時提出がオススメの申請書類
開業すると所得税の確定申告が必要になります。付随する届出書や申告書を提出しなければならず、それぞれ提出期限が異なるため、その都度届け出るのは大変です。そこで、開業届と同時に提出できるその他の申請書類を紹介します。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告を希望する場合、「青色申告承認申請書」を提出し承認を受ける必要があります。開業したその年から青色申告を受けるためには、開業日が1月1日~1月15日なら3月15日まで、1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内に提出しなければいけません。開業届と同封することで、期限内に提出でき、一度の手間で完了できます。青色申告には大きな節税効果があるためぜひ活用しましょう。
青色専従者給与に関する届出書
青色申告では、家族が事業に参加し給与の支給を受ける場合、この専従者給与を経費として計上できます。提出期限は青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、もしくは、1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者がいることとなった場合は、その事実から2か月以内です。開業当初から専従者がいる場合は青色申告承認申請書と一緒に提出しましょう。
参考:国税庁|A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
従業員を雇い、給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合、その旨を所轄税務署長に届け出る必要があります。提出期限は事務所等開設日から1か月以内です。こちらも開業届と一緒に提出できます。
参考:国税庁|A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、半年分ずつ年2回にまとめて納付できる特例制度を受けられます。この制度を受けるための申請書も開業届と一緒に提出が可能です。開業当初の資金繰りの厳しい時期に、従業員を雇った場合には、活用したい制度といえます。
参考:国税庁|A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
まとめ
開業届は、税制面や補助金の受け取り、社会的な信用度の向上など、新規に事業を始める方にとって多くのメリットがあります。提出期限を遅延しても罰則はありませんが、新規事業を開始する際には、早めに活用しましょう。開業当初の忙しい時期でも必要な手続きなので、時間と労力を抑えられる郵送での提出がオススメです。提出期限や郵送方法、注意点など、この記事を確認し、スムーズな開業準備にお役立てください。
]]>- 個人事業主とは法人をつくらず個人で事業を営む者を指す
- 業務委託とは個人事業主が業務を請け負うときのひとつの契約形態である
- 業務委託は成果物に、準委任契約では業務遂行のための作業に報酬が発生する
- 個人事業主は契約・報酬・税金・社会保障などさまざまな面で会社員と違いがある
- 業務委託で働くときは契約内容をよく確認し、成果物の著作権の所在を確認しよう
業務委託と個人事業主の違い
業務委託とは、個人あるいは企業が仕事を請け負う際の契約形態のひとつです。
個人事業主は個人が独立して事業をおこなう形態のひとつです。それぞれ解説します。
業務委託とは
業務委託とは、企業や個人が、業務の一部またはすべてを外部委託することを指します。業務委託は契約形態の一呼称です。したがって、企業の業務を個人が請け負うこともあれば、企業間で業務委託を請け負うこともあります。また、個人の業務を別の個人が請け負うことも業務委託にあたります。
業務委託を個人が請け負う場合、会社員のような雇用契約ではなく、業務委託契約を締結します。業務委託契約はおもに2つの形態があります。
- 請負契約
成果物に対して報酬が発生する形で委託者と受託者が結ぶ業務契約を指す。
- (準)委任契約
業務の遂行を目的に、作業に対して報酬が発生する契約形態である。委任契約、または準委任契約と呼ばれる。
- → 委任契約
弁護士や税理士など法律に抵触する業務をおこなう者に業務を委託し、受託者が遂行する
- → 準委任契約
法律に抵触しない業務を委託、受託者が遂行する。たとえば、ITの業務請負は準委任契約となる。
- → 委任契約
個人事業主とは
個人事業主とは、法人をつくらずに個人で事業を営む人のことです。税務署に開業届を提出することで個人事業主となります。
個人事業主の職業の例としては、飲食店や服飾店などの店舗経営、弁護士や税理士といった士業、開業医、独立して仕事を請け負うコンサル業やエンジニア、漫画家やイラストレーターといったクリエイターなどです。成果物や商品を納品して報酬を得るため、働き方については自分で自由に決められます。
個人事業主と会社員の違い
この項では個人事業主と会社員との違いを詳しく解説します。
報酬の違い
会社員は、企業と雇用契約を結んで業務に従事する働き方です。企業の業務指示に従って働き、賃金が定期的に支払われます。契約で決められた時間に働き、残業をする場合には労働基準法で決められた割増賃金が支払われます。
個人事業主は、企業に提供した成果に対して報酬を得ます。能力が高ければ、会社員と比較してかなりの高収入を得られる可能性があります。
税金の違い
個人事業主は、税金の面で会社員とは違いがあります。
- 所得税の納税方法が違う
個人事業主は、会社員と違って年末調整や所得税天引きの仕組みはない。したがって、個人事業主は毎年自ら確定申告をおこない、所得税を支払う必要がある。
社会保障における違い
社会保障の面においても、会社員と比較して個人事業主は大きな違いがあります。
- 社会保障面
社会保険とは、会社員に加入義務がある健康保険(および介護保険)・厚生年金・労働保険・雇用保険のこと。ただし、個人事業主として生計を立てている場合は一部の社会保険に加入できない。
- 健康保険
日本では国民皆保険制度をとっており、国民はいずれかの健康保険に加入しなければならない。
会社員は、所属企業が運営する組合健保、または中小企業のために運営される協会けんぽという健康保険のどちらかに加入する。個人事業主は国民健康保険に加入する。
また、会社員と個人事業主では、健康保険の保険料にも違いがある。会社員の保険料は所属企業と本人との折半となるが、個人事業主は全額負担である。 - 年金
年金制度は、いわゆる2階建てのつくりになっている。国民全員が加入する国民基礎年金と、会社員が国民基礎年金に加えて加入する厚生年金のふたつが運用されている。
つまり、個人事業主は国民基礎年金のみに加入するが、会社員は、国民基礎年金と厚生年金の両方に加入することになる。このため会社員は、納める年金の額は大きいが、その分将来のもらえる年金の金額も増える仕組みだ。
厚生年金に加入している会社員と比較して、国民基礎年金のみの個人事業主では将来もらえる金額がかなり少なくなるので注意しよう。 - 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業し収入がなくなったときに、失業手当をもらえる国の制度だ。
会社員は、一定の基準を満たすと雇用保険への加入義務が生じる。加入期間が通算12か月以上あれば、失業時に失業手当がもらえる。しかし、個人事業主は、雇用保険に加入できないため、もし失業しても失業手当はもらえない。 - 労災保険
労災保険は、労働者が通勤または業務中に怪我・病気などをした際に保険金が給付される制度で、会社員は加入必須である。一方、個人事業主は原則として労災保険に加入できないが、労働者と同様に保護されるべき立場として、一人親方など一部の個人事業主には、特別加入制度による任意加入が認められている。さらに、2024年11月からは「フリーランス新法」の施行により、特定のフリーランスも特別加入の対象に加わった。
- 健康保険
参考:厚生労働省 – 令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました
- 法律面
個人事業主は労働基準法の適用外となる。なぜなら、労働基準法は会社員を守るための法律だからだ。つまり、個人事業主には最低賃金や残業の概念は適用されず、6時間以上の労働には休憩が義務付けられることもない。 また、なかには悪質な企業(委託者)も存在し、なかなか報酬が支払われないなどのトラブルも頻発している。しかし、こういったトラブルの解消を目的に2024年11月からフリーランス新法という法律が施行された。詳しくは厚生労働省のページを確認しよう。
参考:厚生労働省 – フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
業務委託の注意点
業務委託で仕事を請け負う際、注意すべきポイントを解説します。
偽装請負に気を付ける
準委任契約は、委託者と受託者の契約であるため、会社員のように上司の指示に従って動く必要はありません。
しかしながら、実際の現場では、委託者である企業から、仕事のやり方をまるで部下のように指示されるケースがあります。これはいわゆる偽装請負にあたり、違法行為となります。このような働き方をするのであれば、会社と雇用契約を結ばなければいけません。
法律では実際の業務形態を重視するため、契約書上は準委任契約となっていても実態が上司の指示に従うような働き方であれば法律違反とされます。
業務内容をよく確認する
業務委託を請け負う場合、どこからどこまでが自分の業務範囲かは、契約書に記載されている内容に準じます。この点をあいまいにすると、自分の仕事の範囲がどこまでかがわからず、トラブルにもつながりかねません。
業務範囲はきちんと相談の上で決定し、契約書にも業務内容の範囲を明確に記入することが大変重要です。
2024年11月に施行されたフリーランス新法を確認しておきましょう。
参考:公正取引委員会 – 公正取引委員会フリーランス法特設サイト
著作権が誰に帰属するか必ず確認をする
著作権とは、その作品をつくった人が持つ権利です。著作権を持たない者は、その作品を勝手に使用したり、販売して報酬を得たりすることはできません。これらの行為をおこなうためには、著作権者の承諾が必要です。
業務請負は完成した成果物として納品し、対価に報酬をもらいますが、この成果物について著作権はどちらものものかという問題があります。
結論からいうと、業務請負の場合は、契約により、依頼した企業(委託者)に成果物の著作権が帰属することが多いようです。しかし、双方相談の上、制作者(受託者)に著作権が帰属する契約にすることも可能です。
とくにクリエイター系フリーランスの間では、著作権物の問題でよくトラブルになっています。著作権について認識があいまいな場合は、成果物の著作権が誰に帰属するのか、契約締結のときに契約内容をよく確認するようにしましょう。
まとめ
個人事業主とは、法人をつくらずに個人で事業を営む人のことです。業務委託とは、企業や個人が、業務の一部またはすべてを外部委託することを指します。
つまり、個人事業主が業務を請け負うときの契約形態のひとつが業務委託です。
個人事業主は、会社員と比較して、報酬面、税金面、社会保障面でさまざまな違いがあります。会社員は毎月安定した収入を得られ、手厚い社会保障があります。対して個人事業主は、契約単位で報酬が発生するため月々の収入は不安定になりやすく、社会保障も薄いです。ただし、個人事業主の権利を保護する目的で、2024年11月にフリーランス新法という法律が施行されました。
個人事業主は、トラブルが起きても自分ですべて対応しなければならないため、契約書の内容をきちんと把握しておくことは非常に重要です。とくに業務委託契約では、偽装請負という違法な労働形態に陥る可能性があるので、契約書の業務内容はよく確認しておきましょう。
]]>- 本業フリーランスの年収平均は298.7万円
- 年収の平均額はフリーランスより会社員の方が高い
- 職種的には専門職・技術職の年収が高い傾向にある
- フリーランスの増収には人脈作りとスキルアップが課題になる
- 長期契約の獲得と収入源の複数化が収入安定の鍵になる
フリーランスという働き方は、働く時間や場所が自由に選べる魅力があります。しかし収入面に関しては多くの人が不安を抱えているのも事実です。本稿では、フリーランスの年収事情について解説し、職種別の相場や収入を増やすためのコツを紹介します。
フリーランスの収入事情
この項目では、本業フリーランス(フリーランスを本業とする人)と会社員の平均年収について解説します。
フリーランスの年収
リクルートワークス研究所による調査結果「データで見る日本のフリーランス」では、本業フリーランスの平均年収は298.7万円です。この分布割合の高い3者を見ると、100~300万円未満が36.2%と最も多く、次いで300~500万円未満が27.1%、0~100万円未満は19.4%と続いています。
参考:リクルートワークス研究所|データで見る日本のフリーランス
会社員の年収
国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると給与所得者の平均給与年額は460万円です。収入の分布では、300万円超400万円以下が16.3%と最も多く、次いで400万円超500万円以下が15.4%となっています。
フリーランスと会社員との年収比較
以下の表は、本業フリーランスと会社員の平均年収と分布割合の上位3者を比較したものです。計算年が異なるため会社員は複数年を掲載しています。
本業フリーランスの平均年収と収入分布
| 2019年(令和元年) | 平均298.7万円 | 0~100万円未満が19.4% 100~300万円未満が36.2% 300~500万円未満が27.1% |
会社員(給与所得者)の平均年収と収入分布
| 2019年(令和元年) | 平均438.4万円 | 200万円超~300万円以下 15.0% 300万円超~400万円以下 16.7% 400万円超~500万円以下 14.4% |
| 2020年(令和2年) | 平均435.1万円 | 200万円超~300万円以下 15.3% 300万円超~400万円以下 17.1% 400万円超~500万円以下 14.4% |
| 2021年(令和3年) | 平均445.7万円 | 200万円超~300万円以下 14.6% 300万円超~400万円以下 17.1% 400万円超~500万円以下 14.9% |
| 2022年(令和4年) | 平均457.6万円 | 200万円超~300万円以下 14.1% 300万円超~400万円以下 16.5% 400万円超~500万円以下 15.3% |
| 2023年(令和5年) | 平均459.5万円 | 200万円超~300万円以下 14.0% 300万円超~400万円以下 16.3% 400万円超~500万円以下 15.4% |
これにより年収の平均額は会社員の方が高い傾向にあることがわかりました。
業種別の平均年収
フリーランスの年収は職種によって大きく異なりますが、専門職・技術職の年収は高い傾向にあります。以下の項目では業種別の平均年収一覧とともに、平均額の上位業種と年収額の分布について解説します。
業種別平均年収一覧
下図は「データで見る日本のフリーランス」による、フリーランスの業種別・現在年収一覧です。以下の項目で順位別に解説します。
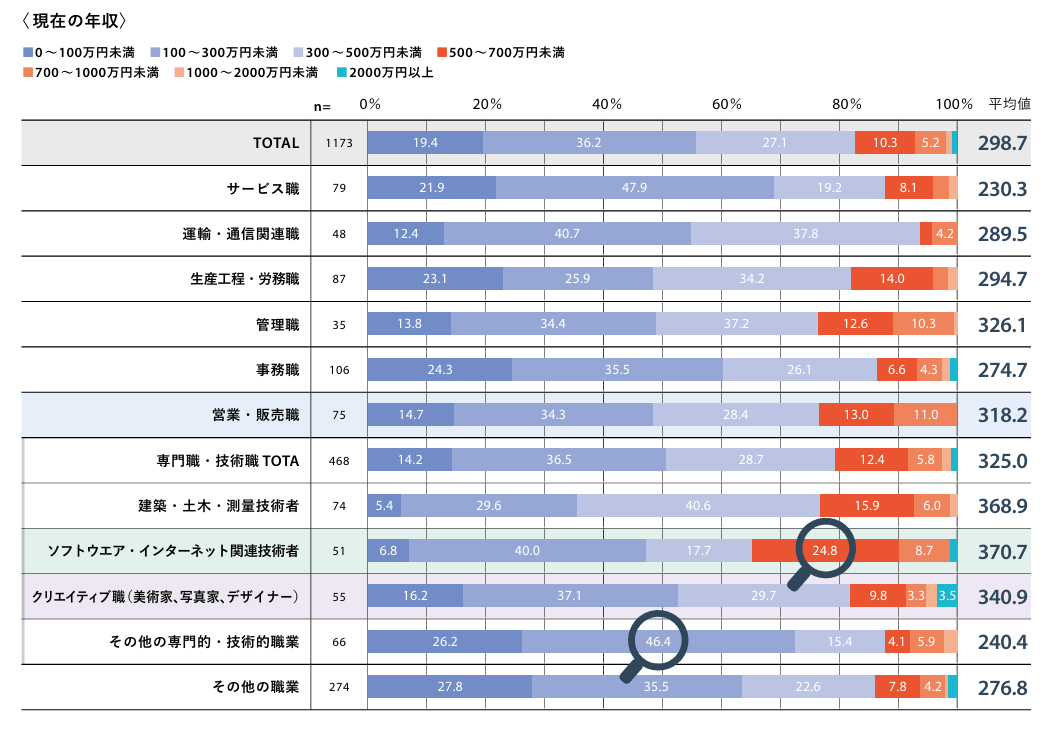
引用:リクルートワークス研究所|データで見る日本のフリーランス P37
1位 IT関連
ソフトウェア・インターネット関連技術者などのIT関連業種の平均年収額は370.7万円で、業種別の第1位です。IT関連業種のフリーランスは高い需要があるため比較的高収入を期待できます。特にAIやクラウド技術に精通しているエンジニアはさらに高い報酬を目指せるでしょう。
2位 建設関連
建築・土木・測量技術者など、建設関連業種の平均年収額は368.9万円で、業種別の第2位です。建設系のフリーランスには、いわゆる一人親方と呼ばれる職人系の技術者が含まれており、技術や危険な職務に対する手当などから高収入の傾向があります。事業の責任者としてスタッフを雇う場合は、収入にその人件費も含まれます。経験や専門性による契約の獲得が収入を安定させる鍵になるでしょう。
3位 クリエイティブ関連
美術家・写真家・デザイナーなど、クリエイティブ関連業種の平均年収額は340.9万円で、業種別の第3位です。フリーランスのクリエイティブ系業種で活動する場合、年収は経験やスキルに応じて大きく変動します。専門的な経験やスキルがわかるポートフォリオを作ることで、さらに高収入の仕事に挑戦できるでしょう。
年収を増やすコツ
フリーランスとして年収を増やすには、いくつかのポイントがあります。以下の項目では代表的なものを中心に4点のコツを紹介します。
人脈を広げる
フリーランスの業務には自分を売り込む営業も含まれています。そのため仕事に関わる人脈の拡大が、新しい仕事の機会につながります。これを実現するためにも業界のイベントやオンラインフォーラムに参加し、積極的に人材交流を図りましょう。また、過去のクライアントとの関係を維持し、リピート案件を狙うことも重要です。
スキルアップに取り組む
フリーランスとして収入を増やすには、スキルアップにつながる学習や訓練が不可欠です。
新しい技術やトレンドを察知して、それに合わせたスキルを磨くことで、より高単価の仕事に挑戦できます。そのためにもオンライン・オフラインを問わず、講習やセミナーに参加して、新たな知識や資格を獲得し、スキルを向上させましょう。
ポートフォリオを充実させる
クライアントにアピールするためには、質の高いポートフォリオが不可欠です。過去の成果物やプロジェクトを整理し、WebやSNSを利用して積極的に実績を公開することで、フリーランスとしての信頼獲得が目指せます。
但し、契約によっては納品した成果物がクライアント企業の著作物(いわゆる職務著作)となるものや、守秘義務が伴う場合もありえます。そのような成果物は契約書の確認や、クライアントに許可を取らなければならない可能性があることも、覚えておきましょう。
節目ごとに料金設定を見直す
料金設定の見直しも、フリーランスにとって収入を左右する重要な要素です。収入アップのためにも新しい技術や資格取得、大型プロジェクトの完了時といった節目ごとに市場調査を行い、業界の平均単価や経済状況の変化と比較して適正な料金設定に見直しましょう。スキルや経験に応じた適切な料金が設定されることも、クライアントの信頼を得る鍵となります。
年収を減らさずに収入を安定させるには
フリーランスとして年収を減らさずに安定した収入を得るためには、事業に対する継続的な取り組みが必要です。以下の項目では代表的なポイントを3点紹介します。
長期契約を獲得する
フリーランスの収入を安定させるには、案件ごとや短期的なプロジェクトだけでなく、長期的な契約を獲得することが重要です。案件のリピートや、定期的な契約を獲得するためにも、クライアントと信頼関係を構築するために努力を継続しましょう。
複数の収入源を確保する
フリーランスは技術革新や競争人口の増加などから起こる価格変動の影響を受けやすく、その変動は収入の増減に直結します。この影響を軽減するには収入源を多様化することが効果的です。例えば、本業以外に副業を持つ、オンラインコンテンツを販売するなど、収入源の複数化に努めるとよいでしょう。
計画的な財務管理を行う
フリーランスは給与所得者とは違い、収入に対する保証がありません。景気の動向などから収入が不規則になることも多いため、計画的な財務管理は常に事業上の課題となります。不測の事態を乗り切るためにも収入が多い時期に貯蓄をし、運転資金を確保しておくことが重要です。
まとめ
今回はフリーランスの年収事情について会社員との比較と合わせて解説しました。フリーランスとして年収を増やすには、スキルの向上やポートフォリオの充実をはじめ、人脈作りや料金設定の見直しといった営業やマーケティングも必要です。これらのポイントを押さえながら、安定した収入を得るための戦略を立て、長期的な成功を目指してください。本稿が事業を継続する一助となれば幸いです。
]]>- 開業届とは個人事業を開業する際に税務署へ申告手続きをするための書類のことである
- 開業届には「個人事業の開業・廃業等届出書」と「個人事業税の事業開始等申告書」がある
- 開業届は事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する
- 青色申告を希望する場合は開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出すると良い
- 開業した後は確定申告を青色申告で行えば所得税の節税になるメリットがある
この記事を見つけたあなたはきっと、開業届をどのような手順で手続きをしたらいいのかわからず、悩んでいることと思います。本記事では、そうした悩みや疑問を解決するために、開業届の種類や提出期限、メリット・デメリットについて詳しく解説します。開業届に加え、青色申告や白色申告など別途書類についても併せて見ていきましょう。
開業届とは
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)とは、個人事業を開業する際に税務署へ申告手続きをするための書類を指します。個人事業やフリーランスを始める上で発生する売上や経費など自身で所得税を計算して、確定申告を行う必要があります。そのことから個人事業主が税務署に申告・納税を行なっているか、正確に管理しなければなりません。
開業届は2種類がある
開業届には2つの種類があり、税務署に提出するものと都道府県税事務所に提出するものに分かれています。なお、提出する管轄税務署については国税庁ホームページで紹介されていますので、こちらよりご確認ください。
参考:国税庁|A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
個人事業の開業・廃業等届出書
税務署に提出する個人事業の開業・廃業等届出書は新たな事業所得、不動産所得あるいは山林所得を得る人が開始した事実が認められる日から数えて1ヶ月以内には提出するものです。
参考:国税庁|個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業税の事業開始等申告書
都道府県税事務所に提出する個人事業税の事業開始等申告書は、個人事業を開始したことについて都道府県の管轄税事務所に申告するものです。「個人事業税の事業開始等申告書」は都道府県によって提出義務の有無が異なります。必ずしも提出が必要とは限らないため、都道府県ごとのルールを確認する必要があります。
参考:東京都主税局|個人事業税の事業開始等申告書
「許認可申請」が必要な業種もある
特例の業種の場合は、開業届を提出する際に許認可申請が必要です。これを取得せず、開業してしまうと業務違反により行政処分・法定責任を負う場合があります。
また、すでに取得した許認可に有効期限が切れていないか、更新時期をチェックする必要があります。ただし、社会保険の扶養に加入されている人に限り、開業後の事業収入が増えてしまうと扶養から外れる場合があります。
| 対象業種 | 許可の種類 | 申請先 |
|---|---|---|
| 飲食店 | 飲食店営業許可 | 管轄保健所 |
| 美容室 | 美容所開設届 | 管轄保健所 |
| 不動産業 | 免許 | 都道府県庁 |
| 建設業 | 許可 | 都道府県庁 |
| 旅館業 | 許可 | 管轄保健所 |
開業届の提出方法と流れ
開業届の提出方法と流れについて、以下を説明しますので見ていきましょう。
1.開業届の入手
まず、開業届を入手しましょう。提出する開業届は国税庁のWebホームページから用紙をダウンロードあるいは、税務署窓口で入手できます。
参考:国税庁|個人事業の開業・廃業等届出書
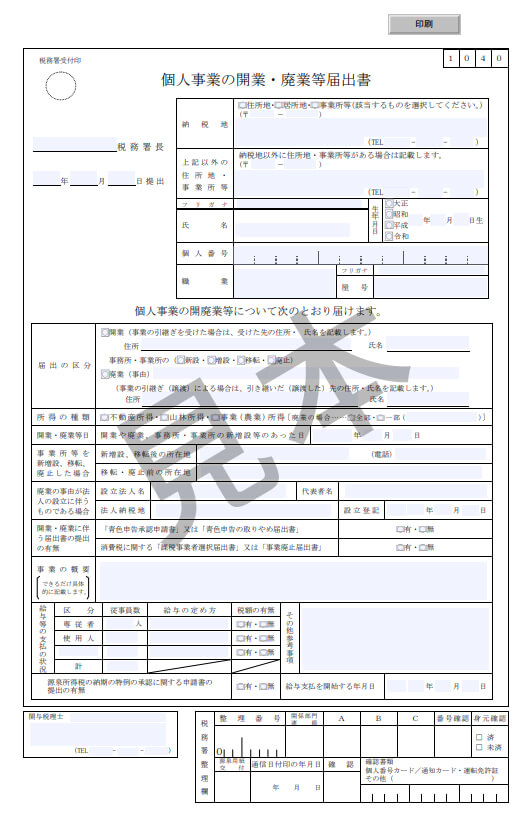
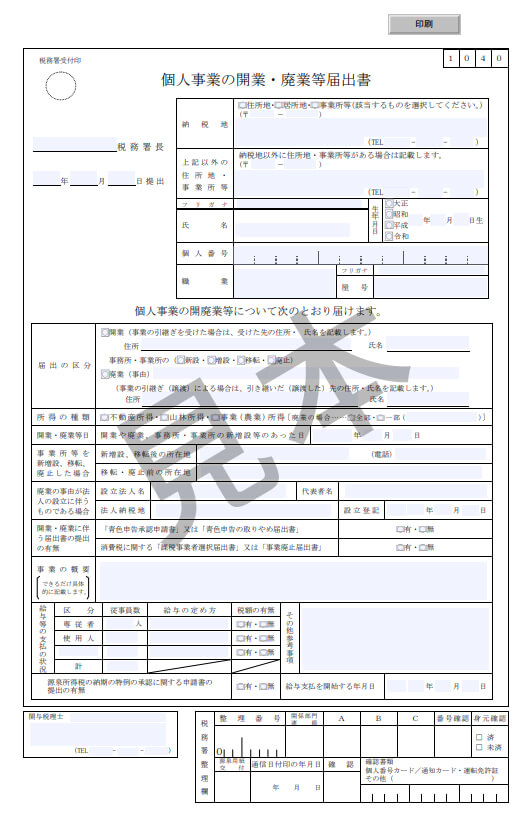
※クリックで画像を拡大できます
2.開業届の作成
入手した開業届の項目に必要事項を記入します。記入すべき項目は「納税地の住所」「生年月日」「職業」などです。屋号については作りたい場合に記入しておきましょう。
3.税務署へ提出
管轄の税務署へ提出または郵送、オンラインを用いたe-Taxでの提出、3通りの選択があるので、自分に合った方法で提出しましょう。それぞれの提出先と利用が可能な時間については、下記を参考にしてください。
| 提出方法 | 提出先 | 利用時間 |
|---|---|---|
| 税務署窓口 | 管轄税務署 | 年末年始除く 平日8時30分~17時30分 |
| オンライン | e-Tax (国税電子申告・納税システム) | 24時間 (ただし、月曜日と土日祝日は8時~0時) |
| 郵送 | 最寄りの郵便局 | 制限なし |
4.開業届の控え
税務署の窓口で提出が完了すると、その場で開業届の控えを受け取れますが、郵送で提出した場合、控えを受け取るまでに1週間ほどかかります。また、e-Taxでオンライン提出した場合は開業届の控えはありません。提出した際のデータ・通信通知が開業届の控えになるため、かならず保存しておきましょう。
開業届はいつ出す?提出期限は?
所得税法第229条により、事業を開始した日から1ヶ月以内を目安に提出しなければなりません。たとえば4月1日に開業したとすると、1ヶ月後の4月30日までに提出するという計算です。ただし、期限を過ぎての提出にペナルティはなく、税務署より提出の催促が来ることはないので、心配する必要はないでしょう。
(開業等の届出)
参考:e-GOV法令検索|所得税法
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
開業届と青色申告は一緒に出すべき?
青色申告を希望する場合は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出するのがおすすめです。事業所得が48万円を超えた場合に課税対象となるため、確定申告を青色申告で行えば所得から最大で55万または65万円が控除されるので、節税対策に有効です。また提出期間は3月半ばまでに所轄税務署へ提出する必要があるため、忘れないよう注意しましょう。
白色申告でも開業届は必須?
本来、青色申告・白色申告に関係なく、開業届の提出は必要ですが、提出しなかったとしても罰則されることはありません。確定申告の際に提出するための書類作成の手間が省けるほか、家計簿のような感覚で単式簿記をつけられるため、白色申告を選択する人もいるようです。
開業届を提出するメリット
開業届を提出する上で、メリットについて説明します。
事業主としての信頼性が高まる
個人事業主として独立したことを公式的に示すためには開業届が必要不可欠です。また開業届を提出することで、法人向けクレジットカードの作成やサービスの申し込みなどの際に信用度が高まるメリットもあります。
小規模企業共済に加入できる
万が一、個人事業主や小規模企業を経営する際に廃業した場合の備えとして、小規模企業共済といういわゆる退職金代わりになる積立金制度があります。加入するには、開業届の提出が必要です。また、小規模企業共済における掛け金は小規模企業共済等掛金控除で全額控除が可能になるため、将来の節税につながるメリットがあります。
屋号を利用して銀行口座を開設できる
開業届を提出する際には、屋号をもとに口座を開設することが可能です。そのためには開業届の控えが必要になるため、くれぐれも紛失には注意しましょう。また、屋号の入った口座があれば、社会的信用が向上するほか、個人と事業の入出金を別々に管理しやすくなるメリットがあるのでおすすめです。
開業届を提出するデメリット
開業届を提出する上でデメリットについて説明します。
開業前に提出すると青色申告の特別控除が受けられない
開業前に開業届を提出するのは避けましょう。開業届はあくまでも事業を開始したことを申告するための書類です。開業届の提出日が開業した日よりも前の日にしてしまうと、青色申告の特別控除を受けられず、節税対策で不利になるなどのデメリットが発生します。そのことから、開業日の設定は提出日から遡って1ヶ月以内にしておきましょう。
所得が一定の基準を超過すると扶養から外れる
開業し、事業収入が増えた場合、所得が一定の基準を超過すると扶養控除および配偶者控除が対象外になってしまいます。所得税に加えて、健康保険に関連することから、扶養の条件から外される可能性があるのです。このことから、自分で管轄の区役所または市役所へ健康保険の加入手続きをしなければなりません。
離職後の失業手当を受給できない
開業届を提出すると、原則として失業手当の受給はできなくなります。ただし、事業開始等による受給期間の特例が2022年7月1日に施行されてからは、要件を満たせば事業期間でも最長3年間、受給期間の特例を受けられます。退職した後は特例申請をしておきましょう。
参考:厚生労働省|事業開始等による受給期間の特例
まとめ
開業届について理解していただけたでしょうか? 開業するには、さまざまな手順を踏んだ上で書類を提出しなければなりません。開業届のほかに許認可申請が業種によって提出先も異なるため、あらかじめ確認してから提出する必要があります。また、特定業種の人が行政機関へ許認可申請を取得せず、開業してしまうと業務違反により処罰されることもあるため注意しなければなりません。メリット・デメリットを理解し、正しい順序で開業届を提出しましょう。
]]>- 補助金とは、国や地方自治体が企業・個人事業主に支給する資金のこと
- 社会問題の解消や、経済活性化を推進することが目的
- 補助金にはさまざまな種類があり、対象者・受給要件・申請方法などが異なる
- 国だけでなく、地方自治体ごとにも補助金制度が実施されている
- 申請したからといって、必ずしも採択されるとは限らない
補助金とは?
補助金とは、国や地方自治体が、企業や個人事業主を支援するために支給する資金のことです。補助金の支給により、社会問題や環境問題の解消・経済活性化を推進することが目的です。
多くの補助金は、申請・審査を経て採択された場合のみ受給できます。採択件数や金額などは、はじめから決まっている場合が多いため、申請しても受給できるとは限りません。
また、多くの補助金は所得税・法人税などの課税対象となるため、基本的には確定申告を行う必要があります。
助成金・給付金との違いは?
助成金と補助金は、意味も目的もほぼ同じです。
助成金は補助金と同じく、国や地方公共団体が企業や個人事業主などに支給する資金のことです。
社会問題や環境問題の解消・経済活性化の推進を目的としています。
補助金と異なる点は、基本的に、要件を満たせば受給できることです。
一方、給付金とは、国・地方公共団体が個人・世帯に対して支給する資金のことです。
主に、貧困家庭への生活支援や災害時の救済措置など、特定の条件を満たす場合に支給されます。
給付金は、事業活動を支援する補助金・助成金とは異なり、一時的な救済措置として給付されるケースが一般的です。
個人事業主も利用できる代表的な補助金
以下では、個人事業主も利用できる代表的な補助金を6つ紹介します。
1.小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)とは、小規模事業者・個人事業主などが販路開拓に必要な経費の一部を国が補助する制度のことです。
通常枠と特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)があり、いずれか1つの枠のみ申請できます。
通常枠とは、自らが作成した経営計画に沿って、販路開拓や事業拡大の取り組みを行う小規模事業者への支援枠のことです。通常枠の補助上限額は50万円ですが、インボイス特例の要件を満たせば、補助上限額に50万円を上乗せして申請できます。
2.IT導入補助金
「IT導入補助金」とは、中小企業・小規模事業者・個人事業主などが、ITツール(ソフトウェア・サービスなど)を導入する際に国が補助する制度です。主に、業務の効率化やDX推進を目的として設立されました。
IT導入補助金のなかでも、「インボイス枠(インボイス対応類型)」は、パソコン・タブレット・ハードウェアなどの導入にも利用できるため、人気があります。
ただし、ITツールの導入もセットで行うことが条件ですので、申請を検討している方は覚えておきましょう。
補助金を申請する際には、IT導入支援事業者とパートナーシップを組む必要があります。IT導入支援事業者とは、生産性向上を目指す中小企業・小規模事業者等へ、ITツールの導入を支援する事業者のことです。
また、補助金対象のITツールは、事前にIT導入補助金事務局のホームページに公開されているものに限ります。
3.中小企業省力化投資補助金
「中小企業省力化投資補助金」とは、中小企業・小規模企業・個人事業者などが、省力化製品(IoT・ロボットなど)を導入する際に国が補助する制度です。省力化製品を活用して、人材不足の解消につなげることを目的としています。
中小企業省力化投資補助金には「カタログ注文型」と、2025年から新設された「一般型」があります。
カタログ注文型とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページにあるカタログに登録された省力化製品のなかから、自社に合った製品を選び、販売事業者と共同申請する方式です。
一方、一般型は、カタログに登録されていない省力化製品やオーダーメイド製品などを活用できる点が特徴です。
4.事業再構築補助金
「事業再構築補助金」とは、コロナ後に事業の再構築を目指す、中小企業・小規模企業・個人事業者などを支援する国の補助制度です。
「事前着手制度」が廃止されてからは、補助金交付決定前に支出した経費は補助対象外となりましたので、注意が必要です。
事業再構築補助金を利用するための基本要件には、事業再構築指針の定義に該当する事業を行うことや、事業計画について金融機関や認定経営革新支援機関等の確認を受けることなどがあります。
事業再構築指針の定義は、「新市場進出」や「事業転換」「業種転換」などです。
たとえば、飲食業であれば、自社商品のテイクアウト販売を行うスペースの設置や、デリバリーサービス事業の立ち上げなどが該当します。
また、航空機の部品を製造する企業が、ロボットや医療機器の部品開発事業に乗り出した例もあります。
事業再構築補助金の申請手続きには、GビズIDの取得が必要です。
GビズIDの取得には一定期間を要するため、手続きは早めに行いましょう。
5.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」とは、中小企業・小規模事業者・個人事業主などが、今後直面する制度(働き方改革・賃上げ・インボイス導入など)へ対応できるように、国が補助する制度です。
また、日本国内に本社及び補助事業を行う場所(工場・店舗など)があることも条件の1つです。
補助対象事業には、以下の2つの事業枠があります。
- 製品・サービス高付加価値化枠:
新製品や新サービスの開発に、必要な設備・システム投資などを支援する事業枠
- グローバル枠:
海外事業を実施している企業の支援枠。主に、必要な設備・システム投資などを構築して、国内事業と海外事業の双方を強化し、国内の生産性向上に努める企業が対象
6.中小企業新事業進出補助金
2025年に新設されたばかりの制度に「中小企業新事業進出補助金」があります。
中小企業新事業進出補助金とは、既存事業とは別に、新市場・高付加価値事業への進出を行う企業や事業主に対して、設備投資等にかかる費用を国が補助する制度です。中小企業・小規模事業者だけでなく、個人事業主も対象となります。
企業や事業主の生産性向上だけでなく、賃上げを促進させることも目的の1つです。
また、同じく2025年に新設された補助金に「中小企業成長加速化補助金」があります。
こちらの補助金は、売上高100億円を目指す中小企業に対して国が補助する制度ですので、比較的事業規模が大きい事業者や企業でなければ対象にはなりません。
補助金の申請方法・流れ
補助金の申請方法や流れは補助金ごとに異なります。申請する際は、その都度要綱を確認しましょう。
以下では、補助対象者の申請方法・流れを解説します。
一般的な補助金の申請方法・流れ
以下の表では、一般的な流れをご説明しています。
-
事前準備
各補助金サイトから公募要領を確認する。郵送、またはネットのどちらから申請するかを決める
ネットから申請する場合は、法人・個人事業主向けの共通認証システムアカウント(GビズID)を取得すると便利 -
公募申請
公募要領・申請書を確認のうえ、必要書類一式を事務局に提出する
提出書類:応募申請書・事業計画書・経費明細書・事業要請書など -
交付申請・交付決定 → 補助事業の開始
採択後は交付申請(補助金を受け取るための手続き)を行う。申請が認可されたら交付決定(補助事業の開始)となる
受取書類:選定結果通知書・補助金交付規程・交付申請書・交付決定通知書など
提出書類:交付申請書・経費の相見積もりなど -
変更申請手続き
交付決定にあたり、事業内容を変更する都合があれば、計画変更申請手続きを行う
提出書類:計画変更申請(必要な場合のみ) -
報告書の提出・補助金交付
事業内容や経費を報告して補助金を受け取る。補助金の対象となる経費に関しては、領収書や証拠書類など、すべて保管しておく
提出書類:実績報告書・経費エビデンス・請求書など
受取書類:補助金額確定通知書・請求書様式など
補助金の公募期間は一か月前後であることが多いため、期間内に所定の書類を揃える必要があります。
その際に、きちんと補助金の必要性をアピールできないと採択されないため、注意しましょう。
補助金を受け取るためのポイント・注意点
以下では、補助金を受けるためのポイント・注意点を8つ解説します。
1.申請する補助金が個人事業主も対象かどうかを確認する
補助金を申請する前には、自社が対象となるかを確認しておきましょう。
補助金のなかには「個人事業者向け」と記載されていないケースもあり、自社が適用されるかどうかがわかりにくいこともあります。
そのため、補助金ごとの詳細要件を確認する前に、前提条件が当てはまるかを大まかに確認しておきましょう。
具体的には、以下の4項目の確認をオススメします。
- 補助対象者かどうか(事業規模・法人格・改行年数・開業実績など)
- 補助対象事業かどうか(補助金の趣旨にあった事業を展開しているかどうか)
- 補助対象経費のものを購入・投資予定か
- 補助対象期間に事業を実施しているか(支出した経費を含む)
2.補助金を受け取るまでは資金計画を立てておく
補助金を申請して採択された場合でも、受け取るまでの期間は、資金計画を立てておく必要があります。理由は、多くの補助金が後払い制であるためです。
たとえば、総額100万円の機械導入に1/2の補助が適用される場合でも、最初に自社で100万円を用意する必要があります。
50万円だけ自社で用意しておき、購入時に残りの50万円を補助金で支払うことはできませんので注意しましょう。
3.補助金を受け取る際の提出書類はきちんとチェックしておく
補助金を受け取る際に提出する書類(報告書・支払証憑類など)はきちんとチェックしておきましょう。提出書類の内容が適当であったり、目的外のモノに経費を支出していたりした場合、支払いを拒否されることがあります。
過去の例では、試作品をつくるために導入した機械に対する補助金が支払われなかったケースもあります。こちらは、試作段階で量産用の機械を購入したとして補助金の支払いが拒否されました。
4.補助事業開始前に支出しないよう気を付ける
一般的に、補助金は補助事業期間内のものに適用されます。そのため、補助事業開始前に支出した経費は補助金の対象外となるケースが多いです。
結果として、補助が受けられない事態を避けるためにも、支出時期には気を付けましょう。
たとえば、事業期間が6月1日から2月28日までの場合、5月31日や3月1日に支出したものは補助を受けられない可能性が高いです。
また、事業期間の最終日に関しては、年度末よりも少し早めに設定されているケースが多いため、こちらも注意が必要です。
5.国だけでなく地方自治体からの補助金の情報もチェックしておく
補助金の支給は国からだけではありません。
地方自治体でも実施していますので、各自治体の情報もチェックしておきましょう。
たとえば、大阪府では、「中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金」を実施しています。
中小事業者に補助金を支給して、脱炭素化や電気料金の削減を促したり、経営力強化を促進させたりすることが目的です。
また、神奈川県では、「ロボット導入支援補助金」を実施していました。こちらは、「ロボットと共生する社会」を実現していくことを目的として設立されました。主に「さがみロボット産業特区」で商品化したロボットを導入する事業者への補助金です。※令和6年度の募集は2025年2月で終了しています。
両者ともに、企業だけでなく、個人事業主も補助対象です。
6.補助金の対象となる領収書・証拠書類などは指定期間保管しておく
補助金の対象となる領収書・証拠書類などは、補助事業終了後、5年間は保管しておく必要があります。
また、「補助金等交付申請書等」には、補助対象外経費も含めて記載する必要があるため、事業期間に発生した補助対象外費用の領収書・証拠書類なども残しておきましょう。
さらに、補助金が支払われた企業は会計検査院の検査を受ける可能性が高いため、必要書類の保管だけでなく、事務処理手続きも正確に行うことが重要です。
7.補助金の不正行為・不正受給が発覚した場合は処罰されるリスクがある
補助金の不正行為・不正受給が発覚した場合、処罰される可能性が高いです。
たとえば、虚偽の申請を行って補助金を受給したり、補助金を目的外に使用したり、補助金の受給額を不当に釣り上げて関係者へ報酬を配賦したりするなどの行為が不正に該当します。
これらの行為が判明した場合、交付決定取消・補助金の返還だけでなく「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、処罰されるリスクがあります。
8.補助金の申請・活用などに迷ったら国が認定する相談機関を活用する
補助金の申請・活用に迷った際は、国が認定する相談機関の活用をオススメします。
国が認定する支援機関は、主に「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」と「よろず支援拠点」です。両者は個人事業主も利用できます。
認定支援機関では、中小企業を支援するうえで、一定以上の専門知識や実務経験がある税理士・公認会計士・金融機関などの支援機関が、相談に応じてくれます。
一方、よろず支援拠点とは、国が設置した無料の経営相談所です。経営上のあらゆる相談に対して何度でも無料で相談を受けられます。
まとめ
補助金の対象者は、受給要件に該当する企業・事業者・個人事業主などです。
補助金にはさまざまな種類があり、対象者・受給要件・申請方法なども異なります。なかには、個人事業主が利用できないものもあるため、事前に受給要件を確認しておきましょう。
また、国だけでなく地方自治体が実施している補助金もありますので、日頃からあらゆる情報をチェックしておくことが大切です。
]]>- 屋号とは、個人事業主が使用する商業上の名前のこと
- 屋号は開業届に必須ではない
- 「○○会社」「○○保険」などは使用できない
- 頻繁に変更すると、顧客や取引先の信頼を失うリスクがある
- 屋号は、ブランディングを確立するのにも役立つ
屋号とは
屋号とは、個人事業主が使用する商業上の名前のことです。
屋号を申請する場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)に記入しましょう。
また、屋号は1つだけでなく、複数取得したり使い分けたりすることもできます。
商号・雅号との違い
屋号と似た言葉に「商号」「雅号」があります。
それぞれの特徴や違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 屋号 | 商号 | 雅号 |
|---|---|---|---|
| 定義 | 個人事業主がビジネスで使用する事務所や商店などの名称 | 法人がビジネスで使用する名称。企業名の正式名称 | 芸術家や文筆家が本名以外につける別名 |
| 対象者 | 個人事業主 | 法人・個人事業主 | 個人(芸術家・著述家・芸能関係者など) |
| 法務局への登記 | 任意(開業届に記載可能) | ・個人事業主は任意 ・法人は必須(法務局で登記が必要) | 不要 |
| 使用制限・制約など | 自由に使用・変更できる | 使用・変更の際に一定の制約がある | 自由に使用・変更できる |
| 銀行口座開設 | 銀行によっては、屋号付き口座(個人口座)が開設できる。法人口座は開設できない | 法人口座名義に企業の商号名を使える | 雅号を屋号(商号)の一部として、口座名義に設定できる |
たとえば、イラストレーターの方が個人事業主の場合、事業名につけるのが屋号で、活動名として使用するのが雅号になります。
また、屋号と商号は、どちらも事業を行う際に事業名・企業名として使用できます。
両者の違いは、登記方法や法的拘束力の範囲です。
開業届に屋号は必要?
個人事業主として開業する際は、税務署に開業届を提出する必要があります。
屋号を使用するタイミングは自分で決められますので、開業届提出後すぐに名乗らないといけないわけではありません。
また、屋号の記載は任意のため、空欄のままでも提出可能です。あとから設定・変更・抹消なども自由にできます。
屋号をつけるメリット・デメリット
開業にあたり、屋号を設定する場合は、開業届の屋号記載欄に記入しましょう。
以下では、屋号をつけることのメリット・デメリットを解説します。
屋号をつけるメリット
以下では、屋号をつけることのメリットを解説します。
- 顧客に事業をアピールできる
屋号をつけることによって、事業イメージが定着しやすくなり、集客や仕事の受注につながります。
- 法人化する際に使っている屋号を商号として引き継げる
法人化の際には、使っている屋号をそのまま商号として引き継げます。
これまで積み上げてきた実績や信用などを失わずに、法人化できるのがメリットです。 - 屋号付き銀行口座を開設できる場合がある
屋号をつけることで、屋号付き銀行口座を開設できる場合があります。
屋号付き銀行口座は、個人名義の口座よりも社会的信頼性が高く、顧客・取引先にも安心して利用してもらえます。
また、口座開設時には屋号記載済みの開業届の控えを提示する必要があります。詳細は銀行ごとに異なるので、都度確認しましょう。
屋号をつけるデメリット
以下では、屋号をつけることのデメリットを解説します。
- 屋号を選定する際に手間がかかる
とくに、法人・企業に商号専用権・商標権を侵害したと見なされた場合、訴えられるリスクがあるため、被らないように注意しましょう。
他の個人事業主と同一名称の屋号をつけることは、法的に問題ありませんが、トラブルに発展するおそれがあるため、重複は避けた方が無難です。 - 屋号を途中で変更する場合は手間がかかる
途中で屋号を変更する場合も手間がかかります。
たとえば、取引先への通知や、金融機関での口座名義変更手続きが必要です。また、名刺を刷りなおしたりホームページを更新したりしなければならず、煩雑な作業が発生する可能性があります。 - 屋号が単一・少数だと事業のイメージが限定されやすい
屋号をつける目的は、自社がどのような事業を行っているかを、顧客・取引先に伝えるためです。
ただし、屋号から想起できない事業を行っている場合、その事業は認識されにくいのがデメリットです。従って、仕事の受注が来ないケースも考えられます。
屋号の手続き・後日申請・変更・抹消方法
以下では、屋号の手続き・後日申請・変更・抹消方法について解説します。
手続き方法
開業届に屋号を記載して税務署に提出すると、屋号の手続き登録が完了します。
開業届に、屋号の記載は義務づけられていないため、決まっていない場合や記載したくない場合は、空欄で提出しても問題ありません。
また、複数事業を行っている場合、それぞれの事業に対して個別に屋号を取得できます。
後日申請・変更方法
屋号は開業届を提出したあとからでも申請できます。また、何度でも変更可能です。
確定申告書・決算書などを提出するときに、新しい屋号をそれらに記載して提出します。
屋号を新たに申請・変更する場合、開業届を再提出する必要はありません。
ただし、変更したことを記録として残しておきたい方は、再度開業届を提出しても問題ありません。
屋号付き口座を開設している場合は、銀行の名義変更手続きで新たな屋号に変更することも忘れないようにしましょう。
抹消方法
使用している屋号を抹消する場合、手続きはとくに必要ありません。屋号をなくしたい場合は、次回の確定申告や決算時に屋号を記入しないようにしましょう。
また、屋号の抹消時に、とくに留意すべき点はありません。
開業届に記載する屋号の決め方
以下では、屋号の決め方について解説します。
使える文字や決める際のポイント
基本的に、屋号は自由に決められます。屋号に使える文字や記号は以下の通りです。
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字
- 数字
- アルファベット
- 6種類の記号(「,」「.」「-」「&」「・」「’」)
屋号を決める際は、わかりやすく、覚えやすいものでかつ、オリジナリティのあるものにしましょう。
屋号を決める際の注意点
以下では、屋号を決める際の注意点について解説します。
使用できない言葉を確認する
屋号には「会社」「法人」などの文字が含められません。理由は、企業以外の者が企業と誤認されるおそれのある名称を使用できないように、法律で定められているためです(会社法・第7条より)。
また、「○○保険」「○○銀行」「○○証券」「○○金庫」なども該当する事業と無関係であれば使用が禁止されています。
さらに、公序良俗に反するような文言(性的・差別的・反社会的な文言)なども避けるべきです。
会社法|e-Gov 法令検索
他の企業名や屋号と同一・類似しているものは避ける
屋号に法的効力はありません。
しかし、トラブルを避けるためにも他の個人事業主と同一または類似の屋号をつけることは避けましょう。
また、つけた屋号が法人・企業に商号専用権・商標権などを侵害したと見なされた場合、訴えられるリスクがあります。
そのため、屋号をつける前に、他社の屋号・商号と重複しないかどうかを調査しておきましょう。
手軽に調査したい場合は、インターネットの活用が有効です。
たとえば、検索エンジンで登録したい屋号を検索したり、法務省のホームページにある「オンライン登記情報検索サービス」を利用したりする方法があります。オンライン登記情報検索サービスは、無料会員登録後に利用可能となります。
以下に、法務省のリンクを載せて置きますので、ご参考になさってください。
法務省|オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について
屋号の変更は慎重に行う
屋号の変更は慎重に行いましょう。
屋号変更に伴い、手間や労力がかかります。
たとえば、名刺の刷りなおし・ホームページの情報更新・銀行口座の名義変更手続きなど、通常業務に加えて、煩雑な処理に追われるリスクがあります。また、顧客や取引先にも混乱や不信感を与えかねません。
屋号の変更回数に制限はありませんが、特別な理由がない限り、なるべく変更は避けましょう。
屋号をうまく活用しよう
屋号を活用してブランディングを確立したり、集客戦略を立てたりすることが大切です。
以下では、屋号の活用方法について解説します。
インパクトのある屋号をつける
屋号を活用したブランディング戦略の1つに、インパクトのある屋号をつけるという方法があります。インパクトのある屋号は、顧客や取引先の記憶に残りやすいという利点があります。
ただし、屋号をつける際はユーザ目線を意識することが大切です。
複雑なもの・読み方が難解なもの・長すぎるものなどは、避けるようにしましょう。
ネット検索で上位に表示されやすい屋号をつける
ネットやSNSから集客したり、検索エンジンで上位表示を目指したりする場合は、シンプルでわかりやすい屋号をつけるように意識しましょう。
また、Webサイトを開設する際には、屋号と同じドメインが取得できるかどうかを確認することも大切です。
ドメインとは、URLの「https://www.◯◯◯.com」の「◯◯◯」に該当する部分です。
ドメインを屋号と同じに設定することで、ホームページの認知度や信頼性が高まります。
屋号と店名は統一する
取引先や顧客の混乱を避けるためにも、屋号と店名は統一しましょう。
また、屋号には事業内容との関連性を持たせることが大切です。
たとえば、「○○ベーカリー」「○○デザイン」などは、一目で何の事業を行っているかわかりやすいため、ブランディングの確立や多くの集客にも期待できます。
まとめ
屋号とは、個人事業主が使用する商業上の名前であり、申請には開業届が必要です。
屋号はブランディングの確立や集客にも役立ち、基本的には、自由に決められます。
一方「○○会社」「○○保険」など企業を想起させる単語は使用できないため、注意が必要です。
また、頻繁に変更すると、煩雑な手続きが増えたり、顧客・取引先の信頼を失ったりするリスクがあります。
屋号をつけるかどうか迷った際には、メリット・デメリットを考慮して自分に合った方を選択しましょう。
]]>- 自由業とは、時間や雇用関係に縛られず専門的スキルを活かす仕事のこと
- 案件ごとの受注や業務委託を結ぶなど、さまざまな就業スタイルがある
- 自由業は働く時間や仕事量を自分で決められる
- 収入が不安定で社会保障に乏しいといったリスクもある
- 自由業を始める前に資金や営業ツールの準備をしておこう
自由業とは?
自由業とは、時間や雇用関係に縛られず、専門的なスキルを活かして活動する職業のことです。案件ごとに受注したり業務委託契約を結んだりと、就業スタイルはさまざまで、自由度の高い働き方が可能なところが特徴です。
自由業と自営業・フリーランス・フリーターとの違い
自由業に類似する語句との違いについて、詳しく解説します。
自営業
税務上では自由業と自営業の違いは明確に定義されていません。
自営業とは自ら事業を営むことで、一般的には店舗やオフィスを構えて商売をする職業を指すケースが多いです。
主な自営業には以下のようなものがあります。
- 飲食業
- 生鮮食品販売
- 生花店
- 士業(税理士や弁護士など)
- 製菓や加工食品製造
- 不動産業
フリーランス
フリーランスとは、案件ごとに業務委託契約を結ぶ働き方です。自由業と同意語として使われることもあります。
フリーランスという言葉には、自由業と同じ意味で使われる場合と、業務委託契約による働き方を指す場合の、2つの使い方があります。どちらの意味かは使用シーンによって異なりますので注意しましょう。
フリーター
フリーターは、フリーアルバイターの略語です。就職せずにパート・アルバイトで生計を立てている人を指します。
フリーターは企業に雇われて働いており、雇用関係が成立している点が自由業と異なります。
自由業の職種例10選
自由業にはどのような職種があるのでしょうか。
具体的な職種名と、職務内容を解説します。
イラストレーター
イラストを描く仕事です。雑誌や書籍の表紙、WEB媒体、広告、ゲームのキャラクターデザインなど、活躍の場は多岐にわたります。SNSでの発信で注目を集め、個展を開いたりオリジナルグッズを販売したりするイラストレーターもいます。
Webデザイナー
Webサイトやアプリケーション、オウンドメディアなどのレイアウトや仕様を担当する仕事です。一般的にはHTML言語やCSS、WordPressなどを用いて構築します。インターネット環境があれば、在宅勤務やリモートワークも可能です。
ITエンジニア
フリーランスのITエンジニアも、インターネット環境があればどこでも仕事が可能な自由業のひとつです。初めのうちは企業に勤めてスキルを磨き、その後独立するITエンジニアも多いです。
カメラマン
人物や風景などを撮影する仕事です。フリーランスで活動するカメラマンも多く、フォトスタジオや結婚式場、大自然など活動場所も幅広いです。撮影以外では、写真素材サイトで写真を販売して収入を得るカメラマンもいます。
配信者
YouTuberやVTuber、ストリーマーといった配信者は、近年新しく生まれた職業のひとつです。動画視聴時に流れる広告や視聴者からの投げ銭によって、主な収益を得ています。そのほか、企業からの依頼で商品やサービスの紹介をする案件や、イベント出演で報酬を得ることもあります。
投資家
株式や不動産、FX、ビットコインなどに投資をして収入を得る職業です。大損をしてしまうリスクと隣り合わせのため、経済についての知識や時流の変化を捉える力が求められます。
少額から行える投資もありますが、まとまった収入を得るためにはある程度の元手が必要です。
小説家・ライター
小説家や劇作家、コラムニスト、脚本家など、文章を執筆する仕事です。近年ではパソコンやスマホを用いて執筆作業を行う人も多く、時間や場所を選ばず作業ができます。
アーティスト
絵画や造形作品などの芸術分野で活躍する職業です。
バンドや歌手といった音楽家や芸能人を含める場合もあります。
ECサイト運営者
ネットショップで、物品を販売して収益を得る仕事です。実店舗が無く、取引はオンライン上で完結するため、自由度の高い仕事といえるでしょう。
競合他社も多いため、トレンドを察知し、効果的に集客するスキルが求められます。
漫画家
漫画を描いて生計を立てる仕事で、主な収入は原稿料や単行本の印税です。
漫画雑誌や漫画アプリへの掲載のほか、企業広告や教材で漫画作品を描くケースも増えてきました。人気作品になると、グッズ化やメディアミックス化することもあります。
自由業のメリット
ここでは自由業のメリットについて解説します。
企業に所属する会社員と比較して自由度が高いとされる自由業ですが、具体的には何が自由なのか、どのようなメリットがあるのかを詳しく説明します。
業務時間や業務量の調整が自由にできる
自由業は、通勤時間や業務量を自身の裁量で自由に調整できるところが特徴です。企業と雇用関係を結んでいる場合は勤務時間が決められていることが多いですが、自由業の場合は成果物の納品がクリアできていれば、働くタイミングは自由です。体調や家庭の都合に合わせて業務を調整できるのは、自由業の大きなメリットといえるでしょう。
通勤の必要が必要がない
会社員の多くはオフィスへ通勤する必要がありますが、自由業の場合は働く場所を自由に決められます。近年はオンライン上で作業を進めたり連絡を取ったりでき、自宅でリモートワークを行う人も増えています。満員電車に乗って通勤する必要がなく、自分の好きな場所で仕事ができるのも自由業のメリットです。
幅広いスキルが習得できる
自由業は自分で仕事を取ってくる必要があるため、営業や交渉力といった本業以外のビジネススキルも総合的に磨かれます。
また、競合他社と差別化して独自性を出すためには、新たな分野へ挑戦し、仕事の幅を広げることも大切です。仕事を通じてさまざまなスキルを習得して、ステップアップすることができるでしょう。
高額収入を得られる可能性がある
自由業は完全成果主義で、報酬額も自分で自由に設定できます。仕事の出来によっては高額報酬を見込めるところは、魅力的な部分でしょう。会社員の場合、業務をたくさんこなしても給料に反映されるとは限りませんが、自由業なら努力した分だけ収入につながります。
定年がない
会社員の多くは、60歳もしくは65歳で定年となります。
厚生労働省のデータによると平均寿命は男性が78.79年、女性が85.75年です。定年からその後の人生が長いため、定年後の生活費に不安を抱える人も少なくありません。自身のスキルを活かして何歳になっても仕事が続けられるところは、自由業の強みといえるでしょう。
参考:厚生労働省|2 都道府県別にみた平均余命
自由業のデメリット
自由業にはさまざまなメリットがある反面、リスクやデメリットも存在します。詳しく見ていきましょう。
収入が不安定
自由業では、仕事が途切れてしまい収入が0円となるケースも珍しくありません。仕事を始めたばかりの頃はクライアントと信頼関係が築けておらず、希望よりも低い報酬額で受注せざるを得ない場面も出てくるでしょう。社会情勢によって仕事が激減するリスクも考えられます。
営業や経理の知識も求められる
成果物を仕上げて納品する以外にも、営業や経理の業務も発生します。会社員であれば専門の部署が手続きを進めてくれますが、自由業の場合は自身で処理しなければなりません。
前年の収入と経費をまとめて、2~3月の間に所定の税務署へ確定申告を行う必要があります。営業として自分を売り込み、仕事を受注するスキルも求められます。そのほか、仕事の進捗管理や体調管理もすべて自分で行わなければなりません。
社会保障に乏しい
企業の会社員と比べると、自由業は社会保障の点で不安があります。
雇用保険が適用外となるため、失業手当の支給はありません。また、年金も国民年金のみのため、将来受けとれる額が少なくなります。国民年金基金やiDeCoなどへの加入といった対策を講じる必要があるでしょう。
すべて自分が責任を負う必要がある
会社員がミスをした場合、ミスをした当人以外に上司や企業も責任を取るのが一般的です。
しかし自由業の場合、すべて自分で責任を負わなければいけません。たとえば確定申告を怠ってしまうと、無申告加算税などのさまざまなペナルティを課せられることがあります。
自由業を始める際のポイント
自由業を始める際のポイントについて解説します。
収入面や福利厚生などで安定している会社員と比べると、自由業はリスク管理が重要です。気を付けたいポイントを詳しく見ていきましょう。
まとまった資金を確保する
自由業の収入は自身の手腕にかかっています。駆け出しの頃は仕事が思うように取れず、収入につながらないことも多いでしょう。
仕事が軌道に乗ってからも油断はできません。コロナ禍で多くの業界が事業閉鎖に追い込まれたように、時流の変化によって収入が激減してしまうリスクもあります。
生活面の不安を軽減するためにも、数か月間無収入でも乗り切れる資金を確保しておきたいところです。
営業ツールを用意する
自由業では自身で営業を行う必要があります。営業のきっかけとなる名刺やダイレクトメールなどのツールは、事前に準備しておくことが望ましいです。
認知度向上につながる、SNSのアカウントやホームページの開設も検討しましょう。
銀行口座や電話番号、メールアドレスは、プライベートのものとは別に業務用のものを用意しておくとよいでしょう。
競合他社と差別化できるスキルを磨く
誰にでもできる仕事は、報酬も安価になりがちです。収入アップを目指すのであれば、競合他社と差別化できるようスキルを磨くことが重要です。競合が少ない分野に進出するのも選択肢のひとつでしょう。
自由業は資格不要で始められる仕事も多いです。しかし資格を持っていると、どのようなスキルを有しているのか客観的な判断がしやすく、クライアントの信頼獲得や安心感につながるでしょう。自由業を始める前に資格の取得を目指すと、仕事の幅を広げられるかもしれません。
業界の将来性を調べる
現在安定している業界でも、5年後、10年後も同じように稼げるとは限りません。
新たに参入するのであれば、業界研究を念入りに行うことが大切です。
まとめ
自由業の強みは、働く時間や業務量を自分の裁量で自由に決められるところです。自身のスキルを磨いて、仕事の幅を広げたり高額収入を目指したりすることもできます。一方で、収入が不安定になりがちで、仕事上のすべての責任を負う必要があるといったリスクも存在します。自由業で働く前に、資金や営業ツールといった準備をしっかりしておくのが成功の鍵です。
]]>- 両者とも業務委託契約を結ぶのが一般的
- 両者ともライフスタイルに合わせた働き方ができる
- 個人事業主として働くには、開業届が必要
- 事業所得を得ている場合、開業届の提出は義務
- 税金・社会保障はどちらも同一
フリーランス・個人事業主は雇用契約と異なり、勤務時間・勤務場所などが自由に選べます。両者共に発注者との間で業務委託契約を結ぶのが一般的です。
また、業務委託契約では、業務の完遂または成果物の完成をもって報酬が支払われます。
フリーランスと個人事業主の違い
フリーランスと個人事業主の違いは、税務署に開業届を提出しているか否かです。
以下では、フリーランスと個人事業主の違いをご説明します。
フリーランスとは
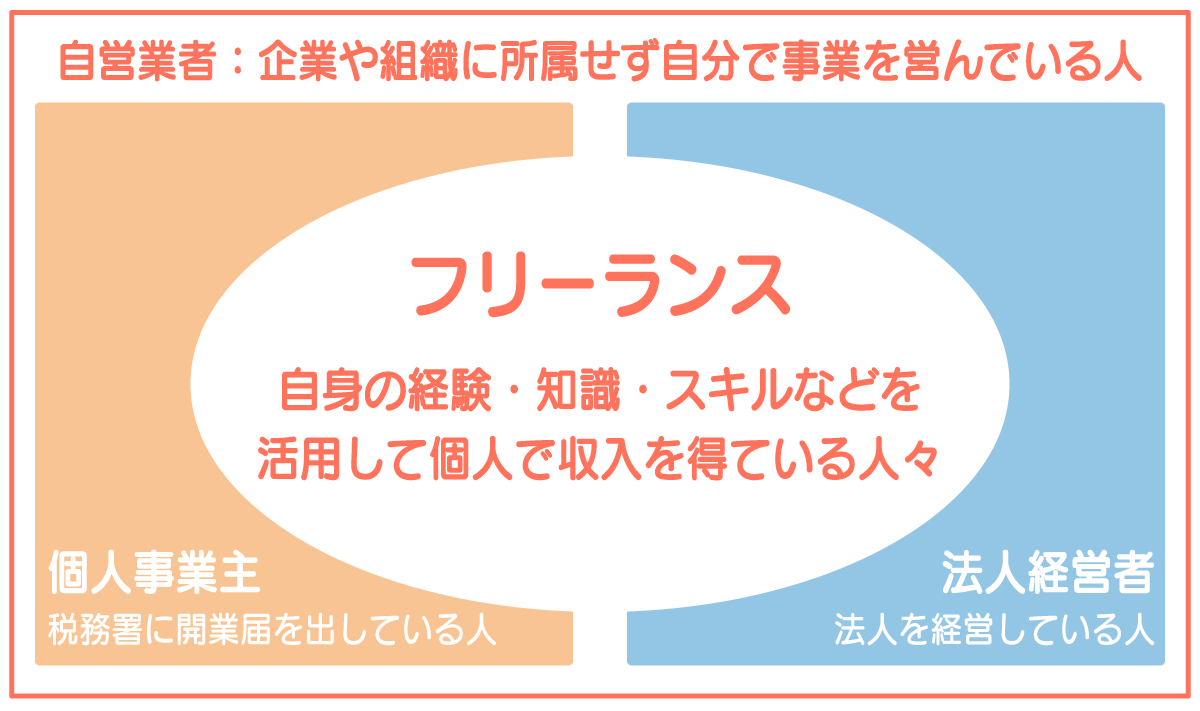
フリーランスとは、働き方の1つです。自身の経験・知識・スキルなどを活用して個人で収入を得ている方々を指します。
フリーランスは、税務署に開業届を提出しなくてもなれますが、公的な支援を受けるには届出が必要です。
個人事業主とは
個人事業主とは、税法上、法人格をもたない事業主のことです。具体的には、税務署に開業届(個人事業の開廃業届出書)を提出して働いているフリーランスを指します。
個人事業主の事業の定義とは、反復性・継続性・独立性のすべてを満たす必要があります。また、法人格を取得していないことが条件です。
従って、個人事業主は事業を繰り返し継続して行う個人とも言い換えられます。
ただし、従業員やアルバイトは雇えますので、一人で事業を行うとは限りません。
開業届を出すメリット
事業所得を得ている場合、原則として開業届の提出は義務付けられています。
未提出でも罰則はとくにありませんが、開業届を提出することで受けられる恩恵もあります。
以下に、メリットをご紹介します。
- 青色申告特別控除が受けられる(節税になる)
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、対象者の給与を経費にできる
- 最長3年間赤字を繰り越せる(繰り越した損失で利益を相殺して、課税所得を減らせる)
- 屋号(法人でいう企業名・店舗名)を設定できる
- 小規模企業共済に加入できる(掛金に応じて共済金が受け取れる)
反面、開業届提出後は、帳簿の記載義務・保存義務が発生します。
フリーランスと個人事業主のどちらで働くか迷った場合は、自分に合った方を選択しましょう。
フリーランス・個人事業主になるメリットとデメリット
以下では、フリーランス・個人事業主になるメリット・デメリットを解説します。
フリーランス・個人事業主になるメリット
以下に、フリーランス・個人事業主になるメリットを5つご紹介します。
- ライフスタイルに合わせた働き方ができる
- スキルや能力に見合った報酬が得られる
- 幅広い経験を積むことでスキルアップできる
- 定年がない
- 開業届を提出することで節税対策になる
フリーランス・個人事業主になるデメリット
以下に、フリーランス・個人事業主になるデメリットを5つご紹介します。
- 収入が不安定
- 交渉・契約・クレーム対応など、すべての雑務を1人で行う必要がある
- スキルや能力が低いと案件を受注できない
- ローンやクレジットカードの審査が通りにくい場合もある
- 年末調整がないため、確定申告が必要
フリーランス・個人事業主の税金・社会保障
フリーランス・個人事業主の税金・社会保障はどちらも同じです。
以下では、フリーランス・個人事業主の税金と社会保障について解説します。
支払う税金・受け取れる年金
フリーランス・個人事業主が支払う税金は、主に「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」の4つです。
また、フリーランス・個人事業主は、国民年金のみに加入します。厚生年金の加入者よりも将来受け取れる年金額が少ないため、あわせて他の年金制度への加入をオススメします。
社会保障
前職で、協会けんぽや組合保険などに加入していた方は、国民健康保険への切り替えが必要です。
退職後も任意継続できる健康保険はありますが、保険料は自己負担となるため、注意しましょう。
フリーランス・個人事業主が受けられる補助金・助成金
フリーランス・個人事業主が受けられる補助金・助成金はどちらも同一です。
以下では、フリーランス・個人事業主が受けられる補助金や助成金について解説します。
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)とは、販路開拓や生産性向上に取り組む小規模事業者等を、支援する制度です。自社の経営を見直したり、持続的な経営に向けた経営計画を作成したりした事業者が利用できます。
補助対象となる経費は以下の11項目です。
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 設備処分費
- 委託・外注費
持続化補助金は、汎用性が高く目的外の使用ができるモノ(車・自転車・文房具・パソコンなど)は、補助対象外ですので注意が必要です。
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)とは、国内外のニーズに対応した新事業を創出するための制度です。新サービスや新商品の開発、試作品開発、生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等の補助として支給されます。
補助対象事業枠には、「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠(海外事業を実施している企業)」があります。
製品・サービス高付加価値化枠は従業員数に応じて補助上限額が決まり、グローバル枠の補助上限額は、一律3,000万円です。
自治体による補助金
自治体ごとに支給形態や内容が異なる補助金や、社会情勢や災害などにより急遽支給される補助金があります。
たとえば、新型コロナウイルスが蔓延した2020年には、事業資金の資金繰り支援として「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」が施行されました。
こちらは、業況が悪化したフリーランス・個人事業主に対して、日本政策金融公庫・沖縄公庫などが、無利子・無担保で融資を行う制度です。
雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、経済的な理由で事業縮小や雇用調整が必要となった事業主に対して、費用を助成する制度です。主に、雇用維持を目的とした休業・教育訓練・出向に要した費用などが助成対象となります。
従業員を雇っているフリーランス・個人事業主も、要件に当てはまれば雇用調整助成金を受給できます。
受給対象者は、雇用保険に加盟している事業者や、事業活動を示す指標(売上高・生産量など)の3か月間の月平均値が、前年同期と比べて10%以上減少している事業者などです。
フリーランス・個人事業主を目指す前に知っておくこと
フリーランス・個人事業主として働く際には、自身を守るための法律を知っておきましょう。
日本フリーランスリーグ(フリーランスの課題を調査する当事者団体)の調査によると、約3人に1人が「クライアントから正当な報酬を得ていない」と回答しています。
他にも、契約内容が曖昧であったり、報酬の未払いや遅れがあったりするなどの問題が生じていることがわかりました。
こうした背景から、2024年11月に「フリーランス新法」が設立されました。
フリーランス新法とは、フリーランスで働く人々を保護する法律のことです。トラブルに巻き込まれた際は、以下のサイトから相談窓口につながりますので、ご参考になさってください。
厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営|フリーランス・トラブル110番
偽装フリーランス問題について知っておく
近年では、偽装フリーランスが問題視されています。基本的に、フリーランスは労働基準法の適用外です。
にもかかわらず、フリーランスが実質労働者と同じ雇用形態で働かされる事例が発生しています。これを、偽装フリーランスといいます。
偽装フリーランスの問題点は、フリーランスが労働者に近い働き方をしている割に、労働基準法が適用されないことです。企業から補償が出なかったり、負担を強いられたりする事例も発生しています。
自分の働き方に疑問を感じた場合は、厚生労働省のリーフレットにある「働き方の自己診断チェックリスト」をご参考になさってください。
厚生労働省|フリーランスとして働く皆さまへ あなたの働き方をチェックしてみましょう
まとめ
個人事業主はフリーランスの一部です。フリーランスが税務署に開業届を提出することで個人事業主となり、公的な支援が受けられます。
また、「フリーランス新法」が施行されたことにより、今後は働きやすくなる見通しです。
とはいえ、偽装フリーランスや報酬の未払い問題など、すぐには解決できない課題もあります。
フリーランス・個人事業主のメリット・デメリットを知ったうえで、どのような働き方を選ぶかを考えましょう。
]]>- 業務委託とは、雇用関係のない企業から業務を受託して報酬を得る働き方のこと
- 民法上の「請負契約」「委任契約」「準委任契約」を総称して「業務委託契約」と呼ぶ
- 働き方の自由度が高く、スキルの熟練度を伸ばしやすい点が、業務委託のメリット
- 営業・業務・事務・会計のすべてに自身で責任を負う必要がある
- トラブル回避のため、業務委託契約書の項目は細かくチェックすることが重要
近年では副業や兼業、フリーランスなど、企業に所属する働き方以外の選択肢が増えています。選択肢の一つとして注目が集まる業務委託とはどういった働き方なのか、正社員や派遣社員と比べて何が違うのか、疑問点も多いでしょう。
この記事では業務委託とは何か、他の契約形態と何が違うのか、メリット・デメリットと併せてご紹介します。
業務委託とは
業務委託とは、雇用関係のない企業から業務の委託を受け、特定の業務や成果物を提供することで報酬が支払われる働き方です。法的に業務委託という名称の契約は存在しませんが、民法上には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」という三種の契約があり、これらを総称して「業務委託契約」と呼ばれています。
業務委託の種類
業務委託は、前述したように三つの種類があります。「請負契約」は、成果物の完成を約束し、その対価に報酬を約束する契約です。「委任契約」と「準委任契約」は、どちらも業務の履行自体に報酬が支払われる契約です。ただし、委託された業務が法律行為を伴う場合は「委任契約」と、法律行為を伴わない場合は「準委任契約」と呼ばれます。
| 委託される内容 | 特徴 | 主な職種例 | |
|---|---|---|---|
| 請負契約 | 仕事の完成を約束し、その対価に報酬を約束する契約 | 完成した成果物に不備がないか、問題なく納品されたかどうかのみ問われる | ・Webデザイナー ・ライター ・プログラマー |
| 委任契約 | 業務の履行自体に報酬が支払われる契約で、法律行為を委託する契約 | 法律行為を扱う業務の遂行のみ求められる | ・弁護士 ・税理士 ・社会保険労務士 |
| 準委任契約 | 業務の履行自体に報酬が支払われる契約で、法律行為以外の業務を委託する契約 | 法律行為を扱わない業務の遂行を求められる | ・ITエンジニア ・コンサルタント ・ドライバー |
業務委託と他の契約形態との違い
業務委託は「業務委託契約」を取り交わす契約の一つで、企業に雇用される関係ではありません。一方、雇用契約や派遣契約は、企業に雇用される関係です。
ここからは、他の契約形態との違いについて、個人事業主・フリーランスも併せてご紹介していきます。
雇用契約・派遣契約との違い
業務委託は企業側と雇用関係になく、成果物の納品または成果を上げることで報酬を得ます。業務時間や順番・方法などの指示を受けない点が特徴です。雇用契約とは雇用関係の有無に、派遣契約とは業務指示の有無や報酬の評価対象に大きな違いがあります。
| 特徴 | 業務委託との違い | |
|---|---|---|
| 雇用契約 | 企業と結んだ雇用契約に従って業務にあたり、報酬を得る | 業務委託は、企業と雇用関係にならない |
| 派遣契約 | 人材派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で業務に就く 業務時間で報酬が支払われるが、業務指示や社内ルールの遵守を求められる | 業務委託は、業務時間や順番・方法などの指示を受けず、成果物の納品または成果を上げることで報酬を得る |
個人事業主・フリーランスとの違い
業務委託は、雇用契約を結ばずに業務の全体または一部を、フリーランスや外部企業へ委託する契約方法のことです。働く時間や業務方法は受託者の裁量に一任されており、成果物の完成度または上げた成果の結果にのみ責任を負います。個人事業主とは契約形態や責任範囲に、フリーランスとは定義されている働き方に違いがあります。
| 特徴 | 業務委託との違い | |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 個人として事業を営む、法的には自営業者のことを指す 提供する商品やサービスに対して全面的な責任を負う | 業務委託は、成果物の完成度または上げた成果にのみ責任を負う |
| フリーランス | 働き方の定義・概念の名称 企業に属さず、個人で案件・業務を請け負う働き方と定義されている | 業務委託は、業務の全体または一部をフリーランスや外部企業へ委託する際の契約方法のことを指す |
業務委託のメリット・デメリット
業務委託を受けて働く場合、さまざまなメリット・デメリットが存在します。ここからは、メリット・デメリットを併せて五つ、ご紹介します。
働き方の自由度が高い
業務委託は、企業側から業務時間や進める順番・方法などを指示されることがないため、受託した業務内容に合わせて、自分に適した時間や場所を選んで働くことが可能です。勤務地や勤務時間などの定めがある正社員と比べると、働き方の自由度が高いと言えます。受託した成果物を完成・提出が問題なくできれば、家庭や趣味と両立しやすいでしょう。
得意分野のスキルが伸ばせる
業務委託では自身で仕事を探すため、受注する案件を得意分野や専門スキルの活かせる仕事のみに絞ることが可能です。スキルの熟練度を上げたい、興味のある分野に挑戦したいなど、自身が理想とする働き方に合わせて契約先を選択できます。
収入が不安定になりやすい
業務委託で収入を得るには営業活動を行って案件を獲得し、業務を完遂させて報酬を受け取るまでの流れを、すべて自分でこなさなければなりません。営業がうまくいかずに契約が十分に取れなかった場合は、収入激減や収入ゼロになる可能性があり、この点は業務委託の大きなデメリットです。
経験やスキルをうまくアピールするためには、得意分野や受注したい案件に適したスキルがあるかを整理し、売り込み方を工夫していく必要があるでしょう。
雇用保険や労災保険に加入できない
業務委託で働く場合、企業と雇用関係になく、委託・受託の関係性です。雇用保険や労災保険は雇用契約を結んだ者を対象に適用される法律であるため、雇用契約を結ばない業務委託には適用されず、加入できません。また、業務委託で働くと個人事業主に該当するため、労働基準法も適用外となります。
営業・事務・会計などを自力で行う必要がある
前述したように、業務委託で収入を得るには営業から報酬を受け取るまでの流れすべてを自分でこなす必要があります。その他、契約関連の事務作業や、保険料・確定申告などの税務処理も自分で行わなければなりません。自身の裁量で自由に仕事を進められるメリットがある反面、企業に雇用される場合よりも責任が増大することを念頭に置きましょう。
業務委託で働く際の注意点
業務委託で働く場合に必要となるのは、契約書の内容や提出物・申請ごとの確認です。それぞれに注意しておくべきポイントを見ていきましょう。
業務委託契約書の内容をチェックしよう
業務委託のトラブルを避けるためには、業務委託契約書の内容が合意通りに明記されているかを確認してから、業務を受託することが重要です。チェックしておくべき項目は以下の七点です。
- 委託の業務範囲
- 求められる成果物の内容
- 契約期間と更新の有無
- 契約解除の条件
- 報酬額や支払方法
- 成果物の権利
- 業務の秘密保持義務
上記の項目がチェックできないまま契約を取り交わしてしまうと、成果物を納品しても報酬が得られない、といったトラブルが起きやすくなります。事前に十分な合意形成を行うことはもちろん、契約書の内容に間違いがないかチェックを怠らないことが、契約時の重要なポイントです。
開業届を提出して確定申告(青色申告)に備えておこう
業務委託で働いている場合、以下の条件に当てはまる人は自身で確定申告を行う必要があります。
- 年間の「事業所得」が48万円を超える
- 年間の「雑所得」が20万円を超える
事業所得と雑所得に明確な線引きはありません。一般的な括りとして、事業所得は「長期的に継続収入・利益が得られること」とされ、雑所得は「単発的な原稿料や講師依頼の謝礼金など事業と言いがたい収入・利益のこと」とされています。
また、業務委託で働く際には、所得税法第229条に定められている開業届を提出する必要があります。提出期限もありますので、忘れずに提出を行いましょう。
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
参照元:所得税法 | e-Gov 法令検索
開業届が提出できていれば、確定申告時に「青色申告」を届け出て「青色申告特別控除(最大65万円までの特別控除)」を受けられるようになります。開業届を提出していない場合は控除が受けられないため、本業として業務委託で働く人は、開業届の提出忘れに注意しましょう。
まとめ
業務委託とは、雇用関係がない企業から業務を受け、成果物の納品・提供で報酬を得る働き方です。法的には業務委託という契約は存在せず、請負契約・委任契約・準委任契約の三種を総称した「業務委託契約」が名称の由来です。企業からの指揮や命令を受けないため、働き方の自由度が高いことや得意分野を活かせるメリットがある反面、収入が不安定で労働基準法の適用外といったデメリットもあります。営業はもちろん事務・会計なども自身で行わなければならないため、契約書の確認や開業届の提出などをしっかりと行い、トラブルを避けることが重要です。
]]>- フリーランスとは、組織に所属せず独自の手段で収入を得る働き方
- メリットは、時間、働く場所、取引相手などを自分で選べ、生涯現役で働ける
- デメリットは、確定申告や時間管理、営業などすべて自分で行う必要がある
- フリーランスを始めるためには、準備と案件の獲得が重要
- 成功のポイントは、資金調達、セルフマネジメント、人脈、営業と、自分の技術向上である
フリーランスという働き方を選択する方が増えています。フリーランスとは、そもそもどのような働き方なのか?また、始めるための準備や案件の獲得方法は何か?などの疑問にお答えします。さらに成功の秘けつまで解説しますので、ぜひお役立てください。
フリーランスとは、どのような働き方?
フリーランスとは、特定の企業と雇用契約を結ばずに、専門スキルによって収入を獲得する働き方をいいます。たとえば企業と業務委託契約を結び案件やプロジェクトに参加したり、個人向けに作成した商品やサービスを提供したりします。さまざまな取引相手に対して、スキルや技術、成果物を提供することで収入につなげる働き方です。
| フリーランスに向いている職種 | |
|---|---|
| エンジニア | ソフトウエア開発やWeb開発など、プロジェクト単位での仕事が多く、リモートでの作業も可能 |
| デザイナー | グラフィックデザインなど、成果物ベースでの契約が多く、多様なクライアントとの柔軟な働き方が可能 |
| SNS運用代行 | SNSへの集客やスタッフ募集、商品やサービスの認知を行う。リモートでの作業も可能 |
| 記帳代行 | 領収書や会計ソフトへの入力作業といった経理事務の一部を担当します。短時間の勤務が可能 |
| ライター/編集者 | 記事作成や編集の仕事は、場所を選ばずにできるため、フリーランスに最適 |
| 動画編集 | 映像素材の収集、編集、プレビュー、納品までオンラインで取引可能。多様な業界からのニーズがある |
フリーランスのメリット
フリーランスは比較的始めやすい働き方です。しかし継続的に収入を得るためには、メリットデメリットを理解する必要があります。はじめにメリットから紹介します。
- 時間や働く場所を自由に選べる
- 取引先や仕事相手も選択できる
- 生涯現役で働ける
時間や働く場所を自由に選べる
大きなメリットは自由度が高いことです。たとえば介護や育児、副業などで時間に制限があるときも、短時間や限定された時間帯、深夜のみなど自分の都合に合わせた時間帯で働くことが可能です。また、自宅やコワーキングスペース、旅行先など、職種によっては働く場所も自分で選べます。
取引先や仕事相手を選択できる
次に、取引先や仕事相手を自分で選べる点もメリットといえます。フリーランスは自分のスキルや技術に共感し、必要としてくれる相手と仕事ができます。ただし、駆け出しのうちは仕事を選ぶ余裕がないこともあり、信頼できる取引先を見極める目を養うことが重要です。
また、組織の一員としてではなく個人として仕事をするため、組織内の人間関係の影響を受けにくいというメリットもあります。
生涯現役で働ける
フリーランスには定年がなく、生涯現役で働くことができます。そのためには、安定した収入を得られるように案件を確保する構造が必要です。さらに自分の健康を維持して働き続けられることも重要になります。フリーランスを始める際、しっかりとした業務計画と将来設計を行いましょう。
フリーランスのデメリット
フリーランスを始めたら多くのやるべきことがあります。詳しく見ていきましょう。
- 確定申告を自分で行う
- タイムマネジメントが必要になる
- 営業を自分で行う必要がある
確定申告を自分で行う
会社員のように給与から源泉徴収され年末調整で所得税が確定するわけではないので、自分で確定申告を行う必要があります。そのためには、日々の収入支出の記帳と管理や、領収書等の帳票整理などが必要です。控除などを上手に活用するために確定申告の方法を理解することも大切なため、自分ができない場合は、専門家や家族に協力をお願いしましょう。
タイムマネジメントが必要になる
フリーランスが信用を得るためには、効率よく業務を行い、期日を守る必要があります。当然のことと思うかもしれませんが、フリーランスは時間が自由だと錯覚してしまい、時間管理の重要性を失念してしまう場合があります。相手があることなので、信用を無くすと仕事が得られない可能性が生ずると覚えておきましょう。
営業を自分で行う必要がある
継続的に案件を獲得していくためには、営業活動は欠かせません。フリーランスは実務だけでなく、金銭管理、顧客管理、健康管理、人脈管理などすべてを自分で決断し実行しなければならず、その中でも案件獲得につながる営業活動は重要な業務です。良好な人間関係の構築が継続的な収入につながることを認識しましょう。
フリーランスを始めるための準備
フリーランスを始めるときの準備について紹介します。開業から提出までに期限のあるものが多いので注意が必要です。
- 税務署へ開業届を提出する
- 銀行で屋号つき口座を開設する
- 市町村の役所で国民健康保険および国民年金への加入手続きをする
- 税務署へ青色申告承認申請書を提出する
開業届を提出する
開業から1か月以内に、税務署から「個人事業の開業・廃業等届出書」を取り寄せ、記入後提出しましょう。開業届を提出しなくても罰則はありませんが、青色申告の申請や屋号つき口座の開設にも必要となりますので、社会的な信用を得るためにも開業届の提出をおススメします。
屋号つき口座を開設する
業務専用の口座を開設しましょう。屋号があると社会的信用度があがりますので、屋号つき口座の開設がおススメです。また、業務の収支とプライベートの収支を区別するためにも、業務専用の口座開設は有効といえます。
健康保険や年金関係の手続きをする
フリーランスになると、国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要です。会社員の場合は社会保険と厚生年金に加入しているため、退職後すぐに離職票や年金手帳を準備して切り替えを行いましょう。また、厚生年金は半額企業負担でしたが、国民年金は全額自己負担になるうえ、将来受け取れる年金額も減る可能性があります。個人年金保険に加入するなどの対策が必要になるかもしれません。
青色申告承認申請書を提出する
確定申告で、開業初年度から青色申告を行うためには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出して、承認を受ける必要があります。「青色申告承認申請書」は、申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。ただし、その年の1月16日以降、新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2か月以内に提出してください。状況に応じて申請書の提出期限が異なるため、注意が必要です。
青色申告では、最大65万円の特別控除や専従者給与の経費計上、赤字の3年間繰り越し計上などのメリットがあり、大きな節税効果があります。
フリーランスの仕事探し、案件の獲得方法
フリーランスになって安定した収入を得るための、案件の獲得方法を紹介します。
前職からの委託や知人の紹介を受ける
これまでに培った技術やスキルを活かすためには、実力を理解している前職から委託を受ける方法が有効です。この場合は、今まで関わってきた業務の一部を委託してもらう場合が多いため、慣れた仕事を継続できます。または、築いた人間関係を活用して紹介してもらう方法です。いつ誰との関わりが、ビジネスチャンスにつながるかわかりませんので、良好な人間関係を築くことがポイントになります。
ブログやホームページ、SNSを活用する
フリーランスを始めたらブログやホームページを開設し、どのような仕事やサービスを提供できるのかを、広くアピールしましょう。消費者は、企業や個人に関わらず、購入先の安全性について確認することがあるため、ホームページや口コミで信用度を上げることも重要です。
また、SNSの活用も案件獲得に貢献してくれます。たとえば、毎日の仕事の成果を撮影してアップするなど、アイデアと工夫次第で不特定多数へのアピールが可能になります。
※成果物の公開について:契約上、制限や守秘義務などが規定されている場合、契約違反になる可能性があるため、注意が必要です。
クラウドソーシングに登録する
グラウドソーシングでは、自分のスキルや資格、技術を登録することで、それを必要とする企業から業務の紹介や委託を受けられます。さまざまな職種に対応しているため、自分の得意分野をアピールしましょう。たとえば、エンジニアならポートフォリオを作成したり、参加したプロジェクトの成果を提示したりすることで、企業側の理解を深め案件獲得につながりやすくなります。
フリーランスエージェントを利用する
アピールできる資格や技術がないときは、フリーランス向けのエージェントへの登録がおススメです。キャリアアドバイザーとの面談で、所持スキルやできることを確認し、向いている案件を紹介してくれます。自分の要望やこれまでの経験を正しく伝えることで、効率的に仕事探しができます。
フリーランスで成功するポイント
フリーランスを継続して成功させるためには、いくつかのポイントがあります。詳しく見ていきましょう。
始める前に資金を蓄える
フリーランスを始めてすぐに収入が見込めるとは限りません。数か月は無収入でも生活できるだけの資金を蓄えておきましょう。金銭的に余裕がなくなると冷静な判断ができなくなります。焦らずに継続できる業務体制を構築するためには、余裕のある資金調達が重要といえます。
セルフマネジメントを重視する
フリーランスを続けるためには、自分の能力を最大限に発揮したパフォーマンスを維持し、向上する必要があります。たとえば、食事や睡眠を十分にとって心と体を安定させることで、よいパフォーマンスが発揮できます。さらに日々のスケジュールを管理できていれば、今やるべきことが明確になり、不要なストレスを抱えることも減るでしょう。正しく自己管理を行うことが重要といえます。
スキルや経験値を高めておく
未経験歓迎の案件も多数ありますが、フリーランスとして成功するためには、スキルや経験、資格をもっている方が案件を獲得しやすくなります。そのため、フリーランスを始める前に、スキルや経験値を高めたり、資格を取得したりして準備をしましょう。資格によっては、案件獲得のみならず報酬に差が生じる場合もあります。フリーランスの仕事をしながらの資格取得も視野に入れて、常に向上心をもつことが大切です。
人脈を活かした営業力を活用する
フリーランス成功のために、もっとも重要なことが人脈と営業力といえます。高いスキルや経験をもって、案件を完遂できるだけでは将来への不安を生じるため、人脈を活かした営業力が必要となります。前職からの知人や取引先に案件の紹介や委託してもらうことも一案です。また、新規で人脈を広げるために、講演会や地元の活動に参加するのもよいでしょう。人との関わりの中で案件を獲得していくことが重要になります。
自己責任で行う意識をもつ
フリーランスを始めると、すべてを自分で考え行動する必要があります。好きな時間に好きな仕事ができる自由な働き方ですが、自分で時間を決め、仕事の獲得から実務まで完遂しなければ収入につなげることは難しくなります。上手くいかないときも、自分で解決の方法を考えたり専門家に相談したりしながら、やるべきことを選択しなければなりません。メリットばかりに目を向けず、地に足を付けた行動と覚悟が肝要になります。
まとめ
比較的始めるのが簡単なフリーランスも、準備とすべきことが多数あります。自分はどのような働き方をしたいのか、フリーランスとしてどのような仕事がしたいのかを明確にしましょう。思い付きで行動するのではなく、念入りな準備から始めてください。
フリーランスを始める際は、この記事を参考にして、継続的に収入を得られるフリーランスを目指してください。
- TOEICスコアは国際的な英語力の指標
- 履歴書に書けるTOEICスコアは600点がベースライン
- 業務で求められる英語レベルは企業や業界によって異なる
- 業務で英語を使う企業では700点以上のスコアが求められる
- スコアアップには自分のレベルに合わせた計画的な学習が効果的
グローバル化が進む昨今、業務で英語を使う企業は国際的な英語力の指標であるTOEICスコアに注目しています。そのためTOEICのスコアは就活生にとって大きなアピールであると同時に、目標に向かって努力できるポテンシャルを示す重要な要素です。本稿では就活に必要なTOEICスコアや業界別の目安とともに、学習のコツを解説します。
TOEICとは
TOEICは「Test of English for International Communication」の略称です。オフィスや日常生活での英語によるコミュニケーション能力を、テストによって公平公正に評価する世界共通の基準として広く知られています。
本稿では受験者数が最も多い「TOEIC Listening & Reading Tests」について解説します。このテストはリスニングとリーディングで構成され、合計990点満点のスコアで評価されるため、正確な英語力の把握や今後の目標設定が可能です。
TOEIC Listening & Reading Testの試験内容
TOEICの試験は、リスニングとリーディングによる合計2時間で200問、990点満点の問題をマークシートで解答します。問題は英文のみの構成で、英文和訳・和文英訳はありません。以下にテスト問題の構成をまとめました。
リスニングセクション
・会話やナレーションを聞き、設問に回答する
・約45分/100問/配点495点
| Part1 | 写真描写問題 | 6問 |
| Part2 | 応答問題 | 25問 |
| Part3 | 会話問題 | 39問 |
| Part4 | 説明文問題 | 30問 |
リーディングセクション
・問題を読んで設問に解答する
・約75分/100問/配点495点
| Part5 | 短文穴埋め問題 | 30問 |
| Part6 | 長文穴埋め問題 | 16問 |
| Part7 | 1つの文書を読み、設問に答える | 29問 |
| 複数の文書を読み、設問に答える | 25問 |
TOEICのスコアと英語レベルの目安
ここまではTOEICの概要について解説しました。この項目ではTOEICのスコアから見る英語レベルについて解説します。
スコアから大別する英語レベル
日本でTOEICテストを実施する国際ビジネスコミュニケーション協会では、TOEICスコアと英語によるコミュニケーション能力を、大きくA~Eのレベルに分けて評価しています。
| TOEICスコア | 英語レベル | 評価(ガイドライン) |
|---|---|---|
| 860~ | A | Non-Nativeとして十分なコミュニケーションができる |
| 730~ | B | どのような状況でも適切なコミュニケーションができる素地を備えている |
| 470~ | C | 日常生活のニーズを充足し、限定された範囲内では業務上のコミュニケーションができる |
| 220~ | D | 通常会話で最低限のコミュニケーションができる |
| 220未満 | E | コミュニケーションができるまでにはいたっていない |
参考|一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 PROFICIENCY SCALE(PDF)
より詳細に見る英語レベル
以下の表ではより詳細に、100点刻みでTOEICのスコアと英語レベルについて書き出しました。
| TOEICスコア | 英語レベル | 評価(ガイドライン) |
|---|---|---|
| 900点~ | 上級・上 | 英語で書かれた高度な専門書を理解できる、ネイティブの議論を理解できる |
| 800点~ | 上級・下 | Webから英語で書かれた情報の収集、同僚との議論を理解できる |
| 700点~ | 中級・上 | 英語で書かれた社内文書や仕事の進め方について理解できる |
| 600点~ | 中級・下 | 英語のメモが理解できる、ゆっくりとしたスピードで話された場合の道順の説明が理解できる |
| 500点~ | 初級・上 | 英語で簡単な質問が理解できる |
| 500点未満 | 初級・下 | 英語で書かれた看板を見て理解できる |
スコアは何点から履歴書に書けるのか
一般的に企業が求めるTOEICスコアの目安は600点以上とされています。そのため基本的な英語力を証明する600点が履歴書に書くベースラインと覚えておきましょう。しかし英語を業務で使用する職種や外資系企業では、730点以上を求められることが多く、英語を頻繁に使用する業務の現場では、800点以上のスコアが求められることもあります。そのような現場では入社後も努力の継続が必要です。志望先の英語レベルは企業研究で見極めましょう。
企業・業界が求めるTOEICスコア
前項ではTOEICのスコアからわかる英語レベルについて解説しました。この項目ではビジネスで英語を活用する企業や業界から求められるTOEICスコアについて解説します。
企業・業界別のスコア基準
一口に英語の活用といっても、その程度は企業や業界によってさまざまです。そこで以下の表に、求められるTOEICスコアの基準を業界別にまとめました。
| IT業界 | 技術文書の理解や海外プロジェクトのために、700点以上が目安 |
| 製造業・商社 | 海外との取引が多いため、730点以上が望ましい |
| 金融業界 | 国際業務がある場合、750点以上を求められることが多い |
| 観光業 | 国際線の客室乗務員は750点以上が求められる |
| 教育業界 | 英語教師や語学スクール講師は、850点以上が求められることもある |
スコアアップのコツ
この項目ではTOEICのスコアアップを目指したおすすめの勉強方法について紹介します。現在のTOEICスコアに照らし合わせて参考にしてください。
リスニングとリーディングのバランスを考えた学習が大切
TOEICはリスニングとリーディングが半分ずつの構成で評価されるため、双方のバランスを考えて学習することが大切です。また本番の体制に合わせた公式問題集を活用し、実際の試験形式に慣れることも効果的です。
計画的に学べるように自分の実力を把握する
TOEICのスコアを上げるためには実力に合わせた計画的な学習が有効です。まずは模擬試験などで現在の実力(現在のスコア)を把握しましょう。自分の実力を把握したら、学習できる時間と実力に合わせた学習計画の立案をおすすめします。
目標スコアを設定して学習する
TOEICは目標スコアによって取るべき対策が大きく異なるため、効率よく学習するためには目標スコアを定めるとよいでしょう。実際にTOEIC関連では参考書をはじめ、点数別に英語レベルを分けた対策課題が掲げられています。
効果的な対策方法
この項目ではTOEICの試験対策について紹介します。得意分野の見極めや、苦手分野を克服するための参考にしてください。
単語力を強化する
TOEICで高得点を取るためには、単語力が必須となります。テストの頻出単語を中心に、ビジネスや日常会話に対応できる単語力を身につけましょう。そのための勉強法としては単語帳の活用をはじめ、移動や休憩などの隙間時間に暗記する方法がおすすめです。TOEICの頻出単語は多くの参考書や教材がありますので、自分に合ったものを選ぶとよいでしょう。
リスニング力を強化する
TOEICのリスニングセクションでは、アメリカ・カナダ・イギリス・オーストラリア・ニュージーランド、5か国の話者が登場します。話者による発音やイントネーションの違いに苦戦しないよう、毎日英語に触れる習慣をつけ、リスニング力を向上させましょう。話者が異なる生きた英語を聞くには、YouTubeや英語ニュースを活用するのがおすすめです。
リーディング力を向上させる
TOEICのリーディングセクションでは、約75分で文章の穴埋めや長文読解といった、合計100問の問題を解かねばなりません。このセクションで求められる能力には以下の3点があります。
| 速読力 | 速解きに必要 |
| 文法知識 | 穴埋め、読解に必要 |
| 長文の理解力 | 読解や複数文章の比較に必要 |
これらの能力を向上させるために、英語の新聞や雑誌を読むことで、語彙力と読解力を鍛えましょう。また時間を計測しながらの学習や速読の練習も時短効果があり、おすすめです。
模擬試験を活用する
時間配分や問題形式に慣れるためにも模擬試験を活用しましょう。模擬試験にはTOEIC公式サイトのサンプル問題や、無料の学習サイトが活用できます。ただし無料の学習サイトは更新されていない情報もありますので、常に最新情報を確認するように心がけてください。
まとめ
TOEICのスコアは、就職活動において英語力とポテンシャルをアピールできる重要な要素です。ただし業務で扱う英語のレベルは業界や企業によって異なりますので、志望する企業が求める英語レベルは企業研究でしっかり見極めてください。
計画的な学習と効果的な対策で、志望する業界や職種に応じたスコアを目指し、就活を有利に進めましょう。本稿がチャレンジの一助となることを願っています。
]]>- 面接への不安や、内定獲得できない焦り、多忙な就活生活でストレスが蓄積される
- 軽い運動習慣を取り入れたり、友人や家族に就活相談したり、趣味の時間を積極的に設けるとよい
- 就活ストレスが悪化すると、就活うつになる恐れがある
- 就活ストレスが悪化する前に、思い切って就活自体を休む期間を設けることも大切
就活を進めていく上で、周りと比べて内定が決まらない焦りや、面接でうまく自分をアピールできるのかという不安を感じた経験は誰しもあることでしょう。このような就活ストレスを上手に解消し、心身ともに健康な状態で就活を継続するための方法を紹介します。
就活ストレスの主な原因とは
就活ストレスの主な原因は、以下の3つです。
- 面接への不安
- 内定が出ないプレッシャー
- 多忙な就活生活に追われるストレス
1.面接への不安
面接対策を十分にしたつもりが、想定外の質問へ対応できなかったときや、アピールの仕方がよかったのか振り返り不安に陥るなど、面接への不安を感じる就活生は多いです。面接は過度な緊張状態を生じるため、ストレスの大きな原因といえます。面接によるストレスは、あなただけが感じているわけではありません。多くの就活生が同じように、不安や緊張を抱えながら面接に挑んでいます。完璧な受け答えを目指すのではなく、リラックスして挑むと本来の力が発揮できるでしょう。
2.内定が出ないプレッシャー
周りの友人達は次々と内定を獲得しているのに、自分だけが内定を得られていない状況は、焦りを感じ不安に陥ることで大きなストレスになります。自分は、社会に必要とされていないのではないかと、自己否定してしまうかもしれません。就活は、自分と相性のいい会社と出会うための活動です。内定が出ないのは、まだその出会いのタイミングが来ていないだけと考えましょう。うまくいかない日があっても、頑張ってきたあなたの価値がなくなるわけではありません。
3.多忙な就活生活に追われるストレス
就活中は、応募書類の作成や企業ごとの選考対策に追われて、プライベートな時間がとれず、ストレスが溜まりやすい状況といえます。就活は人生の重大なターニングポイントなので、時間も労力も注ぎ込みたい気持ちになるでしょう。しかし、ストレスを溜め込みすぎると、意欲が低下し何から着手すべきか迷ってしまうなど、かえって効率が悪くなってしまう可能性があります。就活に集中する日と就活から完全に離れる日を設定して、メリハリをつけた就活生活を心がけましょう。
簡単にできる就活ストレス解消法
簡単に就活ストレスを解消できる方法は以下の通りです。
- 運動をして気分転換を図る
- 友人や家族に相談してみる
- 趣味の時間を積極的に作る
- 思い切って一度就活自体を休む
運動をして気分転換を図る
応募書類作成や選考対策の合間にできる軽いストレッチや、近所でのランニングやウォーキングだけでも効果的な気分転換になります。また、ラジオ体操は、全身の筋肉を効率よく動かす動きが組み込まれているので、デスクワークの合間のリフレッシュに最適です。このような軽い運動を取り入れることで、就活ストレスの軽減が期待できます。
友人や家族に相談してみる
親しい友人や家族に、自分が抱えている就活での悩みを相談して、客観的な視点からアドバイスをもらうこともおすすめです。オンラインでの相談も便利ですが、可能であれば直接会って、悩みを声に出して相談をするほうがストレス解消になるでしょう。また、自分では気づかなかった新たな解決策が見つかる可能性もあります。
趣味の時間を積極的に作る
周りの内定報告に焦り、就活以外に時間を割くことに対して罪悪感を覚える方もいるでしょう。しかし、就活漬けの生活では、就活ストレスで心も疲弊してしまいます。計画的にToDoリストを作成し、就活に取り組む日と趣味に没頭する日を明確に分け、メリハリをつけて就活を進めていくことをおすすめします。趣味の時間で心に栄養を補充しておくと、就活を継続する活力となるでしょう。
思い切って一度就活自体を休む
就活を進めていくことに対して強いストレスを感じる状況ならば、思い切って一度就活自体を休むこともおすすめします。就活ストレスが悪化してしまうと、就活うつになる恐れがあり大変危険です。就活は周りと比べるものではなく、自分が納得できる進路選択が非常に重要です。そのため就活ストレスが深刻な場合は、一度就活自体をお休みして、リフレッシュする期間を積極的に作りましょう。
就活ストレスを相談できる窓口
就活ストレスを友人や家族以外に相談する場合の相談窓口を紹介します。
いざというときに、以下の機関の存在を知っておくだけでも安心です。
- ハローワークの新卒応援窓口
- 大学のキャリアセンター
- 就活エージェント
ハローワークの新卒応援窓口
ハローワークには、新卒の学生を対象とした無料相談窓口が全国に56か所設置されています。面接対策や応募書類の作成支援に加え、就職に役立つセミナーも開催されています。また、就活に関する悩みや不安も個別支援で気軽に相談することができ、個々に寄り添った支援が受けられます。
参考:厚生労働省|新卒応援ハローワークの所在地・連絡先
大学のキャリアセンター
各大学に設置されているキャリアセンターでは、個々の適性に合った就職先の選び方から選考対策まで、幅広い支援を行っています。また、OB・OGの就職先情報や詳細な採用情報も閲覧可能で、就活に役立つ情報が豊富にそろっています。
就活エージェント
就活エージェントは、求人紹介のみならず、求人探しから選考対策、メンタルケアまで総合的な支援を受けられます。自宅からオンラインで気軽に相談でき、担当制を採用しているエージェントも多いので、内定獲得まで一貫したサポートを受けられる心強い味方となるでしょう。
まとめ
就活を進める中で感じるストレスは誰にでも共通する経験です。軽い運動習慣をつけて気分転換をしたり、友人や家族に相談をしたり、趣味の時間を確保するなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。就活が苦しい場合は一度休養を取ることも選択肢の一つです。自分が納得できる就職先を見つけることが重要ですので、焦らず自分のペースで就活を進めていきましょう。
]]>- メタバースは仮想現実(VR)や拡張現実(AR)を利用した仮想空間で活動する技術
- メタバース就活は、仮想空間内で説明会や見学、インターンが可能
- メタバース就活はZ世代に適した採用方法としても期待されている
- 参加には専用アプリやデバイスなど、事前準備が重要
ビジネスだけでなく、就活の場でも活用され始めた「メタバース」とは何でしょうか。比較的新しい技術であるため「メタバース就活」と言われても、イメージできない人が多いかもしれません。
この記事では、メタバースを活用した採用イベント例や、メタバース就活のメリットと注意点についてご紹介します。
そもそもメタバースとは
メタバースとは、仮想現実(VR)や拡張現実(AR)、3DCGなどの技術によって構築された仮想空間で、さまざまな活動を行える技術です。自分の分身となるアバターを作成して、仮想空間に入ります。国内でイメージしやすい事例としては、自身のアバターを仮想空間で自由に活動させられる『マインクラフト』や『フォートナイト』といったゲームが近いでしょう。
就職・採用活動でメタバースが注目される理由は?
メタバースに注目が集まる前、コロナ禍の影響により、対面での就職・採用活動を避けるため、多くの企業が「オンライン就活」を取り入れていました。多くのメリットがある反面、雰囲気やイメージがつかみにくいというデメリットがありました。メリットを活かしつつ、デメリットを減らす方法として、メタバースを活用した仮想空間での就職・採用活動に注目が集まるようになったのです。
メタバースを活用した就職・採用活動では、仮想空間で説明会やオフィス見学、インターンシップなどの体験が可能です。アバターでのコミュニケーションや質疑応答が行え、企業は多様な方法で自社の魅力をアピールできるため、オンライン開催と比べて「雰囲気やイメージがつかみやすい」といった利点があります。
メタバースを活用した採用イベント例5つ
メタバースを活用して行われる就活・採用イベントには、どのようなものがあるのでしょうか。イベントの大まかな内容と併せて、5つご紹介します。
1.企業説明会
企業説明会は、参加者側にとって企業の情報を知る機会であり、企業側にとっては自社をPRする機会として重要な採用イベントです。従来の対面式では、参加者側が参加するためにイベント会場まで足を運ぶ必要があり、遠征費や時間などの制限や負担が発生していました。
メタバースで企業説明会を行う場合、インターネット上の仮想空間で開催するため、場所を問わず全国どこからでも参加が可能です。メタバース空間を常にオープンにしておくと、参加者側が自由なタイミングで企業の情報を確認できるため、より深く企業研究を進められ、ミスマッチを減らせるメリットがあります。
2.合同説明会
合同説明会は、さまざまな業界・業種の企業が一堂に会し、それぞれにブースを設けて、企業PRや事業・業務内容などの情報を広めるイベントです。従来通りの開催方法では、企業側に場所と時間の制約が、参加者側は遠征・宿泊費用などの負担が発生していました。
メタバースで合同説明会を行う場合も、各企業のブースがメタバース空間内に設置されます。参加者は仮想空間内でアバターを操作して、多くの企業を自由に見て回れるため回遊性が高く、応募者側が企業理解を深めやすい点が大きなメリットと言えるでしょう。動画・資料を用いた説明はもちろん、アバターを介したコミュニケーションや質疑応答も行えるため、多様な方法で企業の魅力をアピールできます。
3.オフィス見学
従来通りのオフィス見学では、参加者は企業の予定に合わせて現地に向かう必要がありました。内部を自由に見学することや日程調整も難しく、見学制限を設けたりイベント回数を増やしたりと、さまざまな調整が必要でした。
メタバースでオフィス見学を行う場合、実際のオフィスの様子をメタバース空間内に再現することで、参加者が好きなところから安全にイベントへ参加できます。アバターを用いることで対面のようなコミュニケーションも取れるため、オフィスや現場のリアルな雰囲気を伝えることが可能です。また、メタバースを常設できれば、就活生や転職希望者が時間の制約なしに、好きなタイミングでオフィス見学できるメリットが生まれます。
4.インターンシップ
「実際の業務を体験すること」を目的とするインターンシップは、人員選出や日程・業務調整などが必要であり、開催までには多くの時間とコストがかかります。近年ではインターンシップがそのまま内定に結びつく場合もあるため、インターンシップに参加できるかどうかは、就活生にとって重要なポイントです。
メタバースでインターンシップを行う場合は、オフィスや工場などの実際に働く場所を再現することで、参加者はその場で業務に就いているような、没入感や臨場感を体感できます。メタバース空間であれば、人数制限や天候に左右される心配はありません。たとえ危険を伴う現場の業務であっても、安全にインターンシップを体験できるでしょう。
5.面接・実務型選考
従来の面接は対面式が多く、企業内または企業が借りた会場などを使用して行われており、応募者と企業側の双方にコストや時間的制限などが発生していました。近年では、コロナ禍の影響もありZoomなどのビデオチャットツールを使用したオンライン面接も増えてきましたが、伝えられる情報量に限界があります。
一方、メタバース上での面接は、アバターを用いたアクションや反応で、多くの情報を伝えながらコミュニケーションを取ることが可能です。どこからでもアクセス可能な点はオンライン面接と同じですが、話しかけるタイミングを画面越しに伺う必要がないため、積極的なコミュニケーションが取りやすい点は大きなメリットです。より現実に近い形で再現することで企業内・現場内の雰囲気を伝えられ、相互理解を深めることにもつなげられるでしょう。
メタバース就活のメリット
メタバース就活は、就活生や転職希望者にとって、どのようなメリットがあるのでしょうか。大きなメリットを4つご紹介します。
参加する心理的負担を軽減できる
メタバース就活ではアバターを用いてコミュニケーションを取るため、企業の採用担当者との対話時も、実際に顔を出す必要がありません。対面やオンラインの就活と比べて、容姿や見た目などに左右されずに自己アピールができるため、心理的負担を軽減できます。
遠方からでも安全に参加できる
対面で就活を行う場合、遠方に住む就活生や転職希望者は現地に足を運ぶ必要があるため、時間・金銭・体力面の負担が大きな課題でした。しかし、メタバースであれば全国どこからでも参加が可能であり、時これらの負担を軽減できます。また、公共交通機関の遅延や不慮の事態に巻き込まれる心配もないため、遠方からでも安心安全に参加できるでしょう。
企業の雰囲気・イメージをつかめる
メタバース空間を活用する採用イベントは、企業のオフィスや働く環境などを再現したブースを活用して、説明会やインターンシップなどを行います。セキュリティや安全性の観点から実際には見学できない部署もリアルに再現されることもあり、雰囲気やイメージをより具体的に体感できるでしょう。
オンラインでは企業内や現場などを画面越しの限られた範囲しか見られず、雰囲気やイメージがつかみにくく不安材料になりやすい傾向にあります。メタバースのイベントであれば企業のリアルさを体感しやすく、入社前後のギャップを減らすことにもつなげられます。
オンラインと比べて臨場感がある
オンライン説明会の場合、企業からの一方的な説明を「ただ聴いている」状態が長く続くため、メモを取ることを意識していても、説明会に参加している意識は薄くなりやすいでしょう。
メタバースの説明会は、アバターを介してメタバース空間内を見て回ることが可能です。まるで自分がその場にいるかのような臨場感・没入感が体感できるため、企業の採用担当者の動きを把握したり、他の参加者とコミュニケーションが取れたりと、多くのメリットが得られます。自発的に参加している意識をもって、説明会に参加できるでしょう。
メタバース就活の注意点
メタバース就活には、さまざまなメリットがある一方で留意すべき点があります。メタバース就活を活用する際の注意点をご紹介します。
対面とは違ったアピールが必要
メタバース就活は、アバターを介した仮想空間でのコミュニケーションが基本です。アバターでのアクションや反応の伺い方、自身の個性をアバターに反映させる方法など、対面やオンラインとは異なったアピールが必要になります。対面でのアピールを苦手とする人は、アバターの用意も含めて、事前準備がより重要と言えるでしょう。
ただし、顔出し無しの匿名で参加もできるため、気軽に参加してみることがポイントです。見学イベントの参加から始めて、どのようなアピールができそうか、確認してみるのも有効な手段です。
参加には対応アプリや対応デバイスが必要
メタバース就活への参加には、専用アプリケーションのインストールや、対応デバイスの用意が必要です。就活イベントは多くの場合、事前に必要なツールが公開されています。不明な点がある場合は、大学のキャリアセンターか、主催企業に直接問い合わせてみるといいでしょう。
まとめ
メタバースはVRやAR技術を用いて構築された仮想空間で、アバターを通じてさまざまな活動が可能です。就職・採用活動では、コロナ禍の影響で普及したオンライン式や対面式で行う採用イベント以外の、新しい選択肢の一つとしてメタバース就活が注目されています。企業説明会やオフィス見学、インターンシップなどがメタバース上で行われ、参加者はアバターを使って自由に動いてコミュニケーションを取ることが可能です。オンライン形式と比べて、企業の雰囲気やイメージをつかみやすいとされています。ただし、参加するためには対応アプリやデバイスが必要であり、対面とは異なるアピールが必要となるため、事前の準備が重要と言えるでしょう。
]]>- 企業分析とは、企業が行っている事業や働き方などを調べて分析すること
- 企業分析には、フレームワークの使用がオススメ
- 分析前には、企業のホームページで情報収集を行う
- 分析結果を基に「入社後のビジョン」を思い描く
- 分析後は自分の適性に合うかどうかを考える
企業分析とは?
企業分析とは、企業の事業内容・業務内容・働き方などを調べて分析することです。
企業分析を行う際は、自分のキャリアプランに近い企業かどうかという視点から分析しましょう。
以下に、企業分析のメリットを3点まとめました。
- 各企業の強みや魅力を比較できる
- 志望動機が明確になる
- 自分と合わない企業は避けられる(ミスマッチを防ぐ)
企業分析にはフレームワークがオススメ
企業分析の際には、フレームワークの使用をオススメします。
フレームワークとは、問題解決や分析をするときに使う、考え方や手順を示したものを指します。フレームワークを用いると、誰もが同じ手順で企業分析を行えるため効率的です。
企業分析でフレームワークを使う際は以下の4つのポイントを押さえましょう。
- 企業分析の目的を決める
- 企業分析の期間を決める
- 信頼性の高い情報を集める
- 自分の考え・判断に基づいて分析する
企業分析で使えるフレームワーク
以下では、企業分析の際に使えるフレームワークをご紹介します。
3C分析
3C分析(スリーシー分析・サンシー分析)とは、「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合他社)」「Company(自社)」から構成されるフレームワークのことです。3つのCを書き出すことで、志望企業の将来性や価値観などが見えてきます。
3C分析の目的は、自社(ここでは志望企業)が事業を成功させるために重要な要素・条件などを見つけることです。
以下では、「大手カフェチェーン店に就職したい学生」という設定で、3C分析を行いました。
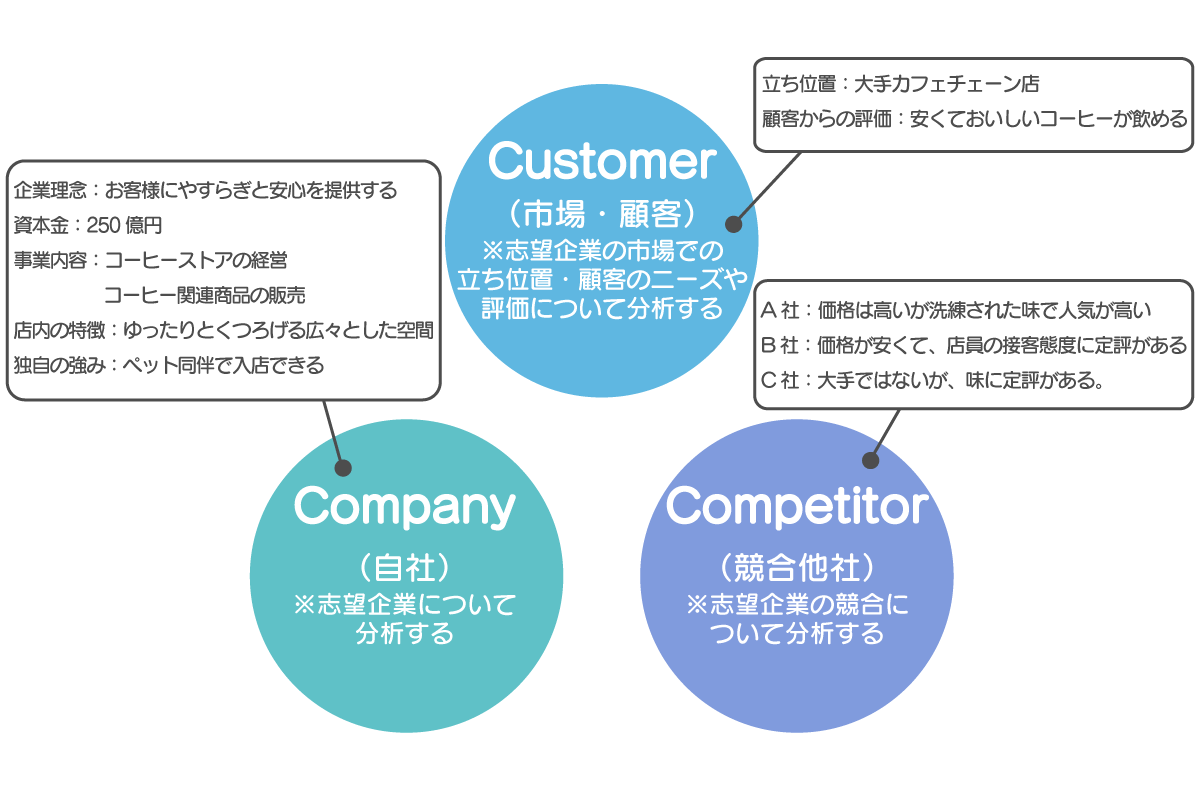
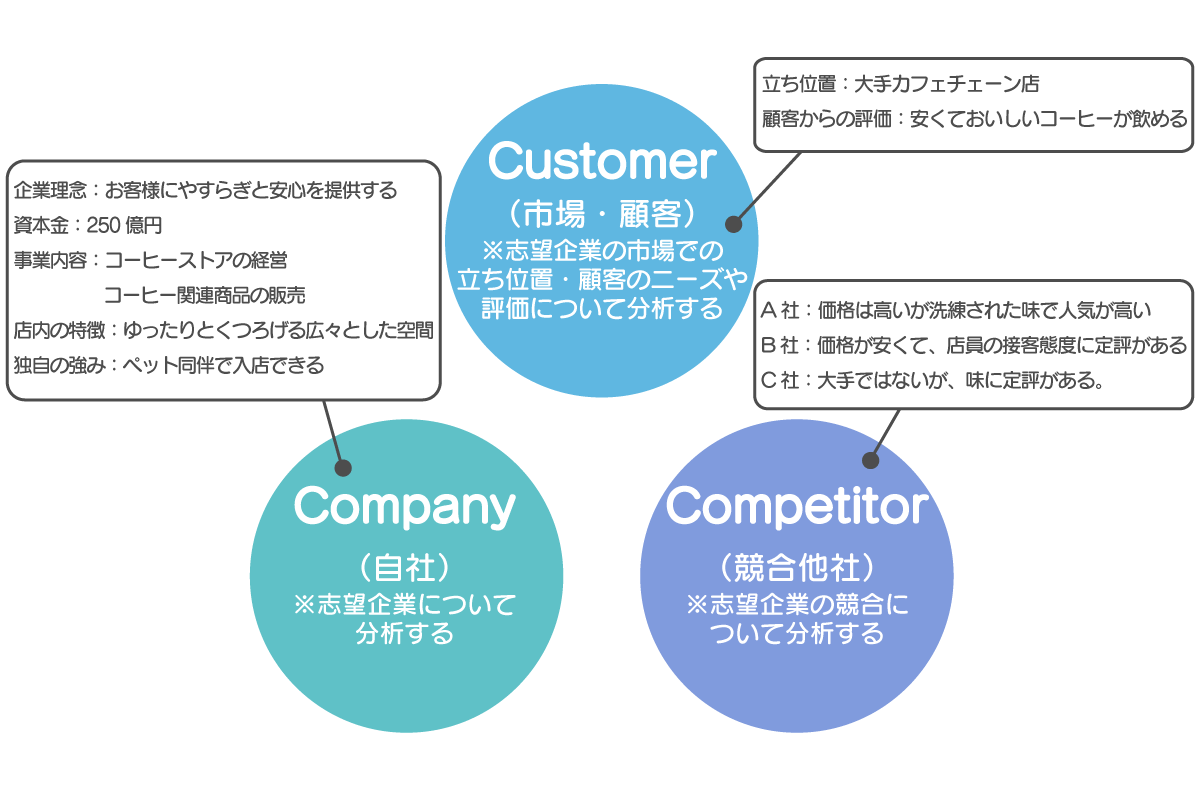
※クリックで画像を拡大できます
PEST分析
PEST分析(ペスト分析)とは、外部環境が、業界・自社にどのような影響を与えるか予測・把握するための手法です。主に、「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の4つの視点から分析します。
以下では、「大手カフェチェーン店に就職したい学生」という設定で、PEST分析を行いました。
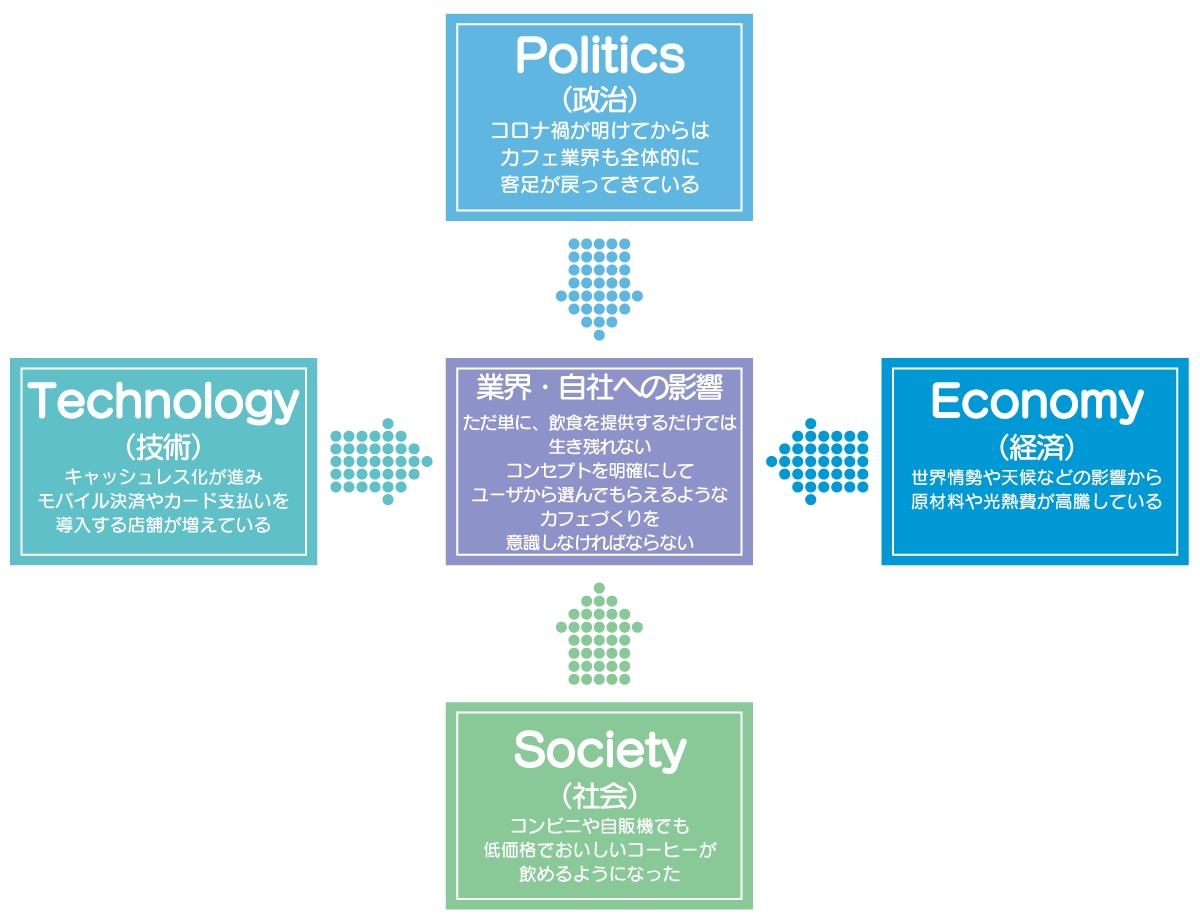
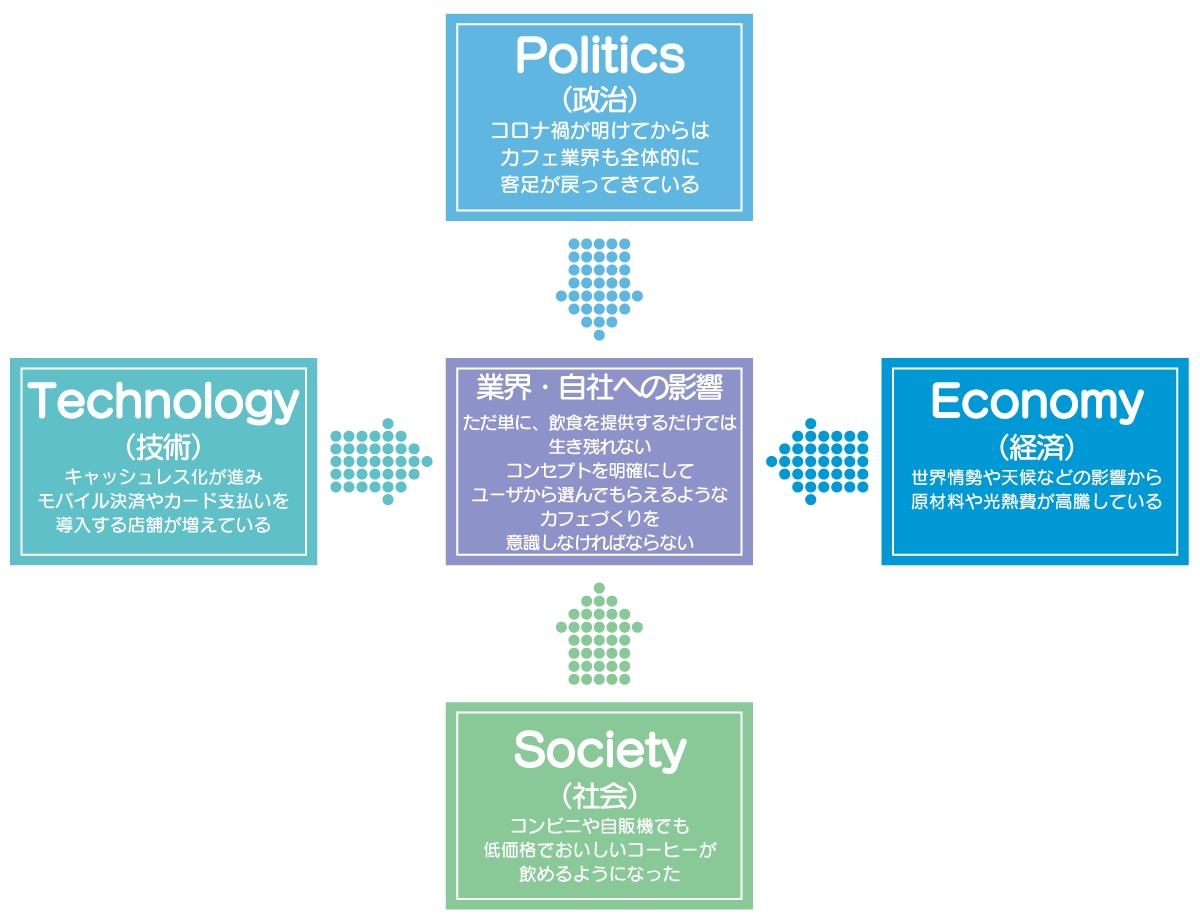
※クリックで画像を拡大できます
SWOT分析・クロスSWOT分析
SWOT分析(スウォット分析)とは、自社の内部環境と外部環境を「強み(長所)」「弱み(短所)」「機会(チャンス)」「脅威(ピンチ)」の4要素に分けて分析する手法のことです。
また、クロスSWOT分析とは、SWOT分析で洗い出した4要素をそれぞれ掛け合わせたフレームワークのことで、「強みの活かし方」「弱みの克服方法」などを見つけていきます。
SWOT分析・クロスSWOT分析は単体で行うよりも、3C分析・PEST分析などと組み合わせると、より効果的です。
以下では、「大手カフェチェーン店に就職したい学生」という設定で、SWOT分析とクロスSWOT分析を行いました。
SWOT分析
| プラス要因 | マイナス要因 | |
|---|---|---|
| 内部環境 | Strength (強み・長所) | Weakness (弱み・短所) |
| ・国内でも知名度が高い | ・人材不足による回転率の悪さ | |
| ・安定した財務基盤 | ・高価格設定 | |
| ・海外に市場を拡大 | ・販路が少ない | |
| 外部環境 | Opportunity (機会・チャンス) | Threat (脅威・ピンチ) |
| ・ペットブーム | ・円安による物価の高騰 | |
| ・SNSの普及 | ・コンビニや自販機の方が早く安く購入できる | |
| ・デジタル化推進 | ・感染症による外出の自粛 |
クロスSWOT分析
| Strength (強み・長所) | Weakness (弱み・短所) | |
|---|---|---|
| Opportunity (機会・チャンス) | 機会×強み | 機会×弱み |
| ・知名度を活かした成長機会の増加 | ・ITを導入して、業務の効率化を図る | |
| ・知名度を活かして有名なペットユーチューバーやインフルエンサーなどとのコラボ商品を販売する | ・SNSフォロワーにクーポン券を配り来店を促す | |
| ・安定した財務基盤があるため、それを元手に事業拡大への投資を行う | ・通販による販路の拡大 | |
| Threat (脅威・ピンチ) | 脅威×強み | 脅威×弱み |
| ・知名度を活かして、ペットボトル飲料を販売する | ・規格外となった食材を有効活用して、販売価格を下げる | |
| ・円安の影響から国内ではなく、市場拡大した海外(ドル高)に輸出して利益を出す | ・コンビニとの共同開発によりコストを削減できるほか、販路を拡大できる | |
| ・感染症対策やそれに伴う施策に資金を投入して、来店しやすいように工夫する | ・感染症対策により宅配事業を始める。デリバリー業者に委託することで、人材不足問題を解消できる |
企業分析を行う前に調べておくこと
以下では、企業分析を行う前に調べておくことについて解説します。
企業概要
企業概要とは、「企業の全体像・事業の概要を記載したもの」です。企業ごとの特色やイメージを知るためにも、チェックしておきましょう。
一般的に、企業概要には以下の10項目が記されています。各企業のホームページ・登記簿謄本などから確認しておきましょう。
- 企業名
- 設立年月日
- 代表者名
- 資本金
- 売上高
- 事業内容
- 従業員数
- 関連会社
- 取引先銀行
- 本社・支店の所在地
事業内容・ビジネスモデル
企業概要のなかでも、「事業内容」の項目はよく読んでおきましょう。
昨今は、複数事業を展開している企業が増えていますので、主力事業以外にも目を通しておきましょう。
一方、ビジネスモデルとは、「企業が収益を得る仕組み」のことです。ビジネスモデルを分析する際は、「企業が誰に対して何をどのように提供しているのか」を図に起こすとわかりやすいです。
ビジネスモデルから、企業の業績や将来性が見えてくると、働き方や必要スキルなどが予測できます。
経営理念・ビジョン・労働環境
企業の「経営理念」「ビジョン」「労働環境」なども重要です。
たとえば、「経営理念」「ビジョン」からは企業風土・価値観などが推察できます。
また、評価制度・年間休日日数・福利厚生などの「労働環境」を重視する方は多いでしょう。
自分と企業の相性を確認しておくことで、ミスマッチを避けやすいです。
採用情報
企業の「採用情報」についても目を通しておきましょう。
企業研究を行ったところで、自分の希望職種の募集がされていなければ意味がありません。
また、採用情報を確認する際は、給与以外の待遇についても確認しておきましょう。
業界内での立ち位置
企業分析と同時に「業界分析」も行いましょう。
企業分析では企業にフォーカスを当てて行うのに対して、業界分析では、競合他社や志望企業が市場のなかでどのような立ち位置かを分析します。
業界分析を行うことで、リーディングカンパニー(特定の業界で主導的地位にある企業)や、技術力が高い企業など、企業ごとの特色が見えてきます。
企業分析後には結果を活用する
最後に、分析結果から企業の将来性や業界内での立ち位置を推測します。
分析時には、プラス要因だけでなくマイナス要因も考慮して、自分の適性と合うかどうかを考えましょう。
また、分析時には、そのときの社会情勢・新技術の情報などの知識が役立つこともあります。普段からさまざまな情報に興味を持っておきましょう。
まとめ
企業分析のメリットやフレームワークの使い方などをご紹介しました。
本記事では、SWOT分析や3C分析など、比較的簡単に活用できるフレームワークを選んでいます。
また、分析後は、入社後のビジョンやキャリアプランについて考えることが大切です。
普段からさまざまな情報に興味を持ち、自分と合った企業を見つけてください。